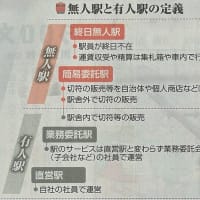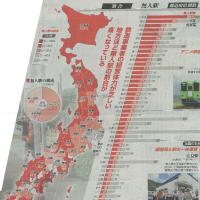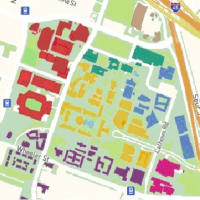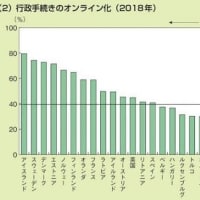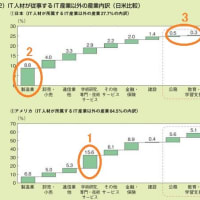ヒューストン再訪(5)から続く。
(1)初めてのひとり旅
時は1961年、大学4年生の夏、人生で初めてのひとり旅にでた。京都駅から夜行列車に乗って中央線の小渕沢から小諸へ、小諸から高崎経由で東京へ、東京駅23時35分発の夜行列車で京都に帰るという5日ほどの行程だった。
この旅の目的は、中央線のスイッチバックと碓氷峠のアプト式電気機関車の体験だった。この二つは、日本からなくなる前にぜひ見ておきたいと思った。
当時の中央線はスイッチバックで峠を越える時代、信越線の碓氷峠はアプト式鉄道だった。スイッチバックは、列車が山腹を斜めに登り、次に斜め後進で山腹を登る。前進と後進のジグザグで峠を超える方法だった。アプト式はレールとレールの中間に歯車用の軌道を敷き、電気機関車の歯車と噛み合わせて急坂を登る鉄道だった。【参考:中央線のスイッチバックは1972年にすべて解消、碓氷峠のアプト式は1963年9月に廃止】
また、この旅では予期しない光景や親切に出会い、今も時々思い出す。その一つは小諸城址の草笛である。
小諸城址での光景、それは黒い頭巾に黒装束と地下足袋(ジカタビ)姿、まるで忍者か修験者のような人が石垣を背に草笛を吹いていた。口上もなく、ただ一心に草笛を吹き続ける姿が非常に印象的だった。後にも先にも草笛を見たのはあの時だけ、草笛は草でなく3センチほどの木の葉で吹くものと知った。今も、石垣を背に忍者姿で草笛を吹く光景が鮮明に現れる。
若い頃の記憶はいつまでも褪せることはない。あのスイッチバックと草笛は「黙々と何かに打ち込むこと」の記憶として頭に焼き付いている。それは、いわばスイッチバックと草笛の教え、その後の人生で難関に出会うたびにこの二つがこころに浮かび、努力した。
(2)小諸城址の草笛
最近、友人に誘われて、静岡の興津から52号線-141号線の約180kmを北上し、小諸城址を再訪した。もちろん、小諸と聞き反射的にあの石垣と草笛が浮かび上り、記憶をたどりたく思った。
昔の記憶を頼りに、ここに違いないと下の写真にある石垣を見付けた。近くで一休みする庭園の手入れをする人に、草笛の思い出を話すと、即座に「横山祖道」とその人の名前がかえってきた。この城址の有名人とは夢にも思わなかったので、驚きとともに来て良かったと思った。遅ればせながら、故人の冥福を祈った。
小諸城址の石垣

下の写真は、草笛禅師「横山祖道」を紹介する看板と草笛再生ボックスである。再生ボックス中央のボタンを押すと、藤村の「千曲川旅情のうた」に対する「横山祖道」作の草笛の曲が流れる。
石垣正面の横山祖道の看板

看板には草笛禅師「横山祖道」「昭和55年まで22年間の亘り雨の日も風の日もこの場所で難しい説教に代えて草笛の優しい音色で旅人や子供に教えを説いた」とある。この説明の下に島崎藤村の「千曲川旅情のうた」が記してある。
あれから55年、ふたたび同じ石垣の前で同じ草笛を聞いた。しかも、あの人はただ者ではなかった。道理で、あの草笛は時の流れに淘汰されることなくいつまでも生きている。半世紀振りの再訪で、目に見えない何かの存在を感じた。ふと、シャルル・トレネ作詞作曲の「詩人の魂」を思った。【詩人の魂:詩人が世を去った後も彼らの歌はいつまでも巷を流れる・・・といったフランスのシャンソン】
石垣のすぐ近くの展望台からは、下の写真のように千曲川が見える。この光景は今も昔も変わらない。懐かしさを感じるthe same old sceneである。
眼下の千曲川

土曜日の城址は人影もまばら、静かに時が流れていく。日本の城の石垣は、大小の石が織りなす曲線美といえる。その曲面には武者返しの機能があり、同時に石垣の崩壊につながる壁面の張り出しを抑える効果もあるという。ヨーロッパでよく見る垂直で幾何学的な城壁とは異質、日本の城には天然とエンジニアリングの融合からくる「趣」がある。
帰途は、小諸から141号線と52号線を南下、興津に向かった。9月中旬の好天に恵まれ、川沿いの山々は美しく、水と緑が豊かな我が国の素晴らしさをつくづくと感じた。
美しい山と川と集落

国道沿いの家々は手入れが行き届き、草むす屋根は見当たらない。外国の小さな集落に比べると、日本の豊かさが良く分かる。しかし、この豊かさはすでに陰り始めている。
国道から外れると途端に家並みが静かになる。舗装していない道はないが、行き交う人が少ない。あちこちにシャッターを下ろした店が目に付き、子供の姿は見当たらない・・・我が国の陰りである。しかし陰りがあれば、日差しもあるはず、見渡せば日差しに向かう新しい方向もある。
まずは現状分析が大切、少子高齢化により誘発されるであろう事象とその対策を、国道を南下する車内であれこれと考えた・・・次回に続く。
お知らせ:
このブログを2010年8月26日に始めて、今回で119回になりました。その内容は、思いつくままに言語、コンピューター、生産管理、ビジネス、国内外旅行などと多岐にわたりました。ここで1、2ケ月の小休止、過去の内容を整理した上でふたたびグローバル化と少子高齢化を念頭に、日本がとるべき方向を検討する積りです。
以上
(1)初めてのひとり旅
時は1961年、大学4年生の夏、人生で初めてのひとり旅にでた。京都駅から夜行列車に乗って中央線の小渕沢から小諸へ、小諸から高崎経由で東京へ、東京駅23時35分発の夜行列車で京都に帰るという5日ほどの行程だった。
この旅の目的は、中央線のスイッチバックと碓氷峠のアプト式電気機関車の体験だった。この二つは、日本からなくなる前にぜひ見ておきたいと思った。
当時の中央線はスイッチバックで峠を越える時代、信越線の碓氷峠はアプト式鉄道だった。スイッチバックは、列車が山腹を斜めに登り、次に斜め後進で山腹を登る。前進と後進のジグザグで峠を超える方法だった。アプト式はレールとレールの中間に歯車用の軌道を敷き、電気機関車の歯車と噛み合わせて急坂を登る鉄道だった。【参考:中央線のスイッチバックは1972年にすべて解消、碓氷峠のアプト式は1963年9月に廃止】
また、この旅では予期しない光景や親切に出会い、今も時々思い出す。その一つは小諸城址の草笛である。
小諸城址での光景、それは黒い頭巾に黒装束と地下足袋(ジカタビ)姿、まるで忍者か修験者のような人が石垣を背に草笛を吹いていた。口上もなく、ただ一心に草笛を吹き続ける姿が非常に印象的だった。後にも先にも草笛を見たのはあの時だけ、草笛は草でなく3センチほどの木の葉で吹くものと知った。今も、石垣を背に忍者姿で草笛を吹く光景が鮮明に現れる。
若い頃の記憶はいつまでも褪せることはない。あのスイッチバックと草笛は「黙々と何かに打ち込むこと」の記憶として頭に焼き付いている。それは、いわばスイッチバックと草笛の教え、その後の人生で難関に出会うたびにこの二つがこころに浮かび、努力した。
(2)小諸城址の草笛
最近、友人に誘われて、静岡の興津から52号線-141号線の約180kmを北上し、小諸城址を再訪した。もちろん、小諸と聞き反射的にあの石垣と草笛が浮かび上り、記憶をたどりたく思った。
昔の記憶を頼りに、ここに違いないと下の写真にある石垣を見付けた。近くで一休みする庭園の手入れをする人に、草笛の思い出を話すと、即座に「横山祖道」とその人の名前がかえってきた。この城址の有名人とは夢にも思わなかったので、驚きとともに来て良かったと思った。遅ればせながら、故人の冥福を祈った。
小諸城址の石垣

下の写真は、草笛禅師「横山祖道」を紹介する看板と草笛再生ボックスである。再生ボックス中央のボタンを押すと、藤村の「千曲川旅情のうた」に対する「横山祖道」作の草笛の曲が流れる。
石垣正面の横山祖道の看板

看板には草笛禅師「横山祖道」「昭和55年まで22年間の亘り雨の日も風の日もこの場所で難しい説教に代えて草笛の優しい音色で旅人や子供に教えを説いた」とある。この説明の下に島崎藤村の「千曲川旅情のうた」が記してある。
あれから55年、ふたたび同じ石垣の前で同じ草笛を聞いた。しかも、あの人はただ者ではなかった。道理で、あの草笛は時の流れに淘汰されることなくいつまでも生きている。半世紀振りの再訪で、目に見えない何かの存在を感じた。ふと、シャルル・トレネ作詞作曲の「詩人の魂」を思った。【詩人の魂:詩人が世を去った後も彼らの歌はいつまでも巷を流れる・・・といったフランスのシャンソン】
石垣のすぐ近くの展望台からは、下の写真のように千曲川が見える。この光景は今も昔も変わらない。懐かしさを感じるthe same old sceneである。
眼下の千曲川

土曜日の城址は人影もまばら、静かに時が流れていく。日本の城の石垣は、大小の石が織りなす曲線美といえる。その曲面には武者返しの機能があり、同時に石垣の崩壊につながる壁面の張り出しを抑える効果もあるという。ヨーロッパでよく見る垂直で幾何学的な城壁とは異質、日本の城には天然とエンジニアリングの融合からくる「趣」がある。
帰途は、小諸から141号線と52号線を南下、興津に向かった。9月中旬の好天に恵まれ、川沿いの山々は美しく、水と緑が豊かな我が国の素晴らしさをつくづくと感じた。
美しい山と川と集落

国道沿いの家々は手入れが行き届き、草むす屋根は見当たらない。外国の小さな集落に比べると、日本の豊かさが良く分かる。しかし、この豊かさはすでに陰り始めている。
国道から外れると途端に家並みが静かになる。舗装していない道はないが、行き交う人が少ない。あちこちにシャッターを下ろした店が目に付き、子供の姿は見当たらない・・・我が国の陰りである。しかし陰りがあれば、日差しもあるはず、見渡せば日差しに向かう新しい方向もある。
まずは現状分析が大切、少子高齢化により誘発されるであろう事象とその対策を、国道を南下する車内であれこれと考えた・・・次回に続く。
お知らせ:
このブログを2010年8月26日に始めて、今回で119回になりました。その内容は、思いつくままに言語、コンピューター、生産管理、ビジネス、国内外旅行などと多岐にわたりました。ここで1、2ケ月の小休止、過去の内容を整理した上でふたたびグローバル化と少子高齢化を念頭に、日本がとるべき方向を検討する積りです。
以上