倫理の起源27
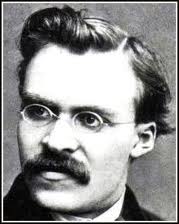
道徳に対して極度の反抗意識を持っていたニーチェは、「良心の疚しさ」や「負い目の意識」を、外に伸長すべき「力への意志」がより強い力に出会って挫折し、その攻撃性を自虐の方向に向けかえられたところに成立すると捉えた。これは「良心」そのものをたいへんネガティヴに見ていたことを意味する。たしかに、過度な疚しさや不必要な負い目を抱えることは、自己の生きる力そのものを殺ぐので、よいことではない。しかし、ニーチェの捉え方は必ずしも当たっていない。
古今東西を通して、「信頼」のないところに人間関係は存在せず、人間関係が存在しなければそもそも人間は存在することができない。そして、その「信頼」とは、個人における「良心」や「負い目の意識」という概念を、関係存在としての人間という把握から照らし出した概念である。両者は同じことの別様の表現に他ならない。ある人が良心や誠実さをもっているということは、すなわちその人がだれかを信頼しているということなのである。たとえその「だれか」が、彼にとって具体的なあれこれの人間を指すのではなく、さしあたり抽象的な他者一般という観念にすぎないとしても。
ニーチェほどの孤絶者といえども、みずからの著作意図をわかってほしい(承認してほしい、信頼してほしい)と痛切に思っていた。そもそも著作を世に問うという行為自体、他者からの承認や信頼を期待している証拠である。彼は実際、ごく少数の友人との付き合いや理解者(信頼者)の出現を子どものように喜んでいたではないか。
以上「信頼」について述べたのとほぼ重なることを、和辻哲郎が『倫理学』のなかでニーチェを批判してもっと詳細に書いている。以下、その一部を引いておこう。
が、ニーチェの立場からはさらに次のごとく言い得るであろう。本来の価値秩序とは歴史的に原始の秩序であるという意味ではなく、宇宙の原理としての権力意志に基づく価値秩序なのである。権力意志の強弱がこの秩序を定める。歴史的にあらわれた道徳はこの本来の秩序に対する人間の解釈に他ならない。古代ギリシアの道徳は 階級による正しい解釈であり、ユダヤ人の道徳は反感による逆倒的解釈である。現代ヨーロッパを支配せる道徳は後者であるゆえに、特にこの道徳の系譜を洗い立てねばならなかった。要するところは権力意志に基づく本来の価値秩序を回復するにある。そうしてこの秩序は、信頼関係というごときものに関わることなく、一人格の意志の強さ、生の豊かさによって定まって来るであろう。(中略)
この反駁は一応もっともなように見える。が、実は信頼関係の中で起こる評価を個人意識の視点から見ているに過ぎぬのである。権力意志の強弱は、あくまでも強弱であって善悪ではない。意志の堅固というごときことも、もし単に一人格についてのみ言われるとすれば、単に意志の堅固であって善ではない。(中略)
冒険的態度のごときも、もしそれが信頼に答える意義を持たなければ、いわゆる暴虎馮河に過ぎぬ。勇気の意義は己れの持ち場を死守するところに存する。そうして持ち場は信頼の表現である。かく見れば、自己の意志の強さや生の豊かさのみから自己が尊敬すべきものとして感ぜられるという見方は当たらない。信頼に答えようとするものが意志の強さや生の豊かさによってこの応答をなしうる時、その意志の強さや生の豊かさが価値あるものになるのである。だからこれらのものが信頼への応答を妨げるときには、逆にそれらは捨離せられるべきものになる。(第一章)
和辻のこのニーチェ批判は、経験と照らし合わせるとき、まことに的確なものというべきである。人々がある人の行為を「勇気がある」と言って褒めたたえるとき、その賞賛は、単に常人がなしえないことをなしたということそれ自体に向けられているのではなく(それだけなら、人前で裸になって見せることも賞賛に値することになる)、すでに特定の状況文脈の中で、周囲の人々によって共同的に期待される行為であるという了解を前提としている。みんなを一様に侵害してくる相手に対して他に先駆けて立ち向かうというように。
ニーチェは、道徳的な善悪の原理(gutとböseの関係)を自然秩序としての強弱や優劣の原理(gutとschlechtの関係)にそっくり置き換えようとしたが、いま見たとおり、これは論理的に破綻している。両原理は互いに対立しあうのではなく、もともとまったく質の異なる秩序原理であって、それゆえ、かえって両原理の一方が他方を相互に包み込む関係にある。道徳的な善として認められる意志や行為のなかに、勇敢さを示すことのように「強い、優れた」あり方が包含されるし、逆に、敵を見事に倒すこと、仲間・手下に寛大さを示すこと、けちけちせず豪勢にふるまうこと、鋭い理解力を開陳することなど、総じて強く優れた力を示すことのなかに、信頼を勝ち得て道徳的に善であるとみなされるあり方が包含されるのである。
この点で問題にしてみるに値するのが、プラトンの『ゴルギアス』である。この作品は、はじめの方で、弁論術の大家・ゴルギアス(および弟子のポロス)が、人を説得することの価値を前面に押し出すのに対し、ソクラテスがそれを、真理の探究や本当によきことを求める営みと縁のない「おべっかの術」であると決めつけるという体裁をとっている。ソクラテスがゴルギアスをやりこめる論法は、例によって彼一流で、惑わされないように読んでいくと、至る所にゴルギアスやポロスの返答の仕方のまずさが現われていて、そんなふうに丸め込まれずに、ここはこう答えるべきだと茶々を入れたくなる部分がいくつもある。すでに検討した、プラトン得意の「言葉の抽象作用」、特に身体にかかわる事柄の、魂にかかわる事柄への比喩・転用を巧みに用いた詐術である。
しかし、私たちがこの作品に大きな関心を引きよせられるのは、むしろ後半部分、カリクレスの登場によって、善(よきこと)や正義というテーマがいっそう重大で深刻な議題として再構成される部分である。ところがソクラテスの強敵として現われたカリクレスは、はじめは威勢がよかったのだが、やがてソクラテスの執拗な論及の前に疲れてしまい、しぶしぶその言い分に従うようになるという流れになっている。ここでも、カリクレスのふがいなさに対して、そんなふうに妥協すべきではない、ソクラテスの論理にも逆襲できるほころびがあるではないか、と言ってやりたい気がする。しかし作者プラトンにとって、ソクラテスの勝利(真理を追究する哲学者の価値)は絶対に勝ち取らなくてはならない第一要請だから、作品構成上、そうせざるを得なかったのだろう。ただ私としては、新たな読者はこういう詐術に丸め込まれませんようにと願うばかりである。
いずれにしても、ここで重要なのは、ニーチェが提供した「強弱、優劣」の価値観に基づく主人道徳と奴隷道徳との決定的相違という問題が、早くもソクラテスに対するカリクレスの異議申し立てというかたちで鮮やかに先取りされていることである。その意味でプラトンはやはり偉大というべきだろう。
カリクレスは言う。ソクラテスは実用に役立たない哲学的な屁理屈ばかりこねて相手をやり込めているが、実際にこの世で権力を掌握して民衆を統治しているのは、強者であり、優れた者たちである。それが自然本来の姿であり、法律習慣の世界では、「不正」と規定されるかもしれないが、自然の世界では、それこそが「正義」なのである。
すなわち、すぐれた者は劣った者よりも、また有能な者は無能な者よりも、多くを持つことこそが正しいのだと。
これがそのとおりだということを明示する事実は、いたるところにある。動物たちの世界においてもそうだし、人間たちのつくりなす全体としての国と国、種族と種族との関係においてもそうだ。いずれにおいても明らかなのは、正義とは常にそのようにして強者が弱者を支配し、強者は弱者よりも多くを持つという仕方で判定されてきたということである。
しかしカリクレスは、道徳や法律の正しさなど追求せずに弱肉強食の現実をそのまま肯定しろと言っているわけではない。右の引用は、ともかくもそういう世の現実を事実として認めた上でなければ話にならないという文脈で言われている。また、彼も国家公共の仕事にかかわるひとりだから、統治が功を奏するために、統治者がどんなすぐれた資質を必要とされるかということに関しては、次のように、きわめてまともなことを言っている。
いや、私のほうに関するかぎり、もうずっと前から言っているはずだ。まず、人よりもたちまさった人間とはどのような人たちかと言えば、それは、靴屋でもなければ肉屋でもなく(引用者注――これはソクラテスが理屈のためにしつこく例示したことへの苛立ちから言われている)、国家公共(「ポリス」とルビあり――引用者)のことがらに関して思慮をもち、いかにすれば一国をよく治めることができるかをわきまえた人たちのことだ。またさらに、ただ思慮においてすぐれているだけでなく勇気をもあわせそなえた人たち、自分の思いついた構想を何でも最後までなしとげるだけの実行力をもち、精神の柔弱さのために途中でくじけてしまうようなことのない、男らしい人たちのことだ。
ここまでは、貴族主義者のプラトン自身も認めていたはずである。ところが、ソクラテスはここから論題を逸らし、「自分自身の魂への配慮をいかにすべきか」という問いを唐突に設定する。戸惑うカリクレスに対して、すぐれた者は欲望を抑えて節制の徳をわきまえる必要があるかと聞く。じつに巧みな誘導である。カリクレスは、「すぐれた支配者」はその有能さに応じて多くを取るのが当然であるという価値観を持っているから、そんな徳はけちくさい奴隷の徳であり、支配力のある人たちは、欲望にブレーキなどかけずに、放埓にふるまってかまわないのだと答えてしまう。その方が味方に多くを分けてやることができるではないか、と。
ここがまさにソクラテス(=プラトン)の攻めどころである。支配者がいくらでも「多く取る」ことが許されるなら、それはまさに人民を搾取する「不正」に結びつく。つまり独裁権力の悪い面が大手を振ってまかり通ることをそのまま認めてしまうことになる。「有能な者は無能な者よりも、多くを持つことこそが正しい」とカリクレス自身が言っているではないか。
ちなみに、プラトンは『国家』に明らかなように、すぐれた「哲人」が統治することを最もよしとしていたのだから、私たちの時代の多数者が正しいと認めているような「民主主義者」ではない。『ゴルギアス』でも、アテナイ民主制の普及者として名高いペリクレスを、国民に媚びる「おべっか政治家」(今のことばでいえばポピュリスト)として批判している。したがってここで彼がソクラテスに説かせようとしているのは、「すぐれた統治者」は、よく社会秩序を維持して国家の繁栄と国民の安寧を保障する使命と責任のために、自分自身に対して節制の徳を修めなくてはいけないということである。これはこれで納得できる話である。
ところが、カリクレスがうっかり「放埓こそすぐれた者の正義にかなう」と答えてしまったことによって、形勢はソクラテスに断然有利になる。カリクレスは、こう答えるべきだったのだ――「もちろん、統治者個人の取り分に関しては適切な程度にしておくべきだろう。だが、そのことと、国家が繁栄するために自分の持てる力を大いに発揮したり、金を惜しまずに使うということとは、別問題だ」。こうすればソクラテスにつけ込まれることはなかったのである。
プラトンは、「節制――放埓」という言葉の二項対立原理を、「だれにとっての」という具体的な条件づけ抜きに設定して、「何がより正しいことか」という抽象命題へと結びつけていく。彼はいつもそういう論理の運びにしたがって議論を進める。つまり私的問題と公的問題とを意識的に混同させるのである。そのことによって、「こういう場合にはそれは当てはまるが、それとは違った条件のもとでは必ずしも当てはまらない」という現実感覚を追放し、柔軟な思考の可能性を意識的に封じるのだ。イデア原理主義者であるゆえんである。
一つだけソクラテスの屁理屈の例を挙げておこう。
彼はカリクレスが「善=快」という図式によって思考しているのに対して、それをひっくり返すために、かくかくの理由で善と快とは同じではないという議論を持ち出す。この「弁論術」は、少し怜悧に頭をはたらかせればすぐにインチキを見破れるような代物である。
ソクラテスの理屈はこうだ。
快と不快とは、同時に進行する。それはたとえば疥癬病みが、かゆいという不快を感じつつ、常に掻きつづけることによってその不快を脱して快を得るような具合だ。これに対して、あることが善であると同時に悪でもあるというようなことはない。よって両者(善と快)とは同じではない、というのである。すでに述べた『パイドン』でさんざん駆使された偽の「証明」と同じような論法である。まことにソクラテスこそは、ゴルギアス以上に「弁論家」である。
ある人にとっての快と不快とはじつは同時に進行しはしない。不快や欲望の高まりがあるからそこに克服の意志が生じ、その意志にふさわしいような処置がとられる。それによって快という状態に達する。どんなに短い時間内における快と不快の関係においても、こうしたプロセスが存在する。
また逆に、あること(特定の意志や行為)が善であると同時に悪でもあるということはあり得る。すでに引いたカントのウソ論文の例のように、「ウソをつく」という「悪」は、同時に妻子や友人の命を救うという「善」につながることがあり得る。孔丘の『論語』では、同じようなテーマが、まったく逆の文脈で語られている。
葉公 孔子に語げて曰く、吾が党に直躬なる者有り。其の父、羊を盗みて、子 之を証せり、と。孔子 曰く、吾が党の直なる者は、是に異なり。父は子の為に隠し、子は父の為に隠す。直は其の中に在り、と。(「子路」18)
このように、「善」とか「悪」という概念は、特定の意志や行為のうちにその判断の適否を求めるなら、だれにとって、どういう条件下において、という但し書きをつけなければ、判断不可能である。だがカリクレスは、ソクラテスのこの屁理屈に反論できなかった。
それでは、逆の意味で「善」と「快」とは違うと言えるではないか、という反論があり得よう。しかしそれに対しては、いや、「快」だって、ある人にとっては快適な行為であっても、それを受ける相手にとっては不快であることがあり得ると切り返すこともできるのである。言語のある抽象的な水準で論理の正しさを競っている限り、ことの決着はいつまでたってもつかない。どういう具体的な条件下でこちらの議論のほうがより適正と言えるのか、ということを常に問わなくてはならないのだ。
ここで行われているやりとりには、そもそも「善」とか「快」とかいう言葉で、君はどういうことをイメージしているのか、という共通了解に達するための議論が不在である。だがプラトンは、これらの抽象語をイデアとして固定化しているために、そういう議論の必要を無視している。けれどもすでに述べたように、「快」を「幸福」という概念にまで拡張し、「善」とは、そこにかかわりあう人々にとってのお互いの幸福が実現している状態である、と表現し直すなら、両者(「善」と「快」)とは必ず一致するのである。
だがプラトンについては、もうこれ以上あまり深追いしないことにしよう。
ニーチェに話を戻すと、彼もまた、この時のカリクレスと同じように、禁欲とか節制とかけち臭さといったあり方を、生の欲望の展開や芸術文化の開花にとって抑圧的なものと考えたがゆえに、激しく否定しようとした。しかしお分かりのように、節制と放胆とではどちらが徳一般にかなうかというような抽象的な対立命題の土俵でこの問題に答えてはならないのである。彼が現代の大衆社会を批判するために、「奴隷道徳」に「主人道徳」を対置した気持ちはわからないではない。しかしニーチェは近代人なのだから、アルカイックな時代の哲学の論理構成にはまり込まずに、もっと冷静かつ柔軟にプラトン(ソクラテス)批判を展開すべきだったろう。それをさせなくさせていたものは、彼自身の激情的な体質であったにちがいない。
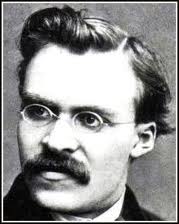
道徳に対して極度の反抗意識を持っていたニーチェは、「良心の疚しさ」や「負い目の意識」を、外に伸長すべき「力への意志」がより強い力に出会って挫折し、その攻撃性を自虐の方向に向けかえられたところに成立すると捉えた。これは「良心」そのものをたいへんネガティヴに見ていたことを意味する。たしかに、過度な疚しさや不必要な負い目を抱えることは、自己の生きる力そのものを殺ぐので、よいことではない。しかし、ニーチェの捉え方は必ずしも当たっていない。
古今東西を通して、「信頼」のないところに人間関係は存在せず、人間関係が存在しなければそもそも人間は存在することができない。そして、その「信頼」とは、個人における「良心」や「負い目の意識」という概念を、関係存在としての人間という把握から照らし出した概念である。両者は同じことの別様の表現に他ならない。ある人が良心や誠実さをもっているということは、すなわちその人がだれかを信頼しているということなのである。たとえその「だれか」が、彼にとって具体的なあれこれの人間を指すのではなく、さしあたり抽象的な他者一般という観念にすぎないとしても。
ニーチェほどの孤絶者といえども、みずからの著作意図をわかってほしい(承認してほしい、信頼してほしい)と痛切に思っていた。そもそも著作を世に問うという行為自体、他者からの承認や信頼を期待している証拠である。彼は実際、ごく少数の友人との付き合いや理解者(信頼者)の出現を子どものように喜んでいたではないか。
以上「信頼」について述べたのとほぼ重なることを、和辻哲郎が『倫理学』のなかでニーチェを批判してもっと詳細に書いている。以下、その一部を引いておこう。
が、ニーチェの立場からはさらに次のごとく言い得るであろう。本来の価値秩序とは歴史的に原始の秩序であるという意味ではなく、宇宙の原理としての権力意志に基づく価値秩序なのである。権力意志の強弱がこの秩序を定める。歴史的にあらわれた道徳はこの本来の秩序に対する人間の解釈に他ならない。古代ギリシアの道徳は 階級による正しい解釈であり、ユダヤ人の道徳は反感による逆倒的解釈である。現代ヨーロッパを支配せる道徳は後者であるゆえに、特にこの道徳の系譜を洗い立てねばならなかった。要するところは権力意志に基づく本来の価値秩序を回復するにある。そうしてこの秩序は、信頼関係というごときものに関わることなく、一人格の意志の強さ、生の豊かさによって定まって来るであろう。(中略)
この反駁は一応もっともなように見える。が、実は信頼関係の中で起こる評価を個人意識の視点から見ているに過ぎぬのである。権力意志の強弱は、あくまでも強弱であって善悪ではない。意志の堅固というごときことも、もし単に一人格についてのみ言われるとすれば、単に意志の堅固であって善ではない。(中略)
冒険的態度のごときも、もしそれが信頼に答える意義を持たなければ、いわゆる暴虎馮河に過ぎぬ。勇気の意義は己れの持ち場を死守するところに存する。そうして持ち場は信頼の表現である。かく見れば、自己の意志の強さや生の豊かさのみから自己が尊敬すべきものとして感ぜられるという見方は当たらない。信頼に答えようとするものが意志の強さや生の豊かさによってこの応答をなしうる時、その意志の強さや生の豊かさが価値あるものになるのである。だからこれらのものが信頼への応答を妨げるときには、逆にそれらは捨離せられるべきものになる。(第一章)
和辻のこのニーチェ批判は、経験と照らし合わせるとき、まことに的確なものというべきである。人々がある人の行為を「勇気がある」と言って褒めたたえるとき、その賞賛は、単に常人がなしえないことをなしたということそれ自体に向けられているのではなく(それだけなら、人前で裸になって見せることも賞賛に値することになる)、すでに特定の状況文脈の中で、周囲の人々によって共同的に期待される行為であるという了解を前提としている。みんなを一様に侵害してくる相手に対して他に先駆けて立ち向かうというように。
ニーチェは、道徳的な善悪の原理(gutとböseの関係)を自然秩序としての強弱や優劣の原理(gutとschlechtの関係)にそっくり置き換えようとしたが、いま見たとおり、これは論理的に破綻している。両原理は互いに対立しあうのではなく、もともとまったく質の異なる秩序原理であって、それゆえ、かえって両原理の一方が他方を相互に包み込む関係にある。道徳的な善として認められる意志や行為のなかに、勇敢さを示すことのように「強い、優れた」あり方が包含されるし、逆に、敵を見事に倒すこと、仲間・手下に寛大さを示すこと、けちけちせず豪勢にふるまうこと、鋭い理解力を開陳することなど、総じて強く優れた力を示すことのなかに、信頼を勝ち得て道徳的に善であるとみなされるあり方が包含されるのである。
この点で問題にしてみるに値するのが、プラトンの『ゴルギアス』である。この作品は、はじめの方で、弁論術の大家・ゴルギアス(および弟子のポロス)が、人を説得することの価値を前面に押し出すのに対し、ソクラテスがそれを、真理の探究や本当によきことを求める営みと縁のない「おべっかの術」であると決めつけるという体裁をとっている。ソクラテスがゴルギアスをやりこめる論法は、例によって彼一流で、惑わされないように読んでいくと、至る所にゴルギアスやポロスの返答の仕方のまずさが現われていて、そんなふうに丸め込まれずに、ここはこう答えるべきだと茶々を入れたくなる部分がいくつもある。すでに検討した、プラトン得意の「言葉の抽象作用」、特に身体にかかわる事柄の、魂にかかわる事柄への比喩・転用を巧みに用いた詐術である。
しかし、私たちがこの作品に大きな関心を引きよせられるのは、むしろ後半部分、カリクレスの登場によって、善(よきこと)や正義というテーマがいっそう重大で深刻な議題として再構成される部分である。ところがソクラテスの強敵として現われたカリクレスは、はじめは威勢がよかったのだが、やがてソクラテスの執拗な論及の前に疲れてしまい、しぶしぶその言い分に従うようになるという流れになっている。ここでも、カリクレスのふがいなさに対して、そんなふうに妥協すべきではない、ソクラテスの論理にも逆襲できるほころびがあるではないか、と言ってやりたい気がする。しかし作者プラトンにとって、ソクラテスの勝利(真理を追究する哲学者の価値)は絶対に勝ち取らなくてはならない第一要請だから、作品構成上、そうせざるを得なかったのだろう。ただ私としては、新たな読者はこういう詐術に丸め込まれませんようにと願うばかりである。
いずれにしても、ここで重要なのは、ニーチェが提供した「強弱、優劣」の価値観に基づく主人道徳と奴隷道徳との決定的相違という問題が、早くもソクラテスに対するカリクレスの異議申し立てというかたちで鮮やかに先取りされていることである。その意味でプラトンはやはり偉大というべきだろう。
カリクレスは言う。ソクラテスは実用に役立たない哲学的な屁理屈ばかりこねて相手をやり込めているが、実際にこの世で権力を掌握して民衆を統治しているのは、強者であり、優れた者たちである。それが自然本来の姿であり、法律習慣の世界では、「不正」と規定されるかもしれないが、自然の世界では、それこそが「正義」なのである。
すなわち、すぐれた者は劣った者よりも、また有能な者は無能な者よりも、多くを持つことこそが正しいのだと。
これがそのとおりだということを明示する事実は、いたるところにある。動物たちの世界においてもそうだし、人間たちのつくりなす全体としての国と国、種族と種族との関係においてもそうだ。いずれにおいても明らかなのは、正義とは常にそのようにして強者が弱者を支配し、強者は弱者よりも多くを持つという仕方で判定されてきたということである。
しかしカリクレスは、道徳や法律の正しさなど追求せずに弱肉強食の現実をそのまま肯定しろと言っているわけではない。右の引用は、ともかくもそういう世の現実を事実として認めた上でなければ話にならないという文脈で言われている。また、彼も国家公共の仕事にかかわるひとりだから、統治が功を奏するために、統治者がどんなすぐれた資質を必要とされるかということに関しては、次のように、きわめてまともなことを言っている。
いや、私のほうに関するかぎり、もうずっと前から言っているはずだ。まず、人よりもたちまさった人間とはどのような人たちかと言えば、それは、靴屋でもなければ肉屋でもなく(引用者注――これはソクラテスが理屈のためにしつこく例示したことへの苛立ちから言われている)、国家公共(「ポリス」とルビあり――引用者)のことがらに関して思慮をもち、いかにすれば一国をよく治めることができるかをわきまえた人たちのことだ。またさらに、ただ思慮においてすぐれているだけでなく勇気をもあわせそなえた人たち、自分の思いついた構想を何でも最後までなしとげるだけの実行力をもち、精神の柔弱さのために途中でくじけてしまうようなことのない、男らしい人たちのことだ。
ここまでは、貴族主義者のプラトン自身も認めていたはずである。ところが、ソクラテスはここから論題を逸らし、「自分自身の魂への配慮をいかにすべきか」という問いを唐突に設定する。戸惑うカリクレスに対して、すぐれた者は欲望を抑えて節制の徳をわきまえる必要があるかと聞く。じつに巧みな誘導である。カリクレスは、「すぐれた支配者」はその有能さに応じて多くを取るのが当然であるという価値観を持っているから、そんな徳はけちくさい奴隷の徳であり、支配力のある人たちは、欲望にブレーキなどかけずに、放埓にふるまってかまわないのだと答えてしまう。その方が味方に多くを分けてやることができるではないか、と。
ここがまさにソクラテス(=プラトン)の攻めどころである。支配者がいくらでも「多く取る」ことが許されるなら、それはまさに人民を搾取する「不正」に結びつく。つまり独裁権力の悪い面が大手を振ってまかり通ることをそのまま認めてしまうことになる。「有能な者は無能な者よりも、多くを持つことこそが正しい」とカリクレス自身が言っているではないか。
ちなみに、プラトンは『国家』に明らかなように、すぐれた「哲人」が統治することを最もよしとしていたのだから、私たちの時代の多数者が正しいと認めているような「民主主義者」ではない。『ゴルギアス』でも、アテナイ民主制の普及者として名高いペリクレスを、国民に媚びる「おべっか政治家」(今のことばでいえばポピュリスト)として批判している。したがってここで彼がソクラテスに説かせようとしているのは、「すぐれた統治者」は、よく社会秩序を維持して国家の繁栄と国民の安寧を保障する使命と責任のために、自分自身に対して節制の徳を修めなくてはいけないということである。これはこれで納得できる話である。
ところが、カリクレスがうっかり「放埓こそすぐれた者の正義にかなう」と答えてしまったことによって、形勢はソクラテスに断然有利になる。カリクレスは、こう答えるべきだったのだ――「もちろん、統治者個人の取り分に関しては適切な程度にしておくべきだろう。だが、そのことと、国家が繁栄するために自分の持てる力を大いに発揮したり、金を惜しまずに使うということとは、別問題だ」。こうすればソクラテスにつけ込まれることはなかったのである。
プラトンは、「節制――放埓」という言葉の二項対立原理を、「だれにとっての」という具体的な条件づけ抜きに設定して、「何がより正しいことか」という抽象命題へと結びつけていく。彼はいつもそういう論理の運びにしたがって議論を進める。つまり私的問題と公的問題とを意識的に混同させるのである。そのことによって、「こういう場合にはそれは当てはまるが、それとは違った条件のもとでは必ずしも当てはまらない」という現実感覚を追放し、柔軟な思考の可能性を意識的に封じるのだ。イデア原理主義者であるゆえんである。
一つだけソクラテスの屁理屈の例を挙げておこう。
彼はカリクレスが「善=快」という図式によって思考しているのに対して、それをひっくり返すために、かくかくの理由で善と快とは同じではないという議論を持ち出す。この「弁論術」は、少し怜悧に頭をはたらかせればすぐにインチキを見破れるような代物である。
ソクラテスの理屈はこうだ。
快と不快とは、同時に進行する。それはたとえば疥癬病みが、かゆいという不快を感じつつ、常に掻きつづけることによってその不快を脱して快を得るような具合だ。これに対して、あることが善であると同時に悪でもあるというようなことはない。よって両者(善と快)とは同じではない、というのである。すでに述べた『パイドン』でさんざん駆使された偽の「証明」と同じような論法である。まことにソクラテスこそは、ゴルギアス以上に「弁論家」である。
ある人にとっての快と不快とはじつは同時に進行しはしない。不快や欲望の高まりがあるからそこに克服の意志が生じ、その意志にふさわしいような処置がとられる。それによって快という状態に達する。どんなに短い時間内における快と不快の関係においても、こうしたプロセスが存在する。
また逆に、あること(特定の意志や行為)が善であると同時に悪でもあるということはあり得る。すでに引いたカントのウソ論文の例のように、「ウソをつく」という「悪」は、同時に妻子や友人の命を救うという「善」につながることがあり得る。孔丘の『論語』では、同じようなテーマが、まったく逆の文脈で語られている。
葉公 孔子に語げて曰く、吾が党に直躬なる者有り。其の父、羊を盗みて、子 之を証せり、と。孔子 曰く、吾が党の直なる者は、是に異なり。父は子の為に隠し、子は父の為に隠す。直は其の中に在り、と。(「子路」18)
このように、「善」とか「悪」という概念は、特定の意志や行為のうちにその判断の適否を求めるなら、だれにとって、どういう条件下において、という但し書きをつけなければ、判断不可能である。だがカリクレスは、ソクラテスのこの屁理屈に反論できなかった。
それでは、逆の意味で「善」と「快」とは違うと言えるではないか、という反論があり得よう。しかしそれに対しては、いや、「快」だって、ある人にとっては快適な行為であっても、それを受ける相手にとっては不快であることがあり得ると切り返すこともできるのである。言語のある抽象的な水準で論理の正しさを競っている限り、ことの決着はいつまでたってもつかない。どういう具体的な条件下でこちらの議論のほうがより適正と言えるのか、ということを常に問わなくてはならないのだ。
ここで行われているやりとりには、そもそも「善」とか「快」とかいう言葉で、君はどういうことをイメージしているのか、という共通了解に達するための議論が不在である。だがプラトンは、これらの抽象語をイデアとして固定化しているために、そういう議論の必要を無視している。けれどもすでに述べたように、「快」を「幸福」という概念にまで拡張し、「善」とは、そこにかかわりあう人々にとってのお互いの幸福が実現している状態である、と表現し直すなら、両者(「善」と「快」)とは必ず一致するのである。
だがプラトンについては、もうこれ以上あまり深追いしないことにしよう。
ニーチェに話を戻すと、彼もまた、この時のカリクレスと同じように、禁欲とか節制とかけち臭さといったあり方を、生の欲望の展開や芸術文化の開花にとって抑圧的なものと考えたがゆえに、激しく否定しようとした。しかしお分かりのように、節制と放胆とではどちらが徳一般にかなうかというような抽象的な対立命題の土俵でこの問題に答えてはならないのである。彼が現代の大衆社会を批判するために、「奴隷道徳」に「主人道徳」を対置した気持ちはわからないではない。しかしニーチェは近代人なのだから、アルカイックな時代の哲学の論理構成にはまり込まずに、もっと冷静かつ柔軟にプラトン(ソクラテス)批判を展開すべきだったろう。それをさせなくさせていたものは、彼自身の激情的な体質であったにちがいない。









