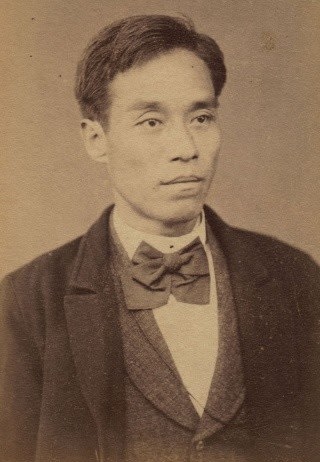
福沢諭吉は「武士」でした。そして真正のナショナリストでした。
その心は、彼が、あの動乱と建設の時代における公共精神を代表しており、当時の日本国民の幸福獲得について、終生、力を尽くして考え抜いた人だったという意味です。福沢は、列強の脅威に取り巻かれる中で、日本の独立を真に成し遂げるには何が必要かを一心に考え抜いた人でした。
しかし福沢にはいくつもの誤解がまとわりついています。
この誤解の種は福沢自身にあるというよりも、福沢読者の側にあります。つまり、読者たちのイデオロギー的立場から来ている部分が大きいのです。
たとえば福沢は、しばしば欧化主義者の代表のように見なされます。
このイメージはリベラル左派の人からは歓迎され、保守派など右寄りの人からは苦々しいものとしてとらえられます。
しかし『学問のすゝめ』(明治五年~九年)や『通俗国権論』(明治十一年)、『民情一新』(明治十二年)その他を見ればわかるとおり、彼は一貫して欧化主義者に批判的でした。彼らを「西洋心酔者流」と呼んで至る所で痛快な揶揄を飛ばしています。
福沢がいち早く西洋近代文明とその背後にある進取の気象に触れ、これをとりあえずのお手本として積極的に摂取すべきだと唱えたことは事実です。
けれども同時に彼は、たえず外に進出していこうとする西洋の強大な力の脅威を人一倍強く感受し、これに対抗する必要性を繰り返し訴えていました。
そのためには、一時、感情的な攘夷思想などに走らず、まず「敵」をよく知ること、「敵」の優れた点を換骨奪胎してわがものとすることこそ大切だと説き続けたのです。いまの言葉で言えば、グローバリズムの不可避的な浸透に対して、ただ精神論的に強がって見せるのではなく、国および国民を守るために、現実的に有効な対策を真剣に模索したわけです。
彼はまた単純な国権主義者と見なされることがあります。
この場合は逆に左寄りの人からは顰蹙を買い、右寄りの人からは好意的に迎えられます。
しかし主著『文明論之概略』(明治八年)や『通俗民権論』(明治十一年)その他を見ればわかるとおり、彼の胸中にあったのは単に内への国家権力の強化ではなく、人民の自主独立の気風を育てることによって官民融和の関係を築き上げることでした。それが日本の文明化にとって不可欠と考えられたのです。
政府は人民によって支えられる。幕末維新の政変も、一部権力者や倒幕勢力の力によるものではなく、人民の気風が高まっていたからである。国権と民権とでは、統治の維持という意味においてもちろん国権が優位に立つが、どちらか一方が強すぎてもダメで、両者が車の両輪のように作用してじっくり協力体制を築いていかなくてはならない。それによって初めて実質的な国力を富ませることができる――これが、福沢の国家建設のグランドデザインでした。
また、福沢は平等主義者だったというとんでもない誤解があります。
福沢諭吉というと、誰もが『学問のすゝめ』冒頭の「天は人の上に人を造らず、人の下に人を造らず」という文句をすぐ連想します。人間の平等は天賦のものなのだ、と。
ところがこれは福沢自身の言葉ではなく、したがって彼の思想ではありません。彼は、「天賦」という言葉を平等や人権に当てはめて用いたことはなく、逆に「天賦」と言う時には、体力や知力や気力などにかかわる、乗り越えられない人間の不平等の実態を形容するときだけでした。
実はこの文句のあとには、「……と云へり」とあるのですが、ほとんどの人がこれを見逃してしまいます。
「……と云へり」とは、「と言われている」という意味なので、「一応そういうことになっている」ということです。
さてその数行後に、「されども今、広く此人間世界を見渡すに」とあって、いかに現実の世が貧富、賢愚、身分、権力においてはなはだしい格差に満ち満ちているかという記述があります。
『学問のすゝめ』はここを発端として、この格差から生じる奴隷根性を少しでもなくし、多くの人が自主独立の気概をもって人生を歩めるようにするには、「学問」がどうしても必要だ、というように展開されていくのです。
「学問」というと難しく聞こえますが、福沢のいう学問とは、「知性の活用」というのとほぼ同じです。つまり、単に学者が文献に首を突っ込んで博識をため込むのとはまったく違います。書物や経験や見聞から得たあらゆる知見を総合し、これを実地に用いて、みんなのために役立てることを意味しているのです。
福沢は、高尚ぶって役に立たない知識ばかり詰め込んでいるオタク知識人を非常にバカにしていました。当時で言えば儒学者の大半がこれに当たります。社会情勢と時代の気運を読めないこうした連中を「腐儒」と呼んでいます。
彼はアメリカに二度、欧州に一度渡航していますが、そこで味わったものは、ただ物質文明の進んだ姿だけではありません。彼を刺激したのは、そういう文明を作り出した西洋人たちの、目には見えない精神、気概、またそれを可能にした社会制度の仕組みとはいったい何なのかということでした。
彼が得た当座の結論は、「人間交際」のあり方のうちにこそその秘密が隠されているというものでした。
彼はしばしば蒸気機関や電信技術について語っていますが、そういう技術文明の秘密は分厚い中産階層(ミドル・クラス)のうちにこそ宿っていると判断しました。そうした力に満ちた階層の活発な交流が、今日の西洋文明を生み出したのだ、と。
西洋にあって日本にまだないもの、それは、ある程度の経済力を蓄えた階層に属する人々による自由で活気溢れる「人間交際」である。こう見抜いた彼は、この力強い気風を学ぶことによって、単なる技術の導入にとどまらず、西洋に負けない国家体制を築き上げることができるはずだと考えたのです。
それを担う底力がいま(当時)の日本にあるか。福沢は、ある、と考えました。
まずは明治維新によってリストラされ旧士族であり、もう一つは、すでに形成されていた商人階級です。
しかし前者は、多くが旧態依然たる儒教的観念や、家禄を失ったことの不満に満たされていました。また後者は、経済力はあっても私的な実利に汲々としており、公共精神を培うだけの知恵や視野に欠けていました。
そこで福沢は、こうした人民の「潜在能力」をうまく引き出し、それを変形させて、国民一丸となって西洋に負けない国家体制を作り上げるべきだと考えたのです。
ことは単なる技術の導入ではなくそれを作り活用していく精神のあり方の問題でした。
『学問のすゝめ』をはじめとした明治初年代の福沢の仕事の眼目は一つです。
無学の一般人民に、何とか世界の物事を知ることの価値を伝え、これまでの人民を卑屈な精神から脱却させて、お互いの自由な生き方を尊重する気風を作り出すこと。
その場合お手本となるのは、さしあたり進んだ西洋文明であるほかはない。しかし西洋文明は、あくまでも「さしあたり」であって、けっして窮極地点ではありません。
『文明論之概略』に盛られた彼の考えによれば、文明の発展は広大で無限であって、西洋文明もその過渡的な一地点にほかなりません。
長い鎖国の間に遅れを取った日本も、やがてこの暫定的なお手本に追いつくことができるし、追い抜くことができる。追いつくまでは、日本にとって西洋文明をお手本とするが、それは「一手段」にすぎません。
その場合、「目的」は、日本を「国家」として西洋に拮抗できるものに仕立て上げるところに置かれます。
そのかぎりで、まず果たすべきは、旧来の封建的しがらみから国民一人一人が解放されることでした。各人が自分の人生を自由に追求する権利を獲得することは、彼の願ってやまないところでした。
彼は権威を否定したのではなく、自由を不当に拘束する権威「主義」を否定したのです。
しかしその「自由」にしても、福沢は、その必要を説いた後に、必ず、人に迷惑が及ぶようなわがままに陥らないように、それぞれの「分」に応じて、責任をまっとうすべきことを付け加えるのを忘れていません。
《人の天然生まれつきは、繋がれず縛られず、一人前の男は男、一人前の女は女にて、自由自在なる者なれども、ただ自由自在とのみ唱えて分限を知らざれば、わがまま放蕩に陥ること多し。すなわちその分限とは、天の道理に基き、人の情に従い、他人の妨げをなさずして我一身の自由を達することなり。自由とわがままとの界は、他人の妨げをなすとなさざるとの間にあり。》(『学問のすゝめ』初編)




















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます