「川柳 くすのき」125号 (H30.4.1)に発表されたものを転載します。なお、同掲載は縦書きで、改行も原稿どおりではありません。編集も少し変えてあります。
凛として 女として 火と水を意識した
西郷かの女(さいごうかのじょ) 1928年(昭和3年)~2014年(平成26年)
黒川 孤遊
新潟県十日町市は豪雪の町である。2㍍を越える雪が降る。この町で86年の生涯を閉じた。「現代川柳『新思潮』」128号の巻頭句が最後の作品。
凛として眉あげていますとも
乱れてはならぬならぬと夏木立
体調がすぐれぬ自分への叱咤とも思える句が目を引く。昭和28年ごろ川柳を知り、後に川上三太郎に師事。いらい60数年を川柳と歩んだ。学業で東京に住んだだけで帰郷、水月寺に嫁いだ。そのころの句だろう。
しきたりの違う鰯を焼いている
花一輪動かしている嫁姑
寺の妻 箒の先の沙羅双樹
最初の句集は「輪廻」(昭和33年)第二句集「凡夫青天」(平成4年)。そして平成26年の「冬の陽炎」(あざみエージェント刊)が最後の句集となった。14、5年前から体調を崩し、入退院を繰り返していたが「冬の陽炎」の最終ページには
ほのぼのと灯る私の現在地
前ページには
いのち燃えつきる日の花筏
一片のはなびらとなりさようなら
と「その日」へ到るのを見据えた句をもってきている。そして
病み臥して合せ鏡を遠ざけり
蝉の一生私の一生風ばかり
墓碑銘はまだ決まらない芒の穂
これらからは、病にありながら川柳を手放さなかった凛とした姿が読み取れる。
かの女には「火」「水」の句が目に付く。
水を汲み火をくべ今日を乱れまじ
廊下隔てて水のいのちと火のいのち
火も水も私の橋を渡れない
こっそりと梯子を降りる炎を抱いて
新思潮の矢本大雪は追悼文で「火は、自らの性ゆえに、絶えず対極にある水を思わずにはいられない。水は火を意識しないが、火は水を強く意識する(中略)内側に燃え盛っていた炎をさらすことなく、句の中で披歴することだけが彼女の矜持だったのだ」と述べている。
一方でこんな句もある
我儘な花をいっぱい飼いながら
驚くな虫百匹を従えて
行きまする足袋の小鉤ももどかしく
生きて物狂いとならむ乱れ髪
かの女が主宰した十日町川柳研究社代表、松田ていこは「川柳も外見も芸術品だった。そして子どものようなかわいらしい一面もあった」と話す。言い換えると「世離れした女」だったのだが、そこからうかがうことのできない「情熱的な女」がいたのだ。
水月寺前、智泉寺の一角に師・三太郎の句碑「しらゆきが くるくる ふるさとの さけぞ」が立つ。かの女が十日町の仲間と建立したものだ。三太郎はかの女を「敏感にして暢然」と評したという。
資料を整理していると、かの女が何かに書いていたのをメモしたものがあった。
「多くの川柳人は始めは時事川柳その他の新聞川柳から入門してきた人が多いが、これらの川柳に満足できなくなる。ここで初めて自分の川柳の進むべき道を考える。難解句も三度読んでみると作者の意図するものが大いに解るし、解らなければ感じればよいと思う。読者と作者の想いが違っていても、それでいいのではないか」
「新思潮」の追悼欄に「愛着の一句」として紹介さている句は
あの星の隣の星になりたくて
















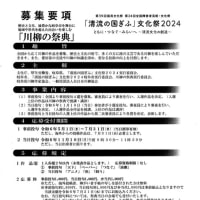
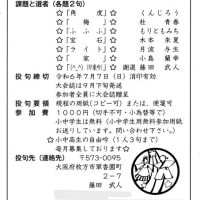

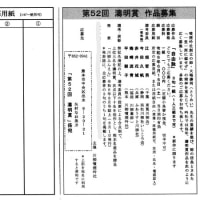
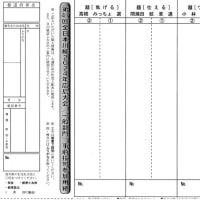
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます