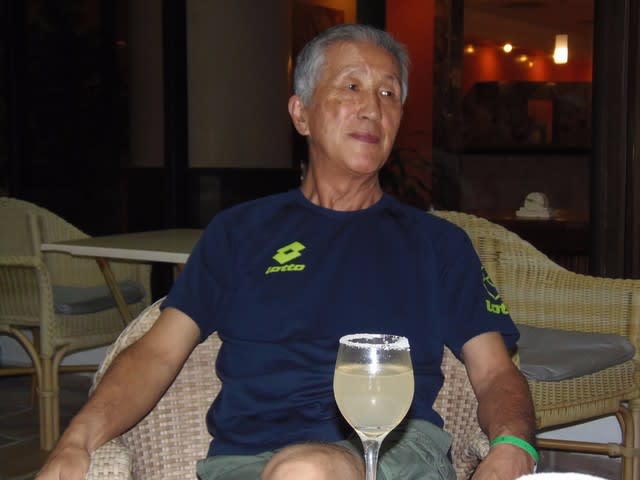キューバに行ったという話をすると、「なんでキューバ?」と問われることが多い。
うーむ、話してもわからんだろうなぁ、というのがあって、
2つある理由のうち、一つだけを理由にすることが多い。
それは、何割かの旅行者に共通する「今のキューバを見ておきたいから」ということだ。
1997年に初めてベトナムを旅行したとき、一番心に残ったのがホイアンの町だった。
旅行者もまばらで、土産品店もそれほど多くなく、人々は素朴そのものだった。
それから数年の後、再び訪れたホイアンは激変していた。
世界遺産の指定という理由もあっただろうが、膨れ上がった数の旅行者、町中にあふれる土産品店。
至る所にあるレストランやカフェ。
観光客相手の人々の目は、人よりもその財布の中身を計っているような目である。
市場や食堂でのんびりと私たちの相手をしてくれた人々はどこへ行ったのか。
あまりの変化に私たちはすっかり悄気てしまった。
その後三度目のホイアンに行ったが、状況はますます悪くなっていた。
町は祭りのように飾られ、ギャラリーまで至る所に店を開いていた。
既にホイアンは、旅行者の郷愁を誘う町ではなくなっていた。
ホイアンは消えたのだ。
2011年、「今のミャンマーを見に行こう」と友人夫妻と4人でミャンマーに行った。
軍事政権の終焉に伴う各国の制裁解除によって、ミャンマーが激変するのは間違いなく、
今だったら、ホイアンの二の足を踏まずに済むのではないかという思いがあった。
確かに、以前訊ねたミャンマーの面影は濃く残っていて、
人々は親切で、にこやかに接してくれた。
アメリカと国交回復したキューバもまた、観光客が激増し、
それに伴って、その客たちが落とす金を巡って人々のあり方が変わるだろう。
そうなってからでは、社会主義国家のキューバに出会うことはできないだろう、
ホイアンやミャンマーと同じく怒濤の如く変わるのではないか。
そういう危惧を抱いて、「今日のキューバを見に行った」のである。

ハバナの通り
もう一つの理由は、遡ること50年近く、まだ学生の時。
中南米研究会というサークルに所属していた時に、
年1回出版したサークル誌「図南」に初めて寄稿した文が「キューバ革命」だったことに発している。
学生運動盛んなりし頃、全くのノンポリだった私だったが、
「革命」という言葉には何故か魅力を感じていた。
ただ学生のいう革命は、主張を聞く限り自己満足にしか思えず、
それなりに満たされている今の日本で、「革命」を叫ぶのには違和感があった。
その頃、中南米研究会でキューバ革命の存在を知り、これこそが革命だと思ったのである。
バティスタ政権を打倒して、貧困と搾取に苦しむ人々のために国を変える。
カストロとゲバラは一躍私の中で英雄となり、それをきっかけに一度はキューバと思ったのだ。
こういうといかにも学生運動に傾斜していたように見えるが、
先に書いたように全くのノンポリだった。
旗振りも角棒も全く経験はなく、毎日サークルの部室で駄弁っていたのである。
中南米研究会も全く政治的色彩のないサークルだった。

トリニダーの葉巻屋さん
今回行ってみて、一つだけ思ったことがある。
キューバは世界で唯一まともな社会主義国家であると私は思っている。
北朝鮮はただの独裁国家だし、中国も今その道を歩もうとしている。
教育や医療費が無料というキューバの社会主義も、
だんだん崩れていくだろうという予兆はある。
大きな外貨獲得策である観光客誘致に関する諸政策が、
その恩恵に預かるか否かで貧富の差を生み、
貧富の差は政治に不満を生み、今でも既にそうではないが、
やがて皆が平等であることは崩れ去ってしまう。

トリニダーの高校生かな?
社会主義国家とというのは、皆が等しく貧乏であることを受容するとき、
初めて成立する制度なのかも知れない。
物質の豊かさや便利さを享受する平等というのはあり得ない。
物欲に目覚めた人の欲は留まることを知らないからだ。
何を持って幸せと思うのか、その価値観が変わらない限り社会主義体制は決して根付かないという気がする。
キューバを思って50年。この世界は激変した。
私の思いも、キューバという国家もまた変わらずにはいられないのだ。
うーむ、話してもわからんだろうなぁ、というのがあって、
2つある理由のうち、一つだけを理由にすることが多い。
それは、何割かの旅行者に共通する「今のキューバを見ておきたいから」ということだ。
1997年に初めてベトナムを旅行したとき、一番心に残ったのがホイアンの町だった。
旅行者もまばらで、土産品店もそれほど多くなく、人々は素朴そのものだった。
それから数年の後、再び訪れたホイアンは激変していた。
世界遺産の指定という理由もあっただろうが、膨れ上がった数の旅行者、町中にあふれる土産品店。
至る所にあるレストランやカフェ。
観光客相手の人々の目は、人よりもその財布の中身を計っているような目である。
市場や食堂でのんびりと私たちの相手をしてくれた人々はどこへ行ったのか。
あまりの変化に私たちはすっかり悄気てしまった。
その後三度目のホイアンに行ったが、状況はますます悪くなっていた。
町は祭りのように飾られ、ギャラリーまで至る所に店を開いていた。
既にホイアンは、旅行者の郷愁を誘う町ではなくなっていた。
ホイアンは消えたのだ。
2011年、「今のミャンマーを見に行こう」と友人夫妻と4人でミャンマーに行った。
軍事政権の終焉に伴う各国の制裁解除によって、ミャンマーが激変するのは間違いなく、
今だったら、ホイアンの二の足を踏まずに済むのではないかという思いがあった。
確かに、以前訊ねたミャンマーの面影は濃く残っていて、
人々は親切で、にこやかに接してくれた。
アメリカと国交回復したキューバもまた、観光客が激増し、
それに伴って、その客たちが落とす金を巡って人々のあり方が変わるだろう。
そうなってからでは、社会主義国家のキューバに出会うことはできないだろう、
ホイアンやミャンマーと同じく怒濤の如く変わるのではないか。
そういう危惧を抱いて、「今日のキューバを見に行った」のである。

ハバナの通り
もう一つの理由は、遡ること50年近く、まだ学生の時。
中南米研究会というサークルに所属していた時に、
年1回出版したサークル誌「図南」に初めて寄稿した文が「キューバ革命」だったことに発している。
学生運動盛んなりし頃、全くのノンポリだった私だったが、
「革命」という言葉には何故か魅力を感じていた。
ただ学生のいう革命は、主張を聞く限り自己満足にしか思えず、
それなりに満たされている今の日本で、「革命」を叫ぶのには違和感があった。
その頃、中南米研究会でキューバ革命の存在を知り、これこそが革命だと思ったのである。
バティスタ政権を打倒して、貧困と搾取に苦しむ人々のために国を変える。
カストロとゲバラは一躍私の中で英雄となり、それをきっかけに一度はキューバと思ったのだ。
こういうといかにも学生運動に傾斜していたように見えるが、
先に書いたように全くのノンポリだった。
旗振りも角棒も全く経験はなく、毎日サークルの部室で駄弁っていたのである。
中南米研究会も全く政治的色彩のないサークルだった。

トリニダーの葉巻屋さん
今回行ってみて、一つだけ思ったことがある。
キューバは世界で唯一まともな社会主義国家であると私は思っている。
北朝鮮はただの独裁国家だし、中国も今その道を歩もうとしている。
教育や医療費が無料というキューバの社会主義も、
だんだん崩れていくだろうという予兆はある。
大きな外貨獲得策である観光客誘致に関する諸政策が、
その恩恵に預かるか否かで貧富の差を生み、
貧富の差は政治に不満を生み、今でも既にそうではないが、
やがて皆が平等であることは崩れ去ってしまう。

トリニダーの高校生かな?
社会主義国家とというのは、皆が等しく貧乏であることを受容するとき、
初めて成立する制度なのかも知れない。
物質の豊かさや便利さを享受する平等というのはあり得ない。
物欲に目覚めた人の欲は留まることを知らないからだ。
何を持って幸せと思うのか、その価値観が変わらない限り社会主義体制は決して根付かないという気がする。
キューバを思って50年。この世界は激変した。
私の思いも、キューバという国家もまた変わらずにはいられないのだ。