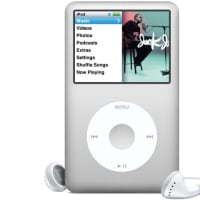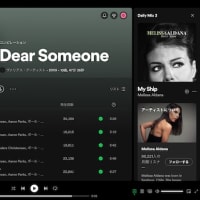相変わらず見えない攻撃のロジック
物を書く人間は「炭鉱のカナリアだ」とよく言われる。実際、「ガスだ。毒ガスだ!」と小生などは毎度騒いでばかりいる。昔はともかく、今ではサッカーはもっぱらテレビ観戦しかしていないというのにアレだが。
で、森保ジャパンが先日行ったオランダ遠征での国際親善試合、カメルーン戦、コートジボワール戦の分析をまとめてみよう。
まず選手別では、吉田や冨安らディフェンスラインの選手を中心に頼もしさが光った。一方、オフェンスでは、相変わらずチームとして何をやりたいのかが判然としなかった。
世間はあのコートジボワール戦終了間際の鮮やかな「サヨナラゴール」にすっかり浮かれ、いわば洗脳されて「バンザイ、よかった」と騒いでいる。だが、ここは冷静かつ客観的に事態を見る必要があると思うのだ。
守備陣の健闘が光った
まず選手別では、あげられるのは守備陣だ。すでに書いた通り吉田と冨安、酒井宏はすばらしいデキだった。
特に冨安はディフェンスだけでなく、ドリブルでボールを持ちあがり要所にパスをつけるなど戦術眼が光った。
また中盤の守備に目を移すと、セントラルMF(アンカー)を務めた遠藤航もよかった。敵の攻撃の芽を潰すプレッシングと競り合い。インテンシティが高く、バイタルエリアを埋めるポジショニングもよかった。
このディフェンスラインとアンカーを結ぶ正三角形のゾーンは重要であり、かつそこを安心して見られたのは大きい。守備の安定はチームの安定。まずはめでたしである。
伊東はレギュラー取りに名乗りを上げた
また右のWBとSHを務めた伊東も、スピードとドリブルで違いを見せた。右サイドに一本、芯が通り、右の大外のレーンは攻めの拠点になった。
特に彼を右WBに使った3-4-2-1は重要なオプションになるのではないか? と感じた。ただ注文をつけるとすれば、伊東にはクロスの精度をもっと磨いてほしい。
かたや、コートジボワール戦でトップ下としてスタメン出場した鎌田もまずまずだった。
彼は2ライン間で巧みにボールを受け、フィニッシュまでもって行ける。あとはインテンシティの高さがもう少しほしい。攻撃の際はもちろん、守備のときもだ。
森保ジャパンは「何をやりたい」のか?
さて一方、チーム全体の「かたち」のほうは相変わらず曖昧模糊としている。
基本になるフォーメーションが4-2-3-1であることはもちろんわかるが、ゲームモデルはよくわからないし、個々のプレー原則もハッキリしない。特に攻撃のときだ。
これは別に2試合を通しセットプレイの1点しか取れなかったから、そういっているわけじゃない。
たとえば巧妙なポジショナルプレイでボールを保持し敵を圧倒して勝つのか?
それとも前線でボールを失えばいっせいに敵に襲いかかり、高い位置でボールを即時奪回してショートカウンターを放つのか?(つまりストーミングだ)。
森保ジャパンのサッカーは、こんなふうにはっきりカテゴライズできないのである。
ストーミング志向かと思ったが……
いや森保ジャパンの立ち上げ当時、前でボールロストするとワントップの大迫と2列目の三銃士(中島、南野、堂安)が激しくストーミングを展開していたので、てっきりあれが「森保監督のサッカー」なのだと思っていた。
だが違ったようだ。なぜなら森保ジャパンは、選手が変わればまったく別のサッカーになるからだ。よくいえば先代の西野ジャパンに学び、選手の自主性を尊重している。
悪くいえば選手まかせのサッカーだ。
これは私がそう言っているだけじゃない。
監督がベースを、オプションは選手が
たとえば10月17日にウェブ配信された「デイリー新潮」の記事で、元「サッカーダイジェスト」編集長の六川亨氏は今回のオランダ遠征について以下のようにいう。
『そんな森保監督が目指すサッカーのコンセプトは、1年ぶりの代表マッチと練習でも「新たに伝えるコンセプトはない」とした上で、「チームにはベースがあってオプションがある。問題を解決、修正能力のあるのが強いチーム」と考え、「ベーシックな部分を伝えたうえで、オプションは選手が話し合った上で変えていって欲しい」と、選手の自己判断を尊重するスタイルである』
森保監督は「ベースは伝えるが、オプションは選手が自分でアレンジせよ」ということらしい。
だが上に書いた通り、そもそもその「ベースにしているスタイル」がどんなサッカーなのかがよくわからないのだ。ひょっとしたら「ベースなるものの〇割」まで選手まかせなのではないか? などと思ってしまう。
六川氏は続けていう。
『ただし不安がないわけでもない。森保監督はスタッフらと共に綿密なスカウティングにより選手を発掘し、A代表と五輪代表のラージグループを広げてきた。それ自体は悪いことではない。気がかりなのは、いつ選手をセレクトする作業に入り、チームとしての完成度を高めていくのか、なかなか見えてこないことである』
これはチーム作りの工程の話だ。だが私の目には「ベースになるスタイル」自体が見えてこないし、もちろん「工程」も見えてはこない。
監督が大枠を示し、あとは現場判断
他方、サッカージャーナリストの西部謙司氏も、新著『戦術リストランテⅥ』(ソル・メディア)で、「森保監督のチームは作り込んでいない。理由は何か?」と問われてこういう。
『私はわざとだと思います(中略)。要はやろうと思えばできる監督なんですよ(中略)。今の日本はピッチ上の選手はほぼ欧州組でみんな最先端のサッカーを知っている。大枠の方針だけ示して、あとは現場の判断で柔軟に対処すればいいという考えなのかなと』
前述の六川氏同様、「監督が大枠だけ示してあとは現場の判断」だと分析する。
ちなみに両氏とも、あくまで現状を客観的に分析しているのであり、「このやり方に賛成だ」と言ってるわけじゃない(疑問も呈しているが、賛成とも反対とも言ってない)
「現在地」を深刻に考えるべきだ
監督が骨格を示し、細部は選手が自主的に考えろーー。
別に悪い考えじゃない。
だが森保ジャパンの立ち上げから、今回のオランダ遠征までもう「どれぐらいの時間がたった」か?
そして現在地はどうか?
つまりオランダ遠征で日本代表が繰り広げた、あのギクシャクしたスムーズさのない攻撃のままで果たしていいのか?
そう考えれば、おのずと答えは出ているような気がするのだが。
物を書く人間は「炭鉱のカナリアだ」とよく言われる。実際、「ガスだ。毒ガスだ!」と小生などは毎度騒いでばかりいる。昔はともかく、今ではサッカーはもっぱらテレビ観戦しかしていないというのにアレだが。
で、森保ジャパンが先日行ったオランダ遠征での国際親善試合、カメルーン戦、コートジボワール戦の分析をまとめてみよう。
まず選手別では、吉田や冨安らディフェンスラインの選手を中心に頼もしさが光った。一方、オフェンスでは、相変わらずチームとして何をやりたいのかが判然としなかった。
世間はあのコートジボワール戦終了間際の鮮やかな「サヨナラゴール」にすっかり浮かれ、いわば洗脳されて「バンザイ、よかった」と騒いでいる。だが、ここは冷静かつ客観的に事態を見る必要があると思うのだ。
守備陣の健闘が光った
まず選手別では、あげられるのは守備陣だ。すでに書いた通り吉田と冨安、酒井宏はすばらしいデキだった。
特に冨安はディフェンスだけでなく、ドリブルでボールを持ちあがり要所にパスをつけるなど戦術眼が光った。
また中盤の守備に目を移すと、セントラルMF(アンカー)を務めた遠藤航もよかった。敵の攻撃の芽を潰すプレッシングと競り合い。インテンシティが高く、バイタルエリアを埋めるポジショニングもよかった。
このディフェンスラインとアンカーを結ぶ正三角形のゾーンは重要であり、かつそこを安心して見られたのは大きい。守備の安定はチームの安定。まずはめでたしである。
伊東はレギュラー取りに名乗りを上げた
また右のWBとSHを務めた伊東も、スピードとドリブルで違いを見せた。右サイドに一本、芯が通り、右の大外のレーンは攻めの拠点になった。
特に彼を右WBに使った3-4-2-1は重要なオプションになるのではないか? と感じた。ただ注文をつけるとすれば、伊東にはクロスの精度をもっと磨いてほしい。
かたや、コートジボワール戦でトップ下としてスタメン出場した鎌田もまずまずだった。
彼は2ライン間で巧みにボールを受け、フィニッシュまでもって行ける。あとはインテンシティの高さがもう少しほしい。攻撃の際はもちろん、守備のときもだ。
森保ジャパンは「何をやりたい」のか?
さて一方、チーム全体の「かたち」のほうは相変わらず曖昧模糊としている。
基本になるフォーメーションが4-2-3-1であることはもちろんわかるが、ゲームモデルはよくわからないし、個々のプレー原則もハッキリしない。特に攻撃のときだ。
これは別に2試合を通しセットプレイの1点しか取れなかったから、そういっているわけじゃない。
たとえば巧妙なポジショナルプレイでボールを保持し敵を圧倒して勝つのか?
それとも前線でボールを失えばいっせいに敵に襲いかかり、高い位置でボールを即時奪回してショートカウンターを放つのか?(つまりストーミングだ)。
森保ジャパンのサッカーは、こんなふうにはっきりカテゴライズできないのである。
ストーミング志向かと思ったが……
いや森保ジャパンの立ち上げ当時、前でボールロストするとワントップの大迫と2列目の三銃士(中島、南野、堂安)が激しくストーミングを展開していたので、てっきりあれが「森保監督のサッカー」なのだと思っていた。
だが違ったようだ。なぜなら森保ジャパンは、選手が変わればまったく別のサッカーになるからだ。よくいえば先代の西野ジャパンに学び、選手の自主性を尊重している。
悪くいえば選手まかせのサッカーだ。
これは私がそう言っているだけじゃない。
監督がベースを、オプションは選手が
たとえば10月17日にウェブ配信された「デイリー新潮」の記事で、元「サッカーダイジェスト」編集長の六川亨氏は今回のオランダ遠征について以下のようにいう。
『そんな森保監督が目指すサッカーのコンセプトは、1年ぶりの代表マッチと練習でも「新たに伝えるコンセプトはない」とした上で、「チームにはベースがあってオプションがある。問題を解決、修正能力のあるのが強いチーム」と考え、「ベーシックな部分を伝えたうえで、オプションは選手が話し合った上で変えていって欲しい」と、選手の自己判断を尊重するスタイルである』
森保監督は「ベースは伝えるが、オプションは選手が自分でアレンジせよ」ということらしい。
だが上に書いた通り、そもそもその「ベースにしているスタイル」がどんなサッカーなのかがよくわからないのだ。ひょっとしたら「ベースなるものの〇割」まで選手まかせなのではないか? などと思ってしまう。
六川氏は続けていう。
『ただし不安がないわけでもない。森保監督はスタッフらと共に綿密なスカウティングにより選手を発掘し、A代表と五輪代表のラージグループを広げてきた。それ自体は悪いことではない。気がかりなのは、いつ選手をセレクトする作業に入り、チームとしての完成度を高めていくのか、なかなか見えてこないことである』
これはチーム作りの工程の話だ。だが私の目には「ベースになるスタイル」自体が見えてこないし、もちろん「工程」も見えてはこない。
監督が大枠を示し、あとは現場判断
他方、サッカージャーナリストの西部謙司氏も、新著『戦術リストランテⅥ』(ソル・メディア)で、「森保監督のチームは作り込んでいない。理由は何か?」と問われてこういう。
『私はわざとだと思います(中略)。要はやろうと思えばできる監督なんですよ(中略)。今の日本はピッチ上の選手はほぼ欧州組でみんな最先端のサッカーを知っている。大枠の方針だけ示して、あとは現場の判断で柔軟に対処すればいいという考えなのかなと』
前述の六川氏同様、「監督が大枠だけ示してあとは現場の判断」だと分析する。
ちなみに両氏とも、あくまで現状を客観的に分析しているのであり、「このやり方に賛成だ」と言ってるわけじゃない(疑問も呈しているが、賛成とも反対とも言ってない)
「現在地」を深刻に考えるべきだ
監督が骨格を示し、細部は選手が自主的に考えろーー。
別に悪い考えじゃない。
だが森保ジャパンの立ち上げから、今回のオランダ遠征までもう「どれぐらいの時間がたった」か?
そして現在地はどうか?
つまりオランダ遠征で日本代表が繰り広げた、あのギクシャクしたスムーズさのない攻撃のままで果たしていいのか?
そう考えれば、おのずと答えは出ているような気がするのだが。