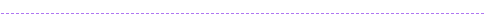高倉天皇は後白河天皇の第7皇子で、
8歳で高倉天皇となり、
20歳で天皇退位。上皇となった。
21歳、高倉上皇は崩御した。
実父(後白河法皇)や義父(清盛)が命じるような感じで
天皇になり、そして退位した。
宮島訪問は、高倉上皇の短い人生の最期の表舞台となった。
・・・
旅の場所・広島県廿日市市宮島町
旅の日・2023年6月10日
書名・平家物語
原作者・不明
現代訳・「平家物語」古川日出男 河出書房新社 2016年発行
・・・
厳島御幸---三歳の新帝誕生
治承四年正月一日。
鳥羽殿には参賀に参る人がありません。
入道相国が朝臣の参賀を許さず、後白河法皇もまた気兼ねなさっていたからです。
二月二十一日。
高倉天皇はべつにこれといったご病気でもいらっしゃらなかったのに
無理にご退位させ申して、春宮が皇位を継がれたのでした。
もちろん入道相国の、「すべては思いのままになるから」となされたこと。
平家一門は、自分たちの時代が到来したぞとばかり、みな大騒ぎです。
高倉天皇は高倉上皇となって、
灯火も減り、宮中警固武士たちも途絶え心細いのでした。
新帝は今年三歳。
幼帝も幼帝。まさに幼君。
「ああ、このご譲位はあまりに時期が早すぎる」

治承四年三月。
高倉上皇が安芸の国の厳島神社へ御幸なさる話が伝わりました。
人々は不審に思いました。
なぜならば、
天皇がご退位になった後の諸社御幸の初めには、
八幡、賀茂、春日などへお出になるのが常の習いでした。
遠い安芸の国までの御幸とは不思議でならないからです。
三月二十九日。
高倉上皇は今年おん歳二十。
お姿はひとしお美しくお見えになるのでした。
鳥羽の草津という船着場からお船にお乗りになりました。

還御---帰路の風雅
三月二十六日。
上皇は厳島へご到着になりました。
入道相国がたいそう寵愛された内侍の邸が上皇の御所となりました。
中二日ご滞在なさって、御経供養や舞楽が行なわれました。
導師は三井寺の公顕僧正であったということです。
この僧正が高座に上り、鐘を鳴らし、表白の詞に
「九重の都を出て、八重の潮路を分け、はるばると参詣なさったおん志しの、忝さ」
と高らかに申されたので、君も、臣も、みな感涙を流されましたよ。
高倉上皇は本社の大宮や客人の宮をはじめ、各社残らず御幸になりました。
それと大宮から五町ばかり山をまわって、滝の宮へもご参詣になりました。
公顕僧正は一首の歌を詠み、その滝の宮 拝殿の柱に書きつけられました。
三月二十九日。
上皇は船出の用意を調えられて帰途に就かれました。
しかし、どうにも風が熟しい。そこでお船を漕ぎ戻させて、厳島のうちの有の浦というところにお泊まりになりました。
上皇はお供の公卿や殿上人におおせになります。
「さあ、皆の者、厳島大明神とのお名残りを惜しんで、作歌しなさい」
そこで少将藤原隆房が詠みましたのは、この一首。
たちかへる
なごりもありの
浦なれば
神もめぐみを
かくる白波

夜半になって波も静まり、あの烈風も収まりましたので、上皇はお船を漕ぎ出させ、
その日は備後の国の敷名の泊にお着きになりました。
今日が何月何日かと申せば、もう四月の一日。
「そうか、今日は衣更えの行なわれる日だ」と、上皇も供奉の人々もそれぞれ都のほうを偲んで、お遊びに興じられます。
四月二十二日。
この日、新帝のご即位の儀式が行われたのです。
安徳天皇でございます。
・・・・