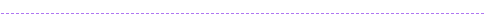昭和6年(1931)の満州事変で、戦時心理が国民に植え付けられ、
昭和12年(1937)の盧溝橋事件で、”国民精神総動員”となり、以後昭和20年まで
戦時体制がつづいていった。
・・・
「福山市史下巻」 福山市史編纂会 昭和53年発行

国民精神総動員運動
日中戦争開始後、近衛内閣が起こした戦争協力の教化運動として有名な国民精神総動員運動は、
県下では昭和12年(1937)10月13日からの第一回国民精神総動員運動週間でスタートを切った。
そして、その後さままざな強調週間が設定され、「一億の心に染めよ日章旗」などという標語を選定するなど、
多彩な行事が繰りひろげられた。
この運動は、「学校生徒児童勿論、男女青年団員、婦人会員、其他一般民衆」を対象とし、
市町村長・学校長・青年団長・婦人会長を推進者として、思想面だけでなく、
衣食住に至るまでさまざまな面から市民生活に統制を加えた。
この地方では、昭和12年10月18日に福山市で国民精神総動員県民大会が開かれ、
翌年2月15日には沼隈郡青年団総動員大会が、2.000人を集めて松永小学校で行なわれた。
運動は人心収攬のために大きな役割を果たしたが、精神運動であっただけに、スローガン倒れに終わったり、
押し付けがましさによる反発も少なくなかった。
・・・
「金光町史・本編」 金光町 平成15年発行
国民精神総動員運動
昭和12(1937)年7月7日、蘆溝橋で日中両軍が衝突、日中戦争が始まった。
これにともない、 岡山県(伊藤武彦知事)は、7月20日県知事諭告(第三号)を発し
「国民心を一つにし、愈忠君愛国精神を発揚し、銃後の支援を完うする」よう県民の奮起を促した。
そうして、同年7月30日、岡山県国民精神総動員実行委員会規程を設けこれを実施することとした。
実行委員には、
官公庁職員、
市町村長、
各種団体代表、
通信報道機関代表、
教育家、
宗教家、
社会事業家、
実業家その他民間有力者が選出されたが、
その運動実施要項の市町村に関する事項には、
実施計画の樹立実行、各種団体の動員、講演会・協議会・映画会等の開催、軍事扶助団体、勤労奉 仕団体等の活動促進が含まれていた。
これと前後して、金光町では、同年7月28日、平田良平町長のもとで緊急町会を町役場で開催、
「充員応召者ならびに鮮満部隊慰問に関する件」を可決した。
時局講演会や映画会、慰問活動などが、この頃から町内でも多くみられるようになり、
日中戦争下町民への教化活動が行われた。
昭和14年11月、岡山県は国民精神総動員運動をさらに拡大強化するため、
市町村・町内各地区・職場などを単位とする実践網組織として、
それぞれ常会を開いて各種協議を行うよう指示し、県下各地で指導者講習会を開催し、趣旨の徹底を図った。
県の指導した常会の組織要項には、
常会月例会の開催、
また常会の組織としては、市町村常会、部落(区) 常会、町内常会などがあった。
町常会は、町長の下で月一回開催、各種委員会関係者、各種団体代表、部落代表者その他指導的人物に集合が掛けられた。
当時の常会では、
特に精神作興(神社参拝、宮城遙拝ほか)、
簡素生活実践(生活の切下、各種儀式の簡素 化、節酒ほか)、
消費節約(節米、燃料節約ほか)、
物資愛護(廃品回収ほか)、その他生産力拡充、勤労増進、 体位向上、戦時貯蓄、銃後後援の徹底などが協議されたことが報告されている。
この時期の常会の慣行は、外形的には戦後の今日まで各区で続けられている。
・・・
「岡山県史第12巻近代」 岡山県 平成元年発行
昭和12年「国民精神総動員運動」の展開
県実行委員会の発足
1937年(昭和12)9月24日、岡山県国民総動員実行委員会が結成され、翌日、委員70人の委嘱が県知事より行われた。
国民精神総動員運動は、日中戦争の全面化にふみきった第一次近衛内閣が国民の思想的統合と団結をはかり、
国民を自発的に戦争体制に動員しようとした思想運動であった。
すでに中央では、9月11日比谷公会堂で政府主催の国民精神総動員大演説会が開かれ、
またその後、10月12日に至って国民精神総動員中央連盟が結成されて全国的に推進されることとなった。
県民130万人を結集し、一大精神運動をはかろうとする同会には、内務省から4574円、文部省から5127円、計9746円が支給され、
委員には
重要官公庁職員17人、
市町村長6人、
貴衆両院議員4人、
県会議員2人、
各団体代表者16人、
通信報道機関代表者5人、
教育家9人、
宗教家4人、
社会事業家4人、
実業家3人、
以上70人であって、表面的には民間人中心の運動という体裁をとっていた。
国民精神総動員週間
1937年10月13日から19日までの一週間、全国的に国民精神総動員週間が設定されて、日本精神の高揚がはかられた。
13日夜には、
岡山市公会堂で講演と映画の会が開かれ、
知事の「国民精神総動員について」
小谷代議士の「北支軍閥の消長を語る」、
呉鎮守府海軍大佐の「今次事変と国民の覚悟」の講演
とニュース映画があり、精神総動員の趣旨が県民に対して強調された。
この強調週間には、県下各地でいろいろな団体による取り組みがなされた。
岡山市連合青年団では、青年団・女子青年団・婦人会が中心となって2.000人の団員を総動員することに決定し、
次の事業を計画・実行した。
すなわち、
13日を「時局生活の日」として時局講演会へ参加する、
14日を「出征将兵へ感謝の日」として正午サイレンを合図に一分間黙禱する、
15日を「非常時経済の日」として金品節約による金を献金する、
16日を「銃後の守りの日」として町内・学区内の遺家族を訪問して家業を補助する、
17日を「報国勇士を讃へるの日」として奥市招魂社に参拝する、
18日を「報国の日」として町内学区内の神社・ 仏閣・街路などの美化作業をする、
19日を「非常時心身鍛錬の日」として学区別に小学校でラジオ体操をする、などの諸事業を行った。
岡山県庁では強調週間に協力するため、知事以下800人の職員が、
毎月一日神社参拝をして皇軍の武運長久を祈る、
毎月一日と十五日を「出征軍人の労苦をしのぶ日」として「日の丸弁当」を用意して生活を簡素にする、
愛国貯金を励行する、など申し合わせて実行することを誓った。
女子義勇隊
1937年11月になると、銃後の守りを強固にする新しい団体として、
女子青年団・婦女子義勇隊の編制と新しい対応人会を統制して市町村単位に女子義勇隊を編制することが行われた。
地域によっては数斑に分け、防空・防火訓練を柱に、平時・戦時両時の構えで公共奉仕の精神と技能を体得することが行われた。
愛国婦人会や国防婦人会も国民精神総動員への対応をはかっていった。
愛国婦人会岡山市分会は11月7日岡山市公会堂で総会を開催し、
日本精神の高揚、非常時における国策遂行の貫徹、銃後における国力の根幹の培養に励むことを宣言し、
夜は出征軍人の慰安会を挙行した。
「非常時突破は銃後から、銃後は婦人の力から」をスローガンに結成された国防婦人会も、
1937年11月には県下に407分会・会員数18万に達し、県下3市・380余町村中で未設置町村は15町村に過ぎなくなっていた。
この間、県内の国婦活動は、
1銃後の守りを堅固にするための婦人国防、
2軍人遺家族の救護、
3傷病兵の慰問、
4出征凱旋勇士の歓送迎などの任務に励んできた。
・・・