5月26日の放送は、冒頭、ジャズ喫茶であった。敷地入り口の木製の看板に“Swifty”と店名。父親の昔のワル仲間(とは言っても、いわゆるヤンキー系の不良ではない)、といった人物がマスターの、登米市内の設定と思われるジャズ喫茶。木材を活かした茶色の内装、膨大な量のレコード(もちろんモノログのLP)が壁を埋め、古いサックスを利用してライトスタンドにして、ひげ面で生成りのシャツ、チノパンのマスターがコーヒーを淹れる。店内の写真を見ると、このマスターは、昔、ジャズのビッグバンドでドラムをたたいていたらしい。
東京だとか、ここから遠い地方を舞台にしたドラマであれば、ああ、型通りの、当時風のジャズ喫茶、と流してしまうところである。田舎町にも、時々こんなもの好きがいるものだ。よくある、紋切り型の場面設定。まあ、東北地方以外のみなさんは、今回もそんなふうに捉えていると思う。ごく一部の、ジャズ喫茶通ともいうべき人々とか、そうだな、小説家村松友視のコアなファンとか、タモリのディープな信奉者とかを除いては。
ところが、私は、今回は、主題歌前のオープニングの場面から、もう涙、涙であった(というか、初回以来、毎回そんなようなものなのだが)。
このシーンは、物語の進行に都合の良いだけの架空のシーンなのではない。
宮城県北、岩手県南の気仙沼、登米、陸前高田、一関、このあたりにはそれぞれの歴史を持つジャズ喫茶が存在している。
登米市には佐沼のエルヴィン、伊豆沼沿い、栗原市分になるコロボックル、気仙沼には、ヴァンガード、今はないガトー、アラベスク、陸前高田のジョニー、そして一関のベイシー。
ジョニーには、照井顕、照井由紀子、ヴァンガードには,故昆野好政、ガトーには故吾妻博、アラベスクには、大内さんというサックス・プレイヤーがいた。みんな、ティーンエイジのころから私の人生に深い足跡を残した人々である。
そして、一関ベイシーには、菅原Swifty正二。正直に言うと、ベイシーには、これまでの生涯、トータルで5回ほどしかお邪魔したことがない。しかし、ベイシーは、なんと言ってもベイシーである。マスターはその昔、早稲田のビッグバンドでドラムをたたいていた。あのカウント・ベイシー本人から、Swiftyというニックネームで呼ばれた。
今回の登米のジャズ喫茶Swiftyは、そういう地域のジャズ喫茶の歴史、独特の風貌をもったマスターたちの人物像、そういったものが複合して融合して、映像作品の舞台として結実したものに他ならない。
内野聖陽の父親の写真が店内に掲載してあった。上半身裸でトランペットを吹く、舞台上の姿である。マスターと内野は、昔、同じバンドでプレイした仲間であった。
内野は、若いころ、音楽を捨てて、ネクタイを締める銀行員となった。(同様に、家業の牡蠣養殖業も捨てた。)
ところで、蛇足かもしれないが、このマスター役の役者さん、どこか、若いころ、国分寺でジャズ喫茶を営んでいた村上春樹をほうふつとさせる、と思う。なんというか、役者として演技している、というよりも、昔プレイヤーであって、今ジャズ喫茶のマスターをしている人物そのものとして存在し得ている。塚本晋也さんという方か。こういう役者というのは、日本のドラマの世界に不可欠な存在である。
このマスターと内野との関係性は、私の好きな、ブレッド&バターの名曲、呉田軽歩つまり松任谷由実作詞作曲の「あの頃のまま」そのものである。こういう関係性は、様々な小説やドラマで繰り返し描かれてきたものだ。
気仙沼に、小中学生のジャズのビッグバンドである、気仙沼ジュニアジャズオーケストラ・スイング・ドルフィンズというものが存在していることは、ご存じない方もいるかとは思う。最近、在籍者が減少して、コロナ禍もあってなかなかご苦労も多いようであるが、リモートも含め年に数回の演奏機会は確保しているという。震災後、アメリカにて演奏する機会もあり、ディズニーランドでの演奏も経験した。再開が見通せないようだが、毎年の仙台の定禅寺ストリート・ジャズ・フェスティバルの常連バンドとして人気を博していた。
第1回目の放送、亀山山頂レストハウス前広場で、内野がトランペットを持ちながら、ジャズを演奏する中学校のブラバン(主人公のモネも在籍していた)の指導をする様子が描かれていた。実際の中学校のブラバンは、ジャズばかり演奏するということはない。
学校の教師ではない社会人の音楽愛好家が指導者を務めるこのブラバンのモデルは、スイング・ドルフィンズにほかならない。そして、内野のモデルは、若いころプロミュージシャンを志し、あるいはずっとアマチュアであって音楽を続けた、気仙沼市内のジャズ・ミュージシャン、スイング・ドルフィンズのスタッフたちに他ならない。あるものは、市役所に勤め、会社勤めし、あるものは家業を継ぎながら、アマチュアとして音楽を続け、子どもたちを指導した大人たち。
内野聖陽のモデルは、半分は、大島の、家業を継がず、まちに勤めに出た父親たちすべてであると同時に、半分は、若いころの演奏活動の後、市役所勤務をしながら、ドルフィンズの会長を務めたピアニスト故佐藤正俊を中心としたスタッフたちである、と言って間違っていないはずである。
私自身は、ジャズというよりもロックであり、プロを目指す道に入ることはなかったのだが、郷里に帰って市役所に勤め、やはり帰郷した友人たちとロックバンドを続けていた。ある時期からは、気仙沼演劇塾うを座という、子どもたちの演劇・ミュージカルの集団のスタッフを務めてきた。(うを座は、昨年来、活動休止中。ちなみに、宮城ことば指導の、フリーアナウンサー佐藤千晶さんは、うを座出身者である。)
内野の演じる父親は、つまり、気仙沼で音楽を続け、子どもたちの活動を支え続けた私たちである、と私自身も含めて言ってしまっては、手前味噌に過ぎるだろうか。
今回の“おかえりモネ”、ジャズ喫茶のことにしろ、子どもたちのジャズ・オーケストラのことにしろ、気仙沼のこと、登米のこと、広く深く調べたうえでドラマ化が進められている。ドラマの進行上は脇道めいたさりげないシーンであっても、地元の人間にとっては必然性のあるシーンばかりで、見逃すことができない、ということになる。
主人公の祖父、藤竜也が山の植樹のシーンで語ることについては、稿を改めることにしたい。










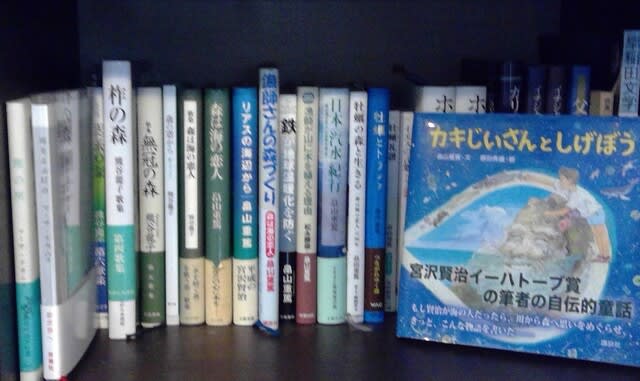










※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます