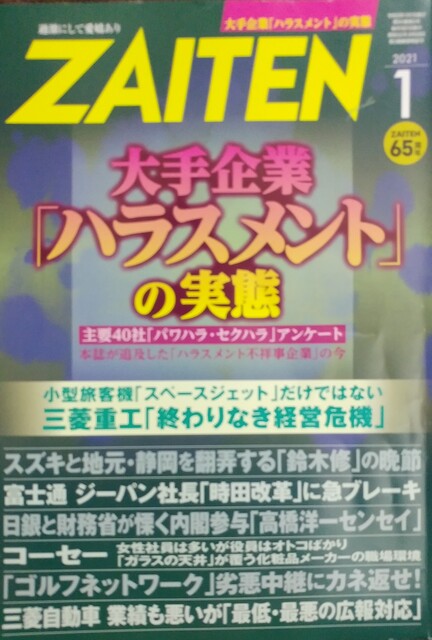■10月1日から「派遣先」に科されるペナルティ
2015年9月11日に改正派遣法(以下「2015年改正派遣法」と呼ぶ)が成立し、9月30日に施行された。
この改正により、派遣法創設以来続けられてきた業務区分による期間制限が、(1)派遣先事業所単位の派遣受入期間の期間制限(原則3年、派遣先の過半数労働組合または過半数代表からの意見聴取を条件として延長可能)、(2)派遣社員個人単位の期間制限(原則3年、派遣会社との雇用契約が無期の場合は制限なし)の2本建てに見直された。
派遣会社に対しては、一部の事業に認められていた届出制が廃止され、許可制に一本化されるとともに、派遣社員の雇用安定化やキャリアアップのための取組が義務化されるなど、大幅に規制が強化されている。派遣先についても、派遣社員と同種の業務に従事する直接雇用の社員との均衡待遇が、「配慮義務」として具体的な行動を求められるようになる等の改正が行われている。
既に施行された2015年改正派遣法について、正しい認識と対応が急がれることはいうまでもないが、もう一つ忘れてはならないのが、本日10月1日に施行される「労働契約申込みみなし制度」である。
これは、派遣先が違法派遣を受け入れた場合、その時点で、派遣先が派遣社員に対して、派遣会社と締結していたのと同じ労働条件で、労働契約の申込みをしたとみなされる制度である。
この制度は、違法派遣を受け入れた派遣先に民事的なペナルティを科すことにより、派遣規制の実効性を確保することを狙いとして、2012年改正派遣法(2012年10月1日施行)に盛り込まれたものである。この制度の施行日が2015年10月1日となっているのは、2012年改正派遣法のなかで、この制度については、施行までに3年間の猶予が設けられた経緯があるためである。
違法派遣の内容としては、次の4つがあげられている。
(1)派遣禁止業務に従事させた場合
(2)無許可の派遣会社から派遣を受け入れた場合
(3)派遣可能期間を超えて派遣を受け入れた場合
(4)派遣法等の適用を免れる目的で、いわゆる偽装請負を行った場合
従来から、(3)については期間制限の基準となる業務区分の定義が、(4)については偽装請負の定義(*1)が曖昧であるとの批判があった。(3)については2015年改正派遣法で業務区分が撤廃されたことに
「知らなかった」では済まされない労働契約申込みみなし制度