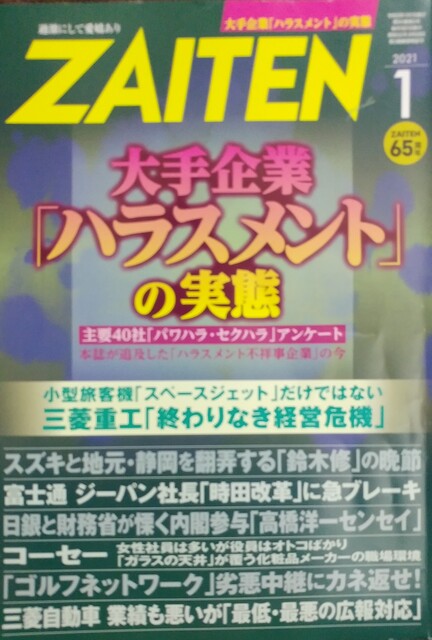連合は7日、東京都内で開催した第14回定期大会で、3期6年の任期を終え退任した古賀伸明会長(63)の後任に、事務局長の神津里季生氏(59)を充てる人事を正式決定した。後任の事務局長には、国内最大の産業別労働組合であるUAゼンセンの逢見直人会長(61)が就任した。
神津会長は大会終了後に記者会見し、重点課題として格差の是正、長時間労働の撲滅、組織の拡大などを挙げた。その上で「社会全体を巻き込み発信力を強めることで、1000万人連合を実現したい」と述べ、組織力強化のため、組合員を1000万人(現在682万人)に増やす
連合、新会長に神津氏就任=「発信力強める」と抱負
神津会長は大会終了後に記者会見し、重点課題として格差の是正、長時間労働の撲滅、組織の拡大などを挙げた。その上で「社会全体を巻き込み発信力を強めることで、1000万人連合を実現したい」と述べ、組織力強化のため、組合員を1000万人(現在682万人)に増やす
連合、新会長に神津氏就任=「発信力強める」と抱負