1.垂木
棟上げが済んで、早く屋根をかけて雨から守りたいところだったが、
ゴールデンウィークに入り、何人かの訪問者があったり、
みかん畑の草刈りをしなければならなかったり、
思わぬ葬式があって、その手伝いがあったりと、
1週間が過ぎてしまった。
垂木は、軒の出を90㎝と長くしたので、45㎜×105㎜と背の高い材を使っている。
棟から軒まで1本で通すと長くて重く、扱いにくくなるのだろうと、
2本に分けることにした。
一の母屋のところで、斜め相欠きで継ぐことに。
背の低い垂木ならそぎ継ぎのようだが、高い垂木はどうするのか
よく分からないので、こうすることにした。

2006年5月8日 垂木掛け
棟上げまでは釘や金物を使わずに組んできたが、これからは釘を多用していくことになる。
釘打ち作業は、進捗が早い。
棟木、母屋、桁に垂木を125㎜の釘で斜め2本打ちする。
これまでに、125㎜と言うような長い大きな釘は、打ったことがなかった。
大きな玄能で大きく振りかぶって、思いっ切り強く打ち込む。

打ち応え充分。

これだけの効きがなければ、屋根が風で飛んでしまうだろう。
節に当たれば、釘が曲がってしまう。
真直ぐに起こして注意深く少しづつ少しづつ打ち込めば、また入っていってくれる。


2006年5月8日 垂木掛け
少し長めに取り付けた垂木の長さを揃えて切る。
30cmほど長めにしていたので、この時には、軒の出は約120㎝あった。
見た目は、軒が深くて家自体のバランスも良く、とても気に入った。

切らずに、このままにしておこうかと思った。
しかし、この長さでは風に耐えられる自信は全くないので、

やはり、計画通りに切ることに。
水糸を張って、一本一本に印をつける。
この大きな断面積の垂木を手のこで切るのは大変だから、電動丸ノコで切ることにしたが、
足場の悪いところで、丸ノコを扱えるのだろうかという不安があった。

ヘタをすれば大ケガだ。

脚立にのって注意深く、注意深く、丸ノコを扱う。
思ったより、うまく切れた。

刻みで修練ができてたのだろうか。

2006年5月9日 垂木の鼻切り 脚立に乗って電動丸ノコを扱う
次々と気持ちよく切り落として、短時間で完了。

合計ちょうど100本の垂木掛けに要した日数は3日。


2006年5月9日 垂木掛け完成 南側より

2006年5月9日 垂木掛け完成 妻側西側より
2.面戸板、広小舞、淀、

今日は朝から雨。
建ち上った骨組みが雨に打たれるのを気にしながら、

屋根下で、面戸板(メンドイタ)広小舞(ヒロコマイ)、淀(ヨド)、の加工。カンナがけや穴あけをする。
面戸板は、軒桁と垂木と野地板との間にできるすき間を埋める板。
1枚1枚寸法を測ってキッチリと収めた

結構メンドーな板だっが、
野地板が済んで屋内から見るとキッチリと収まらずにすき間だらけだった。

このすき間埋めにはあとで苦労させられた。


後で知ったが、垂木に小穴をあけておいて
(小穴というのは、プロが使う言葉で穴ではなく切り欠き程度の溝のことをいう)
面戸板を差し込めば、両サイドのすき間はなくなる。
垂木の加工は、メンドーだが、垂木の背がもっと低くて、
小屋組が天井板で隠れるのなら、このすき間は全く気にならないのだが、
ここでは小屋組部分が現しとなるため、もう少しの工夫が必要だった。

翌日から面戸板のとりつけを始める。
昨日の雨で垂木がふくれており、
晴れの時に寸法取りをして加工した面戸板が入りにくい。
固定は、5寸釘を脳天打ちした。1スパンずつ、脚立を移動させての上り下り作業。
垂木の風による吹き上がりが、気になっていたので、面戸板と垂木を90㎜の釘で連結した。
また妻側の軒は面戸板の替わりに背の低い横木を打ちつけて、垂木と115㎜の釘で連結し、
やはり吹きあがりの防止策とした。
これがどれ程、有効なのかはわからないが。


2006年5月12日 面戸板
広小舞と淀は、垂木の外周にとりつける、縁取り木である。
広小舞を垂木の先へ釘留めする。
垂木の背が高いので苦労なく釘が打てると思っていたが、バウンドしてだめだった。

カケヤで垂木の裏を押さえれば良いと書いてあるので、一人でやろうとしたが、とうてい無理だ。
めんどうだが、仮支柱を立てることに。

2006年5月12日 広小舞の取り付け 仮支柱を立てて
胴縁用材を垂木の先にあてがい、地面と接する方に板切れを敷いて高さを調整する。
これは大正解だった。

とても釘が打ち易い。移動手間はかかるが、慣れれば早い。
妻側へ移り、広小舞を取り付けたら、クネクネと曲がりくねって、とても不細工だ。
垂木に合わせて、取り付けたのが失敗だった。
打ち付けた釘を抜いてやり直すことに。
水糸を張って直線をだすことにした。
妻側は棟の一番高い所まで上っての作業になるので、
水糸を1本張るだけで、上り下りに時間がかかり、作業はなかなか捗らない。

2006年5月12日 妻側の広小舞の取り付け
手間をかけた分だけ、広小舞はキレイに収まった。

続いて淀も取り付ける。

2006年5月14日 広小舞と淀のコーナー部

2006年5月15日 広小舞と淀のコーナー部


面戸板・広小舞・淀完成
3.野地板
野地板は45㎜のすき間をあけて、15㎜のスギ板を上下2枚張る。
小屋裏は現しとするために天井板は張らない。
そのため、この下の野地板が、見上げると見えるので,相欠きとカンナ仕上げをしている。
化粧野地板と呼ぶ。
上の野地板は45㎜×36㎜の垂木を挟み込んで15㎜のスギの荒板を突き付けでとめる。
断熱材は設けない。
雨が気になる。棟上でまでに1回。その後3回。計4回も雨打たせの状態だ。

早く野地板をかけて雨を防ぎたい。木が黒ずんで来る。
下の野地板を貼った時に、ビニールシートをかけたものの、
その後完全に屋根が仕上がるまでに、走り梅雨が来て,7回も雨に降られた。

野地板の長さは、現場合わせとなるため、屋根の上でののこぎり作業となる。
そのことを考えて、野地板は左から右へ張ることに。
板の左端は下で丸のこで切っておいて、上に持ち上げてから垂木に合わせてのこぎりで切り、釘を打つ。
大工が右利きか左利きかによって、この作業位置や順序は大きく違う。
作業能率を上げ、安全でキレイな仕事をするには、このことがとても重要だ。
軒先2枚分は下からはしごで作業し、
3枚目から上は仕上った野地板の上にのって作業をする。

2006年5月15日 化粧野地板張り始め
化粧野地板は、片面のみをカンナ仕上げの指定をしていたが、
相欠きをするとなるとモールダー(切削機械)仕上げでは
両面ともがカンナ仕上げとなるようだ。
入荷した板をみると両面ともキレイに仕上げられ、とても得をしたように思っていたが、

イザ屋根の上へ上げてその上へのると、すべり良いのが難点だった。

6.5寸の勾配はキツイようだ。

ゴム底靴なら滑らずに立っていられるが、
尻をつけて足裏を離すとユルユルと滑り出す。
軒の淀がストッパーの役目をしてくれる。
しかし、上に行くに従い、滑り出せば、滑台のようで止まらない感じがするので、
真中より少し上で、足留めの角材(45×60㎜)を打ち、
安全ロープを張ることにした。
安全ロープは作業時には、邪魔だし、誤ってロープを踏むと滑ってひっくり返りそうになり、
本当に安全かなとも思うが、気持ちの上ではとても安心感がある。


2006年5月15日 化粧野地板張り 安全ロープをつけ、滑り止め材を打ち付けて

化粧野地板張り 安全ロープをつけて
しかし、屋根の上の作業は、気が抜けない。
注意を集中していないと、いつ転落するかわからないので、緊張しっぱなしだ。

それでも、妻は、そんなことには無頓着に、
大した用事もないのに、下から声をかけてくる。
「高い所で作業する時は声をかけてくれるな」
と 言ってあるのに、忘れてしまうのだ。

エライ、迷惑だ。
片面が仕上がったところで、ビニールシートをかけることに。
明日は雨のようだ。

2間×3間のブルーシート6枚をビニールひもと釘で固定。
夜8時頃まで、懐中電灯をつけて作業。
風が吹いて、シートが飛ばされなければ良いが。

残りの片面は、問題なく2日程で完了。

この後は、スペーサーがわりの垂木(45㎜×36㎜)を打って、
上にもう1枚の二段目の野地板を取り付ける。

2006年5月19日 一段目化粧野地板張りを完了後、垂木も打ち終わる
一段目の化粧野地板は、乾燥したものを加工してあったので、扱い易かったが、
二段目の野地板は生木状態のものが多く、乾燥したものに比べると,倍程も重く、
釘を打つと水が飛ぶこともある。
反りも大きく、すき間があいた。それでも問題はなさそうだ。
野地板を下から運び上げては、切って釘で打ちつける。
作業に慣れると、最初よりもずっと早く出来てくる。

2006年5月20日 二段目野地板張り 野地板を担いで運び上げる。

2006年5月21日 二段め野地板張り
それでも、雨にたたられて野地板張り(上下2枚)は8日間を要した


5月22日 2段目野地板張り中の新居と古家の全景
満開のカモミールも枯れてきた頃。

付記 妻・ひろよろ

5月中、夫はほぼ、屋根の上で過ごしていたかもしれない。
高所恐怖症の夫だったが、この頃になると
「慣れとは、エライもんや! 高い所にいても、お尻がムズムズしなくなった」
と、ちょっと得意気だった。

畑にいると、屋根の上の夫は、どこからでも、よく見える。
だから、いつでも、すぐ声がかけやすい。
骨組だけのスケスケの屋根ではなく、野地板を張った屋根の上の夫は、
高い所で、ちょっと、気持ち良さそうに見えたけれど・・・

そうか

やっぱり、まだ、怖がっていたんだ

妻でさえ、なかなか理解しにくい “夫” である。

この屋根作業に使用する、
“何種類かの釘の使用本数リスト”を手渡されて、
金物店へ買い物を、頼まれたことがあった。

プロは、5k箱単位で買うので
店員さんは、本数で買う人には、かなり手間取っていた様子。
家を建てるのに、釘を○百本使うと、
夫は、計算したのだろか


「一人で建てる木組みの家」①~⑫は
こちらから、ご覧ください。
カテゴリー「一人で建てる木組み家」からも、見ていただけます。

 朝夕の冷え込みとは、打って変わり、
朝夕の冷え込みとは、打って変わり、




 カラオケのテレビがセッティングされている様子を見て
カラオケのテレビがセッティングされている様子を見て



 アルコールも入り、一層盛り上がり、
アルコールも入り、一層盛り上がり、




 夕闇に紛れ、夫が、自作の笛を取り出すと
夕闇に紛れ、夫が、自作の笛を取り出すと


 暗くなり、寒くなっても、芋たき会は、続いていました。
暗くなり、寒くなっても、芋たき会は、続いていました。










 芋炊き会に先立つ、“プレイベント” が、
芋炊き会に先立つ、“プレイベント” が、

 誰が絞める
誰が絞める 














 「商売物を、食べて悪いね。損したね」
「商売物を、食べて悪いね。損したね」 産みたて卵ならぬ、産む直前卵を割り、
産みたて卵ならぬ、産む直前卵を割り、 効きそうや
効きそうや 」
」
 芋炊きに先立ち
芋炊きに先立ち

 「えっ、貴重な記録じゃないの?
「えっ、貴重な記録じゃないの? 「おっ、イカが、釣れとるやないか」
「おっ、イカが、釣れとるやないか」

 9月中祭り準備の為、秋の夜釣りができなかった夫は、
9月中祭り準備の為、秋の夜釣りができなかった夫は、















 そういえば、高校の九州修学旅行の時、
そういえば、高校の九州修学旅行の時、
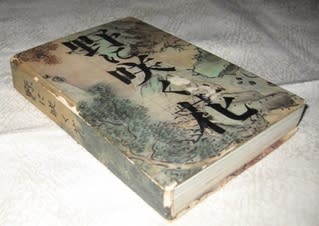





 新居の朝日の昇る東側の妻に、屋根の破風飾りとして、
新居の朝日の昇る東側の妻に、屋根の破風飾りとして、



 破風にある妻飾りをみつけて、Hさんが、
破風にある妻飾りをみつけて、Hさんが、

 」
」
 「私、ハチに刺されたの2回目やから、なんか抗原抗体反応とかで、
「私、ハチに刺されたの2回目やから、なんか抗原抗体反応とかで、 というのも
というのも 

 慣れぬインターネットを検索してくれた。
慣れぬインターネットを検索してくれた。 ・まず、落ち着いて、うろたえないこと
・まず、落ち着いて、うろたえないこと 「ごめんな。お父さん、毒吸ってしまったやん。大丈夫かな」
「ごめんな。お父さん、毒吸ってしまったやん。大丈夫かな」

 実は、 5、6年前、滋賀で、
実は、 5、6年前、滋賀で、



 島の主婦は、完全防備で、農作業をする。
島の主婦は、完全防備で、農作業をする。 マムシでなくて,よかった。よかった。
マムシでなくて,よかった。よかった。














 ぎぇ~、熱帯低気圧が発生してる~~~
ぎぇ~、熱帯低気圧が発生してる~~~  どうぞ、台風に成長しませんように
どうぞ、台風に成長しませんように 
 屋根材を何にするかは大いに迷った。
屋根材を何にするかは大いに迷った。
 知り合いの屋根やさんが言った。
知り合いの屋根やさんが言った。 コリャ、イカン
コリャ、イカン 、妻が言った。
、妻が言った。 ある知人は、
ある知人は、 近所の人は、
近所の人は、 妻に限らず、多くの人が、今もってトタン屋根に反対である。
妻に限らず、多くの人が、今もってトタン屋根に反対である。



 波板を張る前に、しっかり基準線を出しておかないと,
波板を張る前に、しっかり基準線を出しておかないと, さて問題は、張る順番だ。
さて問題は、張る順番だ。






 付記 妻・ひろより
付記 妻・ひろより 夫の屋根材の選択は、
夫の屋根材の選択は、

 厳冬の真夜中、「今晩はサザエが一杯とれるんじゃ」
厳冬の真夜中、「今晩はサザエが一杯とれるんじゃ」 真っ暗な中、グングンと、足場の悪い岩場を歩いていくAさん、
真っ暗な中、グングンと、足場の悪い岩場を歩いていくAさん、 なんでも、遊びに来た孫が
なんでも、遊びに来た孫が 









 一方、Aさんは、
一方、Aさんは、
 オマケに、奥さんのHちゃんからは、
オマケに、奥さんのHちゃんからは、 夫の「一人で建てる木組みの家」は、
夫の「一人で建てる木組みの家」は、






















 結構メンドーな板だっが、
結構メンドーな板だっが、




















