
猫を連れたフォーク歌手ーー『インサイド・ルーウィン・デイヴィス 名もなき男の歌』
越川芳明
アコースティック・ギターの澄んだ響きに煙草の煙。六〇年代のニューヨーク、グリニッジヴィレッジ。売れない芸術家やミュージシャンが安アパートに住んでいる。 フォーク歌手のルーウィン・デイヴィスは、そうした安い家賃さえも払えずに、その日暮らし。友人たちのアパートを転々と渡り歩き、リヴィングのソファーに寝かせてもらう。
一九六一年の〈ガスライト・カフェ〉のライブシーンが印象的だ。ルーウィンが歌うのは、絞首刑になる男のつぶやきを歌った「首を吊るしてくれ」だ。
首を吊るしてくれ ああ 首を吊るしてくれ そうすりゃ オサラバさ もうすぐ死ぬ俺さ 縛り首は構わないが 長いあいだ 墓に横たわる 哀れな男 世界中を渡り歩いた俺さ
これはルーウィンのオリジナル曲ではなく、伝統的な「フォークソング」だ。それでも、あたかも彼のオリジナル曲のように聞こえてくる。人間を善悪の二分法で決めるピューリタン的な発想からは生まれてこない、「犯罪者」の視点の歌だ。神(宗教/倫理観)による「上から目線」ではなく、大衆の「下から目線」で歌われる、まさに人民の歌(ルビ:フォークソング)。
ルーウィンがライブ演奏をおこなうヴィレッジの〈ガスライト・カフェ〉は、暗く湿っぽくボヘミアン的な雰囲気が特徴で、一九五七年にオープンした。バスケットを廻して客に投げ銭をもらう方式で、新進のミュージシャンの登竜門であり、やがてボブ・ディランやホセ・フェリシアーノなども出るようになった。だが、そもそもは、詩「吠える」によって物議を醸すアレン・ギンズバーグら〈ビート世代〉の詩人連中が、パフォーマンスをおこなう店だった。
ルーウィンは、金持ち階級の者たちが住むアップタウンの大学教授の家にもたまに泊めさせてもらっていた。朝、主人のいない家から出て行くときに、教授の猫が外に逃げ出してしまい、なんとか捕まえたものの、玄関のドアはロックされてしまっており、仕方なく教授の愛猫を連れて、また別の友達の家へ向かう。ギターを背負い、片手に足手まといの猫を抱いたルーウィンの姿は、彼の人の好さを表わしていると同時に、前途多難な道を象徴している。
ルーウィンは、起死回生を狙って旅に出る。新人の売り出しに成功しているシカゴのメジャーレコード会社に直接出向いて契約を結ぼうとするのだ。ニューヨークからシカゴまでは、仕事で知り合った男の紹介により、ある二人組の車に乗せてもらう。ガソリン代を折半するという約束だったが、ガソリン代も食事代もたかられる始末。 一緒に旅するのは、相当に変てこな二人組だ。後部座席にどっかと腰をおろしているのは、帽子をかぶり黒めがねをかけた白髭の老人だ。人を見下すようにステッキで肩をつつき、嫌みなことをずけずけとルーウィンに言う。一方、運転手は寡黙な若者で、名前はジョニー・ファイヴといい、老人によれば、彼の「付き人」だという。
あるとき、寡黙なジョニー・ファイヴがぼそっとピーター・オーロフスキーの詩を口ずさむ。
もっと もっと とベッドは泣き叫んだ もっと話して ああ 世界の重さを受けとめたベッドよ あらゆる失われた夢が お前にのしかかる ああ ヘアの生えないベッドよ ファックされない あるいはファックされるベッドよ ああ あらゆる世代のベッドの欠片が お前にこぼれ落ちる
オーロフスキー「私のベッドは黄色に包まれた」(一九五七年)の一節だ。いうまでもなく、オーロフスキーは、五〇年代から七〇年代までギンズバーグのパートナーだったビート詩人。
シカゴのメジャーレーベルの社長、バド・グロスマンがルーウィンの演奏を聴いたあとに、彼に言う。「君は決して下手じゃないが、金の匂いがせんな」と。
コーエン兄弟はなぜ六〇年代の売れないフォーク歌手に焦点を当てた映画を作ったのだろうか。
アメリカの資本主義は、六〇年代以降、過度の情報消費主義へと向かい、歌手も質よりも量(レコードやCDの売り上げ)重視の方向へ向かう。いまや世界は、情報資本主義から金融グローバリズムにまでつき進んできている。
それに対して、「ビートニク」「対抗文化」の思想は、競争よりも協調、自然の征服よりは自然との共生、物質文化よりも精神文化の重視を謳う。 ベトナム戦争後遺症の男を登場させた(『ノーカントリー』や『ビッグ・リボウスキ』)コーエン兄弟らしい、アメリカの主流文化への「ノー!」を、ソフトに、しかし的確に突きつけた映画だ。 (『すばる』2014年4月号)










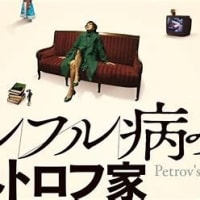
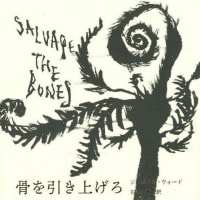

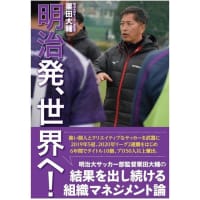












※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます