バランスの悪い家族ーー 柴崎友香『パノララ』
越川芳明
柴崎友香の芥川賞受賞作『春の庭』には、東京・世田谷の洋館が出てくる。かつて写真集になったこともあるというその水色の建物を、近所の古い賃貸アパートに住む主人公は「バランスが悪い」家だと感じる。「一見すると趣と歳月を感じる建物なのだが、しばらく眺めていると、屋根と壁とステンドグラスと塀と門と窓と、それぞれが別のところから寄せ集めたように見えてきた」
本作『パノララ』にも、「バランスが悪い」家が登場する。いや、「バランスの悪さ」では、ずっと過激かもしれない。路地の奥まったところにあるそれは、三種類の構造物からなり、一つはコンクリートの三階建て、そのそばに黄色い木造二階建て、さらにそのそばには、赤い小屋が乗った鉄骨のガレージが、まるでそのつど思いつきで継ぎはぎされたみたいにつながっている。
「それぞれの一階と二階がずれているし、壁が重なっているところも隙間があいているところもある。ブロックで遊んでいて同じ種類のが足りないから別の積み木で継ぎ足した、という感じ」
よく「名は体を表わす」というが、この場合は、「家は人を表わす」というべきか。というのも、「下北沢」という街をモデルにしたとおぼしき「S駅」から徒歩十五分の、この怪獣キメラみたいなへんてこな家には、「寄せ集め」みたいな家族が住んでいるからだ。
住人は父母と三人の子供(といっても、皆もう成人だ)。父・木村将春(ルビ:まさはる)は、小さな建設会社「木村興業」の社長、母・志乃田みすず(本名は正子)はベテラン女優。子供は上から文(ルビ:ふみ)、イチロー(壱千郎)、絵波で、母親がみすずであるのは同じだが、父親は三人とも違う。イチローの父は将春、文の父はみすずが将春と会う前に不倫関係を結んだらしい著名な演出家、絵波の父はイチローが四歳のときにみすずが家出して、一年ほど一緒に失踪していた男(正体不明)といった具合に。
いうまでもなく、この小説のテーマは、「家族とは何か」である。
語り手の「わたし」こと田中真紀子は、いま二十八歳で、関西から東京に出てきて六年になるという。小さな広告企画会社に勤めているが、不安定な非正規雇用者だ。だが、彼女にとって、もっと深刻なのは「過干渉」の母親の存在だ。 真紀子の母親は、ひとり娘のためによかれと思って、着るものから食事、就職、習い事と、なにごとにも口を挟む。その一方で、自分が聞きたくない娘の意見には、無反応を決め込む。娘は、一方的な母親の押しつけを優等生的に聞き入れることで、ストレスや不安を内に溜め込む。そうやってずるずると生きていると、いつまでも自立ができないし、主体的な選択もできない。
つねに相手の言動を気にして、頭の中で自分の言葉を反芻しているうちに、会話が終わってしまう。真紀子の優柔不断な態度が、この小説の自意識過剰な語りの文体に反映している。
たとえば、会社の中で、先輩にあたるかよ子さんに対して反論したくなったときも、「神経質とは言ってないしちょっと違うんじゃないかなと思ったが、うまく説明できそうになかったし、説明することをかよ子さんが望んでいないかもしれないから、言わなかった」
万事、こんな具合なのである。真紀子は母だけでなく、他人に対しても積極的に態度を表明しないし、喜怒哀楽を表に出さない(出せない)。
物語は、真紀子がアパートの更新料が払えなくなり、さほど親しいわけでもないイチローの好意により、木村家の一室(ガレージの上に乗っかった赤い小屋)を安く貸してもらうことから始まる。
彼女は木村家というとんでもない「異世界」に入り込み、そこの住人との交流を通じて、徐々に自立する手だてを学ぶ。確かに、実家の父母とは違って、こちらの父・将春は冬でも暑いと言ってリビングで全裸になってしまうし、母・みすずはロケ撮影や舞台を理由に、まったく家に寄り付かない。天真爛漫というか、無頓着で気のおけない人たちだ。
一方、子供たちにしても、真紀子より二歳年上の文は、中学時代に自傷行為に走ったことがあるらしく、また、大学を出て入った会社も上司によるセクハラで辞めてしまい、その後、ほとんど家にいることになり、そのことに後ろめたさを感じているようだ。そのせいか、家族のために料理だけは力をこめて作る。そのくせ、料理を作った後は皆と一緒に食べずに、自室に閉じこもってしまう。真紀子はそんな文に親近感を持っているが、大学生の絵波は文とほとんど口をきかない。それどころか、文について「不幸顔しちゃって」と、嫌味なことばかり言う。イチローを除いて、木村家の住人はみな相当に「濃い」キャラクターばかりだ。
この小説の白眉は、木村家で暮らし始めてちょうど一年たったある土曜日、悪夢的な出来事がつづくその一日を、ちょうどドラッグでバッドトリップしたみたいに、真紀子が何度もくり返し経験してしまう、最後のほうの数十ページだろう。その日は、母が薬の過剰摂取をして、救急車で病院に運ばれたとの連絡が父からあり、病院に向かうために、S駅のホームで電車を待っていると、送りにきてくれていた絵波が彼女を逆恨みした若者によって線路に落とされてしまう。真紀子は、そんな同じ一日が繰り返し襲ってくるあいだ、そこから抜け出したいと思っているが、なかなか抜け出せない。
それは、真紀子にとっての「通過儀礼」というか、自立のための真の成人式なのかもしれない。木村家は、その「バランスの悪さ」によって真紀子を救う。「バランスの悪さ」というのは、逆にいえば不定形ということであり、フレクシブルに姿を変えられるということである。真紀子が実家からもどってくる(文は金沢へ引っ越しする)ことによって、木村の家族もキメラのごとく形を変えるのだろう。これが「正しい」という家族の形など、初めからないのである。そんなことを考えさせてくれる、バランスのいい小説だった。 (『文学界』2015年3月号)










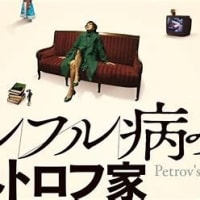
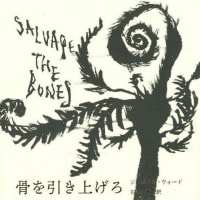

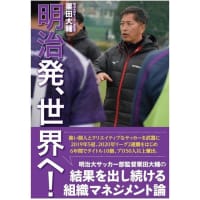












※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます