
「大衆文学読み解く眼力」ーー尾崎俊介『ホールデンの肖像 ペーパーバックからみるアメリカの読書文化』(新宿書房)
越川芳明
「ジャケット買い」と言えば、かつて音楽がレコードの形で売られていた時代に、カヴァージャケットの格好いいデザインや絵を見て、中身を聞かずに買うことを意味した。
著者はアメリカのペーパーバック(廉価版の紙表紙本)を「ジャケット買い」する収集癖があるようだ。そうした収集の合間に、『紙表紙の誘惑』という優れた研究書を上梓してしまった。
通常、学問の大道をゆく学者たちが目を向けたりしない、一見軽薄に見える分野(物語がワンパターンの「ハーレクィン・ロマンス」のような「大衆文学」)の歴史を丹念にひもとき、文学研究の盲点を突く。
本書には、大きく三つの柱がある。
一、ペーパーバック(廉価版の紙表紙本)の出版史、二、イギリスから始まる「ロマンス」史、三、ブッククラブの歴史。
課題へのアプローチの仕方において立派な学者の本だが、それを記述するさいの視点は「上から目線」ではない。たとえば、専門家でない読者に向けて、ページの最下段に丁寧な脚注が付されていて、しかも文章がウィットに富んでいる。隅々まで気配りが効いているのだ。
どの論文やエッセイをとっても、謎解きのように話が展開する。中でも、本のタイトルにもなっている「ホールデンの肖像」というエッセイは、読み応えがある。ペーパーバック版の表紙に描かれた絵めぐる、人気作家サリンジャーと出版社の攻防を論じたものだが、この作家のこだわり(悪く言えば、変質者ぶり)がよくわかる。その他にも、「ハーレクィン・ロマンス」とフェミニズムとの戦いの歴史を丁寧に跡づけたエッセイや、テレビ番組「オプラ・ブッククラブ」に象徴される、文学を商売に変えるアメリカ的な「錬金術」を論じるものなど、まさに目から鱗が落ちるものばかり。
優れた著述家になくてはならない鋭い観察力や、借り物ではない知識がどのエッセイにもにじみ出ている。乾いた喉をうるおすグラス一杯の冷水のように、読後感が心地よい。 (『北海道新聞』2014年1月11日)










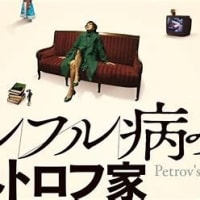
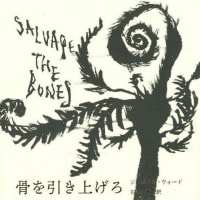

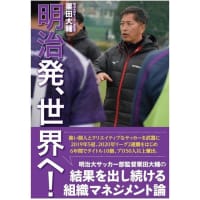












※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます