
一度結んだ縁は切れない。
書評 瀬戸内寂聴『奇縁まんだら』
越川芳明
『日経新聞』の人気連載エッセイ「奇縁まんだら」は、著者と文豪たちとの交流がユーモアのある落ち着いた口調で語られていて、週一回の掲載を待ち焦がれていた人は僕以外にも多いはずだ。
今回の本は最初の一年分、二十一名の作家たちとの出逢いをまとめたもの。横尾忠則による作家たちのシュールな肖像画も数多く収録され贅沢な作りになっている。
著者の生まれたのは、関東大震災の一年前、大正十一(一九二二)年。この本に取りあげられた作家は、島崎藤村、正宗白鳥、川端康成をはじめ大半が明治生まれで、遠藤周作と水上勉だけが唯一大正生まれ。すでに全員この世に生はない。
著者は冒頭でこう言う。
「生きるということは、日々新しい縁を結ぶことだと思う。数々ある縁の中でも人と人との縁ほど、奇なるものはないのではないか」と。
文豪たちについて、奇縁に彩られた面白いエピソードは枚挙に暇がない。学友に連れていってもらった能楽堂で見かけた藤村の小説家としての美しい素顔、川端康成が試みようとしていた源氏物語の現代語訳、毎月の仕事の重みを実感するために原稿料は振込では駄目だという、舟橋聖一の忠告、稲垣足穂から机を貰う「机授与式」の顛末、北京でみつけた宇野千代の徳島の人形師をめぐる小説によって、小説家としての目を開かされたこと、今東光から法名「寂聴」を貰った経緯、小説家など辞めて、小説家など辞めて天才画家(自分)の弟子になれといった岡本太郎の自信、女流文学者の宴会で、阿波踊りを踊りなさい、と命じた最後の「女文士」の平林たい子の貫禄など。
とりわけ、錯綜した男女関係を扱った谷崎潤一郎と、佐藤春夫にまつわる逸話が断然面白い。影の主役である妻たちを登場させているからだ。
著者は若い頃に編集者として、原稿の依頼をしに直接谷崎の家に出かけていき、谷崎が不倫の末に獲得した松子夫人に会っている。「はあ。そらご苦労さんですなあ。でもうちは今、仕事たんとかかえておりまして」と、夫人に体よく断られている。「ああ、この口調が大谷崎の心を射抜いたのだな、と私はうっとりした」と、著者は記す。
本書は、作家によるただの回想録ではない。著者をこれまで小説家として生きさせてくれた「仏縁」への感謝の心が根底に流れているからだ。
「一度結んだ縁は決して切れることはない。そこが人生の恐ろしさであり、有難さでもある」
『エスクァイア』2008年7月号
書評 瀬戸内寂聴『奇縁まんだら』
越川芳明
『日経新聞』の人気連載エッセイ「奇縁まんだら」は、著者と文豪たちとの交流がユーモアのある落ち着いた口調で語られていて、週一回の掲載を待ち焦がれていた人は僕以外にも多いはずだ。
今回の本は最初の一年分、二十一名の作家たちとの出逢いをまとめたもの。横尾忠則による作家たちのシュールな肖像画も数多く収録され贅沢な作りになっている。
著者の生まれたのは、関東大震災の一年前、大正十一(一九二二)年。この本に取りあげられた作家は、島崎藤村、正宗白鳥、川端康成をはじめ大半が明治生まれで、遠藤周作と水上勉だけが唯一大正生まれ。すでに全員この世に生はない。
著者は冒頭でこう言う。
「生きるということは、日々新しい縁を結ぶことだと思う。数々ある縁の中でも人と人との縁ほど、奇なるものはないのではないか」と。
文豪たちについて、奇縁に彩られた面白いエピソードは枚挙に暇がない。学友に連れていってもらった能楽堂で見かけた藤村の小説家としての美しい素顔、川端康成が試みようとしていた源氏物語の現代語訳、毎月の仕事の重みを実感するために原稿料は振込では駄目だという、舟橋聖一の忠告、稲垣足穂から机を貰う「机授与式」の顛末、北京でみつけた宇野千代の徳島の人形師をめぐる小説によって、小説家としての目を開かされたこと、今東光から法名「寂聴」を貰った経緯、小説家など辞めて、小説家など辞めて天才画家(自分)の弟子になれといった岡本太郎の自信、女流文学者の宴会で、阿波踊りを踊りなさい、と命じた最後の「女文士」の平林たい子の貫禄など。
とりわけ、錯綜した男女関係を扱った谷崎潤一郎と、佐藤春夫にまつわる逸話が断然面白い。影の主役である妻たちを登場させているからだ。
著者は若い頃に編集者として、原稿の依頼をしに直接谷崎の家に出かけていき、谷崎が不倫の末に獲得した松子夫人に会っている。「はあ。そらご苦労さんですなあ。でもうちは今、仕事たんとかかえておりまして」と、夫人に体よく断られている。「ああ、この口調が大谷崎の心を射抜いたのだな、と私はうっとりした」と、著者は記す。
本書は、作家によるただの回想録ではない。著者をこれまで小説家として生きさせてくれた「仏縁」への感謝の心が根底に流れているからだ。
「一度結んだ縁は決して切れることはない。そこが人生の恐ろしさであり、有難さでもある」
『エスクァイア』2008年7月号










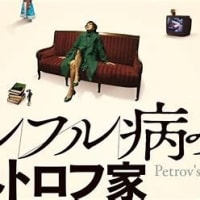
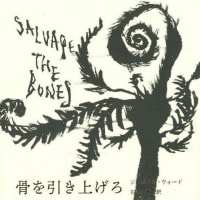

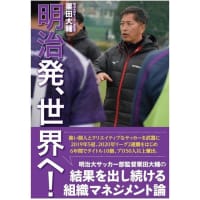












※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます