Far north NSW prepares for floods
原発推進:11大学に104億円 国と関連企業提供、大半は受託研究費--06~10年度より転載
東京大や京都大など11国立大学の原子力関連研究に対し、06~10年度、国や原子力関連企業などから少なくとも104億8764万円の資金が提供されたことが、毎日新聞の集計で分かった。規模の大きな大学は毎年、数億円規模で受け取っている。「原子力推進」に沿う限り、研究資金を安定的に得られる仕組みで、大学が国策に組み込まれている構図が鮮明になった。
各大学への情報公開請求で得た資料を分析した。原子力関連の研究室や研究者が、受託研究▽共同研究▽奨学寄付金▽寄付講座--の形で、国、日本原子力研究開発機構などの政府系団体、電力会社や原子力関連企業から受け取った金額を集計した。未公開部分もあるため、実際にはもっと多いとみられる。
ほとんどは受託研究が占め93億円。特に国からの委託は高額で、文部科学省が福井大に委託した「『もんじゅ』における高速増殖炉の実用化のための中核的研究開発」(5億1463万円、10年度)など億単位も目立つ。
共同研究は総額4億1083万円。企業側が数十万~数百万円を負担することが多い。
奨学寄付金は総額2億1822万円で、研究者が自由に使えるケースも多い。
個人別で最多だったのは、福島第1原発事故直後、当時の菅直人首相から内閣官房参与に任命された有冨正憲・東京工業大教授で1885万円。有冨氏は「持病があり、学会などで海外渡航する際にエコノミークラスが使えず、旅費がかさむ。その点を配慮してくれているからでは」と話す。
企業からの寄付が研究結果をゆがめる恐れについては、「気をつけている。私は安全評価より開発研究が中心で、問題は生じないと思う」と話した。
一方、原発の危険性に警鐘を鳴らし続けてきた京都大の小出裕章、今中哲二の両助教には、「原子力マネー」の提供はなかった。
寄付講座は4大学が電力会社などの寄付で開設し、総額4億9100万円だった。
大学別では、京都大33億640万円、東京大25億5895万円、東京工業大16億7481万円の順だった。【日下部聡】
毎日新聞 2012年1月22日 東京朝刊
東京大や京都大など11国立大学の原子力関連研究に対し、06~10年度、国や原子力関連企業などから少なくとも104億8764万円の資金が提供されたことが、毎日新聞の集計で分かった。規模の大きな大学は毎年、数億円規模で受け取っている。「原子力推進」に沿う限り、研究資金を安定的に得られる仕組みで、大学が国策に組み込まれている構図が鮮明になった。
各大学への情報公開請求で得た資料を分析した。原子力関連の研究室や研究者が、受託研究▽共同研究▽奨学寄付金▽寄付講座--の形で、国、日本原子力研究開発機構などの政府系団体、電力会社や原子力関連企業から受け取った金額を集計した。未公開部分もあるため、実際にはもっと多いとみられる。
ほとんどは受託研究が占め93億円。特に国からの委託は高額で、文部科学省が福井大に委託した「『もんじゅ』における高速増殖炉の実用化のための中核的研究開発」(5億1463万円、10年度)など億単位も目立つ。
共同研究は総額4億1083万円。企業側が数十万~数百万円を負担することが多い。
奨学寄付金は総額2億1822万円で、研究者が自由に使えるケースも多い。
個人別で最多だったのは、福島第1原発事故直後、当時の菅直人首相から内閣官房参与に任命された有冨正憲・東京工業大教授で1885万円。有冨氏は「持病があり、学会などで海外渡航する際にエコノミークラスが使えず、旅費がかさむ。その点を配慮してくれているからでは」と話す。
企業からの寄付が研究結果をゆがめる恐れについては、「気をつけている。私は安全評価より開発研究が中心で、問題は生じないと思う」と話した。
一方、原発の危険性に警鐘を鳴らし続けてきた京都大の小出裕章、今中哲二の両助教には、「原子力マネー」の提供はなかった。
寄付講座は4大学が電力会社などの寄付で開設し、総額4億9100万円だった。
大学別では、京都大33億640万円、東京大25億5895万円、東京工業大16億7481万円の順だった。【日下部聡】
毎日新聞 2012年1月22日 東京朝刊
同じ人物とは思えません。多分この方は偽装日本人でしょう。数年前はシロアリ退治に精を出していたのに、ユッケビビンバとカルビの誘惑には負けてしまい、税金上げろと国民を土壌汚染しています。つまり放射能汚染物質を日本中にまき散らして日本人を殲滅し、日本列島に韓流人種を移住させようと躍起になっているのかな。もちろん白人には顔を殴られてもじーっと我慢の忍の字…消費税を増税し、イラン戦争に協力する二枚舌の日本乗っ取り韓流首相ですね。おそらく
野田総理 マニフェスト 書いてあることは命懸けで実行
野田総理 マニフェスト 書いてあることは命懸けで実行
子どもを被曝から救え! 福島市・放射線汚染地帯の住民が避難プロジェクト開始(1)より転載
- 11/12/21 | 17:00
せめて子どもと妊婦だけでも一時的な避難を――。福島市内でも特に空間放射線量の高い渡利地区で、子どもや妊婦を線量の低い地域へ一時的に避難させるプロジェクトが立ち上がった。
複数の市民団体などで運営する「わたり土湯温泉ぽかぽかプロジェクト」では、一時的な避難を希望する渡利地区の親子を、福島市西部に位置する土湯温泉の旅館に週日や週末滞在させる。現在、土湯にある旅館などと協議中で、まずは1月下旬から3月上旬の実施を目指す。
今回のプロジェクトでは営業中旅館の空室を利用する考えだが、今後は震災後に廃業した旅館を利用する案も出ている。利用者が週日や週末のみ、もしくは通しなど柔軟に宿泊できるプランを想定。渡利~土湯間で往復バスを運行することも検討しており、実現すれば土湯から渡利にある学校へ通うことも可能になる。
3月下旬までに寄付などを通じて宿泊ほかに必要な1000万円を募る方針だが、県や市の助成金制度を利用できないかも探る。
渡利地区の住民が自ら立ち上がった背景には、これまで再三政府に対して避難区域への指定を求めてきたにもかかわらず、認められていないことがある。
同地区では6月に福島市が空間線量を調査したところ、一部地域で毎時3~4マイクロシーベルトという高い線量を記録した。が、その後国も詳細調査を行うものの、避難区域には指定されず、代わりに除染モデル事業の対象となった。

■国際環境NGO FoE Japanが9月に行った調査では依然、空間線量の高い地域があることが判明した
こうした中、住民は政府の調査が一部地域しか対象とならなかったことに加えて、独自で行った調査では除染地区の通学路で高い放射線量が確認されたことなどを理由に、国に対して詳細調査のやり直しや避難区域指定を求めてきた。
10月初旬に一部世帯を対象に説明会が開かれたほか、10月末には業を煮やした住民が東京を訪れて政府に要望書を提出するなどしてきたが、事態は進展していない。
12月20日、プロジェクトについて東京都内で会見を開いた運営団体の1つ、渡利の子どもたちを守る会の菅野吉広代表は「結局国や県や市は動いてはくれないし、今後も(動くことは)ないだろう。子どもたちをこれ以上被曝させるわけにはいかない。子どもたちを被曝の危険から守るためにプロジェクトを立ち上げた」と力を込める。
避難問題は渡利の住民に暗い影を落としている。同地区にある小・中学校の生徒数は合計950人に上る。また未就学児童の4~5割程度は自主避難しているとみられる。
菅野代表によると、自主避難を希望していたとしても、現実的には仕事や経済的な理由で避難したくてもできない世帯が数多くある。また、自主的に避難したものの、避難先で仕事が見つからず、貯金を使い果たしてしまったケースもあるという。
その点から言えば土湯は渡利から車で30分程度の距離のうえ、空間放射線量も毎時0.1~0.2マイクロシーベルトと渡利より大幅に低い。プロジェクト運営主体の1つ、福島老朽原発を考える会の阪上武代表は「避難するには費用や仕事、子どもの転校などハードルがある。が、土湯は渡利から30分程度でそんなに悲壮な決断はしなくていい」と利点を話す。
ただし、あくまで一時避難は「今考えうる最良の選択」(渡利の子どもたちを守る会の菅野代表)にすぎない。今後も引き続き政府に対しては避難区域の指定や疎開の必要性などを訴え続けていく考えで、そのうえで今回のプロジェクトは「政策提言的なプロジェクト」と、運営に参画する国際環境NGO FoE Japanの満田夏花理事は話す。
福島市中心に除染作業が始まる中、除染の効果については懐疑的な見方も多い。また、天候や除染などによって放射性物質が一部に集中し、放射線量が高くなる場所も発生しており、特に子どもを持つ周辺住民にとっては不安な日々が続いている。住民が自ら立ち上げたプロジェクトは一時的ではあれ、こうした「救い」となることは間違いない。
※タイトル横写真:渡利の子どもを持つ世帯の現状について説明する渡利の子どもたちを守る会の菅野代表
(倉沢 美左 =東洋経済オンライン)
- 11/12/21 | 17:00
せめて子どもと妊婦だけでも一時的な避難を――。福島市内でも特に空間放射線量の高い渡利地区で、子どもや妊婦を線量の低い地域へ一時的に避難させるプロジェクトが立ち上がった。
複数の市民団体などで運営する「わたり土湯温泉ぽかぽかプロジェクト」では、一時的な避難を希望する渡利地区の親子を、福島市西部に位置する土湯温泉の旅館に週日や週末滞在させる。現在、土湯にある旅館などと協議中で、まずは1月下旬から3月上旬の実施を目指す。
今回のプロジェクトでは営業中旅館の空室を利用する考えだが、今後は震災後に廃業した旅館を利用する案も出ている。利用者が週日や週末のみ、もしくは通しなど柔軟に宿泊できるプランを想定。渡利~土湯間で往復バスを運行することも検討しており、実現すれば土湯から渡利にある学校へ通うことも可能になる。
3月下旬までに寄付などを通じて宿泊ほかに必要な1000万円を募る方針だが、県や市の助成金制度を利用できないかも探る。
渡利地区の住民が自ら立ち上がった背景には、これまで再三政府に対して避難区域への指定を求めてきたにもかかわらず、認められていないことがある。
同地区では6月に福島市が空間線量を調査したところ、一部地域で毎時3~4マイクロシーベルトという高い線量を記録した。が、その後国も詳細調査を行うものの、避難区域には指定されず、代わりに除染モデル事業の対象となった。

■国際環境NGO FoE Japanが9月に行った調査では依然、空間線量の高い地域があることが判明した
こうした中、住民は政府の調査が一部地域しか対象とならなかったことに加えて、独自で行った調査では除染地区の通学路で高い放射線量が確認されたことなどを理由に、国に対して詳細調査のやり直しや避難区域指定を求めてきた。
10月初旬に一部世帯を対象に説明会が開かれたほか、10月末には業を煮やした住民が東京を訪れて政府に要望書を提出するなどしてきたが、事態は進展していない。
12月20日、プロジェクトについて東京都内で会見を開いた運営団体の1つ、渡利の子どもたちを守る会の菅野吉広代表は「結局国や県や市は動いてはくれないし、今後も(動くことは)ないだろう。子どもたちをこれ以上被曝させるわけにはいかない。子どもたちを被曝の危険から守るためにプロジェクトを立ち上げた」と力を込める。
避難問題は渡利の住民に暗い影を落としている。同地区にある小・中学校の生徒数は合計950人に上る。また未就学児童の4~5割程度は自主避難しているとみられる。
菅野代表によると、自主避難を希望していたとしても、現実的には仕事や経済的な理由で避難したくてもできない世帯が数多くある。また、自主的に避難したものの、避難先で仕事が見つからず、貯金を使い果たしてしまったケースもあるという。
その点から言えば土湯は渡利から車で30分程度の距離のうえ、空間放射線量も毎時0.1~0.2マイクロシーベルトと渡利より大幅に低い。プロジェクト運営主体の1つ、福島老朽原発を考える会の阪上武代表は「避難するには費用や仕事、子どもの転校などハードルがある。が、土湯は渡利から30分程度でそんなに悲壮な決断はしなくていい」と利点を話す。
ただし、あくまで一時避難は「今考えうる最良の選択」(渡利の子どもたちを守る会の菅野代表)にすぎない。今後も引き続き政府に対しては避難区域の指定や疎開の必要性などを訴え続けていく考えで、そのうえで今回のプロジェクトは「政策提言的なプロジェクト」と、運営に参画する国際環境NGO FoE Japanの満田夏花理事は話す。
福島市中心に除染作業が始まる中、除染の効果については懐疑的な見方も多い。また、天候や除染などによって放射性物質が一部に集中し、放射線量が高くなる場所も発生しており、特に子どもを持つ周辺住民にとっては不安な日々が続いている。住民が自ら立ち上げたプロジェクトは一時的ではあれ、こうした「救い」となることは間違いない。
※タイトル横写真:渡利の子どもを持つ世帯の現状について説明する渡利の子どもたちを守る会の菅野代表
(倉沢 美左 =東洋経済オンライン)
福島民友の1月24日の一面に地域振興券を検討するという記事が載っています。これは福島県内だけで使える『福島限定通貨』です。要するに福島県にじーっとしていろ、放射性物質をあび続けろ、という国家権力の本心でしょう。乞食県知事の佐藤雄平は犯罪者ですから積極推進するんでしょうね。
『放射能、みんなであびれば怖くない』か…

『放射能、みんなであびれば怖くない』か…

「脱原発世界会議」2日間で1万1500人が参加、世界各地から核の被害についての報告も(2)より転載
- 12/01/16 | 11:45


ローラン・オルダム氏はタヒチ(フランス領ポリネシア)出身。フランスによる核実験被害者団体「モルロアと私たち」の会長を務める。オルダム氏によれば、フランスは1966年から30年間にモルロア(ムルロア)環礁で計193回の核実験を実施。「海中に生じた穴が崩壊して15~20メートルの津波を引き起こす可能性が指摘されている」(同氏)。
続けて同氏は「これまでフランスでは核の被害を訴える訴訟が約700件も起こされているが、勝訴はわずか2件。ポリネシア住民が勝訴したケースはない」と指摘。「加害者が裁く」裁判の不合理を訴えた。

続いて登壇した「オーストラリア非核連合」共同代表のピーター・ワッツ氏は、先住民アボリジニー。「出身地ではウラン採掘による環境汚染が深刻で、住民にも多くの健康被害が出ている。オーストラリアで採掘されたウランが東京電力の福島原発で使われていたことを知って大きなショックを受けた」と語った。

日本の報告者である田部知江子氏は、原爆症認定集団訴訟弁護団に参加する弁護士。「国は原爆症の認定に際して残留放射線や内部被ばくの影響を考慮しておらず、被害が過小評価されてきた」と田部氏は指摘。「集団訴訟での相次ぐ勝訴判決を通じて認定基準の見直しがようやく進みつつある」と語った。

最後に発言したアンドレアス・ニデッカー氏はスイスの医師で、放射線医学が専門。「核戦争防止国際会議スイス支部長」を務めている。同氏は原子力エネルギーには、「コスト」「安全性」「廃棄物」「水」「放射能」「資源」「安全性」の面で「7つの欠陥」があるとし、「核エネルギーの民生利用はあまりにも危険で高価で時代遅れだ」とした。また、福島原発事故については、「長期的な内部被ばくの影響は甚大なものになりうる。発がんのみならず、心疾患や血管系疾患などさまざまな疾患が懸念される」と語った。
国際会議は15日も開催され、「放射能から子どもを守る」「原発のない東アジアをめざして」「地域発・原発に頼らない社会の作り方」などをテーマとした討論が行われた。
(岡田 広行 =東洋経済オンライン)
- 12/01/16 | 11:45


ローラン・オルダム氏はタヒチ(フランス領ポリネシア)出身。フランスによる核実験被害者団体「モルロアと私たち」の会長を務める。オルダム氏によれば、フランスは1966年から30年間にモルロア(ムルロア)環礁で計193回の核実験を実施。「海中に生じた穴が崩壊して15~20メートルの津波を引き起こす可能性が指摘されている」(同氏)。
続けて同氏は「これまでフランスでは核の被害を訴える訴訟が約700件も起こされているが、勝訴はわずか2件。ポリネシア住民が勝訴したケースはない」と指摘。「加害者が裁く」裁判の不合理を訴えた。

続いて登壇した「オーストラリア非核連合」共同代表のピーター・ワッツ氏は、先住民アボリジニー。「出身地ではウラン採掘による環境汚染が深刻で、住民にも多くの健康被害が出ている。オーストラリアで採掘されたウランが東京電力の福島原発で使われていたことを知って大きなショックを受けた」と語った。

日本の報告者である田部知江子氏は、原爆症認定集団訴訟弁護団に参加する弁護士。「国は原爆症の認定に際して残留放射線や内部被ばくの影響を考慮しておらず、被害が過小評価されてきた」と田部氏は指摘。「集団訴訟での相次ぐ勝訴判決を通じて認定基準の見直しがようやく進みつつある」と語った。

最後に発言したアンドレアス・ニデッカー氏はスイスの医師で、放射線医学が専門。「核戦争防止国際会議スイス支部長」を務めている。同氏は原子力エネルギーには、「コスト」「安全性」「廃棄物」「水」「放射能」「資源」「安全性」の面で「7つの欠陥」があるとし、「核エネルギーの民生利用はあまりにも危険で高価で時代遅れだ」とした。また、福島原発事故については、「長期的な内部被ばくの影響は甚大なものになりうる。発がんのみならず、心疾患や血管系疾患などさまざまな疾患が懸念される」と語った。
国際会議は15日も開催され、「放射能から子どもを守る」「原発のない東アジアをめざして」「地域発・原発に頼らない社会の作り方」などをテーマとした討論が行われた。
(岡田 広行 =東洋経済オンライン)
放射能汚染地帯で暮らす福島県民の苦悩、不安募らす子育て家庭 おざなりの除染作業より転載
(東洋経済オンライン 2012年01月12日掲載) 2012年1月18日(水)配信

郡山市の桃見台公園
福島市渡利地区──。福島県庁から1キロメートルほどの距離にある閑静な住宅地が、福島第一原子力発電所事故による高濃度の放射能で汚染されている事実が判明。住民に不安が広がっている。
「9月に行われた大学教授と市民団体による調査で、自宅の庭先から高い数値が計測された。その後の市による測定でも数値は高かった。事態の深刻さが明らかになった以上、政府や東京電力には、この地区の子ども、妊婦を避難させる方策を一刻も早く講じてほしい」。こう語るのは、渡利地区に住む裏澤利夫さん(77)だ。
福島市環境課は11月28日、裏澤さん宅の空中放射線量を初めて測定。庭の柿の木の下の土壌から1メートルの高さで毎時2.95マイクロシーベルト、50センチメートルの高さで同5.45マイクロシーベルトという高い数値が計測された。地表から1センチメートルの高さでは毎時30マイクロシーベルトをオーバーしており、市職員のサーベイメーターでは測定不能となった。
汚染が深刻な福島市 高い放射線の中で生活
1メートルの高さで毎時2.95マイクロシーベルトという数値は現在、住民が避難する際に国が支援を行う「特定避難勧奨地点」の指定基準(年間積算放射線量推計値が20ミリシーベルトを超えると推定された地点。8月時点では1メートルの高さで毎時3.0マイクロシーベルト)に匹敵するか、もしくは上回っている可能性が高い。
一方、50センチメートルの高さでの5.45マイクロシーベルトは南相馬市で設定されている「子ども・妊婦基準」(同2.0マイクロシーベルト)を大きく上回る。裏澤さん宅が南相馬市にあったとしたら、小学校4年生(9歳)および4歳の孫娘を持つ裏澤さん一家は国の責任で避難生活が認められていたはずだ。
ところが現在、裏澤さん一家には何の支援もない。福島市が消極的なこともあり、国が福島市内に特定避難勧奨地点を設けることに及び腰であるためだ。
しかし、住民の不安は高まる一方だ。子どもが浴びる放射線量を少しでも減らしたいと考えた裏澤さんの二男は、妻と子ども2人を市内の放射線量が比較的低い親戚の家に自主的に避難させることを決意。11月中旬から、自宅近くの小学校への通学にはバスを使わせ、帰りは二男が自家用車で親戚宅まで送るという生活に踏み切った。現在、母子3人は週末だけ自宅で寝泊まりするものの、庭先には出ずに屋内で一日を過ごす。
同じ渡利地区に住む阿部裕一さん(38)は妻および1歳8カ月の娘と3人暮らし。だが、妻が働いていることもあり、遠隔地に避難することは困難だ。「やむをえず、週末には県内外の温泉地などにクルマで出向く『週末避難』を余儀なくされている」(阿部さん)。
阿部さんの家計は火の車だ。「すでに週末避難の繰り返しでクルマ1台分の出費となってしまった」(阿部さん)。国や東電からの補償もなく、すべて自分持ちだ。
「渡利の子どもたちを守る会」の代表で、2児の父親の菅野吉広さん(43)は「多くの家庭が経済的に疲弊している。避難の是非をめぐり、家庭内不和や家庭の崩壊も起きかねない状況にある」と説明する。阿部さんも「本当にここに住んでいていいのかと不安に駆られて気持ちがぐったりすることが多い」と打ち明ける。
(東洋経済オンライン 2012年01月12日掲載) 2012年1月18日(水)配信

郡山市の桃見台公園
福島市渡利地区──。福島県庁から1キロメートルほどの距離にある閑静な住宅地が、福島第一原子力発電所事故による高濃度の放射能で汚染されている事実が判明。住民に不安が広がっている。
「9月に行われた大学教授と市民団体による調査で、自宅の庭先から高い数値が計測された。その後の市による測定でも数値は高かった。事態の深刻さが明らかになった以上、政府や東京電力には、この地区の子ども、妊婦を避難させる方策を一刻も早く講じてほしい」。こう語るのは、渡利地区に住む裏澤利夫さん(77)だ。
福島市環境課は11月28日、裏澤さん宅の空中放射線量を初めて測定。庭の柿の木の下の土壌から1メートルの高さで毎時2.95マイクロシーベルト、50センチメートルの高さで同5.45マイクロシーベルトという高い数値が計測された。地表から1センチメートルの高さでは毎時30マイクロシーベルトをオーバーしており、市職員のサーベイメーターでは測定不能となった。
汚染が深刻な福島市 高い放射線の中で生活
1メートルの高さで毎時2.95マイクロシーベルトという数値は現在、住民が避難する際に国が支援を行う「特定避難勧奨地点」の指定基準(年間積算放射線量推計値が20ミリシーベルトを超えると推定された地点。8月時点では1メートルの高さで毎時3.0マイクロシーベルト)に匹敵するか、もしくは上回っている可能性が高い。
一方、50センチメートルの高さでの5.45マイクロシーベルトは南相馬市で設定されている「子ども・妊婦基準」(同2.0マイクロシーベルト)を大きく上回る。裏澤さん宅が南相馬市にあったとしたら、小学校4年生(9歳)および4歳の孫娘を持つ裏澤さん一家は国の責任で避難生活が認められていたはずだ。
ところが現在、裏澤さん一家には何の支援もない。福島市が消極的なこともあり、国が福島市内に特定避難勧奨地点を設けることに及び腰であるためだ。
しかし、住民の不安は高まる一方だ。子どもが浴びる放射線量を少しでも減らしたいと考えた裏澤さんの二男は、妻と子ども2人を市内の放射線量が比較的低い親戚の家に自主的に避難させることを決意。11月中旬から、自宅近くの小学校への通学にはバスを使わせ、帰りは二男が自家用車で親戚宅まで送るという生活に踏み切った。現在、母子3人は週末だけ自宅で寝泊まりするものの、庭先には出ずに屋内で一日を過ごす。
同じ渡利地区に住む阿部裕一さん(38)は妻および1歳8カ月の娘と3人暮らし。だが、妻が働いていることもあり、遠隔地に避難することは困難だ。「やむをえず、週末には県内外の温泉地などにクルマで出向く『週末避難』を余儀なくされている」(阿部さん)。
阿部さんの家計は火の車だ。「すでに週末避難の繰り返しでクルマ1台分の出費となってしまった」(阿部さん)。国や東電からの補償もなく、すべて自分持ちだ。
「渡利の子どもたちを守る会」の代表で、2児の父親の菅野吉広さん(43)は「多くの家庭が経済的に疲弊している。避難の是非をめぐり、家庭内不和や家庭の崩壊も起きかねない状況にある」と説明する。阿部さんも「本当にここに住んでいていいのかと不安に駆られて気持ちがぐったりすることが多い」と打ち明ける。
日光国立公園は基準下回るより転載
2012年1月20日(金)19時9分配信 共同通信
環境省は20日、福島、栃木、群馬3県にまたがる日光国立公園のうち、栃木県日光市側の山林や遊歩道など41地点で実施した放射線量の測定結果を公表した。昨年12月14日時点の線量は毎時0・05~0・13マイクロシーベルトで、いずれも国の負担で除染を進める基準の0・23マイクロシーベルト(追加被ばく線量で年1ミリシーベルト相当)を下回った。日光市は首都圏の小学校の修学旅行先として人気が高い。
2012年1月20日(金)19時9分配信 共同通信
環境省は20日、福島、栃木、群馬3県にまたがる日光国立公園のうち、栃木県日光市側の山林や遊歩道など41地点で実施した放射線量の測定結果を公表した。昨年12月14日時点の線量は毎時0・05~0・13マイクロシーベルトで、いずれも国の負担で除染を進める基準の0・23マイクロシーベルト(追加被ばく線量で年1ミリシーベルト相当)を下回った。日光市は首都圏の小学校の修学旅行先として人気が高い。
福井も福島と同じように原発銀座ですので、親しみを感じます。ここで事故が起こったら日本海の魚も食べれなくなりますね。困るな。
原発「関西が最も危険」より転載
2012年1月20日(金)19時17分配信 共同通信
福井県内の原発7基の再稼働差し止めを滋賀県の住民らが求めた大津地裁の仮処分審で「材料や機器劣化による原発事故の危険性は関西エリアが最も高い」とする井野博満東大名誉教授の意見書を住民側が提出することが20日、訴訟関係者への取材で分かった。井野氏は意見書で、炉の健全性を評価するため圧力容器内に置かれた試験片の耐性を分析。「最も劣化が進んだ玄海原発1号機に次ぎ、全国でワースト2~6が福井県に集中」と指摘。
原発「関西が最も危険」より転載
2012年1月20日(金)19時17分配信 共同通信
福井県内の原発7基の再稼働差し止めを滋賀県の住民らが求めた大津地裁の仮処分審で「材料や機器劣化による原発事故の危険性は関西エリアが最も高い」とする井野博満東大名誉教授の意見書を住民側が提出することが20日、訴訟関係者への取材で分かった。井野氏は意見書で、炉の健全性を評価するため圧力容器内に置かれた試験片の耐性を分析。「最も劣化が進んだ玄海原発1号機に次ぎ、全国でワースト2~6が福井県に集中」と指摘。
自民個人献金、72%が電力業界 09年、役員の90%超 より転載
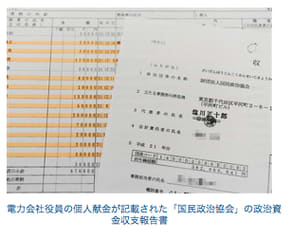
電力会社役員の個人献金が記載された「国民政治協会」の政治資金収支報告書
自民党の政治資金団体「国民政治協会」本部の2009年分政治資金収支報告書で、個人献金額の72・5%が東京電力など電力9社の当時の役員・OBらによることが22日、共同通信の調べで分かった。当時の役員の92・2%が献金していた実態も判明した。電力業界は1974年に政財界癒着の批判を受け、企業献金の廃止を表明。役員個人の献金は政治資金規正法上、問題ないが、個人献金として会社ぐるみの「組織献金」との指摘が出ている。福島第1原発事故を受け、原子力政策を推進してきた独占の公益企業と政治の関係が厳しく問われそうだ。
2011/07/23 02:02 【共同通信】
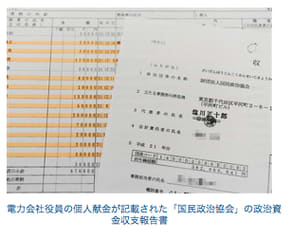
電力会社役員の個人献金が記載された「国民政治協会」の政治資金収支報告書
自民党の政治資金団体「国民政治協会」本部の2009年分政治資金収支報告書で、個人献金額の72・5%が東京電力など電力9社の当時の役員・OBらによることが22日、共同通信の調べで分かった。当時の役員の92・2%が献金していた実態も判明した。電力業界は1974年に政財界癒着の批判を受け、企業献金の廃止を表明。役員個人の献金は政治資金規正法上、問題ないが、個人献金として会社ぐるみの「組織献金」との指摘が出ている。福島第1原発事故を受け、原子力政策を推進してきた独占の公益企業と政治の関係が厳しく問われそうだ。
2011/07/23 02:02 【共同通信】
SPEEDI情報 米軍に提供より転載
1月17日 0時7分 NHKニュース
東京電力福島第一原子力発電所の事故原因を究明する国会の「事故調査委員会」は、初めての本格的な質疑を行い、参考人として招致された文部省の担当者が、放射性物質の拡散を予測する「SPEEDI」と呼ばれるシステムによる予測データを、事故の直後に、アメリカ軍に提供していたことを明らかにしました。
国会の事故調査委員会は、16日、政府の事故調査・検証委員会の畑村委員長や東京電力の事故調査委員会の委員長を務める山崎副社長らを参考人として招致し、公開で初めての本格的な質疑を行いました。この中で、文部科学省科学技術・学術政策局の渡辺次長は、放射性物質の拡散を予測する「SPEEDI」と呼ばれるシステムで、事故の直後に行った予測のデータについて、外務省を通じて直ちにアメリカ軍に提供していたことを明らかにしました。SPEEDIのデータは、文部科学省が「実態を正確に反映していない予測データの公表は、無用の混乱を招きかねない」として、一部を除き、事故の発生から2か月近く公表しませんでしたが、アメリカ軍に提供した理由について、渡辺次長は「緊急事態に対応してもらう機関に、情報提供する一環として連絡した」と説明しました。また、質疑では、事故調査委員会の石橋委員が「平成19年の新潟県中越沖地震の経験がありながら、東京電力は、地震と津波に対して、対応が甘かったのではないか」と指摘したのに対し、東京電力の山崎副社長は「事業者として、忠実に対策を取ってきたと思っているが、考えているような前提をすべて覆すようなことが起きた。もう少し考えなければならないということがあるならば、考えていきたい」と述べました。質疑を終えて記者会見した事故調査委員会の黒川委員長は、原発事故の対応にあたった菅前総理大臣や枝野経済産業大臣の参考人招致について、「検討事項に入っている」と述べました。事故調査委員会は、30日に次回の質疑を行うことにしています。
1月17日 0時7分 NHKニュース
東京電力福島第一原子力発電所の事故原因を究明する国会の「事故調査委員会」は、初めての本格的な質疑を行い、参考人として招致された文部省の担当者が、放射性物質の拡散を予測する「SPEEDI」と呼ばれるシステムによる予測データを、事故の直後に、アメリカ軍に提供していたことを明らかにしました。
国会の事故調査委員会は、16日、政府の事故調査・検証委員会の畑村委員長や東京電力の事故調査委員会の委員長を務める山崎副社長らを参考人として招致し、公開で初めての本格的な質疑を行いました。この中で、文部科学省科学技術・学術政策局の渡辺次長は、放射性物質の拡散を予測する「SPEEDI」と呼ばれるシステムで、事故の直後に行った予測のデータについて、外務省を通じて直ちにアメリカ軍に提供していたことを明らかにしました。SPEEDIのデータは、文部科学省が「実態を正確に反映していない予測データの公表は、無用の混乱を招きかねない」として、一部を除き、事故の発生から2か月近く公表しませんでしたが、アメリカ軍に提供した理由について、渡辺次長は「緊急事態に対応してもらう機関に、情報提供する一環として連絡した」と説明しました。また、質疑では、事故調査委員会の石橋委員が「平成19年の新潟県中越沖地震の経験がありながら、東京電力は、地震と津波に対して、対応が甘かったのではないか」と指摘したのに対し、東京電力の山崎副社長は「事業者として、忠実に対策を取ってきたと思っているが、考えているような前提をすべて覆すようなことが起きた。もう少し考えなければならないということがあるならば、考えていきたい」と述べました。質疑を終えて記者会見した事故調査委員会の黒川委員長は、原発事故の対応にあたった菅前総理大臣や枝野経済産業大臣の参考人招致について、「検討事項に入っている」と述べました。事故調査委員会は、30日に次回の質疑を行うことにしています。










