教育実習の時、一番最初に言われたことは「生徒にとっては教師であろうが教育実習生であろうが関係ない。実習生だからという甘えは捨てて、目の前の生徒に全力で向かってほしい。」同じようなことは現場に入ってからもあった。例えば新任とベテラン、正規と講師、男と女など安易な区分けをしがちだが、生徒にとっての教師はonly oneである。大切なことは「~である」ということよりも「どういう授業をするか?」ということである。
そういう観点でいえば、原則的には従来型の校長であろうが公募校長であろうが私はどちらでも構わないと思っている。ただ、「公募校長」についてこだわっているのは
 というように、さまざまな課題が「公募校長」によって改善されるという幻想をふりまき拙速に導入しているからであろう。今年度は928人の応募者から、レポート審査で195人にしぼり、10分の1次面接と15分の2次面接を経て11人が採用された。
というように、さまざまな課題が「公募校長」によって改善されるという幻想をふりまき拙速に導入しているからであろう。今年度は928人の応募者から、レポート審査で195人にしぼり、10分の1次面接と15分の2次面接を経て11人が採用された。
実際に面接を受けた「公募校長」である玉川さんの言葉は重い。


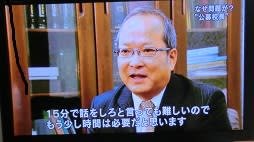
そして、予想以上のトラブルが短期間に起きた。
 それに対して大阪市教育長は
それに対して大阪市教育長は

 と他人ごとみたいな顔でコメントしていたが、選ばれた側よりも選んだ側の資質の方が大きいのではないかと考える。ここにメスを入れないと、レポートの課題を1つから3つに増やし、面接時間を2倍の30分に改めても解決しないのではないかと思う。
と他人ごとみたいな顔でコメントしていたが、選ばれた側よりも選んだ側の資質の方が大きいのではないかと考える。ここにメスを入れないと、レポートの課題を1つから3つに増やし、面接時間を2倍の30分に改めても解決しないのではないかと思う。
次に、11人の配属についての問題点が指摘された。各地域に偏ることなく赴任させるというのを見た時ため息が出た。
 これでは「公募」した意味がない。ここにも選ぶ側のしっかりとした考え、見通しがないという問題点が顕著にでている。「何のために選ばれたのか」と言って3ヶ月で辞職した校長の気持ちは理解できる。新しい制度を開始するなら、従来のやり方も変えないといけないのではないか。
これでは「公募」した意味がない。ここにも選ぶ側のしっかりとした考え、見通しがないという問題点が顕著にでている。「何のために選ばれたのか」と言って3ヶ月で辞職した校長の気持ちは理解できる。新しい制度を開始するなら、従来のやり方も変えないといけないのではないか。
最後に取り上げられていた「公募校長」の山口さんのやろうとしていることは共感ができた。この人の下なら気持ちよく仕事ができるだろうなという思いを持った。実践の中から出てきた言葉には教育行政に関わる人は耳を傾けるべきである。山口さんの話していることは、教育現場を経験した人であれば予想できたことで「やっぱりな」というのが正直な感想。評論家的に言っていても説得力はないが、「公募校長」という制度のもとに選んだ人が言っているのだから、選んだ側は真摯に受け止めて支援してあげないとつぶれてしまう。
 地域に密着する公立学校の基本である。そのことを実践していこうとすると大きな壁にあたる。
地域に密着する公立学校の基本である。そのことを実践していこうとすると大きな壁にあたる。
細かい基準によるしばりである。悪平等主義といっても良い。ただ、これも長い経過の中でつくられてきたものであるので悩ましいことではある。




 それぞれの学校、地域には長い間に育まれてきた文化がある。山口さんだけではなく転勤した時には必ずぶつかる壁である。そのことを踏まえた上の改革でなければならないと考えている。したがって最低でも6年は必要である。
それぞれの学校、地域には長い間に育まれてきた文化がある。山口さんだけではなく転勤した時には必ずぶつかる壁である。そのことを踏まえた上の改革でなければならないと考えている。したがって最低でも6年は必要である。
そうなると任期は3年という原則そのものが、本気で仕事させる気があるのかなという疑問を抱かせる。アンケートに示された現場の校長の悩みにいかに応えていくことこそ真の改革につながると強く思った。

 でないと混乱は広がる一方となる。
でないと混乱は広がる一方となる。
そういう観点でいえば、原則的には従来型の校長であろうが公募校長であろうが私はどちらでも構わないと思っている。ただ、「公募校長」についてこだわっているのは
 というように、さまざまな課題が「公募校長」によって改善されるという幻想をふりまき拙速に導入しているからであろう。今年度は928人の応募者から、レポート審査で195人にしぼり、10分の1次面接と15分の2次面接を経て11人が採用された。
というように、さまざまな課題が「公募校長」によって改善されるという幻想をふりまき拙速に導入しているからであろう。今年度は928人の応募者から、レポート審査で195人にしぼり、10分の1次面接と15分の2次面接を経て11人が採用された。実際に面接を受けた「公募校長」である玉川さんの言葉は重い。


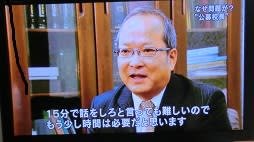
そして、予想以上のトラブルが短期間に起きた。
 それに対して大阪市教育長は
それに対して大阪市教育長は
 と他人ごとみたいな顔でコメントしていたが、選ばれた側よりも選んだ側の資質の方が大きいのではないかと考える。ここにメスを入れないと、レポートの課題を1つから3つに増やし、面接時間を2倍の30分に改めても解決しないのではないかと思う。
と他人ごとみたいな顔でコメントしていたが、選ばれた側よりも選んだ側の資質の方が大きいのではないかと考える。ここにメスを入れないと、レポートの課題を1つから3つに増やし、面接時間を2倍の30分に改めても解決しないのではないかと思う。 次に、11人の配属についての問題点が指摘された。各地域に偏ることなく赴任させるというのを見た時ため息が出た。
 これでは「公募」した意味がない。ここにも選ぶ側のしっかりとした考え、見通しがないという問題点が顕著にでている。「何のために選ばれたのか」と言って3ヶ月で辞職した校長の気持ちは理解できる。新しい制度を開始するなら、従来のやり方も変えないといけないのではないか。
これでは「公募」した意味がない。ここにも選ぶ側のしっかりとした考え、見通しがないという問題点が顕著にでている。「何のために選ばれたのか」と言って3ヶ月で辞職した校長の気持ちは理解できる。新しい制度を開始するなら、従来のやり方も変えないといけないのではないか。最後に取り上げられていた「公募校長」の山口さんのやろうとしていることは共感ができた。この人の下なら気持ちよく仕事ができるだろうなという思いを持った。実践の中から出てきた言葉には教育行政に関わる人は耳を傾けるべきである。山口さんの話していることは、教育現場を経験した人であれば予想できたことで「やっぱりな」というのが正直な感想。評論家的に言っていても説得力はないが、「公募校長」という制度のもとに選んだ人が言っているのだから、選んだ側は真摯に受け止めて支援してあげないとつぶれてしまう。
 地域に密着する公立学校の基本である。そのことを実践していこうとすると大きな壁にあたる。
地域に密着する公立学校の基本である。そのことを実践していこうとすると大きな壁にあたる。細かい基準によるしばりである。悪平等主義といっても良い。ただ、これも長い経過の中でつくられてきたものであるので悩ましいことではある。




 それぞれの学校、地域には長い間に育まれてきた文化がある。山口さんだけではなく転勤した時には必ずぶつかる壁である。そのことを踏まえた上の改革でなければならないと考えている。したがって最低でも6年は必要である。
それぞれの学校、地域には長い間に育まれてきた文化がある。山口さんだけではなく転勤した時には必ずぶつかる壁である。そのことを踏まえた上の改革でなければならないと考えている。したがって最低でも6年は必要である。そうなると任期は3年という原則そのものが、本気で仕事させる気があるのかなという疑問を抱かせる。アンケートに示された現場の校長の悩みにいかに応えていくことこそ真の改革につながると強く思った。

 でないと混乱は広がる一方となる。
でないと混乱は広がる一方となる。













