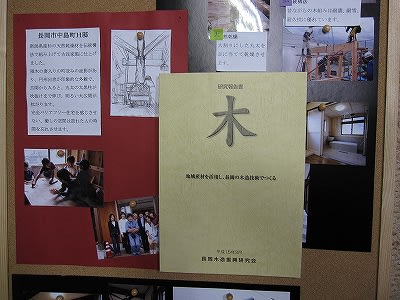このブログもだいぶ検索ヒットが多くなってきましたが、中でも「長期優良住宅」についての検索が多いようなので、補足として掲載します。
●国土交通省関連
長期優良住宅法関連情報
最終更新:平成21年6月1日
長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅である「長期優良住宅」について、その建築及び維持保全に関する計画 (「長期優良住宅建築等計画」といいます。)を認定する制度の創設を柱とする「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成20年12月に公布され、平成21年6月4日に施行されます。
この法律では、長期優良住宅の普及の促進のため、構造躯体の劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性の性能を有し、かつ、良好な景観の形成に配慮した居住環境や一定の住戸面積を有する住宅の建築計画及び一定の維持保全計画を策定して、所管行政庁に申請します。当該計画の認定を受けた住宅については、認定長期優良住宅建築等計画に基づき、建築及び維持保全を行うこととなります。
詳しくはこちら
●促進事業・補助金について
「長期優良住宅普及促進事業」は、住宅供給の主要な担い手である中小住宅生産者による長期優良住宅への取組の促進及び長期優良住宅に関連する仕組みとしての住宅履歴情報の普及を図ることにより、良質な住宅ストックの形成を促進するため、中小住宅生産者により供給される長期優良住宅に対して助成を行うものです。
本事業の助成の対象となる住宅は、法律に基づき長期優良住宅としての認定を受け、所定の住宅履歴情報を整備する必要があるほか、見学会の開催や、今年度内の一定時期までの竣工・引渡しなどが求められます。
■ エントリー(事業者募集)期間
平成21年6月4日(木)~平成21年8月7日(金)
■ 補助金交付申請(補助対象住宅申請)期間
※エントリーが完了していることが前提です。(エントリーと本申請を同時に行うことも可能です。)
平成21年6月4日(木)~平成21年12月11日(金)
■ 補助金額
本事業による補助金の額は、補助対象となる建設工事費の1割以内の額で、かつ対象住宅1戸当たり100万円を上限とします。なお、補助を受けることのできる住宅の戸数は、一の補助事業者あたり25戸を上限とします。
(団体・グループによる場合は、代表者に対して一定の附帯事務費を補助します。)
■ 対象者
申請者は、以下の要件を全て満たす方です。
○ 年間の新築住宅供給戸数が50戸程度未満の住宅供給事業者
○ 建築主と住宅の建設工事請負契約を締結(又は売買契約を締結※)し、かつ当該住宅の建設工事を行う者
※建設業と宅地建物取引業を兼ねる者が、住宅の建設工事を行い、かつその販売を自ら行う場合についても本事業の対象
くわしくはこちら
長期優良住宅へ・・・
●国土交通省関連
長期優良住宅法関連情報
最終更新:平成21年6月1日
長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅である「長期優良住宅」について、その建築及び維持保全に関する計画 (「長期優良住宅建築等計画」といいます。)を認定する制度の創設を柱とする「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成20年12月に公布され、平成21年6月4日に施行されます。
この法律では、長期優良住宅の普及の促進のため、構造躯体の劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性の性能を有し、かつ、良好な景観の形成に配慮した居住環境や一定の住戸面積を有する住宅の建築計画及び一定の維持保全計画を策定して、所管行政庁に申請します。当該計画の認定を受けた住宅については、認定長期優良住宅建築等計画に基づき、建築及び維持保全を行うこととなります。
詳しくはこちら
●促進事業・補助金について
「長期優良住宅普及促進事業」は、住宅供給の主要な担い手である中小住宅生産者による長期優良住宅への取組の促進及び長期優良住宅に関連する仕組みとしての住宅履歴情報の普及を図ることにより、良質な住宅ストックの形成を促進するため、中小住宅生産者により供給される長期優良住宅に対して助成を行うものです。
本事業の助成の対象となる住宅は、法律に基づき長期優良住宅としての認定を受け、所定の住宅履歴情報を整備する必要があるほか、見学会の開催や、今年度内の一定時期までの竣工・引渡しなどが求められます。
■ エントリー(事業者募集)期間
平成21年6月4日(木)~平成21年8月7日(金)
■ 補助金交付申請(補助対象住宅申請)期間
※エントリーが完了していることが前提です。(エントリーと本申請を同時に行うことも可能です。)
平成21年6月4日(木)~平成21年12月11日(金)
■ 補助金額
本事業による補助金の額は、補助対象となる建設工事費の1割以内の額で、かつ対象住宅1戸当たり100万円を上限とします。なお、補助を受けることのできる住宅の戸数は、一の補助事業者あたり25戸を上限とします。
(団体・グループによる場合は、代表者に対して一定の附帯事務費を補助します。)
■ 対象者
申請者は、以下の要件を全て満たす方です。
○ 年間の新築住宅供給戸数が50戸程度未満の住宅供給事業者
○ 建築主と住宅の建設工事請負契約を締結(又は売買契約を締結※)し、かつ当該住宅の建設工事を行う者
※建設業と宅地建物取引業を兼ねる者が、住宅の建設工事を行い、かつその販売を自ら行う場合についても本事業の対象
くわしくはこちら
長期優良住宅へ・・・