歴史の誤解シリーズ。
今回は「服部半蔵」です。
服部半蔵といえば、忍者のイメージが強く、いろいろなフィクションに忍者として登場します。
忍者ハットリくんというアニメもありました。
実際はどうだったのでしょうか?
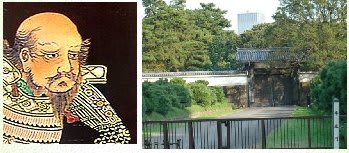
普通、服部半蔵といえば服部正成(左絵)のことをいいます。
正成は、戦国時代から安土桃山時代の三河の武将です。
松平氏(徳川氏)の譜代家臣、徳川十六神将のひとりで、槍の名人として、数々の戦で家康を支えました。
後に、父親が伊賀出身であったために、伊賀同心を統率する立場になったことで、徳川家に仕える忍者の首領とみられるようになったのです。
ということで、半蔵自身は三河武士で、忍者ではありません。
本能寺の変の折りには、堺に滞在していた家康が、甲賀・伊賀を通って伊勢から三河に抜ける神君伊賀越えに際し、正成が伊賀、甲賀の地元の土豪と交渉し、彼らに警護させて一行を安全に通行させて、無事岡崎まで帰しました。
これが、伊賀同心、甲賀同心として徳川幕府に仕えるきっかけを作りました。
東京地下鉄半蔵門線・半蔵門駅は、半蔵の部下が警備を担当した江戸城の門(写
真右)の名に由来します。
ということで、忍者を束ねていたのが服部半蔵なのです。
ところで、伊賀者の給料は甲賀者に比べると随分と少ないそうです。
なぜ?
甲賀はルーツを遡ると、平家の落ち武者のようです。
そして、地元の小豪族となり、六角氏と主従関係を結ぶようになり、六角氏亡き後は織田信長、豊臣秀吉と仕えてきた「侍」の一門です。
それに対して伊賀の方は、決まった主を持たず、その時その時の金銭契約であっちに付いたりこっちに付いたりしていました。
これは「足軽」のする事なんです。
甲賀は正社員、伊賀は臨時雇いだったのですね。
今回は「服部半蔵」です。
服部半蔵といえば、忍者のイメージが強く、いろいろなフィクションに忍者として登場します。
忍者ハットリくんというアニメもありました。
実際はどうだったのでしょうか?
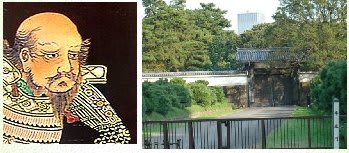
普通、服部半蔵といえば服部正成(左絵)のことをいいます。
正成は、戦国時代から安土桃山時代の三河の武将です。
松平氏(徳川氏)の譜代家臣、徳川十六神将のひとりで、槍の名人として、数々の戦で家康を支えました。
後に、父親が伊賀出身であったために、伊賀同心を統率する立場になったことで、徳川家に仕える忍者の首領とみられるようになったのです。
ということで、半蔵自身は三河武士で、忍者ではありません。
本能寺の変の折りには、堺に滞在していた家康が、甲賀・伊賀を通って伊勢から三河に抜ける神君伊賀越えに際し、正成が伊賀、甲賀の地元の土豪と交渉し、彼らに警護させて一行を安全に通行させて、無事岡崎まで帰しました。
これが、伊賀同心、甲賀同心として徳川幕府に仕えるきっかけを作りました。
東京地下鉄半蔵門線・半蔵門駅は、半蔵の部下が警備を担当した江戸城の門(写
真右)の名に由来します。
ということで、忍者を束ねていたのが服部半蔵なのです。
ところで、伊賀者の給料は甲賀者に比べると随分と少ないそうです。
なぜ?
甲賀はルーツを遡ると、平家の落ち武者のようです。
そして、地元の小豪族となり、六角氏と主従関係を結ぶようになり、六角氏亡き後は織田信長、豊臣秀吉と仕えてきた「侍」の一門です。
それに対して伊賀の方は、決まった主を持たず、その時その時の金銭契約であっちに付いたりこっちに付いたりしていました。
これは「足軽」のする事なんです。
甲賀は正社員、伊賀は臨時雇いだったのですね。









