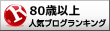10月後半の近況報告、庭先の1本の山茶花の花も又、咲き始める時季になりました。
10月後半の近況報告、庭先の1本の山茶花の花も又、咲き始める時季になりました。
フィンランドから3度目の来日のEspoon Taidoのカッリ君、今回も二週間の稽古、体位の法形は、師にも勝るとも劣らぬ手技の操法が出来るようになってきました。
躰道草創期に完成された法形で力強さを感じ、かつ実戦的な法形でもある、躰道の成り立ちを証明するために、是非に後世に伝承したい法形です。
エーロ君、おはようございます。東京にも木枯らし1号が吹き寒くなって来ましたが、ヘルシンキの寒さは如何ですか、毎日稽古に明けくれしていることと思います。
Espoon行きも10日と迫りました、楽しみにしております。早速ですが、宿泊先のホテルにはipadを使用する設備がありますか?、成田空港で用意した方が良いですか、お知らせください。
早速の返信ありがとう、入間市も朝晩は寒くなってきました。庭先の山茶花も咲き始めました、これから日増しに寒くなってまいりますが、一週間後のフィンランド行きを楽しみにしております。
10月28日、一週間後に10~15度気温の低い、フィンランド行きに備えている。体調の状態を出来るだけチェック、血圧は上110、下は70台で基準値内。
血圧は19歳の陸上自衛隊に入隊する時とは変わることなく過ごしてる。血圧の上下は遺伝もある様なので両親には感謝。
3ヶ月前の血液検査も全て良し、内視鏡検査で消化器系も良く、体重も19歳の時と変わることのないよう精進して来た。武道を志す者の心得の1つでもあると思っています。