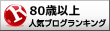今回の社会人大会でも特別競技として「制の法形」が行なわれた、 個人戦には 19名の選手が出場した。
今回の社会人大会でも特別競技として「制の法形」が行なわれた、 個人戦には 19名の選手が出場した。
制の法形は、躰技に受け技が加わり、予測できない瞬時の攻撃に対応でき、より実戦(野戦)的な要素が加えられ、多くの方々に躰道の実戦技が理解して頂けるものと思います。
主に天制、地制の法形は、正確な受け技が必要になります。止め受け、受けながし、捕り受けの術技は、体得することが必要となり、又一つ一つの受け技と運足を入れての三動一体の受け技は、正確性と多くの年数を要します。
写真は大会当日、競技を終えた 2~3名の選手に話しかけ、何故手を開いて受けるのか、腕にひねり(捻り)が必要なのか、何故、肘は正中線に置くべきなのか?理解してないですね。参考までに、中段外受け、内受け共に同じ位置が基本です。
制の法形は、長年の玄制流空手の術技と躰技を融合させ実戦を想定した、創始最高師範祝嶺正献先生の最高傑作と言って過言ではないと思います、一動も疎かにしないよう実技に取り組んで頂きたいと思います。
双手下段払いや双手中段受けで実際に、蹴りや突きを受けて試して下さい、受ける事が出来ますか?、結果をお知らせ下されば幸いです。
仁制の法形は、多数の相手を想定した、接近戦に対応しなければならない法形です。
肘技の猿臂が多く、後当て、揚げ当て、横当て、回し当等は、当ての反動を体軸に伝え、相手の力を利用し動きに加速を加え、四方当ての基本業技で、一瞬に囲みを破る感覚を習得すると良いですね。
この感覚を法形の要所要所に取り入れ、緩急、強弱の度合いができ、単調になりやすい仁制の法形も、実戦的な法形に変化できると思います。