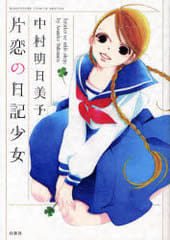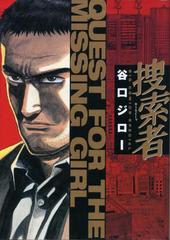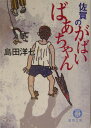「海街diary1 蝉時雨のやむ頃」 吉田秋生 小学館
彼氏と朝を迎えた佳乃の下にある知らせが届いた。それは幼い頃に母以外の女性と家を出た父が亡くなったというものだった。夜勤で葬儀に出られない姉・幸の代わりに、佳乃は妹・千佳と共に父が住んでいたという小さな町へと赴く。そこへ迎えに来たのは佳乃たちにとって異母妹にあたる「すず」という少女だった・・・
海の見える街・鎌倉を舞台に家族とはそして優しさとは何かと問いかけるストーリー
漫画好きさんの間では評価の高い吉田秋生さんの新シリーズ。
やっとこ読みました
一言でいうと「やられた」という感じ(笑)
吉田さんの描く作品は静と動のように正反対のイメージを持っていても「カルフォルニア物語」や「BANANA FISH」のようにアメリカ映画に通じそうなテイストが共通しているように思っていましたが、今回は乾いた大地に沁みこむ水のような作品ですね
冒頭「やられた」と言ったのは、個人的な話になりますが実は私も似たような家庭境遇を経て来てて、実際に異父弟妹もいたりするから・・・
登場人物である3姉妹にとっても感情移入をしてしまった訳なのです
早くに母を失い、そしてまた父を失い他人の中で暮らしていたすずを引き取り、3姉妹から、4姉妹となった香田家の姉妹ですが、それぞれのキャラから発せられるセリフが胸を打ちます・・・
「大人のするべきことを子供に肩代わりさせてはいけないと思います。
子供であることを奪われた子供ほど悲しいものはありません」
「死んでいく人とと向き合うのはとてもエネルギーのいることなの。
許容量が少ないからってそれを責めるのは酷なことなのよ」
ちょこっとね、昔を思い出しました。
理性と感情という違いもあるけど、理解をすることと、受け入れたり、許すということは別なんだよね。
そして後者の方がより難しい・・・
私にはまだ見ぬ弟妹と対面する日が来るかどうかは判らないけど、もしそのことで葛藤する日が来たら、この漫画を思い出そうと思いました。
それにしても・・・すずちゃん、いじらしすぎ
「裕也ほんとにみんなに会いたいのかなって。
あたしたちに会うの ほんとはまだつらいんじゃないかなって思ったから・・・」
苦労しているから人の心の機微がとっても判って・・・いや、しっかりし過ぎている位に他人の気持ちが判りすぎるトコロに彼女が乗り越えてきた背景が見えてね、目頭がジーンとね
今までの切ない話とはちょっと違い、このゆったりと穏やかに流れる雰囲気に吉田秋生さんの新境地をみた気分です
1と銘打っているって事はこのシリーズで2巻以降も出るって事なんでしょうけど、とっても気になる作品ですね
出来ることならあの4姉妹に幸多かれと祈りたいわ(漫画だけと・笑)
彼氏と朝を迎えた佳乃の下にある知らせが届いた。それは幼い頃に母以外の女性と家を出た父が亡くなったというものだった。夜勤で葬儀に出られない姉・幸の代わりに、佳乃は妹・千佳と共に父が住んでいたという小さな町へと赴く。そこへ迎えに来たのは佳乃たちにとって異母妹にあたる「すず」という少女だった・・・
海の見える街・鎌倉を舞台に家族とはそして優しさとは何かと問いかけるストーリー
漫画好きさんの間では評価の高い吉田秋生さんの新シリーズ。
やっとこ読みました
一言でいうと「やられた」という感じ(笑)
吉田さんの描く作品は静と動のように正反対のイメージを持っていても「カルフォルニア物語」や「BANANA FISH」のようにアメリカ映画に通じそうなテイストが共通しているように思っていましたが、今回は乾いた大地に沁みこむ水のような作品ですね
冒頭「やられた」と言ったのは、個人的な話になりますが実は私も似たような家庭境遇を経て来てて、実際に異父弟妹もいたりするから・・・
登場人物である3姉妹にとっても感情移入をしてしまった訳なのです
早くに母を失い、そしてまた父を失い他人の中で暮らしていたすずを引き取り、3姉妹から、4姉妹となった香田家の姉妹ですが、それぞれのキャラから発せられるセリフが胸を打ちます・・・
「大人のするべきことを子供に肩代わりさせてはいけないと思います。
子供であることを奪われた子供ほど悲しいものはありません」
「死んでいく人とと向き合うのはとてもエネルギーのいることなの。
許容量が少ないからってそれを責めるのは酷なことなのよ」
ちょこっとね、昔を思い出しました。
理性と感情という違いもあるけど、理解をすることと、受け入れたり、許すということは別なんだよね。
そして後者の方がより難しい・・・
私にはまだ見ぬ弟妹と対面する日が来るかどうかは判らないけど、もしそのことで葛藤する日が来たら、この漫画を思い出そうと思いました。
それにしても・・・すずちゃん、いじらしすぎ
「裕也ほんとにみんなに会いたいのかなって。
あたしたちに会うの ほんとはまだつらいんじゃないかなって思ったから・・・」
苦労しているから人の心の機微がとっても判って・・・いや、しっかりし過ぎている位に他人の気持ちが判りすぎるトコロに彼女が乗り越えてきた背景が見えてね、目頭がジーンとね
今までの切ない話とはちょっと違い、このゆったりと穏やかに流れる雰囲気に吉田秋生さんの新境地をみた気分です
1と銘打っているって事はこのシリーズで2巻以降も出るって事なんでしょうけど、とっても気になる作品ですね
出来ることならあの4姉妹に幸多かれと祈りたいわ(漫画だけと・笑)