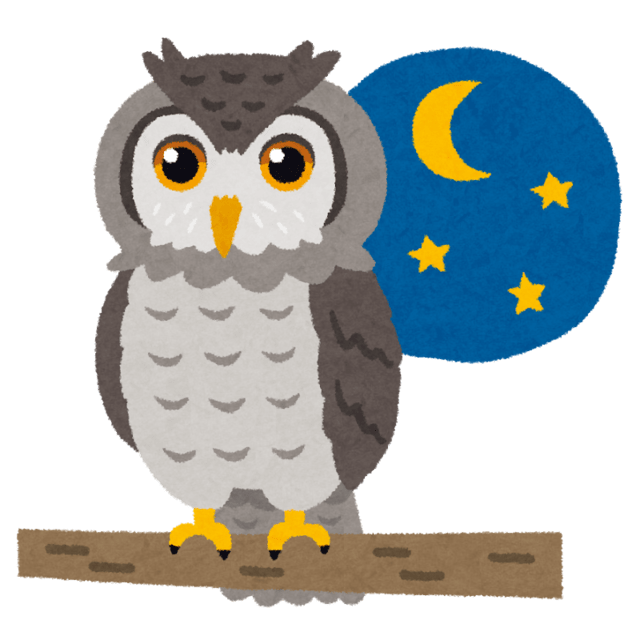“東日本大震災の防潮堤”とは、震災後に設置された岩手・宮城・福島の三県にわたる339キロの防潮堤のことである。
この防潮堤の約7割が完成ているが、完成してみると「新防潮堤は高すぎる」とか、「津波が来る時、海の変化が見えず怖い」とか、景観や漁業、環境などの生態系への影響が懸念されている。
この防潮堤については、計画段階から疑問が呈されていたが、先日のテレビ“そこまで言って委員会”の元官僚 小松正之氏が、「この防潮堤は土木業者しか喜ばない」と語っていた。また同氏は、反対意見は誰にも出来るので、自分に何が出来るのかを考えてからいってほしいと言っていた。
己を含めてあとの祭りはよくあることだが、人の意見をよく聴き対応を考えてから議論を戦わすしかあるまい。その結果であれば、防潮堤のことを含めてあとの祭りとなっても仕方ないといわざるを得まい。
また、元財務省官僚 的場順三氏も同じようなことを著書“座して待つのか、日本人”に書いていた。なお、同氏は、“平成”の呼称にも関与していたようだ。
以前、東北本線の車窓から“日本三景”のひとつである宮城県松島を見たことがあるが、高い防潮堤が出来て今はどのように見えるのだろう。そして、どうしてこんな事になったのだろうかと思わざるを得ない。
日本は海で囲まれた綺麗な国であったが、自然がこのように失われていくのを見ると本当に残念に思う。“コンクリートから人へ”のスローガンがあったが、コンクリート社会は今も続いており、“人からコンクリートへ”にはなってほしくない。
人間は、コロナ禍を機にそろそろ変わらなければならない時代がきているのだ。 「変わる時代 変えるスタイル 未来志向」である。
「十勝の活性化を考える会」会長
注) 日本三景
日本三景(にほんさんけい)は、日本の3つの名勝地のことである。
日本三景は以下の3つの名勝地を指す(記載順は全国地方公共団体コードの順番による)。全て海(沿岸)にある風景となっており、各々古くから詩歌に詠まれ、絵画に描かれていた。
江戸時代前期の儒学者・林春斎が、寛永20年8月13日に執筆した著書『日本国事跡考』の陸奥国のくだりにおいて、「松島、此島之外有小島若干、殆如盆池月波之景、境致之佳、與丹後天橋立・安藝嚴嶋爲三處奇觀」と書き記した。これを端緒に「日本三景」という括りが始まったとされる。
日本三景碑(天橋立)
その後、元禄2年閏1月28日(グレゴリオ暦1689年3月19日)に天橋立を訪れた儒学者・貝原益軒が、その著書『己巳紀行』(きしきこう)の中の丹波丹後若狭紀行において、天橋立を「日本の三景の一とするも宜也」と記している。これが「日本三景」という言葉の文献上の初出とされ、益軒が訪れる以前から「日本三景」が一般に知られた括りであったと推定されている。
日本三景を雪月花にあてる場合、「雪」は天橋立、「月」は松島、「花」は紅葉を花に見立てて宮島をあてている。
(出典:『ウィキペディア(Wikipedia)』より抜粋)
著書 「座してまつのか、日本人」の主な内容
- バブル後遺症の本質
変化は不連続に起きている、供給過剰の是正、問題の先送りをやめよ
- なぜ失敗を教訓にできないか
政治家の資質を問う、選挙民には選挙民の責任、縦割り行政では「土俵」ができない、建前だけの議論は不毛だ
- そもそも危機管理とは何か
シビアな議論を避けるな、デジタル化で生まれた新しい危機
- 日本史に埋まっている知恵
もともと融通無碍な国、機械以上の人間の感覚、歴史を学んで視点をかえよ
- 経験と教訓(様々な出会いの中で)
「地獄にお供します」、名誉欲を捨てた人ほど強い など