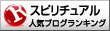同じ国で同じ言葉を母国語に持っていようと
その人の持つ感覚や、想像性がその単語にも意味を加えている。
もちろん、語彙の豊富さはある程度関係があるけれど
基本的な語彙の中でも差が生まれている。
同じことを表現するにも感覚が違えば
何となく使う単語にも違いは現れるし
その単語の持つ意味への感覚がが微妙に違うと受け取り方も変わる。
これが違う言語になれば尚更誤差は生まれているのだと思う。
どんなネイティブであっても
人間にとっての母国語は1つだと言われているのだから
途中から学んだ人たちでは大きな差だろう。
話を戻すと、この人が話すことは自分の中にスッと入る
または入ってこないということが起きるのは
言葉に対してもつ感覚が微妙に違うから。。。
普段の会話ではそう難しい問題にはならないけれど
それこそ、感覚的なものを言葉に置いて話てしまうと
この現象は如実に現れていく。
言葉の持つ力は1+1=2ではない。
個々の中で意味をイメージしてしまっているものだ。
だから同じ感覚を持つ人としか深い理解をしあえない。
言葉は便利な道具であり完璧な道具ではない。
知識はそこに生まれる創造を消してしまうのかもしれない。
知識は時には必要で、時には邪魔にもなる。
自分の創造性に蓋をしてしまう可能性もある。
本来持つ言葉はただの言葉だけでなく
そこに発生している広がりも汲み取ることで
必要な引き寄せも起こっているのだろう。