(2月11日)
主題(に近い表題の)ブログを2月3日に投稿したが、再訪があるのか、週を超した今も結構読まれている。こんな反響があった「最後の引用文はユーゴー・レミゼラブルからとあるが、出典を明らかにしてください」(ユーゴー愛読者群馬県60歳代)。最後の引用とは=泣く赤ちゃんには母が寄り添う、若者が悲しめば必ず娘が慰める。老人が嘆いても誰も声をかけない」(ユーゴー・レミゼラブルより)=を指している。縄文遺跡の荒廃を目の辺りにした老人(K氏)が愛犬チャビとともに泣き出した事情を語った。情景を現すに最適な文句と気づいて加えた。しかし、出典となる元の章頁を明らかにせず引用したのは、一巻にして2000頁の2巻作品、あわせて4000頁に及ぶ元本をひっくり返す余裕が投稿子にはその日になく、うる覚え記憶で書きいれた。
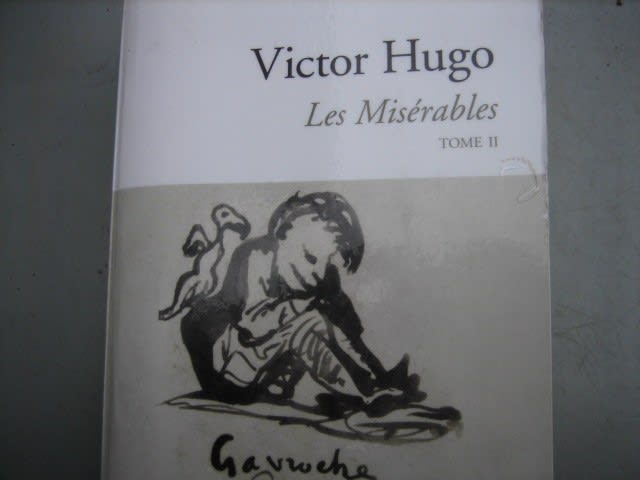
写真:同書第二巻の表紙。ガブロッシュは少年兵として30年争乱に参加した。彼も銃弾に倒れる。
そのあたりは気持ちの奥に引っかかっているうえに、貴重な指摘をうけたこの機会に4000頁を探ってみた。このブログサイトは訪問者が少ないに加え読者反応が全く希薄です。
さてぱらりぱらりの繰り返し、見つかりました。
<<La misere d’un enfant interesse une mere, la misere d’un jeune homme interesse une jeune fille, la misere d’un vieillard n’interesse personne. C’est de toutes les detresses la plus froide>(livredepoche版Les miserables第2巻第9のOu vont-ils1407頁、M.Mabeufの項)
訳;泣く子には母が寄り添う、悲しむ若者には娘が慰める、老人の悲しみはいかなる人の同情を引かない。あらゆる悲惨のなかで、それがもっとも冷たい(前回の訳とあまり変わらず)
文豪にしては珍しく<la misere><interesser>を3度繰り返している。
misereを調べるとsort digne de pitie, malheur extreme (robert micro)慰めに値する境遇、不幸の極限とある。これを3度繰り返す意味とは、極限が3通りとも同じ「程度」であると表現するために違いない。しかし、文の中身ではその程度が主体の加齢に同期して「深刻化」すると読者に気づかせるためであろう。
赤ちゃんは泣き声で彼のmisereを母に教える。その悲惨とはおなかがすいた、おしめが濡れている程度である。若者は何を嘆くのか。きっとおなかがすいた以上の悲惨を感じているのだろう。試験に通らなかった、作品が評価されないかもしれない。しかし彼には未来が残る、脇に寄りそう娘に優しく、明日があるわよと慰められているではないか。
しかし、老人の<misere>は生活か心情の破綻であろう、これこそが惨めに尽きる。人は彼にこそ慰めをかけるべきなのに、誰しも一片の同情、一言の慰めを寄せない。彼に母はいないし、脇に座る娘など期待できる訳がない。未来はとっくに視界から消えている。
3度繰り返したmisereの意味合いとは、若さの未来と老いの途絶を語ったものだ。ユーゴーとはどの文脈を選んでもロマンティシズムが流れている。
投稿子はこれを読んだ時に3様の惨めさがあるわけだから、寄り添う慰めるなどと分けて、その句を記憶していたが、読み返して、文豪の「単純すぎる」繰り返しの奥深さに気づいた。小筆の至らなさを露呈した。
さて、東京日野市、21世紀。
老人K氏が浅川土手でチャビとともに泣いたところで、人のひとりも声をかけてくれなかった。吹き抜けた北風よりも冷たい人情を、ユーゴーは19世紀も半ばにすでに喝破していたのだ。
廃墟にむせび泣くユーゴーの了
(2月11日)
補遺;Les miserablesで泣いた老人はMabeuf氏。物語のなか、フランス革命での国民公会議員に選ばれ、国王ルイ16世の死刑議決に賛成を投じた(1793年1月)。公会には700を超す議員が所属し、それぞれが死刑に賛成か否かを弁舌とともに表明した。結果、賛成387票(執行をのばす条件付きを含む)、反対334票で死刑が決まった。賛成した議員は王政復古(1814~1830年)となって、regicides(王殺し)とさげすまされたうえ、アンシャンレジーム政府から資産没収、公職追放など懲罰を被った。
Mabeuf氏は老いさらばえ、夕食の用意にも事欠く様となった。
<<M.Mabeuf ouvrit sa biblioteque , regarda longtemps tous ses livres l’un apres l’autre, comme un pere, oblige de decimer ses enfants...(同書1407頁)
マブッフ氏は書棚を開けて蔵書すべてを、長く時をかけて一冊二冊と眺めた。あたかも子の十分の一殺(decimer)を命じられた父親のように...
十分の一刑とは全員から十分の一の割で死刑とする制度。隊の動きが鈍いので要塞を落とせないなど(全員を殺せないから)で実行された(ローマの風習)。子をdecimerするとは飢饉か、あるいは懲罰か。ナチがパルティザンによる人的被害をうけた報復に、村にこの刑を実行した。
Mabeuf氏は公会議員にも選ばれた名士、しかし今は王朝、regicideに声をかける奇特な人はいない。往時に贅を誇って集めた稀覯本を一冊二冊と売り、生活をしのいだ。
売る本の種も尽きた最期に1830年の争乱に参加し命を失う。
主題(に近い表題の)ブログを2月3日に投稿したが、再訪があるのか、週を超した今も結構読まれている。こんな反響があった「最後の引用文はユーゴー・レミゼラブルからとあるが、出典を明らかにしてください」(ユーゴー愛読者群馬県60歳代)。最後の引用とは=泣く赤ちゃんには母が寄り添う、若者が悲しめば必ず娘が慰める。老人が嘆いても誰も声をかけない」(ユーゴー・レミゼラブルより)=を指している。縄文遺跡の荒廃を目の辺りにした老人(K氏)が愛犬チャビとともに泣き出した事情を語った。情景を現すに最適な文句と気づいて加えた。しかし、出典となる元の章頁を明らかにせず引用したのは、一巻にして2000頁の2巻作品、あわせて4000頁に及ぶ元本をひっくり返す余裕が投稿子にはその日になく、うる覚え記憶で書きいれた。
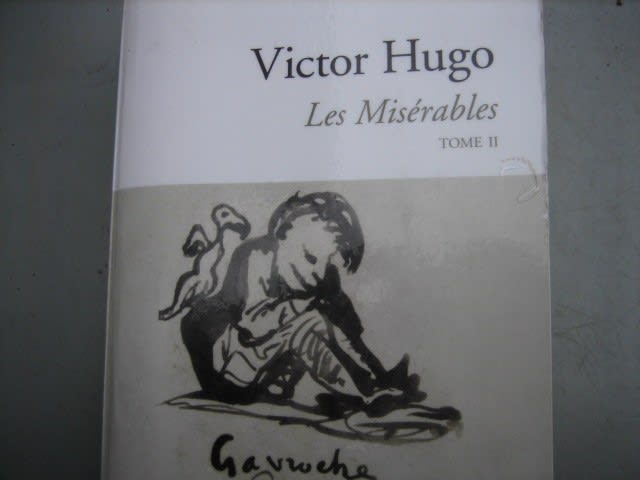
写真:同書第二巻の表紙。ガブロッシュは少年兵として30年争乱に参加した。彼も銃弾に倒れる。
そのあたりは気持ちの奥に引っかかっているうえに、貴重な指摘をうけたこの機会に4000頁を探ってみた。このブログサイトは訪問者が少ないに加え読者反応が全く希薄です。
さてぱらりぱらりの繰り返し、見つかりました。
<<La misere d’un enfant interesse une mere, la misere d’un jeune homme interesse une jeune fille, la misere d’un vieillard n’interesse personne. C’est de toutes les detresses la plus froide>(livredepoche版Les miserables第2巻第9のOu vont-ils1407頁、M.Mabeufの項)
訳;泣く子には母が寄り添う、悲しむ若者には娘が慰める、老人の悲しみはいかなる人の同情を引かない。あらゆる悲惨のなかで、それがもっとも冷たい(前回の訳とあまり変わらず)
文豪にしては珍しく<la misere><interesser>を3度繰り返している。
misereを調べるとsort digne de pitie, malheur extreme (robert micro)慰めに値する境遇、不幸の極限とある。これを3度繰り返す意味とは、極限が3通りとも同じ「程度」であると表現するために違いない。しかし、文の中身ではその程度が主体の加齢に同期して「深刻化」すると読者に気づかせるためであろう。
赤ちゃんは泣き声で彼のmisereを母に教える。その悲惨とはおなかがすいた、おしめが濡れている程度である。若者は何を嘆くのか。きっとおなかがすいた以上の悲惨を感じているのだろう。試験に通らなかった、作品が評価されないかもしれない。しかし彼には未来が残る、脇に寄りそう娘に優しく、明日があるわよと慰められているではないか。
しかし、老人の<misere>は生活か心情の破綻であろう、これこそが惨めに尽きる。人は彼にこそ慰めをかけるべきなのに、誰しも一片の同情、一言の慰めを寄せない。彼に母はいないし、脇に座る娘など期待できる訳がない。未来はとっくに視界から消えている。
3度繰り返したmisereの意味合いとは、若さの未来と老いの途絶を語ったものだ。ユーゴーとはどの文脈を選んでもロマンティシズムが流れている。
投稿子はこれを読んだ時に3様の惨めさがあるわけだから、寄り添う慰めるなどと分けて、その句を記憶していたが、読み返して、文豪の「単純すぎる」繰り返しの奥深さに気づいた。小筆の至らなさを露呈した。
さて、東京日野市、21世紀。
老人K氏が浅川土手でチャビとともに泣いたところで、人のひとりも声をかけてくれなかった。吹き抜けた北風よりも冷たい人情を、ユーゴーは19世紀も半ばにすでに喝破していたのだ。
廃墟にむせび泣くユーゴーの了
(2月11日)
補遺;Les miserablesで泣いた老人はMabeuf氏。物語のなか、フランス革命での国民公会議員に選ばれ、国王ルイ16世の死刑議決に賛成を投じた(1793年1月)。公会には700を超す議員が所属し、それぞれが死刑に賛成か否かを弁舌とともに表明した。結果、賛成387票(執行をのばす条件付きを含む)、反対334票で死刑が決まった。賛成した議員は王政復古(1814~1830年)となって、regicides(王殺し)とさげすまされたうえ、アンシャンレジーム政府から資産没収、公職追放など懲罰を被った。
Mabeuf氏は老いさらばえ、夕食の用意にも事欠く様となった。
<<M.Mabeuf ouvrit sa biblioteque , regarda longtemps tous ses livres l’un apres l’autre, comme un pere, oblige de decimer ses enfants...(同書1407頁)
マブッフ氏は書棚を開けて蔵書すべてを、長く時をかけて一冊二冊と眺めた。あたかも子の十分の一殺(decimer)を命じられた父親のように...
十分の一刑とは全員から十分の一の割で死刑とする制度。隊の動きが鈍いので要塞を落とせないなど(全員を殺せないから)で実行された(ローマの風習)。子をdecimerするとは飢饉か、あるいは懲罰か。ナチがパルティザンによる人的被害をうけた報復に、村にこの刑を実行した。
Mabeuf氏は公会議員にも選ばれた名士、しかし今は王朝、regicideに声をかける奇特な人はいない。往時に贅を誇って集めた稀覯本を一冊二冊と売り、生活をしのいだ。
売る本の種も尽きた最期に1830年の争乱に参加し命を失う。















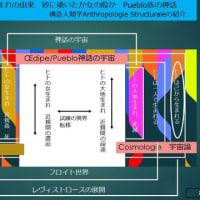












※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます