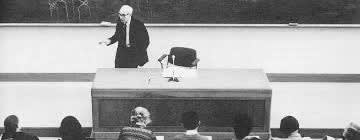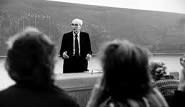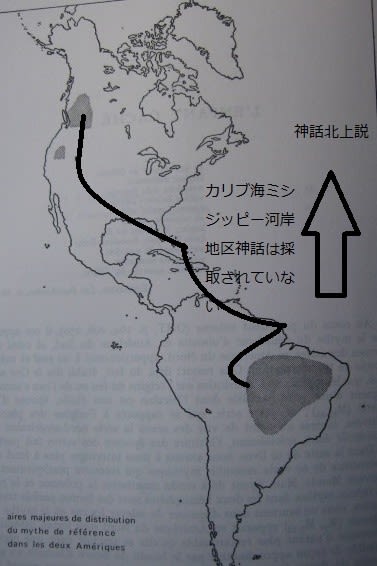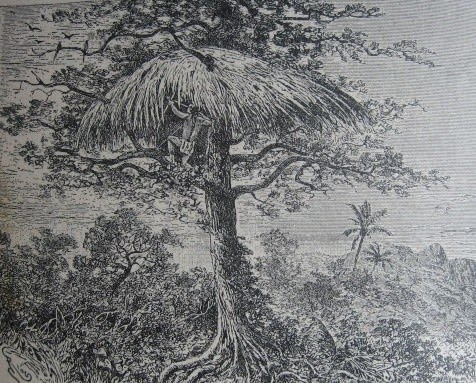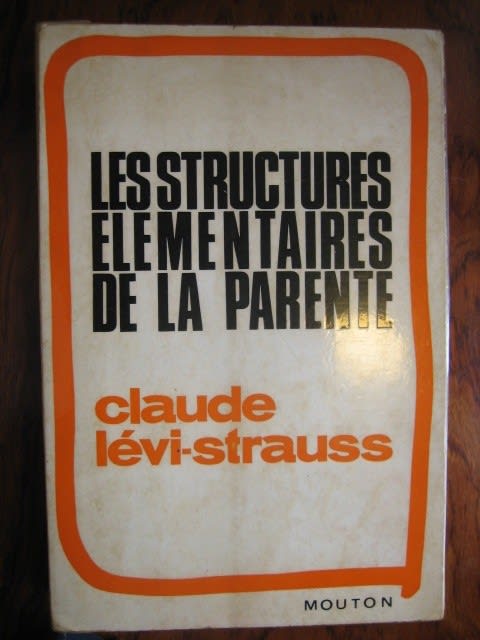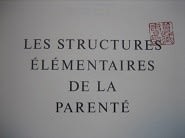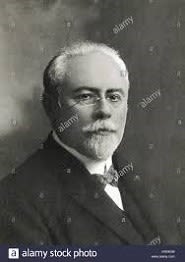未開人の幼児は西欧の幼児よりも劣るか?
レヴィストロースは少々手のこんだ策に入る。
>Toute tentative hasardeuse d’assimilation se heurterait, en effet, a la contestation très simple qu’il n’existe pas seulement des enfants, des primitifs et des allienes, mais aussi , et simultanement, des enfants primitifs , et des primitifs allienes< (103頁)
訳;向こう見ずの同一化の試みは単純な問題にぶつかる。子供、未開人、気の触れた者だけを(同じ発達レベル)として比定するだけでは事足りない、未開人の子供、未開人の気の触れた者も発達理論に組み込まなければならない。
注;向こう見ず...はこの文節の直前に「あらゆる発達の変異を統合する理論がいずれ構築される」との予言に対しての返答。assimilation同一はピアジェの学説総体の換喩と解釈できる。
続いて
>Cette objection vaut d’abord , contre les etudes récentes consacrees aux entants dits ‘primitifs’, non parce qu’ils appartiennent a des sociétés différentes a la notre, mais parce qu’ils manifestent un incapacite d’accomplir certaines operations logiques. Ces travaux font d’alleus apparaitre une difference, et non une ressemblance, entre les anomalies de la pensee infantiles et la pensee primitive normaqles.<(同)
訳;この (ピアジェに対する) 反論は、「未開人」の子供性状は(彼自身の予測と)研究結果とが異なっていた。なぜならば(その差違が)未開社会に由来するのではなく、(「未開」とされる子)彼らの論理遂行能力に欠陥があるからとしている。その意味で価値がある。
「彼自身」とは訳注で、その「彼」は後文に出てくる。
それにしても上の2の引用は唐突感が強い。訳を試みながら具体性が弱い、前述、前々述の意味する処との絡みに理解が回らなかった。続く文で種明かしが出てくる。
>A la difference de la pensee magique de l’homme primitif, ou la connection entre les idées est prise pour une connection entre les phénomènes, les enfants etudies prennent la connection entre les phenomenes pour une connection entre les idées<(同)
訳;未開人成人が持つ魔術に対する考え方は、あらゆる思考を結ぶ体系は事象を結びつける為にあるが、研究対象とした(未開の子とされる)子達は思考を結ぶ体系のために事象の結びつきを見つける。
Vygotski(発達心理学のもう一方の雄)の引用(The problem of the cultural development of child 425頁 1929年)です。この一文を導入する為に上記2文節を唐突にも差し挟んだ。

写真はネットからヴィゴツキー
この引用を理解する為に小筆はある例を思い出した;
1 幼児の理解「雪かき車は雪を食べて生きている」(NHKの読者投稿番組の聞き留め)。幼児が雪を「食べる」事象を目撃し、生きるために食べる「思考」に結びつけた。
2 魔術の考え方「不幸な死は祟る」との思想が先に立ち、天変地異に結びつける(崇徳天皇、菅原道真などの例)。飢饉は道真の死霊が祟っているのだと。
ここにピアジェとヴィゴツキーが並んだ。しかし発達心理学の深みには部族民蕃神は入り込めない。ネット情報と若干のコメントを入れる。
>子どもは内言(独り言)を習得していくことで、ことばを思考の道具として使いこなせるようになり、黙読できるようになります。小学校低学年ではほぼ内言を使いこなすことはできないものの、小学校3~4年生以降くらいには内言が完成し、自分の頭のなかで思考することができるようになります<(ネットサイト3分で読めるヴィゴツキーから)
ピアジェは発達段階を外容と内実に分け「構造化」し、外界刺激で構造そのものが変態するという、いわば機械論を展開した(蕃神)、ヴィゴツキーは外界に言語、教育などを当て、内実の発展を説いた、目的論と言える。(レヴィストロースが指摘する)ピアジェ説の欠陥の構造体の変遷とハイパーコンバージェンスはヴィゴツキーで解消されている。
言語、教育を文化(神話、通過儀礼)に置き換えれば「未開」人の発達様態は文明人のそれと変わらないと言い切れる。
この後には、未開人の社会での成人と子供の差異、世代間の葛藤など民族誌学の観察を紹介に入る。世代差異は、文明社会でも同じく観察できる。これらが意味する処は、文明と未開の系統発生、それら着地点の優劣、その結果の「未開人」の演繹思考の欠如説は誤りを導くに他ならない。
未開人の幼児も西欧の幼児も同じ立ち位置を占める。
傍証として幾人かの心理学者の見解が紹介される。
>Il ne faut pas croire a je ne sais quelle misterieuse necessite interne qui ferait repasser l’evolution individuelle par tous le chemains tortueux de histoire....La ’repetition’ ontogenerique n’est qu’une fausse histoire : elle est plus tot une selection de modeles offerts par la langauage...<(105頁)(P.Guillaume)
訳;私にはとても理解できない仕組みなのだが、何らかの神秘的な必要性が精神の内側に存在しそれが個の進化を、遅々として長き(系統の)歴史を用いて、再発生させる、こんな戯言を信じてはならない。個体発達が繰り返されるとは「偽り」の話しでしかない。それは言語体系が提供する種々の選択肢からある一つを選ぶ作業である。
(少々強い訳である。それは’je ne sais quelle’(知るものか)、ferait(faire起こす動詞の条件法だからあり得ない事象)、fausse偽り...など文全体で否定の強さを見せる点に留意したから)
Paul Guillaume(1878~1962年)ゲシュタルト心理学(それ以上の解説はネットで見られない。著作は多い)
>La culture la plus primitive est toujours une culture adulte, et par cela meme imcompatible avec les manifestation infantiles qu’on peut observer dans la civilisation la plus elevee.(107頁)S.IsaacsのIntellectual growth in young childrenからの引用
Susan Isaacs(1885~1948年イギリス)幼児教育
訳;最も「未開」とされる文化でも「成人」の文化です。それは最も進化している文明の子供が現す言行とは一致しない。

写真はSusanIsaacsネットから
両氏の引用をヴィゴツキーの引用文と併せ読むと理解が早い。ピアジェ発達説の否定と受け止められる。最後にレヴィストロースの言葉を;
>La ‘regression’ apparente n’est donc pas un retour a un stade archaique de l’evolution intellectuelle de l’individu ou de l’espece : c’est la reconstition d’une situation analogue a celle qui preside aux debuts de la pensee individuelle seulement<
訳;(未開とされる社会に)際だつ後退とは系統、あるいは個体の知的進化の古典段階への逆転現象ではない。人の思想に宿る進化過程の原初に位置する思考を再現しているだけである。
意味の深い一言です。部族民蕃神の解釈は動詞のpreside(現在形)を注視するから過去に個人を仕切っていた状態ではない。その場合はpresida(単純過去)を用いる。すると個人が先験として持つ智を再現したのだとなる。ここでカントに行ってしまうが、常に平凡さ(banalite)に陥る悪癖のなせる処だから、読者諸氏に解釈を譲ります。了
最後に;
レヴィストロースが批判するピアジェの論点は「未開」社会を幼児的社会とした進め方にあります。未開人の個体発達の起点は文明人のそれよりも劣位にあるとした、系統発達と個体発達を組み合わせの様(向こう見ずな同一化)を批判している。実学としての発達心理学、それが今も教育現場で応用されている実情を批判している訳ではありません。