(2023年7月25日)前回(23日)投稿の最後行は : « pour atteindre le réel il faut d’abord répudier le vécu, quitte à le réintégrer par la suite dans une synthèse objective dépouillée de tout sentimentalité » (61頁) 訳; 真実réelに行き着くにはまず現実世界を退け、続いてあらゆる感覚(sentimentalité)をはぎ取った「synthèse objective客観的統合」の手法で現実を再構築する。なにやらかが分からないsynthèse objectiveを持ち出した。これを一応、客観的統合として受け入れる。
では,
現象論がsynthèse objective客観的統合をしてvécuとréelを結びつける仕組みを探ると :
メルロポンティが伝える体験する場vécu、彼の語でmilieu(場)とはあらゆる信号が混じり合う混濁の視界世界です。横溢する光、色、形の(体験している)外景から真実信号のみを抜き取り、サントヴィクトワールの山容をキャンバスに真に描き、その姿こそ神が創造した実際réelだとしたセザンヌを例にあげている。音の入り交じりの混濁からオペラ魔笛を作曲したモーツアルト、言葉の氾濫から詩を綴ったランボー(例:L'étoile a pleuré rose au cœur de tes oreilles / l’homme saigné noir à ton flanc souverain (お前の耳の紅を垂らす涙が星の戸惑い、お前の腹の慎みに男は黒い血に染まるVoyellesより) を取り上げ神が創造した真の姿réelを求めるのは人の知覚(創造)としている。
ChampとRéel, ここには視野と知覚との断絶がある。
(以上はMerleau-Ponty著Causerieから。なお彼は場が「混濁、混沌する」とは言っていない。場にしても神が創造しているので、混乱を見せるわけがない。あるがままの状景としていた)。

Collège de Franceでの「講義神話学、裸の男」模様(1968年頃)
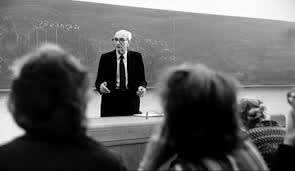
知覚(perception)を通して、vécuの場から意味をなす信号を取り出してréel世界に仕上げる。レヴィストロースが指摘した「客観的統合」は、ポンティの主張する知覚perceptionであった。デカルトがコギト(神から授かった智)で本質を解析した手順と、人に備わる神よりの贈り物、知覚を探りあげた進め方は、出発点は異なるものの、デカルトと同様です。
なお上引用で手の込んだ修辞をレヴィストロースが用いている。(邦訳本には言及がなかったので)訳注として ; 女主人(maîtresses)とは男主人(maître)の女性形なるも、独自の用法が控える。愛されている若い(可愛い)女、チヤホヤされるから威張っている。これが発展して口煩い女、さらには妾メカケに煩さが敷延している。これらは始めから女性形のmaîtresse、ここには尊敬の含意は希薄である(以上はRobertから)。
ではここでの「mes trois maitresses私が愛するこ煩い3の中年女」とは誰か。前文に女性(形)探すと、2人は(psychanalyse géologie)見つかる。さらなる一人は女性に「性転換」したla marxismeマルクス主義が出てきた。文法を逸脱させて3人の煩い中年女を表に出した。Maîtreとしたらは尊敬の意を含む、marxismeに当てるに躊躇する。一からげに中年女と束ねて、口うるささと定見の欠如を強調した。性転換にレヴィストロースの修辞が隠される(一部、ワケ知りの識者はレヴィストロースを共産主義よりとするが、全くの誤解です)。
筆は実存主義にすすむ ;
« Quant au mouvement de pensée qu'il allait s'épanouir dans l'existentialisme, il me semblait être le contraire d'une réflexion légitime en raison de la complaisance qu'il manifeste envers les illusions de la subjectivité. Cette promotion des préoccupations personnelles à la dignité de problèmes philosophiques risque trop d’aboutir à une sorte de métaphysique pour midinette, excusable au titre de la procédé dialectique, mais fort dangereuse si elle doit permettre de tergiverser cette mission dévolue à la philosophie jusqu'à ce que la science soit assez forte pour la remplacer, qu'il est de comprendre l'être par rapport à lui-même et non point par rapport à moi. Au lieu d'abolir la métaphysique, la phénoménologie et l'existentialisme introduisaient deux méthodes pour lui trouver des alibis » (同)
実存主義が花開くに向かった思想の流れについて、正統性を帯びる考慮とは逆の方向だと私は思えた。理由は主観性の幻想、かつそこに安住しているからである。哲学課題に個人性を持ち込む思い込み、それ故に「お針子」哲学に陥る危険、弁証法をお題目にした言い逃れと批判する。弁証法は哲学に対して然るべき使命を持つ、しかしこの科学(実存的弁証法)が哲学に取り替わると言いくるめるのであれば、危険な思考であると言わざるを得ない。存在はそれ自身が考える。私(moi)との対峙で考えるものではない。現象論と実存主義は形而上学を否定した思考ではない。別々の論点で存在(前分のl’être)に逃げ場を提供したのだ。
訳注:パリのお針子は針と布を両手に持ち、針で糸を縫えば布がつながる、これを経験して後「お針子理性」を獲得した。この実存過程をお針子哲学とレヴィストロースが名付け、実存主義の主張はそれと同類と見破った。
2:最後の文句「存在へ逃げ場を」
« la phénoménologie et l'existentialisme introduisaient deux méthodes pour lui trouver des alibis » 存在(前分のl’être)に逃げ場を提供したのだ。
Pour lui彼のために、彼はl’êtreを指す。現象論と実存主義が存在に逃げ場を与える。何を意味するか ;
現象論とはレヴィストロースによれば存在を「客観的統合」して信号(理性)に変える。「見える世界」から「見えない世界」を再構築する(前述)。存在を知覚するperceptionは官能則に属するけれど、見るは発端で理性活動の客観性objectivitéを駆動して、森羅を見えない世界に「再構築」を踏む、この工程が存在に逃げ道alibisを与えていると言える(レヴィストロースは現象論を否定する立場を採らない)。
ではサルトルは ;
森羅とは存在、存在を経験してヒトは自由になれる(理性を獲得する)。この実存主義にレヴィストロースが噛み付いたのは「経験を通して個が理性を修得する」絡繰り。これは存在を大上段に構えて蘊蓄を傾けた思考であり、(思考の対象にならない)存在を取り上げ、「理性付き」の隠れ場alibisを与えた。
その工程は「個人の思い込みpréoccupations personnelles」にすぎないとレヴィストロースに全否定される。
(サルトル実存主義を批判するのは、ある意味、易しい。「個人の経験」が個人の理性を育成するのだとしたら、個人それぞれの理性は個々バラバラになってしまう。世界中のヒトの理性とは論理、演繹帰納、因果律に統一されているから、それとは真逆の説明を展開している。理性とはデカルト、カントが曰わった如く、ヒトは神から理性を授かった、としか考えられない)
レヴィストロースはこれに続く著作「野生の思考」で1章の全行をサルトル批判に費やしている(歴史と弁証法Histoire et dialectique)。
悲しき熱帯61頁 旅の紙片 了(7月25日)
では,
現象論がsynthèse objective客観的統合をしてvécuとréelを結びつける仕組みを探ると :
メルロポンティが伝える体験する場vécu、彼の語でmilieu(場)とはあらゆる信号が混じり合う混濁の視界世界です。横溢する光、色、形の(体験している)外景から真実信号のみを抜き取り、サントヴィクトワールの山容をキャンバスに真に描き、その姿こそ神が創造した実際réelだとしたセザンヌを例にあげている。音の入り交じりの混濁からオペラ魔笛を作曲したモーツアルト、言葉の氾濫から詩を綴ったランボー(例:L'étoile a pleuré rose au cœur de tes oreilles / l’homme saigné noir à ton flanc souverain (お前の耳の紅を垂らす涙が星の戸惑い、お前の腹の慎みに男は黒い血に染まるVoyellesより) を取り上げ神が創造した真の姿réelを求めるのは人の知覚(創造)としている。
ChampとRéel, ここには視野と知覚との断絶がある。
(以上はMerleau-Ponty著Causerieから。なお彼は場が「混濁、混沌する」とは言っていない。場にしても神が創造しているので、混乱を見せるわけがない。あるがままの状景としていた)。

Collège de Franceでの「講義神話学、裸の男」模様(1968年頃)
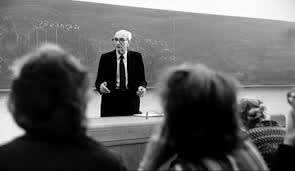
知覚(perception)を通して、vécuの場から意味をなす信号を取り出してréel世界に仕上げる。レヴィストロースが指摘した「客観的統合」は、ポンティの主張する知覚perceptionであった。デカルトがコギト(神から授かった智)で本質を解析した手順と、人に備わる神よりの贈り物、知覚を探りあげた進め方は、出発点は異なるものの、デカルトと同様です。
なお上引用で手の込んだ修辞をレヴィストロースが用いている。(邦訳本には言及がなかったので)訳注として ; 女主人(maîtresses)とは男主人(maître)の女性形なるも、独自の用法が控える。愛されている若い(可愛い)女、チヤホヤされるから威張っている。これが発展して口煩い女、さらには妾メカケに煩さが敷延している。これらは始めから女性形のmaîtresse、ここには尊敬の含意は希薄である(以上はRobertから)。
ではここでの「mes trois maitresses私が愛するこ煩い3の中年女」とは誰か。前文に女性(形)探すと、2人は(psychanalyse géologie)見つかる。さらなる一人は女性に「性転換」したla marxismeマルクス主義が出てきた。文法を逸脱させて3人の煩い中年女を表に出した。Maîtreとしたらは尊敬の意を含む、marxismeに当てるに躊躇する。一からげに中年女と束ねて、口うるささと定見の欠如を強調した。性転換にレヴィストロースの修辞が隠される(一部、ワケ知りの識者はレヴィストロースを共産主義よりとするが、全くの誤解です)。
筆は実存主義にすすむ ;
« Quant au mouvement de pensée qu'il allait s'épanouir dans l'existentialisme, il me semblait être le contraire d'une réflexion légitime en raison de la complaisance qu'il manifeste envers les illusions de la subjectivité. Cette promotion des préoccupations personnelles à la dignité de problèmes philosophiques risque trop d’aboutir à une sorte de métaphysique pour midinette, excusable au titre de la procédé dialectique, mais fort dangereuse si elle doit permettre de tergiverser cette mission dévolue à la philosophie jusqu'à ce que la science soit assez forte pour la remplacer, qu'il est de comprendre l'être par rapport à lui-même et non point par rapport à moi. Au lieu d'abolir la métaphysique, la phénoménologie et l'existentialisme introduisaient deux méthodes pour lui trouver des alibis » (同)
実存主義が花開くに向かった思想の流れについて、正統性を帯びる考慮とは逆の方向だと私は思えた。理由は主観性の幻想、かつそこに安住しているからである。哲学課題に個人性を持ち込む思い込み、それ故に「お針子」哲学に陥る危険、弁証法をお題目にした言い逃れと批判する。弁証法は哲学に対して然るべき使命を持つ、しかしこの科学(実存的弁証法)が哲学に取り替わると言いくるめるのであれば、危険な思考であると言わざるを得ない。存在はそれ自身が考える。私(moi)との対峙で考えるものではない。現象論と実存主義は形而上学を否定した思考ではない。別々の論点で存在(前分のl’être)に逃げ場を提供したのだ。
訳注:パリのお針子は針と布を両手に持ち、針で糸を縫えば布がつながる、これを経験して後「お針子理性」を獲得した。この実存過程をお針子哲学とレヴィストロースが名付け、実存主義の主張はそれと同類と見破った。
2:最後の文句「存在へ逃げ場を」
« la phénoménologie et l'existentialisme introduisaient deux méthodes pour lui trouver des alibis » 存在(前分のl’être)に逃げ場を提供したのだ。
Pour lui彼のために、彼はl’êtreを指す。現象論と実存主義が存在に逃げ場を与える。何を意味するか ;
現象論とはレヴィストロースによれば存在を「客観的統合」して信号(理性)に変える。「見える世界」から「見えない世界」を再構築する(前述)。存在を知覚するperceptionは官能則に属するけれど、見るは発端で理性活動の客観性objectivitéを駆動して、森羅を見えない世界に「再構築」を踏む、この工程が存在に逃げ道alibisを与えていると言える(レヴィストロースは現象論を否定する立場を採らない)。
ではサルトルは ;
森羅とは存在、存在を経験してヒトは自由になれる(理性を獲得する)。この実存主義にレヴィストロースが噛み付いたのは「経験を通して個が理性を修得する」絡繰り。これは存在を大上段に構えて蘊蓄を傾けた思考であり、(思考の対象にならない)存在を取り上げ、「理性付き」の隠れ場alibisを与えた。
その工程は「個人の思い込みpréoccupations personnelles」にすぎないとレヴィストロースに全否定される。
(サルトル実存主義を批判するのは、ある意味、易しい。「個人の経験」が個人の理性を育成するのだとしたら、個人それぞれの理性は個々バラバラになってしまう。世界中のヒトの理性とは論理、演繹帰納、因果律に統一されているから、それとは真逆の説明を展開している。理性とはデカルト、カントが曰わった如く、ヒトは神から理性を授かった、としか考えられない)
レヴィストロースはこれに続く著作「野生の思考」で1章の全行をサルトル批判に費やしている(歴史と弁証法Histoire et dialectique)。
悲しき熱帯61頁 旅の紙片 了(7月25日)


















