
昭和19年十月十五日。岩国沖。
第五艦隊。重巡「那智」通信室。
ここに、立松がおります。
海軍少尉。
遡る事、昭和18年8月31日。立松は海軍少尉に任官しております。
「海軍兵科第二期予備学生」だったのです。
さて、重巡那智は、レイテ沖海戦時に於いて、「志摩艦隊」の一翼として出撃致します。
その後の那智の詳細につきましては、「くだまき」の得意とするところでもございますが、割愛致します。
昭和18年10月25日、マニラ湾にて、空母「レキシントン」の部隊により撃沈されております。
807名もの戦死者を出します。生存者は220名。
この220名の中に立松もおりました。
立松はその後「第101航空戦隊司令部付」となります。部隊は厚木から横浜水上、そして伊賀へ移転します。
そこで終戦を迎えます。
那智は大破でした。そこからの生還者。奇跡に近い。
上記は、「不当逮捕」の一節です。
酔漢は、「横須賀鎮守府公報」を調べましたが、立松少尉を見つける事は出来ませんでした。(これは調べ方が悪いのかもしれません。引き続き調べます)
さて、終戦後、立松の取った行動は異常です。
まず最初に、部隊の倉庫から「拳銃」と「弾薬」を持ち出します。
実家の庭に倉庫を作り、ここに隠します。
何の為か。
本人の遊びです。
自分で的を作り、東急東横線を電車が通過するたびにその的に向かって撃っているわけです。(電車の音で銃声が聞こえないようにしております)。
一節には、「野良犬」を標的にしていたとの噂もでる程。
彼の屈折した一面を見る事が出来ます。
彼がどうして、「読売新聞社 社会部記者」に成り得たか。
当然、時の社主「正力松太郎」の存在が出てまいります。
立松は侑諸ある家系。軍に於いても、代々上級将校を輩出し、司法の場に於いても祖父、父との上級判事でした。これは先の「くだまき」でも語ったところです。
でも社内では、その詳細を知る者はおりませんでした。
本田靖春氏は、「立松は拳銃以上の物を手に入れた。簡単にして人を殺傷出来うる、ペンを持たされたのだから。彼が記者としての仕事に快感を覚えたのも彼の性格からは納得できる」
こう著しております。
立松和博を戦中からその経歴を掻い摘んでお話しいたしました。
さて、お話しを昭和32年10月に戻そうと思います。
前回の続き、立松が愛車「ビュイック」を駆って銀座から朝帰りのところからです。
朝日の尾川が、徹夜明けで社から戻ろうと、日本橋付近を歩いております。
一緒にいる記者が赤い外車を目撃致します。
「尾川さん。あれ、すごいですねぇ。外車ですよ外車!真っ赤な奴!こんな時代になったんですねぇぇ・・」
「何だと!赤の外車!」
ふと、先を見ますと、ビュイックがこちらへ向かって来ます。
「おい!ヨミウリのタテマツ!あのやろう!!」
「あれが、立松の車?」
「あんなもん、この日本に何台あるのかよ!立松に決まっている」
ビュイックは、その前で止まります。
「朝日の尾張さん!おはようございます」
「立松、お前なぁ、何してんだよ!」
「いやぁ、取材!ってね・・・言いたいんだけど」
車の中には、女の子が数名(車の中めい一杯に乗っけている状態)おります。
「おまぇ、女ばかり連れて居やがって。取材なんて嘘っぱちやろう!」
「これから、この子達を家までおくらなきゃいけないんで。じゃぁ」
大きな音を立てて車を走らせていきます。
「畜生!タテマツぅぅ」
その日の朝刊は、前回ご紹介いたしました。
各社が歯ぎしりをして悔しがった事も。
立松は、社には戻っておりませんが、大きな事件が勃発致します。
翌10月19日。新聞記事に名前の掲載された「福田」「宇都宮」は当然、読売新聞本社に対して「事実無根」と抗議をいたします。
しかし、両名の取った行動はこれだけではありませんでした。
同日、午後、「東京地方検察局」へ「名誉棄損の疑い」で告訴致します。
告訴の対象として「記事出筆の記者」「小島読売新聞編集局長」。情報提供者としての「某検事」と上司たる「野村検事正」「花井検事総長」でした。
翌日には、検察への出頭を立松は受けております。
10月24日未明。
読売新聞社社会部内。
「おかしい、この早さは、一体何だ。これまでの検察の動きとは違っている」
立松が話し始めております。相手は同じ社会部記者の先輩「三田」。
「第一、告訴状が受理されて一週間経たない内に(実際は6日目)呼び出し、俺が取材をしてきた数々の事件でも・・・これは聴いたことが無い」
「そう、俺もそう思う。第一この手回しの良さは、『名誉棄損』では絶対にない事例だ」
「売春汚職そのものの捜査はこれからなんだ。白黒つかないうちにだぜ。高検が『名誉棄損』だなんて、言えるわけないんだ!」
「うーーん。立松よ。対して意味を持たない。こう考えられないか?顔だせば?お前のことだから簡単に済むんじゃないか?」
三田は、東京高検主任検事「川口」との昨日のやり取りを思い出して、立松へこう話しております。
「じゃぁ出かけるか。午後にでも」
午前4時。
二人は記者室の仮眠室へ向かいました。
10月24日。午後4時。東京高検内。三階「公安検事室」
先に、部屋で取調べを受けていた滝沢が立松の顔を見るなり。
「立松さん!川口検事ったらひどいんですよ!何度も、何度も、記事の出所を教えろ!これしか言わないんですから!」
立松の顔色が変わります。
(そうか。高検が知りたかったのは、「ニュースソース」だったのか!冗談ではない!)
川口は滝沢への態度とは違って、立松には穏やかに話始めた。
立松と川口は旧知の間でありました。
「立松さん、久しぶりじゃないですか。僕が東京を出た間に大きな病気をして大変な思いをされたと聞きましたが。お体の方はもうよろしいのですか?」
「まぁな!川口さん、こんな事を聴くために俺を呼び出したんじゃないんだろ?」
「出張先から呼び出しされてねぇ。君の事件にかかわるとは思ってなかったんだけど。僕が君と旧知の間柄とは知られているんだ。君には遺恨を残したくないし、また、感情的になったと思われるのも嫌だから、この取調べは大津検事に頼もうと思うんだが、どうだろう」
「遠回しに話さなくても、俺はかまわんよ」
立松は、やはり遠回しにしか話しが出来ない川口の立場は理解出来ているものの、内心「ニュースソースを話せって!冗談じゃない!」と考えているのでした。
大津検事との会話は、「取調べ」と言うよりもこれは手続き的なものであったから、立松も少しは息を抜くことが出来ました。
「手洗い。行っていいか?」
立松がトイレへ入ると、昔取材した検事と鉢合わせになります。
つれション状態でその検事は立松にこう耳打ち致します。
「岸本さん(検事長。高検No2)が君を逮捕すると言っている」
立松は、腹をくくるしかありませんでした。
(やはりな。あいつが絡んでいやがった!)
「電話、少しでいい。借りられないか?」
その検事は嘗て立松へ情報を提供したこともある検事でした。
自室へ連れて行きます。
10月24日。午後7時。読売新聞社社会部内。社会部警察回り。萩原の電話が鳴る。
「立松!どうした?」
「今、高検内。ある検事の部屋。手短に言う。メモ取れ。いいか、一字一句漏らすなよ!俺は逮捕される。社内のメモを処分する。自宅へガサ入れがあるだろう。そこは頼む。検察を挑発しないように。以上。部長へ伝える事」
電話はこれで切れました。
「部長!立松からです。高検から電話です。部長にこれを」
今しがた、取ったばかりのメモを部長に渡します。
「何だって!立松が逮捕だとぉぉ。容疑は何だ?『名誉棄損』?これじゃ、おかしいじゃないか!」
「おそらくですよ。部長。これは憶測なんですがね」
社内きっての参謀と呼ばれ、冷静である萩原はこう続けました。
「『証言拒否』これではないかと。いわゆるその線での容疑としか・・・」
「それにしても、おかしいじゃないか。萩原君、三田君と明日、高検へ行ってみてはくれんか」
「そうします」
10月25日。午後。東京高検内。
岸本の立場は検事長。現在は高検N02。
萩原と三田は、訪ねて行った「岡原次席検事」の部屋にどうして、岸本がいるのかが不可解でした。
陣頭指揮をモットーとしている岸本です。
彼が、ここに居るという事は、立松の一件が、岸本自らが指揮を取っているという事を物語っているのでした。
三田も萩原も一新聞記者の記事に発端とされる事件の割には、物々しいものである事を感じざるを得ませんでした。
萩原は、直接、岸本に対して聞き出そうとします。
「おかしいじゃありませんか!立松を宣誓供述に回すことだけは止めてもらいたい!」
「おや、単刀直入に聞いてくるねぇ。そんな事はせんよ、安心したまえ。大所高所から判断して、正々堂々とやるだけだよ」
岸本の薄ら笑いが、妙にに自信たっぷりです。
「どういう意味なんだ!」
「名誉棄損がはっきりしているじゃないか」
「ですがね。いいですか。記事そのものが重要な証拠となる『名誉棄損』においてですよ。もはやおおくの読者に目に触れ、今となっては回収は不可能でしょ。この記事で起訴か不起訴か決める。これは過去の事件を見ても明らかじゃないですか!立松の逮捕はもはや必要たる理由がない!」
さらに萩原は岸本に突っ込みます。
「何言ってるんだ。過去は過去。必要か不必要かは、こちら(検察)が決める事だ!」
「過去はこうですよね『真相事件』(共産党系出版物事件)と、恐喝と絡んでいた『政界ジープ事件』があるだけです!立松逮捕は、大きな社会問題になる!」
岸本は再び笑みを浮かべます。
「これから、会議だ。君たちと議論している暇なぞ無いんだ!失敬する!」
岸本は、部屋を去ろうとしております。ドアに手を掛けたそのとき、岸本は萩原の方を振り向きます。
「君たちは大変な弁護士を雇ったようだね」
これだけ言い残すと、岸本は、部屋から出て行きました。
「三田君、我々側に『木内弁護士』がいる事を岸本は知っている・・どうして・・・」
検察内で、岸本と木内が「犬猿の仲」でいる事は、誰しもが知っていることなのでした。
10月24日。東京高検。大会議室。立松と川口検事。
「立松君。大津検事からはどんな事を聴かれた?」
「どうにもこうにもない!ニュースソースを明かせ!これだけ。物別れ」
「立松君、強硬手段を取りたくはない。これは解ってくれたまえ。ニュースソースを言ってくれたら、君はここから出られるんだから」
「冗談じゃない!そんな気はさらさらないね!記者やめろ!ってことと同じじゃないですか!」
「そこまで考えなくたって・・・」
「ああ、同じだ!川口検事。あなたは、記者としての私を殺そうというのですか!」
立松には計算がありました。「自身の逮捕」は、最悪の事態として想定はしているのですが、「まさか、そこまでは高検はしてこない」こうした見方の方が確立的に高いと考えております。
「そこを、何とか、話してくれないか!」
「ダメだ!絶対に話さない!ニュースソースを話すことだけは出来ない!」
延々と同じ質問、回答が続きます。
「川口検事、ですがね、『売春汚職』の結末を見ないこの時期に新聞記者である私の逮捕に何の意味があるんですか?」
「・・・・・・・・・・・・」
この質問には、答えない川口。
沈黙が長い。
午後10時。会議と称して、中座していた、大津が部屋に入ります。
書類を携えております。
何やら、川口とひそひそ話の後、立松の正面に座りました。
「立松さん。御気の毒なのですが・・・・・」こう切り出された立松。次の言葉は想像しております。
「あなたを逮捕することになりました」
午後11時。会議室、隣室。
「川口検事、僕はどこに留置されるんだい?」
「とりあえず、丸の内」
立松は「丸の内署」へ拘置されます。
10月25日。読売新聞社、社会部内。応接室。
小島編集局長。景山社会部長。長谷川社会部次長。記者、萩原、三田。
「新聞記者が、事実と違ったからって、逮捕される?こんな事は聴いたことは無い!」
「だったら、逮捕されて無罪になったら、その検事は逮捕されるか?それと同じ理屈なんだ!」
「職権乱用じゃないか!人権侵害もいいところだ!」
いきり立った景山は、壁に灰皿を投げつけます。
全員がその行動に驚きます。
「冷静」萩原同様、これは景山の呼び名でもあったのです。
「おかしい。妙だ・・・・そうは、思わんか?」
長谷川がようやく口を開きました。
「何か、言論統制的な匂いも感じる・・」
「岸本の噂が気になります」
三田が切り出しました。
「なんだね?」
「去年の秋、競馬好きな代議士『河野一郎』農林大臣の時ですね。自分の経営する牧場にですよ、英国産の種馬を輸入してまして、そのう関税法違反で地検で捜査していたんですよ。輸入元の商社の社員が、河井検事が知らない内に、釈放されて・・・事件は闇の中。これは、そうも岸本の差し金だったとこれは噂なんですがね・・」
「じゃぁ。裏では、政界と岸本の癒着がかぁ?」
「それだけじゃない。造船疑惑のときの岸本は、どちらかと言うと『われかんせず』でしたからね。特捜の生みの親、馬場事務次官が、検察の人事権を握っているほどに立場が逆転したわけです。」
「馬場が目の上の瘤だと岸本が思っているのか?」
「これは確かです」
「検察内の派閥抗争!」
「合点がいく!」
話しを先に進めます。
立松逮捕の記事。
下記。

10月26日、読売朝刊一面。
この記事が掲載されるのは、立松逮捕から翌々日の事なのでした。
立松の拘置生活。取調べは、並みのものではなかったのでした。
第五艦隊。重巡「那智」通信室。
ここに、立松がおります。
海軍少尉。
遡る事、昭和18年8月31日。立松は海軍少尉に任官しております。
「海軍兵科第二期予備学生」だったのです。
さて、重巡那智は、レイテ沖海戦時に於いて、「志摩艦隊」の一翼として出撃致します。
その後の那智の詳細につきましては、「くだまき」の得意とするところでもございますが、割愛致します。
昭和18年10月25日、マニラ湾にて、空母「レキシントン」の部隊により撃沈されております。
807名もの戦死者を出します。生存者は220名。
この220名の中に立松もおりました。
立松はその後「第101航空戦隊司令部付」となります。部隊は厚木から横浜水上、そして伊賀へ移転します。
そこで終戦を迎えます。
那智は大破でした。そこからの生還者。奇跡に近い。
上記は、「不当逮捕」の一節です。
酔漢は、「横須賀鎮守府公報」を調べましたが、立松少尉を見つける事は出来ませんでした。(これは調べ方が悪いのかもしれません。引き続き調べます)
さて、終戦後、立松の取った行動は異常です。
まず最初に、部隊の倉庫から「拳銃」と「弾薬」を持ち出します。
実家の庭に倉庫を作り、ここに隠します。
何の為か。
本人の遊びです。
自分で的を作り、東急東横線を電車が通過するたびにその的に向かって撃っているわけです。(電車の音で銃声が聞こえないようにしております)。
一節には、「野良犬」を標的にしていたとの噂もでる程。
彼の屈折した一面を見る事が出来ます。
彼がどうして、「読売新聞社 社会部記者」に成り得たか。
当然、時の社主「正力松太郎」の存在が出てまいります。
立松は侑諸ある家系。軍に於いても、代々上級将校を輩出し、司法の場に於いても祖父、父との上級判事でした。これは先の「くだまき」でも語ったところです。
でも社内では、その詳細を知る者はおりませんでした。
本田靖春氏は、「立松は拳銃以上の物を手に入れた。簡単にして人を殺傷出来うる、ペンを持たされたのだから。彼が記者としての仕事に快感を覚えたのも彼の性格からは納得できる」
こう著しております。
立松和博を戦中からその経歴を掻い摘んでお話しいたしました。
さて、お話しを昭和32年10月に戻そうと思います。
前回の続き、立松が愛車「ビュイック」を駆って銀座から朝帰りのところからです。
朝日の尾川が、徹夜明けで社から戻ろうと、日本橋付近を歩いております。
一緒にいる記者が赤い外車を目撃致します。
「尾川さん。あれ、すごいですねぇ。外車ですよ外車!真っ赤な奴!こんな時代になったんですねぇぇ・・」
「何だと!赤の外車!」
ふと、先を見ますと、ビュイックがこちらへ向かって来ます。
「おい!ヨミウリのタテマツ!あのやろう!!」
「あれが、立松の車?」
「あんなもん、この日本に何台あるのかよ!立松に決まっている」
ビュイックは、その前で止まります。
「朝日の尾張さん!おはようございます」
「立松、お前なぁ、何してんだよ!」
「いやぁ、取材!ってね・・・言いたいんだけど」
車の中には、女の子が数名(車の中めい一杯に乗っけている状態)おります。
「おまぇ、女ばかり連れて居やがって。取材なんて嘘っぱちやろう!」
「これから、この子達を家までおくらなきゃいけないんで。じゃぁ」
大きな音を立てて車を走らせていきます。
「畜生!タテマツぅぅ」
その日の朝刊は、前回ご紹介いたしました。
各社が歯ぎしりをして悔しがった事も。
立松は、社には戻っておりませんが、大きな事件が勃発致します。
翌10月19日。新聞記事に名前の掲載された「福田」「宇都宮」は当然、読売新聞本社に対して「事実無根」と抗議をいたします。
しかし、両名の取った行動はこれだけではありませんでした。
同日、午後、「東京地方検察局」へ「名誉棄損の疑い」で告訴致します。
告訴の対象として「記事出筆の記者」「小島読売新聞編集局長」。情報提供者としての「某検事」と上司たる「野村検事正」「花井検事総長」でした。
翌日には、検察への出頭を立松は受けております。
10月24日未明。
読売新聞社社会部内。
「おかしい、この早さは、一体何だ。これまでの検察の動きとは違っている」
立松が話し始めております。相手は同じ社会部記者の先輩「三田」。
「第一、告訴状が受理されて一週間経たない内に(実際は6日目)呼び出し、俺が取材をしてきた数々の事件でも・・・これは聴いたことが無い」
「そう、俺もそう思う。第一この手回しの良さは、『名誉棄損』では絶対にない事例だ」
「売春汚職そのものの捜査はこれからなんだ。白黒つかないうちにだぜ。高検が『名誉棄損』だなんて、言えるわけないんだ!」
「うーーん。立松よ。対して意味を持たない。こう考えられないか?顔だせば?お前のことだから簡単に済むんじゃないか?」
三田は、東京高検主任検事「川口」との昨日のやり取りを思い出して、立松へこう話しております。
「じゃぁ出かけるか。午後にでも」
午前4時。
二人は記者室の仮眠室へ向かいました。
10月24日。午後4時。東京高検内。三階「公安検事室」
先に、部屋で取調べを受けていた滝沢が立松の顔を見るなり。
「立松さん!川口検事ったらひどいんですよ!何度も、何度も、記事の出所を教えろ!これしか言わないんですから!」
立松の顔色が変わります。
(そうか。高検が知りたかったのは、「ニュースソース」だったのか!冗談ではない!)
川口は滝沢への態度とは違って、立松には穏やかに話始めた。
立松と川口は旧知の間でありました。
「立松さん、久しぶりじゃないですか。僕が東京を出た間に大きな病気をして大変な思いをされたと聞きましたが。お体の方はもうよろしいのですか?」
「まぁな!川口さん、こんな事を聴くために俺を呼び出したんじゃないんだろ?」
「出張先から呼び出しされてねぇ。君の事件にかかわるとは思ってなかったんだけど。僕が君と旧知の間柄とは知られているんだ。君には遺恨を残したくないし、また、感情的になったと思われるのも嫌だから、この取調べは大津検事に頼もうと思うんだが、どうだろう」
「遠回しに話さなくても、俺はかまわんよ」
立松は、やはり遠回しにしか話しが出来ない川口の立場は理解出来ているものの、内心「ニュースソースを話せって!冗談じゃない!」と考えているのでした。
大津検事との会話は、「取調べ」と言うよりもこれは手続き的なものであったから、立松も少しは息を抜くことが出来ました。
「手洗い。行っていいか?」
立松がトイレへ入ると、昔取材した検事と鉢合わせになります。
つれション状態でその検事は立松にこう耳打ち致します。
「岸本さん(検事長。高検No2)が君を逮捕すると言っている」
立松は、腹をくくるしかありませんでした。
(やはりな。あいつが絡んでいやがった!)
「電話、少しでいい。借りられないか?」
その検事は嘗て立松へ情報を提供したこともある検事でした。
自室へ連れて行きます。
10月24日。午後7時。読売新聞社社会部内。社会部警察回り。萩原の電話が鳴る。
「立松!どうした?」
「今、高検内。ある検事の部屋。手短に言う。メモ取れ。いいか、一字一句漏らすなよ!俺は逮捕される。社内のメモを処分する。自宅へガサ入れがあるだろう。そこは頼む。検察を挑発しないように。以上。部長へ伝える事」
電話はこれで切れました。
「部長!立松からです。高検から電話です。部長にこれを」
今しがた、取ったばかりのメモを部長に渡します。
「何だって!立松が逮捕だとぉぉ。容疑は何だ?『名誉棄損』?これじゃ、おかしいじゃないか!」
「おそらくですよ。部長。これは憶測なんですがね」
社内きっての参謀と呼ばれ、冷静である萩原はこう続けました。
「『証言拒否』これではないかと。いわゆるその線での容疑としか・・・」
「それにしても、おかしいじゃないか。萩原君、三田君と明日、高検へ行ってみてはくれんか」
「そうします」
10月25日。午後。東京高検内。
岸本の立場は検事長。現在は高検N02。
萩原と三田は、訪ねて行った「岡原次席検事」の部屋にどうして、岸本がいるのかが不可解でした。
陣頭指揮をモットーとしている岸本です。
彼が、ここに居るという事は、立松の一件が、岸本自らが指揮を取っているという事を物語っているのでした。
三田も萩原も一新聞記者の記事に発端とされる事件の割には、物々しいものである事を感じざるを得ませんでした。
萩原は、直接、岸本に対して聞き出そうとします。
「おかしいじゃありませんか!立松を宣誓供述に回すことだけは止めてもらいたい!」
「おや、単刀直入に聞いてくるねぇ。そんな事はせんよ、安心したまえ。大所高所から判断して、正々堂々とやるだけだよ」
岸本の薄ら笑いが、妙にに自信たっぷりです。
「どういう意味なんだ!」
「名誉棄損がはっきりしているじゃないか」
「ですがね。いいですか。記事そのものが重要な証拠となる『名誉棄損』においてですよ。もはやおおくの読者に目に触れ、今となっては回収は不可能でしょ。この記事で起訴か不起訴か決める。これは過去の事件を見ても明らかじゃないですか!立松の逮捕はもはや必要たる理由がない!」
さらに萩原は岸本に突っ込みます。
「何言ってるんだ。過去は過去。必要か不必要かは、こちら(検察)が決める事だ!」
「過去はこうですよね『真相事件』(共産党系出版物事件)と、恐喝と絡んでいた『政界ジープ事件』があるだけです!立松逮捕は、大きな社会問題になる!」
岸本は再び笑みを浮かべます。
「これから、会議だ。君たちと議論している暇なぞ無いんだ!失敬する!」
岸本は、部屋を去ろうとしております。ドアに手を掛けたそのとき、岸本は萩原の方を振り向きます。
「君たちは大変な弁護士を雇ったようだね」
これだけ言い残すと、岸本は、部屋から出て行きました。
「三田君、我々側に『木内弁護士』がいる事を岸本は知っている・・どうして・・・」
検察内で、岸本と木内が「犬猿の仲」でいる事は、誰しもが知っていることなのでした。
10月24日。東京高検。大会議室。立松と川口検事。
「立松君。大津検事からはどんな事を聴かれた?」
「どうにもこうにもない!ニュースソースを明かせ!これだけ。物別れ」
「立松君、強硬手段を取りたくはない。これは解ってくれたまえ。ニュースソースを言ってくれたら、君はここから出られるんだから」
「冗談じゃない!そんな気はさらさらないね!記者やめろ!ってことと同じじゃないですか!」
「そこまで考えなくたって・・・」
「ああ、同じだ!川口検事。あなたは、記者としての私を殺そうというのですか!」
立松には計算がありました。「自身の逮捕」は、最悪の事態として想定はしているのですが、「まさか、そこまでは高検はしてこない」こうした見方の方が確立的に高いと考えております。
「そこを、何とか、話してくれないか!」
「ダメだ!絶対に話さない!ニュースソースを話すことだけは出来ない!」
延々と同じ質問、回答が続きます。
「川口検事、ですがね、『売春汚職』の結末を見ないこの時期に新聞記者である私の逮捕に何の意味があるんですか?」
「・・・・・・・・・・・・」
この質問には、答えない川口。
沈黙が長い。
午後10時。会議と称して、中座していた、大津が部屋に入ります。
書類を携えております。
何やら、川口とひそひそ話の後、立松の正面に座りました。
「立松さん。御気の毒なのですが・・・・・」こう切り出された立松。次の言葉は想像しております。
「あなたを逮捕することになりました」
午後11時。会議室、隣室。
「川口検事、僕はどこに留置されるんだい?」
「とりあえず、丸の内」
立松は「丸の内署」へ拘置されます。
10月25日。読売新聞社、社会部内。応接室。
小島編集局長。景山社会部長。長谷川社会部次長。記者、萩原、三田。
「新聞記者が、事実と違ったからって、逮捕される?こんな事は聴いたことは無い!」
「だったら、逮捕されて無罪になったら、その検事は逮捕されるか?それと同じ理屈なんだ!」
「職権乱用じゃないか!人権侵害もいいところだ!」
いきり立った景山は、壁に灰皿を投げつけます。
全員がその行動に驚きます。
「冷静」萩原同様、これは景山の呼び名でもあったのです。
「おかしい。妙だ・・・・そうは、思わんか?」
長谷川がようやく口を開きました。
「何か、言論統制的な匂いも感じる・・」
「岸本の噂が気になります」
三田が切り出しました。
「なんだね?」
「去年の秋、競馬好きな代議士『河野一郎』農林大臣の時ですね。自分の経営する牧場にですよ、英国産の種馬を輸入してまして、そのう関税法違反で地検で捜査していたんですよ。輸入元の商社の社員が、河井検事が知らない内に、釈放されて・・・事件は闇の中。これは、そうも岸本の差し金だったとこれは噂なんですがね・・」
「じゃぁ。裏では、政界と岸本の癒着がかぁ?」
「それだけじゃない。造船疑惑のときの岸本は、どちらかと言うと『われかんせず』でしたからね。特捜の生みの親、馬場事務次官が、検察の人事権を握っているほどに立場が逆転したわけです。」
「馬場が目の上の瘤だと岸本が思っているのか?」
「これは確かです」
「検察内の派閥抗争!」
「合点がいく!」
話しを先に進めます。
立松逮捕の記事。
下記。

10月26日、読売朝刊一面。
この記事が掲載されるのは、立松逮捕から翌々日の事なのでした。
立松の拘置生活。取調べは、並みのものではなかったのでした。















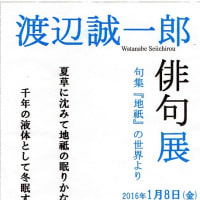










※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます