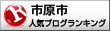精神障害者のご家族の会
「市原市こころの健康家族会(こすもす会)」の例会に参加しました。
五井公民館

この日は、初めて参加される方がいらして、その方の不安・苦しみ・悩みに対して
皆さんが口々にご自分の経験をお話しし、励ましておられれました。
これこそ最良のカウンセリング。家族会の意義は本当に大きいですね。
それにしても、今回
ご家族の壮絶な日常・・・生の声を聞いて、私は何度も言葉を失うほどショックを受けました。
支援が必要でも、そもそも声を挙げられない方もまだまだたくさんいらっしゃると思いますし、
どこに助けを求めたら良いかわからない方、助けを求めたのにかえって傷つけられた方も多い。
「地域共生社会の実現」とは言っても、精神障害への対応は非常に遅れているのが現状です。
それだけに、こうした家族会の果たす役割はとても大きいと思うのですが、
残念ながら県内各地の家族会は次々と解散、あるいは高齢化が進んでいるそうです。
こうした問題も、一体どうすれば良いのでしょうか・・・
とにかく様々考えさせられました。
「市原市こころの健康家族会(こすもす会)」の例会に参加しました。
五井公民館

この日は、初めて参加される方がいらして、その方の不安・苦しみ・悩みに対して
皆さんが口々にご自分の経験をお話しし、励ましておられれました。
これこそ最良のカウンセリング。家族会の意義は本当に大きいですね。
それにしても、今回
ご家族の壮絶な日常・・・生の声を聞いて、私は何度も言葉を失うほどショックを受けました。
支援が必要でも、そもそも声を挙げられない方もまだまだたくさんいらっしゃると思いますし、
どこに助けを求めたら良いかわからない方、助けを求めたのにかえって傷つけられた方も多い。
「地域共生社会の実現」とは言っても、精神障害への対応は非常に遅れているのが現状です。
それだけに、こうした家族会の果たす役割はとても大きいと思うのですが、
残念ながら県内各地の家族会は次々と解散、あるいは高齢化が進んでいるそうです。
こうした問題も、一体どうすれば良いのでしょうか・・・
とにかく様々考えさせられました。