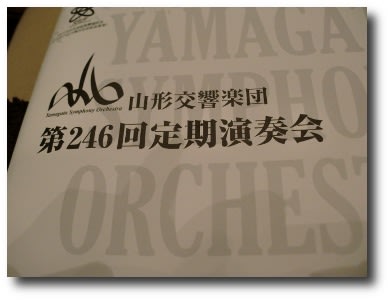日曜の午後は、山形交響楽団の第246回定期演奏会に出かけました。午後3時15分ごろチケット交換に並び、辛うじて残っていたボックス席を確保しました。少しすると、ホワイエで「ウェルカム・コンサート」が始まりました。丸山倫代さん(1st-Vn)、黒瀬美さん(2nd-Vn)、井戸健治さん(Va)、それに渡邊研多郎さん(Vc)によるカルテットで、メンデルスゾーンの弦楽四重奏曲第2番の第1楽章とメンデルスゾーンの「歌の翼に」でした。しばらくぶりのロビーコンサートで、たいへん新鮮に感じました。

開演前のプレコンサートトークでは、新事務局長の西浜さんと今回の指揮者の鈴木秀美さんのお二人で、曲目の解説を話します。興味深かったのは、メンデルスゾーンの交響曲第4番「イタリア」の4つの楽章を、それぞれ「秋・冬・春・夏」と解釈する、というところ。これは、鈴木秀美さんが、フランス・ブリュッヘン率いる18世紀オーケストラで演奏旅行をしていたころ、フランス・ブリュッヘンが述べたものだそうで、そのときに感心して取り入れたものだそうです。次の「田園」交響曲では、歴史と伝統という手垢のついたところを洗い落とし、ディテールは薄化粧して演奏するとのこと。どんなベートーヴェン演奏になるか、楽しみです。鈴木秀美さん、実はメンデルスゾーンが大好きだそうで、その天才性をかなり強調しておりました。
まもなく楽員の皆さんが登場します。第1ヴァイオリン(8)、第2ヴァイオリン(6)の対向配置で、その後方にヴィオラ(5)とチェロ(5)が並びます。正面奥にはフルート(2)とオーボエ(2)、その奥にクラリネット(2)とファゴット(2)、そして両脇には、左側にホルン(2)、右側にはトランペット(2)とティンパニ、正面最奥部にコントラバス(3)という二管編成です。コンサートマスター席には、高橋和貴さんが座ります。
1曲目は、メンデルスゾーンの交響曲第4番イ長調作品90「イタリア」です。第1楽章:アレグロ・ヴィヴァーチェ。今回のパンフレットの解説も、実は指揮者の鈴木秀美さんが書いていますが、その中で、
としているとおり、冒頭の開始の音が、実に明るく、溌剌としたものです。休みなしに始まる第2楽章:アンダンテ・コン・モトは、鈴木さんの言葉を借りれば、「ハリー・ポッターに出てくる本」を開くと、そこから不思議な物語が始まるように、革表紙の古い本が語り出す古い物語のような音楽です。不思議な時の流れを刻むように、低音部がリズムを刻みます。ノン・ヴィヴラート奏法によって山響の弦楽の澄んだ美しさが際立つことは、先刻承知のはずなのに、ホールに響くしなやかな音に、今さらのように感じます。
第3楽章:コン・モト・モデラート。なるほど、この楽章が春の雰囲気というのは、言い得て妙です。しなやかな音楽の中で、ナチュラルホルンと木管による角笛のような響きは、なんとも牧歌的に、効果的に聞こえます。そして終楽章はプレストで、沸騰するサルタレロ。夏の盛りの音楽のように、実に気持ちいい!
休憩のあとは、ベートーヴェンの交響曲第6番ヘ長調作品68「田園」です。
オーケストラは編成が若干変わり、フルート(2)の右にピッコロ(1)、トランペット(2)の後方にトロンボーン(2)が加わります。
第1楽章:アレグロ・マ・ノン・トロッポ。やや速めのテンポで、実に軽やかにしなやかに始まります。弦楽に過度の表情付けはなし。でも、ファゴットやクラリネットは、ブラボー! 聴き慣れた音楽ではありますが、「田舎に到着したときの愉快な感情の目覚め」として実にいい味です。
第2楽章:アンダンテ・モルト・モト。「小川のほとりの情景」の標題のように、弦楽合奏の夢見るような柔らかさ、しなやかさが、途切れることなく連続します。ファゴット、いいなあ。
第3楽章以降は、第5楽章まで連続して演奏されます。軽やかに受け継がれる音のかけあいが実におもしろい。例の嵐の場面も、2nd-Vnから気配が変わり、嵐がやってくるところが、よーくわかりました。コントラバスの活躍は、生演奏ならではの醍醐味。嵐が過ぎ去るところも、ティンパニの音がだんだん弱くなることで表現していることも、あらためて実感しました。終楽章の再現も、単に夢見る人ではなく、力強さの加わった人になったようで、堂々とした歩みになっています。
ほぼ満席の聴衆の拍手に応え、指揮の鈴木秀美さんが話します。内容は、若いメンデルスゾーンの復興の努力のおかげで、J.S.バッハの音楽が私たちに身近なものになったこと。アンコールとして、そのバッハの音楽から、カンタータ第107番より「コラール」を。これも、ほんとに素晴らしいものでした。


終演後のファン交流会では、鈴木秀美さんの人気を裏付けるように、多くの人が集まりました。「山形は、食べ物も飲み物も美味しいので、気をつけないといけない。本番まで意識を保っていないと。今晩が一番あぶない(笑)」なるほどね~(^o^)/
鈴木秀美さんのチェロでメンデルスゾーンのチェロ・ソナタのCDを見つけたので、購入してサインをしてもらいました。私のミーハー・コレクションに、また宝物が一枚加わりました(^o^)/


【追記】
プログラムの表紙だけでなく、内容も変わってきています。ロビーコンサートのプログラムも明記されていますし、楽団員のインタビューや、楽団ニュースの(多分)連載も始まりました。こういうのは、ファンにとってはたいへん嬉しいものです。岩手の「アマデウスへの旅」や東京・大阪での「さくらんぼコンサート」の様子など、山形では聞くことのできない、我らが山響の活躍と評判なども、やっぱり知りたいものです。コンサートスケジュールも、定期演奏会だけでなく、各地で色々な機会があるんだなあと、あらためて認識。こういう改善は、たいへんありがたいところです。新事務局長を中心としたスタッフの皆様の努力に敬意を表します。


開演前のプレコンサートトークでは、新事務局長の西浜さんと今回の指揮者の鈴木秀美さんのお二人で、曲目の解説を話します。興味深かったのは、メンデルスゾーンの交響曲第4番「イタリア」の4つの楽章を、それぞれ「秋・冬・春・夏」と解釈する、というところ。これは、鈴木秀美さんが、フランス・ブリュッヘン率いる18世紀オーケストラで演奏旅行をしていたころ、フランス・ブリュッヘンが述べたものだそうで、そのときに感心して取り入れたものだそうです。次の「田園」交響曲では、歴史と伝統という手垢のついたところを洗い落とし、ディテールは薄化粧して演奏するとのこと。どんなベートーヴェン演奏になるか、楽しみです。鈴木秀美さん、実はメンデルスゾーンが大好きだそうで、その天才性をかなり強調しておりました。
まもなく楽員の皆さんが登場します。第1ヴァイオリン(8)、第2ヴァイオリン(6)の対向配置で、その後方にヴィオラ(5)とチェロ(5)が並びます。正面奥にはフルート(2)とオーボエ(2)、その奥にクラリネット(2)とファゴット(2)、そして両脇には、左側にホルン(2)、右側にはトランペット(2)とティンパニ、正面最奥部にコントラバス(3)という二管編成です。コンサートマスター席には、高橋和貴さんが座ります。
1曲目は、メンデルスゾーンの交響曲第4番イ長調作品90「イタリア」です。第1楽章:アレグロ・ヴィヴァーチェ。今回のパンフレットの解説も、実は指揮者の鈴木秀美さんが書いていますが、その中で、
さて、交響曲《イタリア》は黄金色に輝く収穫の喜びをもって始まります。
としているとおり、冒頭の開始の音が、実に明るく、溌剌としたものです。休みなしに始まる第2楽章:アンダンテ・コン・モトは、鈴木さんの言葉を借りれば、「ハリー・ポッターに出てくる本」を開くと、そこから不思議な物語が始まるように、革表紙の古い本が語り出す古い物語のような音楽です。不思議な時の流れを刻むように、低音部がリズムを刻みます。ノン・ヴィヴラート奏法によって山響の弦楽の澄んだ美しさが際立つことは、先刻承知のはずなのに、ホールに響くしなやかな音に、今さらのように感じます。
第3楽章:コン・モト・モデラート。なるほど、この楽章が春の雰囲気というのは、言い得て妙です。しなやかな音楽の中で、ナチュラルホルンと木管による角笛のような響きは、なんとも牧歌的に、効果的に聞こえます。そして終楽章はプレストで、沸騰するサルタレロ。夏の盛りの音楽のように、実に気持ちいい!
休憩のあとは、ベートーヴェンの交響曲第6番ヘ長調作品68「田園」です。
オーケストラは編成が若干変わり、フルート(2)の右にピッコロ(1)、トランペット(2)の後方にトロンボーン(2)が加わります。
第1楽章:アレグロ・マ・ノン・トロッポ。やや速めのテンポで、実に軽やかにしなやかに始まります。弦楽に過度の表情付けはなし。でも、ファゴットやクラリネットは、ブラボー! 聴き慣れた音楽ではありますが、「田舎に到着したときの愉快な感情の目覚め」として実にいい味です。
第2楽章:アンダンテ・モルト・モト。「小川のほとりの情景」の標題のように、弦楽合奏の夢見るような柔らかさ、しなやかさが、途切れることなく連続します。ファゴット、いいなあ。
第3楽章以降は、第5楽章まで連続して演奏されます。軽やかに受け継がれる音のかけあいが実におもしろい。例の嵐の場面も、2nd-Vnから気配が変わり、嵐がやってくるところが、よーくわかりました。コントラバスの活躍は、生演奏ならではの醍醐味。嵐が過ぎ去るところも、ティンパニの音がだんだん弱くなることで表現していることも、あらためて実感しました。終楽章の再現も、単に夢見る人ではなく、力強さの加わった人になったようで、堂々とした歩みになっています。
ほぼ満席の聴衆の拍手に応え、指揮の鈴木秀美さんが話します。内容は、若いメンデルスゾーンの復興の努力のおかげで、J.S.バッハの音楽が私たちに身近なものになったこと。アンコールとして、そのバッハの音楽から、カンタータ第107番より「コラール」を。これも、ほんとに素晴らしいものでした。


終演後のファン交流会では、鈴木秀美さんの人気を裏付けるように、多くの人が集まりました。「山形は、食べ物も飲み物も美味しいので、気をつけないといけない。本番まで意識を保っていないと。今晩が一番あぶない(笑)」なるほどね~(^o^)/
鈴木秀美さんのチェロでメンデルスゾーンのチェロ・ソナタのCDを見つけたので、購入してサインをしてもらいました。私のミーハー・コレクションに、また宝物が一枚加わりました(^o^)/


【追記】
プログラムの表紙だけでなく、内容も変わってきています。ロビーコンサートのプログラムも明記されていますし、楽団員のインタビューや、楽団ニュースの(多分)連載も始まりました。こういうのは、ファンにとってはたいへん嬉しいものです。岩手の「アマデウスへの旅」や東京・大阪での「さくらんぼコンサート」の様子など、山形では聞くことのできない、我らが山響の活躍と評判なども、やっぱり知りたいものです。コンサートスケジュールも、定期演奏会だけでなく、各地で色々な機会があるんだなあと、あらためて認識。こういう改善は、たいへんありがたいところです。新事務局長を中心としたスタッフの皆様の努力に敬意を表します。