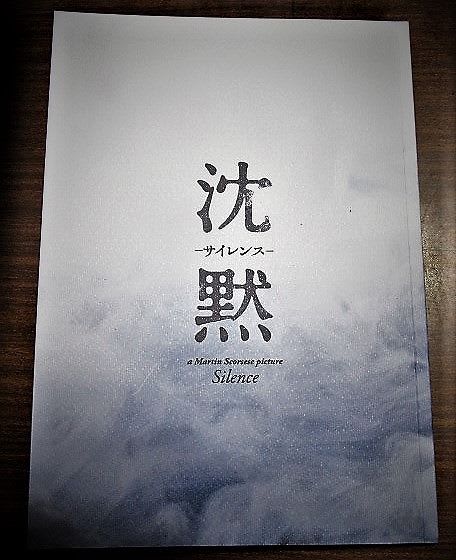先週から少しづつジャングル状態のキウイの剪定をしてきた。
気温はある程度高い日にやってはいたが、風が冷たいうえにときおり突風がやってくる。
そのたびに出鼻をくじかけることもあったが、少しづつ続けることが大切であることがわかっている。

昨年、強剪定したので大胆な剪定はしなかったが、それでも剪定は躊躇が伴う。
上をずっと向いていると首が疲れてくる。
間違って大事な枝を伐ってしまうこともある。


なかなか教科書のようなきれいな剪定はできない。
とりあえず、混みいった所から剪定はするが絡んだ枝を駆除するのは意外に時間がかかる。
枝によっては結束したり誘引したりする。
きりがないのできょうで終わりとする。
そろそろ、畑の荒耕にとりかからないとまた野菜の植え付けが遅れてしまう。
牧歌的な農的な生活の中に時間というものの制約が迫ってくる。
気温はある程度高い日にやってはいたが、風が冷たいうえにときおり突風がやってくる。
そのたびに出鼻をくじかけることもあったが、少しづつ続けることが大切であることがわかっている。

昨年、強剪定したので大胆な剪定はしなかったが、それでも剪定は躊躇が伴う。
上をずっと向いていると首が疲れてくる。
間違って大事な枝を伐ってしまうこともある。


なかなか教科書のようなきれいな剪定はできない。
とりあえず、混みいった所から剪定はするが絡んだ枝を駆除するのは意外に時間がかかる。
枝によっては結束したり誘引したりする。
きりがないのできょうで終わりとする。
そろそろ、畑の荒耕にとりかからないとまた野菜の植え付けが遅れてしまう。
牧歌的な農的な生活の中に時間というものの制約が迫ってくる。













 画像は同社HPから
画像は同社HPから