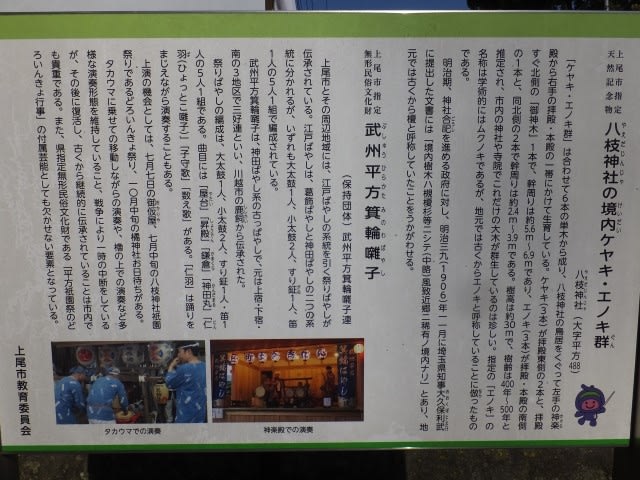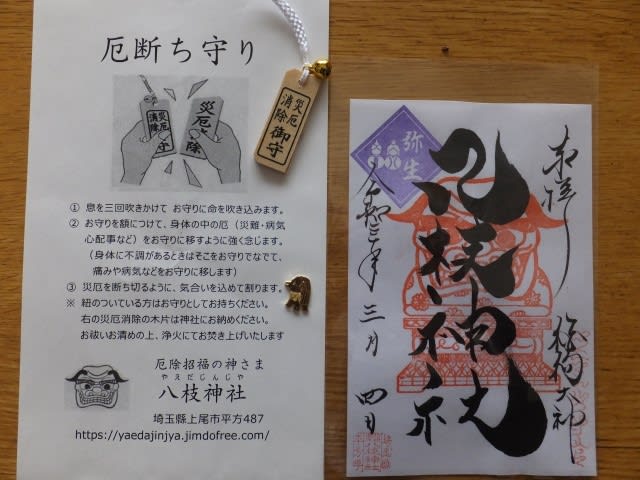本州の南海上に前線が南下してオホーツク海の高気圧から冷たい北東の風が吹き込み、関東地方では木曜日から猛暑に一服の清涼を感じています。過ごしやすい陽気は今日も続いています。昨日は茨城県での在宅勤務でしたが早めに仕事を切り上げ、帰りに埼玉県行田市の古代蓮の里に寄り道して田んぼアートを見てきました。友部から北関東自動車道と東北自動車道を利用して1時間20分で羽生ICへ、そこから20分ほどで到着します。4年前に一度訪れたことがあります。

平日は駐車場は無料です。車を停めて古代蓮会館の展望塔へ向かいます。

エレベータへ向かう途中、過去の田んぼアートの写真が展示されています。右下は4年前に訪れた時に見たコンドルの地上絵です。

エレベータで高さ50mの展望塔へ登り上がり、東側の水田を見下ろします。2015年にはギネスに登録された巨大なアートが広がります。今年のデザインは「アオアシ」です。行田市のHPから引用します。
今年の図柄は、昨年に引き続いて日本の代表的な文化であり、国際的にも人気が高い「アニメ」、「マンガ」に着目。その中で、今注目を浴びている人気サッカーアニメ『アオアシ』とコラボレーションすることといたしました。絵柄は主要キャラクター「青井葦人(あおいあしと)」「福田達也(ふくだたつや)」「一条花(いちじょうはな)」の3人を描き、『アオアシ』とのコラボレーションを祝して行田市の花である古代蓮をあしらいました。(引用おわり)
あれ? 古代蓮はどこ?・・・

右側に描かれていました。横幅が広く、1枚の写真にはおさまりません。

こちらは設計図面です。遠近法が考慮されています。

高さ50mの展望塔からは関東地方の山々を遠望できるみたいですが、昨日は低い雲が垂れ込め日光連山や関東山地は見えません。うっすらと筑波山が見えていました。

こちらは東京スカイツリー。距離は54km。意外と近いです。

帰りに、古代蓮(行田蓮)を見てきました。

行田蓮の説明です。古代蓮の里に近い公共施設建設工事の際、偶然出土した種子が自然発芽して甦り池に開花しているのが発見されました。地中深く眠っていた多くの蓮の実が出土し、自然発芽して一斉に開花した事は珍しいことといわれています。古代蓮の里では、自生地から移植した古代蓮が育てられています。この古代蓮は、1400年から3000年前のものと推定されています。

蓮の花の命は4日間。7時~9時の間に開花して4日目の昼にはすべての花弁が散ってしまうそうです。午後3時過ぎに閉じていない花は3日目で、残り1日の命です。

こちらも3日目の花? 昨日は暗い曇り空だったので、2日目の花が遅い時間まで咲いていたのかもしれません。

花が散った後は、蜂の巣のような花弁の中にぎっしりと実が詰まっています。

古代蓮池の先に、先ほど上った高さ50mの展望塔

古代蓮池を散策後、駐車場に戻ります。
駐車場近くには世界の蓮園があり、40種類、約2万株が展示されています。ほとんど咲き終わっていたので、一輪だけ紹介しておきます。

西光寺白蓮です。花弁数20~26枚の一重咲種。花色は純白で、外弁はわずかに緑色を帯びています。
蓮の花は終盤で1週間ほど遅かったようです。次回はジャストの時期の早朝に訪れてみたいです。