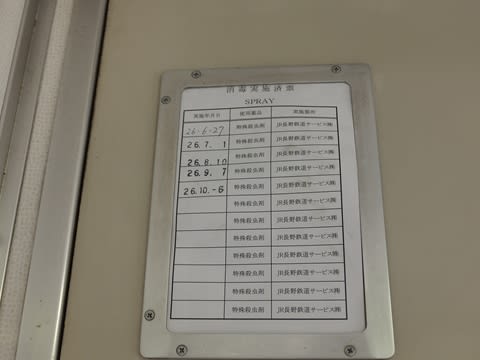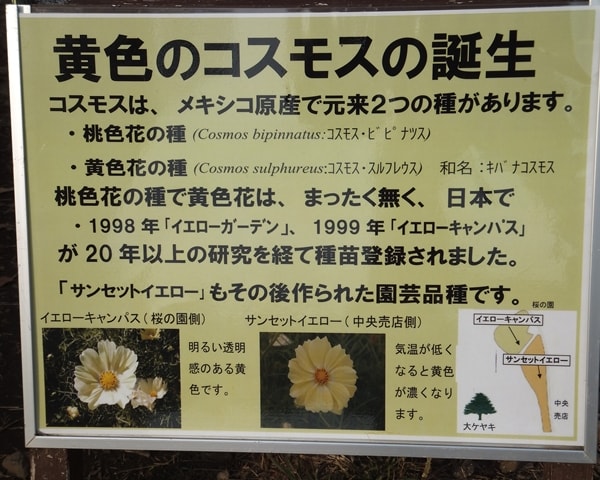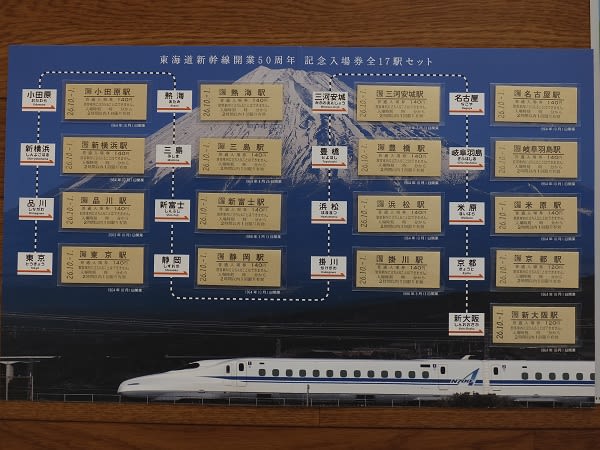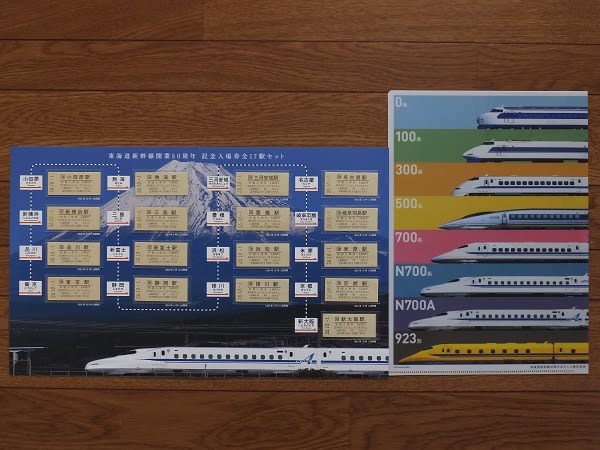今日も午前中を中心に日差しに恵まれ、暖かな秋の一日でした。八王子では最高気温が23.7℃まで上がり半袖Tシャツでも過ごせる陽気です。自宅近くの国立東京工専では昨日、今日と「くぬぎだ祭」が開催されています。昨年は台風の影響で中止となってしまいましたが、今年は天気に恵まれ大勢のお客さんが訪れています。狭間駅に電車が到着するたびにワイワイガヤガヤ話し声が聞こえてきます。息子がクラブ活動で模擬店を出しているので、昨日様子を見てきました。そして今夜は恒例の花火大会です。花火を見学後に単身赴任先の茨城県へ車で戻る予定にしています。
午前中、陵南公園から甲州街道のイチョウ並木、狭間公園を散策してきました。今年は気温が低めに経過していますが木々の色付きは例年並みの印象です。9月から10月に登った那須岳や武尊山では例年よりも相当早い紅葉でした。紅葉前線が里に下りてくるペースが遅いのでしょうか。

陵南公園のモミジです。木の上のほうから赤く染まってきました。

武蔵野陵参道のケヤキです。2年前にバッサリと剪定したため、すっきりしました。色付きは昨年より早めです。

続いて甲州街道のイチョウ並木を紹介します。町田街道入口の歩道橋から高尾方面を眺めます。

こちらは八王子方面。色付きは順調です。沿海州で発達中の低気圧から延びる寒冷前線が通過する明日の夜から急激に気温が下がってきそうなので、今週末には一段と色づくことでしょう。今年のイチョウ祭りは11月15日、16日に開催されます。

狭間公園にやってきました。狭間駅西側高架橋のツタが赤く色づいてきました。

公園南側のケヤキも黄色く染まりつつあります。公園を歩いていると感じませんが体育館(エスフォルタアリーナ八王子)がオープンして狭間駅周辺は様変わりしました。
午前中、陵南公園から甲州街道のイチョウ並木、狭間公園を散策してきました。今年は気温が低めに経過していますが木々の色付きは例年並みの印象です。9月から10月に登った那須岳や武尊山では例年よりも相当早い紅葉でした。紅葉前線が里に下りてくるペースが遅いのでしょうか。

陵南公園のモミジです。木の上のほうから赤く染まってきました。

武蔵野陵参道のケヤキです。2年前にバッサリと剪定したため、すっきりしました。色付きは昨年より早めです。

続いて甲州街道のイチョウ並木を紹介します。町田街道入口の歩道橋から高尾方面を眺めます。

こちらは八王子方面。色付きは順調です。沿海州で発達中の低気圧から延びる寒冷前線が通過する明日の夜から急激に気温が下がってきそうなので、今週末には一段と色づくことでしょう。今年のイチョウ祭りは11月15日、16日に開催されます。

狭間公園にやってきました。狭間駅西側高架橋のツタが赤く色づいてきました。

公園南側のケヤキも黄色く染まりつつあります。公園を歩いていると感じませんが体育館(エスフォルタアリーナ八王子)がオープンして狭間駅周辺は様変わりしました。