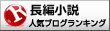江戸の町に奇怪(きっかい)な流行(はや)り病(やまい)が広がろうとしていた。原因が掴(つか)めない疫病で、全(すべ)ての民百姓が恐れ慄(おのの)くのみであった。こうした一件は奉行所の関与することではなく、町の混乱を鎮めるための取り締まり以外、手の施(ほどこ)しようがなかったのである。
「妙な流行り病だが、こればっかりは、なっ! ははは…」
兵馬は杯(さかずき)を傾けながらお芳の置屋で独(ひと)り言(ご)ちた。言う迄もなく、酌はお駒である。摘みにする酢味噌の鯉の洗いが冷酒に合う。
「ですわね…。本当(ほんと)、困りましたわ。枕を高くして寝られやしない…」
「…だな」
兵馬はそう軽く受け流すしかなかった。探索の当てがない災(わざわ)いだから、兵馬でも手が出なかったのである。
「こうした場合は徳利の精…いや、やはりここは素戔嗚(スサノオ)さまか…」
杯(さかずき)を飲み干し、小声で兵馬が頬を緩めて呟(つぶや)いた。
「なにか、おっしゃいました?」
「いや、なんでもない…」
兵馬は思わず口を噤(つぐ)み、鯉の洗いを口に含んだ。ふと見遣れば、前栽(せんざい)の紫陽花の色鮮やかさも褪(あ)せ、早からぬ梅雨明けを告げている。今年も暑い夏が巡ろうとしていた。
「それにしても急に暑くなったな…」
お駒が団扇(うちわ)で兵馬を煽(あお)る。
「冷やし飴(あめ)の季節ですわね…」
「ああ…。だが今年は、余り出歩けぬからのう…」
「嫌だわ、兵馬さまったら。そう言われて、すぐ出歩くんだから…」
お駒が、いつも攣(つれ)れなく消える兵馬に釘を刺した。
「おお、そろそろ降り出したか…」
生暖かい風を吹き消すかのように、梅雨の終わりを告げる激しい雨が落ち始めた。
「それにしても、蔦屋の味噌田楽は美味(おい)しゅうございますわ。いつも、ありがとう存じます」
「いやなに…。好物ゆえ、寄ったついでよ。ははは…他意はない。払いは払う」
兵馬がお芳の置屋で飲み食いした分は月締めで支払わられていた。
「分かってますよ」
お芳が話に加わる。
「夏場はいいとして、冬場はどうすんですっ?」
お駒が何気なく訊(たず)ねる。
「ああ、木の芽のことか…。気になった故(ゆえ)、某(それがし)もいつやら店の者に訊(たず)ねたことがある」
「どう言ってました?」
「なんでも、持ち山の山中に洞(ほこら)があり、その中の氷室(ひむろ)で凍らせておくと言っておったな。縄暖簾(なわのれん)を上げた頃からだそうじゃ…」
「ということは、寛永の頃ですわね…」
「まあ、そうなるか…。山椒の風味あっての味噌田楽だからのう。洞か…。洞の中なら寒かろうが、流行り病の心配はなさそうだな、ははは…」
兵馬は笑いながら小鉢の鯉の洗いを口中(こうちゅう)へと放り込んだ。だが放り込む際(さい)、洗いの甘味噌が袴(はかま)にポトリと落ちたことまでは気づいていない。お駒は見ぬ振りをして見過ごした。
ひょんなことで流行り病の原因が知れたのは、それから半月ほどしてである。とはいえ、それは兵馬だけが知る事実だった。兵馬がその事実を知ったのは、いつもの奉行所勤めを終え、蔦屋の味噌田楽を買い求めに歩き出したときだった。その日は、暑さもあってか人通りは疎(まば)らで、細い辻を回り近道をしようと兵馬はしていた。そのとき突然、底冷えするような冷たい風が吹き渡ったかと思うと、兵馬の前に得体のしれない物の怪(け)が現れたのである。
「なに奴っ!」
兵馬は無意識に叫び、刀の柄(つか)に手をかけ身構えた。
『へへへ…旦那』
物の怪に旦那と呼ばれる筋合いなど、兵馬にあろうはずがない。最初は少しゾクッ! とした兵馬だったが、何度も不思議な出来事に出食わしているから、心もそんなには昂(たかぶ)らない。要するに、怖さに対する免疫とでも言うべきものが備わっていたのである。
「旦那などと馴れ馴れしく呼ぶなっ!」
『すいやせん…。出来の悪いのは死につきでして…』
「死につきっ! なんだ、それはっ!?」
『ですから、死につきなんでやす。生まれつきの逆でして…』
「ああ、そういうことか。紛(まぎ)らわしい言い方をするなっ!」
『どうも、すいやせん…』
「それで、改めて訊ねるが、その方、いったい何者だ。見たところ、この世の者ではないようだが…」
『へい、左様(さよう)で…。あの世の者です。掻(か)い摘(つま)んで申せば、徳利の精は、おいらの兄貴になりやす』
「徳利の兄貴…どこかで聞いたことがある名だが…」
『そりゃ、そうでしょ。徳利坂は、よくご存じで?』
「ああ、いつぞやの徳利坂の一件か…。で、その徳利の精の弟分が拙者に何用だっ!」
「何用もなにも…ちょいと兄貴に事づかりやしてね」
「なにをっ!」
『疫病の一件をっ!』
「おお、そのことかっ! して、なんぞ知っておるなら申してみよっ! 何故(なにゆえ)世の人々を苦しめるっ!」
恐怖心はどこへやら、兵馬は詳しく知りたくなった。原因が分かれば、世のためにもなるからだ。
『へへへ…。馬鹿にしちゃいけねえや。悪さをして、おいら達を苦しめているのはお前さん方、世の人々じゃねえかっ!』
そうはっきり言われれば、兵馬も返す言葉がない。
「…」
兵馬は思わず口籠(くちごも)った。
『分からねぇ~のかい? へへへ…じゃあ、言ってやらぁ。訳が分からねぇ普請でおいら達の住処(すみか)を潰(つぶ)し、住めねぇ~ようにした覚えはねぇ~のかよぉ!?』
環境破壊のことを申しておるのか…と、兵馬には刹那(せつな)、思えた。
「それは…」
『答えられねぇ~だろっ! まっ! 自業自得ってことさっ! へへへ…』
徳利の精の弟分はニヒルに嗤(わら)い捨てた。
「いや、それはこちらが悪い…。ならば、いかにせよとっ!?」
『素直に悪~ぅございました、と反省する他(ほか)ねぇ~だろっ! 言葉じゃダメだぜ、態度でなっ! まっ! その態度見てからの、こった!』
病魔退散はお上(かみ)や世間の人々の反省次第ということらしい。
その後、病魔がすぐに退散したのか? までは定かでない。ただ、兵馬がお芳の置屋で、お駒に膝枕(ひざまくら)をさせ寛(くつろ)いでいるところを見ると、どうも退散したように思える節(ふし)がなくもない。^^
完
オリジナルとは、今までになかった新しい考え方や新しく作られた物である。では、オリジナルの物を使って新しく作られたものや新しい考え方はオリジナルではないのか? という問題に突き当たる。正解はオリジナルではなくオリジナルに近い物[モドキ]ということになるだろう。発明や発見されたものを元に新しく考えられたり作られたものは実用新案と呼ばれているが、その類(たぐい)だ。ナントカ賞は戴けるのだろうが、画期的でないだけに実に暗い。^^ 困ったことに電子計算機[コンピュータ]を生み出した人間が、今やその電子計算機で新しい物を作ったなどと過信する情けない時代なのである。社会を明るくするような画期的な発明、発見がなされていない事実も頷(うなず)ける。
とある研究所である。
「先生っ! 出来ましたっ!」
今年、助手から講師に昇格した鼻下(はなした)が明るい満面の笑顔で顎野(あごの)教授に告げた。
「出来たのっ!? 妙だなぁ~。私の考えだと出来る訳がないんだが…」
「それが出来たんですっ!」
「ほんとに出来たのっ!? どれどれ…」
顎野教授は電子顕微鏡を覗(のぞ)き込んだ。
「おおっ! き、君っ!! どんどん減ってるじゃないかっ!!」
「そ、そうなんですっ!! やったぁ~~!! ぼ、僕、ノーベル賞、もらえますかねぇ~!?」
「もらえる訳(わきゃ)ないだろっ! この薬品は僕が考え出した薬のコピーなんだからさっ!」
「オリジナルじゃないってことですかっ?」
「ああ、まあそうなるわなっ! 僕が先に発明した薬のコピーなんだから…」
「そうなりますか…」
「ああ、そうなる…」
鼻下の明るい顔は急にショボ暗くなった。
オリジナルは明るくなり、そうでなければ暗くなるのである。^^
完