注文住宅による家づくりでも
共同住宅(マンション)での新居でも、
間取りは私たちの暮らし方を
大きく左右する重要な要素です。

※YAMADA×IDC大塚家具大阪南港ショールームにてインテリアセレクトの打ち合わせ
その間取りと深い関係にあるのが、
実は家具の選択と配置。
家具のサイズやデザイン、
配置の仕方一つで
部屋の使い勝手も居心地も、
さらには広さの感じ方までもが
驚くほど変化します。

※リビングの使い勝手とインテリア性、広さの印象をイメージして空間を広く感じる工夫をご提案
生活をスムーズにし、
空間を最大限に活かして
快適な暮らしを実現するためには、
家具を選び、
どこにどう置くのかという
視点が欠かせません。
「家具選びと配置」によって
どのように空間の機能性と
心地よさを高め、
さらには広さの感覚まで
コントロールできるのか?。
リビング、ダイニング、寝室、
子ども部屋、和室など、
さまざまな部屋における
家具レイアウトの工夫例や、
収納や多機能家具の選択によって
得られるメリット、
また具体的な統計データや
研究結果も今回は参考に。
家具選びや住まいのレイアウトを
検討している方はもちろん、
今住んでいる部屋を
もっと快適にしたい、
あるいはリフォームや
模様替えを検討中の方にも
参考になる内容です。
僕が普段からの住まいの設計前に
考えて住まい手さんにも
ご提案させていただいている内容なので
現実的なお話です。
家具と間取りの深い関係が腑に落ち、
空間づくりが
より分かりやすくなるかと
思います。
家具選びと間取りの基本。
家づくりやリフォーム時に
見落としがちな
家具選びと
間取りの基本的な
考え方の整理を。
間取りとは、
単に部屋数や部屋の広さを
決めるだけではありません。
人の動きである
動線をどのように確保するか、
どこに収納を配置するか、
どの部屋がどのように使われるのか、
といった暮らしの全体像を
具体化していくことです。
家具はその間取りの上に
置かれ、
実際の使い勝手を
左右する重要なアイテムです。
暮らし方に合わせた家具選び。
国土交通省が
公表している「住宅市場動向調査」では、
一戸建て・マンション問わず、
多くの人が収納不足や
動線の不便さを感じているという
結果が報告されています。
家具は大きければ
良いというものでも、
小さければ良い
というものでもなく、
自分たちの生活スタイルを
考慮して選ぶことが大切です。
たとえば、
家族構成が多い場合は
ダイニングテーブルを大きめにして
団らんの場を重視する一方で、
狭い空間であれば
ダイニングテーブルを
折りたたみ式にして
スペースを有効活用するなどの
工夫が必要になります。
家具のスケール感とレイアウト。
間取り図上では、
部屋の広さは数字で示されますが、
実際に人が暮らし、
家具が配置されると
「感じる広さ」は大きく変わります。
ソファやテーブル、
ベッドなどが配置されると、
一気に部屋が狭く見えることも。
たとえば、
天井まである大きな本棚を置いた場合、
天井の高さを強調する効果が
期待できる一方で、
視界を遮ってしまうという
デメリットもあります。
こうしたスケール感の
バランスを考慮しながら
家具の配置をすると、
同じ広さでもずいぶんと
印象が変わりますから。
生活動線の確保。
家具を配置するときに
最も重要なのが「生活動線」です。
人が通るために必要なスペースは
最低でも60cm以上、
できれば80〜90cm程度を
確保するとゆったり通れると
言われています。
※実際に住宅の場合は
住む人の移動の仕方や体格などの
個人差を精査します。
なので動線がスムーズだと、
日常生活のストレスが
大幅に軽減されます。
逆に動線が歪だったり狭かったりすると、
何か取ろうとするときに
家具を迂回しなければならなかったり、
すれ違いが
窮屈になったりして
居心地の悪さを感じる原因になります。
家具配置がもたらす空間の印象。
間取りの広さそのものは
変えられなくても、
家具配置の工夫によって
視覚的な奥行きや広がりを
演出することができます。
広がりを感じる配置と
圧迫感を与える配置の違いは大きく、
同じ7帖や10帖の部屋でも
印象がまったく異なるケースも
珍しくありません。
視線の抜けを意識する。
家具の背の高さや
配置方向を工夫することで、
視線が部屋の奥へと抜ける
レイアウトが可能になります。
たとえば、
リビングに大きなソファを置く場合、
入口から見てソファの背面が
視線を遮らない位置に配置すると
奥行きを感じやすくなります。
逆に部屋の真ん中に
背の高い家具を置くと、
それだけで視線が中断され、
部屋の奥行きが感じられなくなります。
「抜け感」と「囲まれ感」の使い分け。
部屋を広く見せるには
「抜け感」が大切ですが、
快適性を高めるには場合によっては
「囲まれ感」も必要です。
たとえば、
リビングの一角に
小さなラウンジチェアや
パーテーションを使って
半個室のような空間をつくると、
そこだけ落ち着ける
カフェ的な雰囲気が生まれます。
一方で、
家族みんなでくつろぐ
大きなスペースは
できるだけ視線を通して、
開放的に演出するのが
良いかと思います。
部屋全体を開放するだけが
正解ではありません。
カラーコーディネートと素材感。
配置だけでなく、
家具の色や素材が
空間に与える影響も。
明るい色や光を
反射しやすい素材の家具は
空間を広く見せ、
ダークカラーやマットな素材は
落ち着きや高級感を演出します。
視線が行き止まりにならないように、
床や壁とのコントラストも
意識する事大切です。
白やベージュなど淡い色の床材なら、
家具に少し濃い色を取り入れることで
家具の形が際立ち、
空間のメリハリが生まれます。
家具と動線設計—効率的な暮らしを叶えるコツ
スムーズな動線は、
生活のストレスを
低減するためにも
非常に重要な要素です。
たとえば、
家事動線を短縮する配置にすると
家事負担が軽減し、
家族が自然と協力し合えるような
レイアウトにもつながります。
「動線の確保」や
「家具と通路の関係性」を深く。
家事動線の短縮・・・・・・。
厚生労働省の調査によると、
共働き世帯が増えていることに伴い
家事時間を如何に減らすかが
家づくりの大きな
課題となっています。
キッチンからダイニング、
リビングへの移動が
スムーズになるように
家具を配置すれば、
調理や食卓の準備などの
日常作業がスピードアップします。
たとえばダイニングテーブルの脇に
カウンターやサイドボードを置くと、
配膳や片付けの動線が短くなり、
家事効率が向上しやすくなります。
部屋間の移動動線と家具配置。
部屋と部屋をつなぐ
廊下や引き戸の位置に注目し、
通行に支障をきたす配置を
避けることも大切です。
マンションなどでは、
限られたスペースを
最大限に活かすために
家具を壁際に寄せがちですが、
扉の開閉を妨げるほど近くに置くと、
扉を開け閉めするたびに
ストレスを感じることになります。
扉や引き戸の動作範囲を考慮して、
家具の設置場所やサイズを。
一時置きスペースの確保。
動線だけでなく、
「一時置きスペース」を
確保できる家具を配置すると
暮らしがより快適になります。
たとえば玄関に収納ベンチを置けば、
座って靴を履けるだけでなく、
荷物を一時的に
置く場所としても便利です。
洗濯物をたたむスペースが
欲しい場合は、
洗面室やランドリールームのそばに
カウンターを設けたり、
折りたたみテーブルを
壁に付けたりするのも
良い方法だと思います。
多機能家具とスモールスペースの活用。
部屋が十分に広い場合は
家具をゆったり配置しても
問題ないかもしれませんが、
都市部のマンションなどでは
スペースに限りがあることが多いもので
そんなときに活躍するのが
「多機能家具」です。
収納機能を備えた
ベッドやソファベッド、
折りたたみ式のテーブルなど、
1つの家具で
複数の役割を果たしてくれる
アイテムを上手に選ぶことで、
狭い空間でも
快適な暮らしが実現できます。
収納機能付きベッド。
ベッド下に引き出しが付いている
タイプの収納付きベッドは、
衣類やリネン類などを
しまう場所として有用です。
特にワンルームや1LDKなどでは、
クローゼットが小さかったり
収納スペースが
限られていたりすることが
よくあります。
ベッド下のスペースを
有効活用することで、
衣類の整理だけでなく
季節用品や趣味のアイテムなども
収納できるため、
空間がすっきりとします。
折りたたみ式テーブルやデスク。
ダイニングテーブルはもちろん、
ワークスペース用の
デスクも折りたたみ式を選ぶことで、
使わないときに
コンパクトに畳んで
部屋を広く使うことができます。
リモートワークの普及に伴い、
仕事用スペースを
確保する必要がある方は
増えていますが、
常にデスクを置くのは
場所を取るという
ジレンマがあります。
壁に取り付けられる
折りたたみデスクを使えば、
必要なときにだけ展開し、
作業しないときは
スマートに片付けられます。
家具の軽量化・キャスター付きのメリット。
スモールスペースでは、
状況に応じて
家具のレイアウトを
頻繁に変えることが想定されます。
そこで役立つのが
キャスター付きの
収納家具やスツールなど。
簡単に移動できるので、
来客時にはスツールを
ダイニングに持ってきたり、
掃除の際には家具を
サッと動かせたりと、
フレキシブルに空間を使い分けられます。
家具が重いと、
模様替えをするたびに
大変な労力がかかり、
結果的に部屋の使い方が固定化しがちです。
収納の重要性と選び方。
家具配置と同じくらい
重要なのが「収納」の計画です。
収納家具をどう選び、
どこに配置するかは、
部屋の美観や使い勝手だけでなく、
片付けへのモチベーションにも
直結します。
家族が使いやすく、
スッキリ片づく収納計画を
立てることで、
部屋の快適度は格段にアップします。
収納計画は間取りと同時に考える。
新築やリフォームの段階から、
収納スペースの確保を
念入りに考えることが理想です。
とはいえ、
すでに完成している間取りや
賃貸物件でも、
収納家具の工夫次第で
快適度は大きく向上します。
クローゼットが少ない
狭い場合でも、
壁面収納やオープンラックを
効果的に使うことで、
意外と多くの荷物を整理することが可能です。
視界に入る収納・入らない収納の使い分け。
見せる収納と隠す収納を使い分けると、
空間の演出に変化が生まれます。
たとえば、
お気に入りの食器や雑貨は
飾るように収納して
インテリアの一部に取り入れる一方で、
生活感のある日用品や
細々したものは扉付きの収納に
隠すといった方法です。
全てを見せる収納にすると
視覚的に雑多になりがちですし、
逆に全てを隠す収納にすると
個性がなくなりますから、
バランスを意識することが大切です。
収納量と出し入れのしやすさ。
「たくさん収納できる」だけでなく
「取り出しやすい」ことも重要です。
家族が日常的に使うものが
取りにくい場所にあると、
結局使わなくなったり
片付けが疎かになったりする
ケースは多いです。
特にキッチンやリビングなど、
使用頻度の高いものをしまう収納は
動線上にあることが
望ましいかと思います。
たとえば、
大きめのリビング収納を
テレビボードと一体化させることで、
リモコンや雑誌、
書類などをサッと片づけられ、
リビングを常にスッキリ保ちやすくなります。
まだまだ書きたいことは色々あるのですが
今回のblogでは
ここまでにしておきます。
続きは次回に・・・・・。
もしこれから
注文住宅の間取りを考える場合、
あるいは賃貸や
既存住宅のリフォームを
検討している場合は、
早い段階から
家具選びや配置プランを
意識しておくと、
情報整理にもキチンと考えがおよび
家づくりや
インテリアコーディネートが
最適解に近づきやすくなります。
限られた空間のなかでも
暮らしの質を
グッと高めるチャンスは
たくさんあります。
今ある空間をどう活かすか、
これからの間取りを
どう計画していくか、
ぜひ考えを深めてみてください。
家づくりは
人生の大きなプロジェクトであると同時に、
家具選びと配置次第で、
日常の程よさも
何倍にも膨らませることが
できますから。
皆さんの住まいづくりや
模様替え、
インテリアが
より充実したものになりますように。
やまぐち建築設計室は
その家に暮らす家族の過ごし方を
デザインする設計事務所です。
暮らしの意識と時間を丁寧に。
‐‐----------------------------------------
■やまぐち建築設計室■
奈良県橿原市縄手町387-4(1階)
建築家 山口哲央
https://www.y-kenchiku.jp/
住まいの設計、デザインのご相談は
ホームページのお問合わせから
気軽にご連絡ください
------------‐-----------------------------










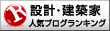

















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます