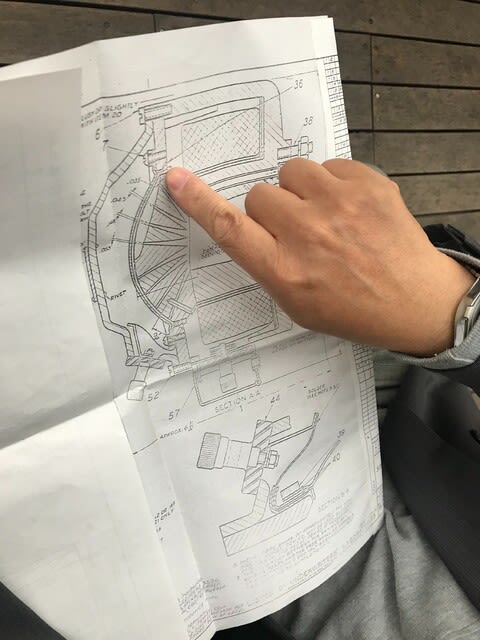私の朝食です、2日以上かけて作る醗酵玄米に
さて、「美味し」と言える時はどんなときでしょうか
a、美味しいと知らされた(教えられた)
b、美味しいと味覚が判断した
c、美味しいと心が感じ、快感を得た

蕎麦打ちも少し上手くなってきました、時々美味しいのがやっと打てるようになりました
aの仮設、美味しいには絶対的な定義があって、その定義をクリアしているので「美味しいと知らされた」のか
bの仮設、経験上の知識や情報分析で味覚が「美味しいと判断」したのか
cの仮設、美味しいと心が「感じて」、興奮したとか、心が揺れたとか、幸せな気分になったとかの「気持ちが動く」ことなのか
う〜ん、やはり、私は「美味しい」とはcの「感じて、何かを得る」ものなのだと思います
「美味しい」とは一般的にはどういったモノを食べたときなのかを調べてみると
一説によれば「美味しい」というものや定義が、あるわけではないそうで
美味しいと思う感情があるだけ、との説もあり、
なるほどわたしもそう思います
美味しいと感じるには「味」「外観」「彩」「香り」「触感」「体調」等々の様々な要素を五感で感じて

「美味しい」と感じるのだとおもう
同じ所で同じものを食べても、美味しいと感じる時と、こんなものだったかな?
と、あまり美味しくないと感じる時があります
美味しいかどうかは自分の体調や気持ちなど様々な要素によっても感じ方が違うと思います
「美味しい」は感性であり、
条件を満たす定義があるわけではないと思います
対する「旨い」
これは「あじ」という定義に基づいたものだと思います

砂糖は「甘い」と教わりました、塩は「しょっぱいと」、「酸っぱい」や「苦い」も教わった「味」の定義です
今はこれに「旨味」が加わって味の五大要素と云うらしいですね

「旨い」は、これらの「味が良い」事の総称だと思います
積み上げた知識、情報を分析し「味が」「旨い」と理解するものだと思います
因みに「 旨い」をどんどん足しても「美味しい」になるとは限らないそうです
こう考えると

もしかしたら、「旨いは左脳」が判断し
「美味しいは右脳」が感じるものなのでしょうか
そういえば目、も同じような働きがあり
左目は右脳に働き、右目は左脳に働く、なんてことを聞いたことがあります

自分の気持ちを相手に伝えたければ、
相手の左目を見て、感情込めて伝えるとより効果的、だなんて事もほんとかウソか(笑)
感性の「美味しい」
と
知性の「旨い」
だと、私は思いますが・・・・・

さてさて、本題どえ~す
いつもどおり私の勝手なオーディオ持論ですので、何のエビデンスもありません
が
美味しいは=「楽しい音」
旨い=「良い音」
だと私は思っています
オーディオの闇の部分に
「答えの無い良い音」の定義があります
なぜか音楽を楽しむ、多くの一般の方々には認知されないのが
「趣味人が愉しむオーディオ・サウンド」

今までも、そんな方々が「良い音とは何か」と、散々議論がされてきましたが
なかなかその明確な答えはありませんでした
議論を尽くしても、結局最後は「好み」となってしまうとこが多かったからです
聴く人の「好みで違う良い音」の追求
これでは他人や世間一般から趣味のオーディオが認知されることは無いと思います
勿論趣味ですから、「認められなくても、まあそれはそれでよい」のだ、と言われる方もいらっしゃいますが
私は他人から、認められないようなオーディオは意味が無いと思っています
誰からも認められるような、「美味しい音」を我が装置で奏でたいと思っています
先程、「旨い」は左脳が判断し、「美味しい」は右脳が感じるものではないのか
右目と左目の、右脳と左脳への影響説を書きましたが
耳も、もしかしたらそんな働きがあるのではないでしょうか
一般的に音や色は右脳で判断されるというが、
聴力も右脳派、左脳派に分かれのではないだろうか
利き腕、利き目、と同じように利き耳もあって
左耳が良く聞こえる人は右脳が敏感に反応し、感性が強く反応する
なんてことは無いのかな?
料理の天然の素材と違って、オーディオ機器は誰かが
良い(旨い)と思って作られた工業製品
メーカーの工業製品は感性を作れない、販売店もできない
オーディオ機器は「良い音の機器」と、「それほどでもない」機器の二種類
ダメなものは製品として作られることは無いと思います
このアンプはとても音が悪くて、大飯食らいで、歪んで、増幅もろくにしないアンプ、
なんて売れないですよね(※うちのアンプはみんなこんな感じ(笑))
その良い音の機器(旨い素材)を組み合わせて
楽しい音楽を奏でるシステム(美味しい料理)を作ることが
「趣味のオーディオ」だと思います
いよいよ、本題のメインテーマです(笑)

美味しい料理(楽しいサウンド)って
旨い素材(良い音の機器)を繋げただけでは
けっして奏でないのです