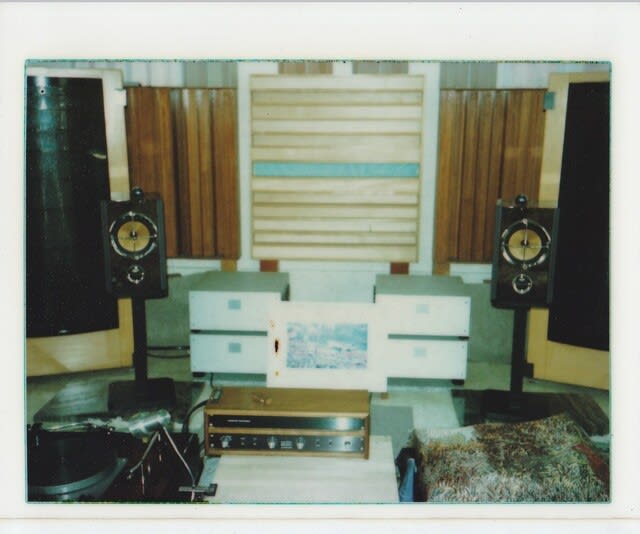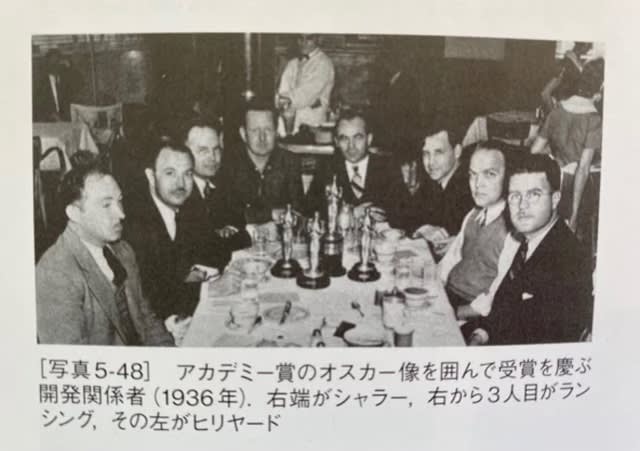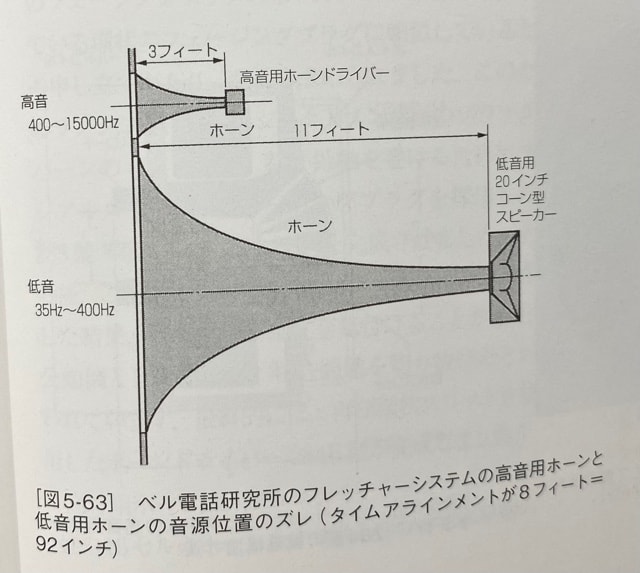人生におけるターニングポイントを書き出すと反省ばかりで人生をやり直すしかなくなるので
オーディオだけのターニングポイントを書かせて貰います
小学生の5〜6年の頃、親戚のバリバリのロッカーの叔父さんが、最新のコンポーネントステレオを買ったので
あげるよと部屋まで持ってきてくれた、テクニクスのセパレートステレオ
その数年前に、小学校何年だったのだろう、そのおじさんの家に行って初めてステレオ見て
すげ〜、かっこい〜、おじさんスゴイね〜と、とても気に入っていた様なので、持ってきてくれたとのことだった
奥さんとよく聞いていたカーペンターズのレコードも一緒に頂いたのが、我がオーディオの始まりのターニングポイントだった
とにかく嬉しくて、スピーカーの姿が見たくて、前面の格子のグリルを壊してスピーカーの姿を見た記憶がある

始めたてみた本格的なスピーカがゲンコツ
なんだこの真ん中の電球は?音を出すと光のか?、と思ったが光らない
叔父さんにこの電球ひからない、壊れてるんじゃないの?と文句言って
その無残な姿のスピーカーをみた叔父さんに、怒られた記憶があります、直ぐ何でも分解してしまいごめんなさい
レシバーでFMを聞き、愛読書となるFMレコパルを読みはじめ、オーディオが目覚めた感がある
FMで音楽を聴き始めれば、当然次はカセットデッキに走る
同級生のお父さんがSONYを辞めて電気店を開いた、SONYが良いよと勧められて
中学一年の時ついに「カセット伝助を購入」勿論、全額新聞配達で自分で購入しました
中学では、放送委員会に属し吹奏楽部やコーラス演奏を、同時に購入したステレオマイクで録音し
昼食時に全校生徒にそれを流し、随分と活躍したものです、先生方からも絶大な支持を集め
昼休みの音楽はお前に任す、と2年生の時に言われて調子に乗り
当時好きだった「春ウララ」を掛けたところ
担任がすっ飛んできて、演奏途中で止められ
結果放送委員会からも追放された暗い事件も有ったが
中二の時に、SONYから独立した同級生のお父さんに「オーディオ・フェア」に連れてい居てもらい
次なるターニングポイントJBLとの出逢いを迎える
国産の多くのスピーカーが並ぶ賑やかな会場で
YAMAHAだったかな片側6個くらい山積みされたスピーカーの裏側の、小さなスペースで
他とは全く違う、とんでもなくリアルな音で鳴っていたスピーカーが有った
その音に、鳥肌が立つくらいに興奮したのを覚えています
これは何ていうスピーカーなんですか?
これは、「JBL L200Bといい、JBLは世界一のスピーカーメーカーだよ」と言われ
そうかJBL!は凄い、スピーカーはJBLしかないんだ
国産とは世界が違う、他はぜんぜんダメ使い物にならない
俺は将来絶対にJBLを買う!
そう誓った中二の時の、感動と興奮は今も忘れることは有りません。
まもなく、カセットでんすけのローンが終わると
早くも夢のJBLスピーカーを買おう、と思ったが新聞配達で手が届いたのはLE8Tのユニットだけ

(以来48年間使い続けています)
ゲンコツの入っていた箱のバッフルを剥がして(怒られた)強引にLE8Tをはめ込んで鳴らしました
LE8Tのローンが終わると次はアンプとなるのですが、
先ほどの、中二で行ったオーディオフェアで唯一購入できたのが
「世界のオーディオ」という雑誌でした、超高額でしたが買いました
この雑誌との出会いもその後のターニングポイントのきっかけになりました
この本の最初のページに出ていたのがSANSUIの「AU606」707は隅に小さく出ていたので
俺が買うのはこれしかないと購入、
と云うかここで取り上げてた製品で買えるものは、このアンプ位でした
この本で見た世界最高のオーディオ機器、いったいどんな音がするのか興奮しながら想像していました
ここで取り上げた世界最高の組み合わせがL300やLNP2Lスレッショルドのアンプ等々
総額600万円を超える超高級なステレオに憧れを抱き
そうか、これが世界最高の音なんだ、いつか見てみみたい、聴いてみたい~
と毎日毎日眺めていました
AU606のローンが終わったのは高校生になってました、
縁あってLUX LX33を買い、真空管アンプとの付き合いもこのころから
憧れのサウンドを奏でた、JBL4310が欲しくて、愛車のGT38バイクを売って買いに行って
その後お世話になる事になる販売店で、あれは中古で古いから、最新のJBL4311Bのほうが全然良いよと買わされ、
人生初めての詐欺に遭ったりしたが

JBLへの情熱は冷めずに、L300や4343へとローンは続いた
アンプもJBLにはマランツ!、と勝手に思い込みモデル140を手にしたり

憧れのモデル7に似ているだけで手にしたアンプもありました
オーディオショップに入り浸っていた時

販売店の店員さんが近くまで試聴機持ってきたから、ついでに聴いてみる?
と、憧れのMLASを、なんと自宅で聞く機会をいただき、歓喜し
その凶器のような情熱的なサウンドに酔いしれたことも有りました
感謝!
憧れのMLASと同じ輸入元で同じような音がするよと、根拠の無い店員Mさんの勧めでAGI 511bを購入し
やがて社会人となり本格的なオーディオローンが始まった
家までMLAS持ってきて聴かせてくれたMさんに、必ずML1L買いますからと言っていたが
結局社会人になったてスピーカーのローンも終わりかけたころ現れたのが「クレル」
自慢気にMさんがまたまた自宅に持ってきてくれて
あッつレビンソンはもう古い「クレルの宇宙感」は「情熱のレビンソン」より新しいサウンドだ
と即、購入デモはシルバーだったが、納品はブルーパネルだった

その後はクレルKSA50やパム2のローンでがんじがらめの社会人生活が始まった
また、そんなある時、その店で聴いたマーチンローガンCSLには驚いた
アッ!、これはこれからスピーカーの世界が変わる
もうJBLの時代は終わったと感じ、その後あれほど憧れていた4343を手放すことにした
手放す前にどうしてもやりたかった、あの瀬川さんがやった4343のML2L、BTLマルチもやってみた

私は既にチェロになっていたのでML2Lは持っていなかったが、
どうしてもやりたくて数人の友達に「ml2l貸して」とお願いし
強引に8台借りてきて4343の最後の美声に皆で酔いしれた、返す時間違えないようレビンソンマークの上に名前を書いた(笑)
音はもう覚えていないですが、高域はBTLにしないほうが全然綺麗でしたね、BTLは力が有るが音は濁る
最新のサウンドマーチンローガンにウハーをいろいろ試したが結局はclsのみ、
チェロのパレット・スイート・パフォーマン・のアンプを使い、
これぞ夢にまで見たハイエンドオーディオ
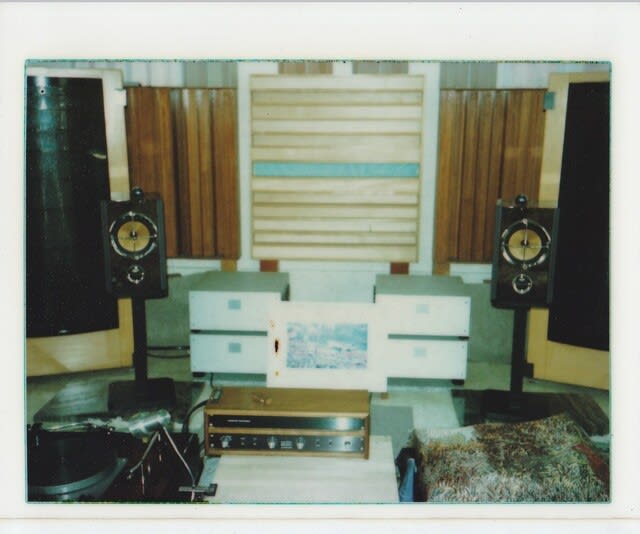
おれは、とうとう世界最高のサウンドを手にしたんだと勇んでいた時
なんともショボいアンプを手にもって、友人がおとづれ
これ聴いて、と置いて行った

何だこのショボいアンプは、まさかこのショボいアンプでわがチェロアンプと聴き比べろというのか
怒りがこみあげてくような、ショボいアンプだったが、聴いてみて驚いた
fob sd05 フルデジタルアンプ、アッこれからはアンプも変わる、
もうレビンソンやチェロの時代ではない・・・
これも大きなターニングポイントとなり、これを機にハイエンドオーディオ機器は全て売却しました
思い起こせば小学生の時から、途切れることなく続いたオーディオのローンもこれで終了
ハイエンドを辞めた理由はデジタルアンプの出現で時代が変わることを感じた事と
それまでWEを語る人が嫌いで、あまり手を出さなかったが
ハイエンドと同時進行でWE618bやWE755aを手にしていて、weの心躍るような力強い音の魅力に惚れこんで
ハイエンドオーディオの、意味の無い良い音には魅力を感じなくなっていたのも事実であった

知人がaltecA4スピーカーを鳴らすべく、weサウンドインクに86アンプを買いに行くと言い
その買い物にお共して、出遭ったのがwe91bアンプのキット、限定でスペシャルパーツが5台分有るとの事
we91bの噂は知っていたが、球無しで50万円を超えていた高級キットを、つい衝動買い
WE300Bは完実電気で販売したものを祈念に買っておいたので持っていたので直ぐに音は出たが
正直、WE91bとWE755Aの組み合わせは、そんなに良いとは思えなかった
we91bはaltecミニ7を鳴らし、755aはラックスのアンプで鳴らしていた
その後、旧友故o氏との様々なweの驚きの巡り合いがあり、氏の作ったwe120aレプリカ初号機
二号機が有ったのか知らないが、今も私の愛用器です

その後、数年間はオーディオに振れる事も無かった気がする
社員が増えて事務所に置いてあったオーディオ機器を、撤去
自宅に持ち帰り、自宅のA5とWE91Bを鳴らしたところ、びっくりするような音で鳴り
WEサウンドに目覚め、このブログと共にオーディオを再開したのもターニングポイントですね
A5は当時、クレルや、チェロで鳴らしたことも有ったが、アンプの音を聞いているようで、全く面白みが無かった
やがて迎えたターニングポイントが励磁型でした、
たまたまwe91bを修理にもっていったTオーディオで、
ハイエンドを辞めたならこんな大昔の方式だけど音は素晴らしいよ
まさかそんな古い廃れた方式の音が良い分けない、音が良ければ衰退するはずがない、アルニコが最高なはずだよ
といっていたが聴いてみて、びっくり
結局気が付けばほとんど励磁型に変わってしまった我がシステム
オーディオは出遭いが全てですね、人と出会うから音と出会えるのかな?
次の出遭いは何だろう?、と旅しながら思ってこのブログを書きました