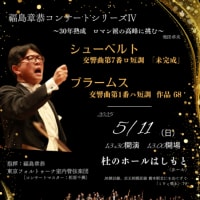ベルリンに着いてからというもの、機内に閉じ込められたり、空港に荷物を取りに行っても袖にされたり、衣料品や食料品を購入に街へ出掛けたり、およそ観光らしきことをしていないが、まあ、美術館巡りや名所の梯子ばかりが観光でもあるまい。地元の方と同じ衣料品店で、同じ下着や靴下を買い、同じスーパーマーケットで、パン、牛乳、ハム、チーズなどを買うのも、ベルリンを味わっていることになろう、と自らを慰めている。

夜は、ベルリン・ドイツ・オペラ初訪問。前回と前々回の滞在では、建物の外観だけ眺めるに留まったが、今夜はようやく内部に潜入することがてきた。
今宵の出しものは、プッチーニ「マノン・レスコー」。指揮はサイモン・ラトル。同劇場2004年12月のプレミエ以来、33回目の公演とのこと。
マリア・ホセ・シーリのマノンは、前半の2幕こそ、ピッチに不安があったものの尻上がりに調子を上げ、終幕の「ひとりさびしく」の絶唱は見事なものであった。
ホルヘ・デ・レオンのデ・グリューは、これぞテノールという輝かしい声、トーマス・レーマンのサージェントはじめ、他の歌手陣も充実した舞台であったと思う。
ラトルは、良く言えば精気のある指揮ぶり。ただ、音楽を少し引っ掻き回し過ぎるかなぁ? という印象も残る。そんなに煽らなくても美しいのに、と言う場面がなくもなかったが、彼のモーツァルトやブルックナーを聴いたときほどの違和感はなかった。
終演後の聴衆は熱狂的。
この大きな喝采の中で、わたしが最初に思ったことは、
「ああ、この人たちに、新国立劇場の《蝶々夫人》を観せたい」
ということ。
今宵の公演も、レパートリー公演として優れたものであったとは思うが、演出にしろ、舞台にしろ、歌手の役作りにしろ、新国立劇場の「蝶々夫人」ほど磨き上げられ、極められたものではなかったからである(もちろん、それは止むを得ないことだけれど)。それほどまでに佐藤康子の蝶々さんも、山下牧子のスズキは美しかった。
なお、戦後再建された旧西ベルリン唯一の歌劇団も、内装の劣化は隠せない。椅子のクッションは昭和の映画館ほどではないにしても快適には遠く、クロスもところどころ綻びている。
なお、わたしの座席は、平戸間10列目中央であったが、少なくともこの座席での音響はよろしくない。「ピットの音が上に昇っては降りてくる」という類のオペラハウスの醍醐味とは無縁、残響の乏しい乾いた音。もう少しアコースティックがよければ、さらに感動できていただろう。
それにしても、開演前に頂いたレモネードは美味かったなぁ。