ヴィクトール•フランクル (Viktor Emil Frankl 1905-1997)『夜と霧』霜山徳爾訳(みすず書房)1956年

庵主が小学生5-6年の頃、父親の本棚に並んでいた「夜と霧」(初版本)を読んだ。本を開くや、ナチスドイツの強制収容所で写した何枚もの無惨な写真が出てきて、恐れおののいた記憶がある。虐殺場面などの残虐なシーンが続くので、新版ではこれらは収録されてないはずである。その時の写真の印象が強烈で、本の内容について、どのように思ったかについては全くおぼえていない。しかし、読み直してみて、評判どおり読むべき20世紀の一冊であると思った。
初版は本文の前に「解説」があり、ナチスの強制収容所であるアウシュビッツ、ベルゼン、ブッシェンワルト、ダッハにおいて、どのような残虐で非道な事が行われていたかが、細かく書かれている。第三帝国のあらゆる悲惨な道が、強制収容所での死へと続いていた。ユダヤ人、ロシアの戦争捕虜、パルチザン、連合国捕虜、夜と霧の囚人、ジプシー、障害者、侵略に協力する事を拒否したり、あるいは侵略者に抵抗した市民は、いずれもゲシュタポによって、その家庭から引きずり出された。これら無辜の人々を待ち受けていたのは死であり、たとえ運よくここを出れたとしても、身体は痛めつけられ、心にはすっかりひびが入れられていた。この「解説」では、ナチスの強制収容所の状況が詳しく報告されている。「ホロコーストは捏造だと」いう主張を一蹴できる資料である。
「劣等」民族や人種に対する「最終的解決」はナチズム哲学の具体的な実践であり、強制収容所における集団虐殺であった。一方において、これは戦時における労働奴隷の確保を前提に、使えない弱者や病者を順次、ガス室で抹殺していくといった合理的、能率的な計算にもとずくものであったとされる。この悪魔的な非人間性は、ナチス思想とドイツ人独特の合理主義とベルトコンベアー式近代工業をミックスして発揮されたものだ。アウシュビッツの正門ゲートには、Arbeit macht Frei (労働は自由への道)という象徴的標語が掲げられていた。
著者フランクルは1905年にウィーンで生まれる。フロイド、アドラーに師事し、ウィーン学派の精神分析医であった。1938年ドイツによるオーストリア併合後、この国のユダヤ人に苦難が始まる。そして1942年に家族とともに強制収容所に送り込まれる。単に一家がユダヤ人だという理由だけで。両親、妻、二人の子供はガス室で、あるいは餓死あるいはチブスで病死した。フランクだけが奇跡的に生き延びたのである。日常が死と隣り合わせの状況で、心理学者の眼で強制収容所を見つめ、生きると言う意味を考え続けた。ここで生き残った人とそうでなかった人の差は、運以外になんであったのか? そのヒントを本文からいくつか引いて紹介する(文章は一部改変)。
• どんなときにも自然を見つめる。
『労働の最中に一人二人の人間が、自分の傍で苦役に服している仲間に、丁度彼の目に談った素晴しい光景に注意させることもあった。たとえばバイエルンの森の中で、高い樹々の幹の間を、まるでデューラーの有名な水彩画のように、丁度沈み行く太陽の光りが射し込んでくる場合の如きである。あるいは一度などは、われわれが労働で死んだように疲れ、スープ匙を手に持ったまま土間に横たわっていた時、一人の仲間が飛び込んできて、極度の疲労や寒さにも拘わらず日没の光景を見逃させまいと、急いで外の点呼場まで来るようにと求めるのであった。そして、われわれはそれから外で、酉方の暗く撚え上る雲を眺め、また幻想的な形と青銅色から真紅の色までのこの世ならぬ色彩とをもった様々な変化をする雲を見た。そしてその下にそれと対照的に収容所の荒涼とした灰色の損立小屋と泥だらけの点呼揚があり、その水溜りはまだ撚える空が映っていた。感動の沈黙が数分続いた後に、誰かが他の人に「世界ってどうしてこう綺髭なんだろう」と尋ねる声が聞えた』
地球の自然にやすらぎを求めるのは、おそらく虫をはじめとする全ての動物の習性であろうと思う。習性への回帰が命を延ばす。
• 希望を失う事が免疫を低下させる
『勇気と落胆、希望と失望というような人間の心情の状態と、他方ではその抵抗力との間にどんなに緊密な連関があるかを知っている人は、失望と落胆へ急激に沈むことがどんなに致命的な効果を持ち得るかということを知っている。私の仲間のFは期待していた解放の時が当らなかったことについての深刻な失望が、すでに潜伏していた発疹チブスに対する身体の抵抗力を急激に低下せしめたことによって死んだ。彼の未来への信仰と意志は弛緩し、彼の肉体は疾患におちいったのである。このI例の観察とそれから出てくる結論とは、かつてわれわれの収容所の医長が私に注意してくれた次の事実と合致する。すなわち1944年のクリスマスと1945年の新年との間に、われわれは収容所では未だかつてなかった程の大量の死亡者が出ているのである。彼の見解によれば、それは過酷な労働条件によって、また悪化した栄養状態によって、また悪天候や新たに現われた伝染炊患によっても説明されえるものではなく、むしろこの大量死亡の原因は、単に囚人の多数が、クリスマには帰れるだろうという素朴な希望に身を委せた事実の中に求められるのである』
安易な希望的な観測は、予想がはずれるとかえってダメージが大きい。しかし、楽天的であることと精神のタフネスの維持が二律背反とは思えない。
• ユーモアーと遊びを忘れずにいる
『もし収容所にはユーモアがあったと言ったならば、驚くであろう。もちろんそれはユーモアの芽のごときものに過ぎず、また数秒あるいは数分間だけのものであった。ユーモアもまた自己維持のための闘いにおける心の武器である。周知のようにユーモアは通常の人間の生活と同じに、数秒でも距離をとり、環境の上に自らを置くのに役立つのである。私は数週間も工事場で私と一緒に働いていた一人の同僚の友人に、少しずつユーモアを言うようにすすめた。すなわち私は彼に提案して、これからは少くとも一日に一つ愉快な話をみつけることをお互いの義務にしようではないかと言った。彼は外科医で、ある病院の助手であった。私は彼に、たとえば彼が後に家に帰って以前の生活に戻った時、収容所生活の癖がどんなにとれないかを面白く描いて、彼を笑わせようと試みた。このことを語る前に先ず説明しておかなければならないのが、労働場では、労働監督が巡視にやってくる時には、看視兵は労働のテンポをその時早めさせようとして、いつも「動け、動け」と言ってわれわれをせきたてるのが常だった。だから私は友に語った。もし君が手術室に立って、そして長く統く胃の手術をしていたとする。すると突然手術室係りが飛び込んできて「動け、動け」と知らせる、それは「外科部長がやってきた」ということなのさ』
ユーモアと遊びはどんな時にも必要である。これは人をパニックから救ってくれる。
• 人生(世界や社会や他人)に何を求めるかではなく、それが私に何を求めているかを問う。
『既述の如く、強制収容所における人間を内的に緊張せしめようとするには、先ず未来のある目的に向って、緊張せしめることを前提とするのである。囚人に対するあらゆる心理治療的あるいは精神衛生的努力が従うべき標語としては、おそらくニーチエの「何故生きるかを知っている者は、殆んどあらゆる如何に生きるかに耐えるのだ。」という言葉が最も適切であろう。すなわち囚人が現在の生活の恐しろい「如何に」(状態)に、つまり収容所生活のすさまじさに、内的に抵抗に身を維持するためには、何らかの機会がある限り囚人にその生きるための「何故」をすなわち生きる目的を意識せしめねばならないのである』
et lux in tenebris lucet (光は闇を照らしき)
闇に光を探すのではなく、自ら闇に灯りをともすべし。「一隅を照らす」と天台の教えにもある。言い換えると、人生にはそれぞれ納得できるストリーの創造が必要であるということである。
• 精神的愛の確信
『その時私は或ることに気がついた。すなわち私は妻がまだ生きているかどうか知らないのだ!そして私は次のことを知り、学んだのである。すなわち愛は、1人の人間の身体的存在とは関係が薄く、愛する人間の精神的存在と深く関係しているかということである。愛する妻がまだ生きているかどうかということを私は知らなかったし、また知ることができなかった(妻はこの時にはすでに殺されていた)もし私が当時、私の妻がすでに死んでいることを知っていたとしても、私はそれにかまわずに今と全く同様に、この愛する直視に心から身を捧げ得たであろう』
付記:今日の京都新聞 (2019/07/23・ 30面)に、たまたま『ナチスの「安楽死」政策』というコラム記事がでていた。ナチスドイツの障害者「安楽死」政策で、約20万人もの人が犠牲になった。この背景には「経済性、効率性、生産性といった社会にとっての価値基準」があるとしている。
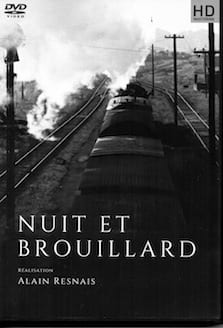
















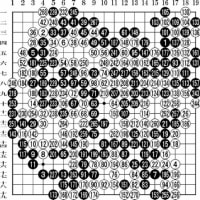









※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます