映画は戦争を止められるか? 大林宣彦監督が新作語る
残酷さ鮮明に描く
「皆さんに意識されていなかったが、僕は原爆投下について6回か7回、映画で描いている。今度は(米軍のB29爆撃機)エノラ・ゲイから原爆が広島に落ち、主人公たちが殺されてしまうことをはっきりくっきりと描いた。これはただごとではなく(撮影を)やっているうちにどうしても本気になる」
監督は日本の自主製作映画の先駆者だ。商業映画に進出して「転校生」「時をかける少女」「さびしんぼう」の尾道三部作などで若者から熱狂的に支持された。振り返れば商業映画第1作のホラー「HOUSE/ハウス」をはじめ、表現手法は違っても戦争を描いた映画を撮り続けていたことに気づいたという。
「同じことをやってきているんだよね、僕は。戦争を知っている最後の世代(である自分)が、戦争のむなしさ、恐ろしさ、ばかばかしさ、無謀さ、残酷さを背後にして描いてきた。戦争の暴力的な力の存在。それが僕の映画の全部にあった」
1938年生まれ、戦時中に幼少期を過ごした。「敗戦少年世代」と自らを呼ぶ。「子どもであるがゆえ戦争体験は関係ないと大人は思うかもしれないが、子どもだからこそ大人を一生懸命観察した。この大人は信用できるか、できないか。痛いほど身にしみて感じるのは、むしろ子ども」と訴える。
虚実の間のまこと
「映画は未来の若者たちのために存在する」と語る大林監督
現代の日本への懸念を隠さない。「日本人ぐらい学び下手の国民はいない。体験したことを簡単に忘れて能天気に過ごしている。僕たち戦争を知っている子どもとしてはそれが悔しくてね。忘れるなよ、こんな大事なことをと言いたい」
「映画人はすべからくジャーナリストでなければいけない」と語り「情報という『他人ごと』を映画の物語性によって『自分ごと』として実感してほしい」と説く。「映画には虚と実の間にまことがある。その真実を力に僕たちは映画を撮っている。僕が映画を作っている理由でもある」
「切迫感」という言葉を繰り返した。一見平和に見える日本だが、背後に戦争の影が忍び寄っていないか。そんな切実さがにじむ。
もっとも、自分より若い世代の映画人から「過去の歴史を変えることはできないが、映画で未来を平和に変えることはできる」といわれ、希望も見いだす。「映画は未来の、幸せに生きる若者たちのために存在する。それが映画の誇り、自慢」と力強く語った。
「海辺の映画館」は東京国際映画祭で11月1日に上映される。20年公開予定。
(文化部 関原のり子)
[日本経済新聞夕刊2019年10月21日付]














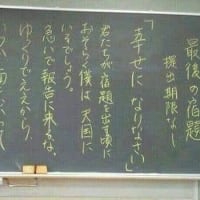

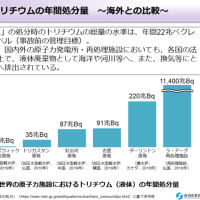
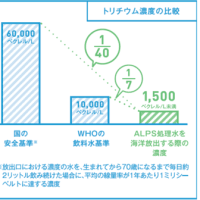
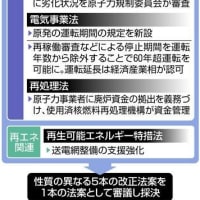








※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます