『菅江真澄遊覧記1』(内田武志 宮本常一 編訳 東洋文庫54 平凡社)
「伊那の中路」
二つの星に献上する文。
「秋風がそぞろにふいて、きょうは七月七日になった。わたくしも旅の途上、この里にきて久しくなり、七夕の夜空を仰ぎみることは、あい難い縁である。夜の明けるのを待って、子供たちは小さい人形の頭に糸をつけて軒に引き渡し、日暮れの空を待ち、女の子たちはお化粧し、きれいに着飾って大ぜい集まり、ささらをすって歌をうたう。今宵の星をお慰め申し上げるのであろう。ねぐらに帰るむらがらすも、声をそえ、夕昏の空に羽をならべて、橋をつくるかのように、いそいで飛びわたっていった。遠方の高嶺もなごりなく暮れはじめて、星ひとつ光りだしたかとみるまに、天の川がいま波だつようにみえてきた。紅葉の橋がかかって星もうれしいことだろうと、人の世の思いにたとえて、天空の世界まで思いやった。今宵、心もやすらかに、波しずかな天の川を行き通い、うちとけた深い仲の逢瀬をたのしんでいることだろう。神代の昔から、相会う折の少ない二星の契りは、つらい定めの例とされてきた。何のたよりも許されない一年のつらさに、安らかに眠る夜も少なかろうと、人々は空を仰いでは、今夜のたむけにと、幾度も、唐詩、和歌などを誦した。今月今日のこの夜、世の人々はうやうやしくふたつの星を拝み奉る」
と、天の川が東の空にうつり流れるまでまどいした。










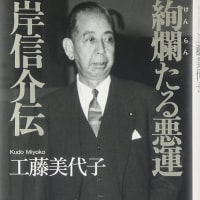
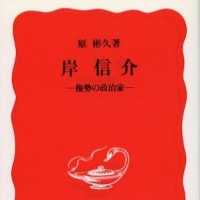

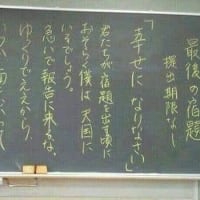

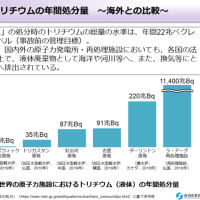
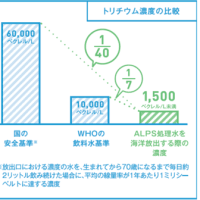
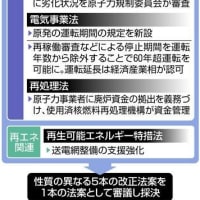








※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます