「父に代わって一家を支える」 五木寛之
(『わが人生の歌がたり』 五木寛之 2007年 角川書店)
母が死んで、いちばん困ったのは、父が茫然自失して、まったく頼りにならなくなってしまったことです。ですから中学一年だった自分が、弟とまだ幼い妹の面倒を見て、一家を支えなければなりません。
父は、貧しい農村から師範学校に入り、苦学して検定試験もたくさん受け、少しずつ少しずつ出世の階段を、爪で這い上がるようにして生きてきた人です。少し良くなってきたかと思ったときに敗戦で、夢に描いた教育界での出世の階段も突然はずされてしまう。それどころか、職業も、最愛の妻も亡くしてしまったのです。国語の教師として自分の思想の背景になっていた本居宣長とか平田篤胤とか賀茂真淵とか、そういう学問も突然禁じられてしまった。「剣道何段」と威張っていたことすら、むしろ恥ずかしいことでしかなくなってしまう。
こういうふうに、国家、民族の運命と個人的な自分の暮らし全部が一挙に崩壊してしまったのです。中学生の私は、何て情けない父親だろうと思っていましたけれども、父の立場になってみると、わかる気がしてきます。
父は朝鮮のどぶろくをどこからか手に入れてきて、朝から飲んで酔っ払うようになってしまいました。
あんなに凛々しく堂々として、朝夕、私に国語を講義したり、『日本書紀』を暗記させたり、剣道の切り返しをやらせたりして、「日本男児云々」と意気軒昂だったのが、もうグズグズの男に成り下がってしまった。
ソ連兵が家に略奪に来たとき、家族を守るために命がけでぶつかっていって、撃たれて死んだってよかったんじゃないか。ところが、できなかった。家族を救えなかった家父長の自己嫌悪ととにかくいろいろなことが重なって、父親はもうほとんど役に立たない状態でした。そうなると、私がものすごくはりきってしまい、家族を自分で支えるんだと、こういう生意気な少年になっていました。
いっぱしの大人の仲間入りをして、中学一年生なのに、一緒に飲めないお酒を飲んでみたり、タバコを吸ってみたりしました。
とにかく肩肘張らないと、混乱のなかで一家を支えて生きていくことはできなかったんです。それまで通用していた朝鮮の通貨がツルツルの紙の赤や青のソ連の軍票に切り替わって、持っていたお金が全部役にたたなくなった。引き揚げは始まらないし、とりあえずここで身を寄せ合って暮らしていかなければならない。日本人はみんなそれぞれ行商をしたり、日雇い労働に出たり、いろいろな形で自活を始めるわけです。大人たちに混じって、十四歳の少年が突っ張って生きるためには、やはりタバコくらい吸わないと、「なんだ、このガキ」とばかにされますから、背伸びしてやったんだろうと思うんです。
私も街に出て、いろいろな仕事を見つけて働きました。しばらく行商をやったり、ソ連兵の将校たちの宿舎に行って、片言のロシア語で、「パパニェット、ママニェット、ラボタ。ダヴァイ(お父さんもいない、お母さんもいない、仕事をおくれ)」「フレーブ。ダヴァイ(パンを欲しい)」なんて言ってね。同情してくれるソ連の将校たちの家で薪割りや掃除をしたり、靴を磨いたり、下働きをして、帰りに大きな黒パンや肉の塊を一つもらってくる。
帰ってくると、弟や妹、肩寄せ合って暮らしているほかの避難家族たちにもそれを分けてあげて、周りからはなかなか甲斐性のある子どもだと思われていました。
大人たちと一緒にやけくその酒盛りの席では、みんな歌を歌うわけです。新しい情報が入ってきませんから、歌うのはみんな戦前の歌でした。ラジオもない、新聞もない。日本がどうなっているかわからない。覚えているのは昔の歌だけで、それを次から次へと歌ったものです。
私がいまも覚えている昔の歌のほとんどは、当時、大人たちと一緒に歌って覚えたものですね。なかでも印象に残っているのは、『国境の町』という歌です。
国境の町(作詞=大木惇夫 作曲=阿部武雄)
橇の鈴さえ寂しく響く
雪の曠野よ町の灯よ
一つ山越しゃ他国の星が
凍りつくよな国境
故郷を離れてはるばる千里
なんで想いがとどこうぞ
遠きあの空つくづく眺め
男泣きする宵もある
行方知らないさすらい暮らし
空も灰色また吹雪
想いばかりがただただ燃えて
君と逢うのはいつの日ぞ
人は悲しいときに、明るい歌で元気づけられるというのでもない。悲しいときには、強い言葉とか元気な激励の言葉ではなくて、「わかるよ、おれもそうなんだよ。本当に生きていることは大変だね」という言葉のほうに、心は支えられるのではないでしょうか。
「遠きあの空つくづく眺め 男泣きする宵もある」と涙ながらに歌ううちに、それでもなんとか生きていかなきゃという気持ちが湧いてくるものなんですね。歌ったのは、みんなそういう孤独の歌、さすらいの歌、心細い歌ばかりだったように思います。
あの時期ほど、歌の歌詞が身にしみて、心に迫った時代はありませんでした。まして多感な少年時代ですから、なおさらですが、あの時期を支えてくれたいわゆる歌謡曲には恩義を感じています。ですから一生こういう大衆の歌う歌を大切にしていこうという気持ちがあるのです。













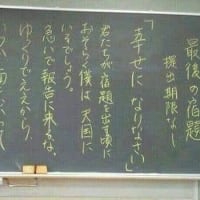

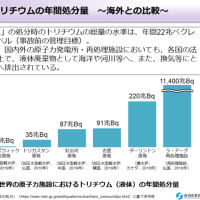
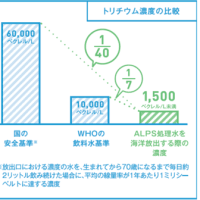
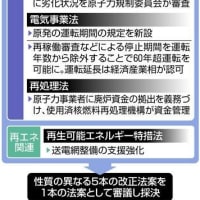








※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます