盲友
藤本トシ「地面の底が抜けたんです」より
蜘蛛の糸の主人公カンダタのような悪人でも、生涯のうちには蜘蛛をふみ殺さずにおいてやったかすかな善事があるように、思い出は、たいてい湿っぽい陰をもつ私にも、たった一つ、かみしめればすがしい香のたつ過去がある。
かつて私の友に、といっても年は九ツもうえなのだが、本川さんという盲女がいた。この友は手足もたいへん不自由だったので、お風呂いがいの外出は殆どしなかったのである。病みほうけて一見みるかげもないこの人に、私は初めて会ったときから心をひかれた。
それは、「あれ新患や」と言われることが、私にはまだ侘しくてならなかった頃のこと、ぼんやり戸口にたたずんでいると唄が聞こえてきた。向かい寮からである。
ゆうぐれに
ながめ見あかぬすみだがわ
つきに風情はまっちやま
帆あげた舟がみゆるぞえ
あれ とりが鳴くとりの名も
みやこに名所があるわいな
美声。しかも心にしみる唄いぶり。私は思わず声の方へ歩み寄った。これが本川さんだったのである。
縁とはふしぎなもので、それからまもなく、私はこの人の手紙の代筆をするようになっていた。つづいて縫いはり洗濯にまで及んでいったのである。こうして十一年の日が流れた。(外島時代からの通算である。)
昭和十九年の冬、本川さんは風邪をこじらせて部屋から病室へ移った。しかし、じきに戻れると思っていたのに、病状はおもいに反して、半月ほどのうちにめっきり衰弱してしまったのである。なにしろひどい食糧不足だったので、ろくに食べていなかったせいもあろう。
ある朝、みまいにゆくと、当惑げな付添い(㊟同病者の患者看護)の顔が待っていて、私を廊下へ手まねいた。
「本川さんはなあ、熱いお湯がほしいと言うから飲ませてあげると、これぬるいわ・・・、と言うんよ。こっちがびくびくするほど煮えたったのをあげても、やっぱりぬるいって言うんよ」
このささやきを聞いたとき、私は、はっとむねをつかれた。舌も咽喉も麻痺したのである。
多くの病友の死をみつめてきた私の眼は、ほそい寝息のなかに、この友にもついにきた生のかぎりの翳をみた。その夜、先生からも付添いに注意があったそうである。
翌日たずねると本川さんはいきなりこう言った。
「私、死ぬんやろかー」
「そうや・・・。極楽へゆけるのよ」
ちゅうちょなく答える私の背を付添がこづいた。このようなばあい、心とくちと正反対に言うのが常識である。私もしばしばこれをやった。だが本川さんにはその必要はないと思ったのである。この人の心は決定けつじょうしていると、つねづね思っていたからである。なんにもお祀りしていない自分の押入れのまえに坐って、朝夕合掌しているだけだが、その姿にはしんけんさがあふれていた。
「ありがとう。じゃ今日から準備するわ」
と言った友の言葉は、低かったがはっきりしていた。
しかし・・・準備とはなに・・・。心のか、物質面のことか、私はそれをはかりかねた。そのまま日は二、三日流れたのである。
三日目の夜、空襲警報が出ないうちにと病室へ走って行ったが、その戻りのこと、
「本川さんな、こんどは今日からねまきを朝晩かえてくれって頼むんよ。そんなに汚さんのになあ」
洗濯ものを私の手にわたしながら付添いがこう言ったのである。このときサッと謎がとけた。本川さんはたとえ洗いざらしでも、さっぱりした身なりで臨終を迎えようとしているのであった。
つぎの日、私はびっくりしてしまった。本川さんが小唄を唄うと言うのである。あんたが何時もほめてくれたから今日は聞かせると言うのである。やがて唇がうごきはじめた。
うめ に も は・・・・・る の
い ろ そ え て
わか み・・・・・ず・・・・・
聞きとれたのはここまでであった。だが声にはならずとも、唇は最後まで唄のつづきの動きを見せていたのである。風雲急となってからは一回も唄わなかったその唇が・・・。
唄い終わったとき私は拍手を送った。付添いもいつかきていて手を打っていてくれた。その夜更け、友は従容として逝ったのである。
・・・・・・・・・
じぶんも盲目となって今しみじみ思えば、しっとりと・・・そして爽やかにむねにしみた小唄、「ゆうぐれ」のあの余韻は、そのころは生地獄のようだった癩盲の苦を、超え得たものの凱歌のひびきであったのだ。
「梅にも春」は、わが手で拓いたその道を、みごと歩みおおせた者が、いのち終わる日、我れと我が身に贈ったことほぎ唄であったのか。すべてのものに告げる別れも、そのこころの奥にひそめて・・・。
ともかく、私の知るかぎりでは愚痴を言わなかった人。あの透明な笑いが、ときおり耳によみがえる。
1969年(昭和44年)













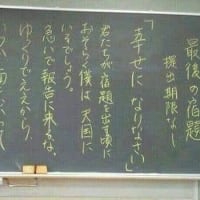

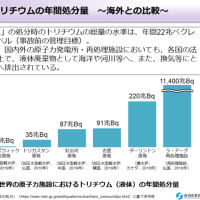
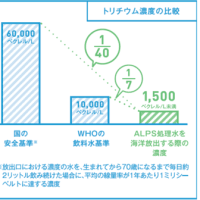
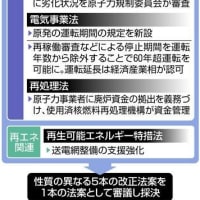








※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます