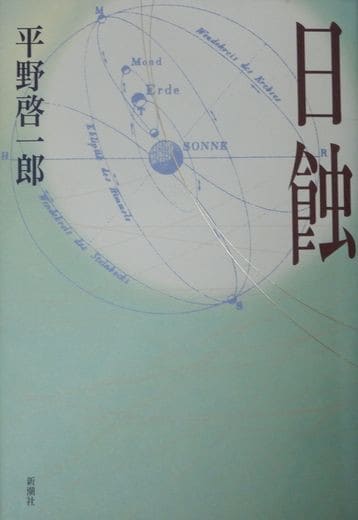
ひょんなことから、平野啓一郎の作品を2冊購入しました。初めて読む作家です。
この作家を知ったのは、映画「三島由紀夫vs東大全共闘」の中で、インタビュー映像が流れていたこととからです。その時は、三島に影響を受けた作家のひとりか、くらいにしか思わず、インタビュー内容もほとんど覚えていませんでした。
その後、NHK番組「100分で名著」の金閣寺のシリーズでは解説者として登場していて、三島への深い理解を披露したり、Twitterの#NewsPickタグでは頗る真っ当なツイートが見られたりとで、この作家の作品を読んでみたくなったわけです。
というわけで、デビュー作の「日蝕」から読んでみました。
1999年の芥川賞受賞作、もう22年前の作品です。

帯には、三島由紀夫の再来ともいうべき神童が文芸に聖性を呼びもどす、とあります。
なんかよくわからないコピーですが^^;

こちらが売り文句。
三島の再来というだけあって、言葉の使い方が古風というか優雅というか、私にとっては難解な小説です。三島作品でいえば、豊饒の海第三部・暁の寺、といった雰囲気でしょうか。
例を挙げると、難読の漢字、熟語が頻発します。たとえば、「塋域」「錬稠」「壁龕」「覬覦」「蟲豸」「鷹鸇」などなど。
上の行のかぎ括弧内、読めますか?というより、表示できますか?out of 常用漢字は当たり前。JIS第二水準はおろか、第三水準、第四水準も登場^^;。処理系によっては表示できない端末もあるかと思います。
これらの難読字は前後関係から意味を類推して読み進むこともできますが、それはせずに辞書(ネット)で意味を調べながら読んだので、時間がけっこうかかりました。
三島の特徴のひとつは、ずばぬけた語彙の多さであると私は思っているのですが、語彙の点に関しては三島に勝るとも劣らない作家だと思いました。
また、旧式の表記や漢字、たとえば、輝く→赫く、確かに→慥かに、やがて→軈て、なお→猶、を使うので、これも読解を難しくしている一因になります。さらに同じ意味の語句を別表記、たとえば、空→蒼穹、空→昊、というのも見られます。
テーマは神学、信仰についてなので、専門用語を知らないと理解しづらい箇所も多くありました。普遍論争、唯名論、トマス主義、Summa、などの知識をある程度調べないと小説の中に入りきれないかもしれません。
こう書くと、なんか難しい本で読む気がなくなる、と思いそうですが、小説好きの人は多かれ少なかれ、難解な言葉や手ごわい文章をあえて好む傾向を有する人が少なくないと思います。それは読後の達成感や自己の向上感が得られるせいで、そんな小説好きの心理をうまく衝いているような文体だと感じました。
さて、肝心のストーリーですが、舞台はフランスからイタリアの中世。ファンタジーの時代です。
登場キャラクターも錬金術師、アンドロギュヌス、でえだらぼっちまでいろいろ。
ストーリー自体はシンプルでキャラクターもわかりやすくて語彙の難解さとは対照的にすんなりと頭に入ってきたのですが、作者からのメッセージの方はまた難解だと思います。異端排除へのアンチテーゼ?復活の奇跡?いまいちわかりませんでした。
例えていうなら、煌びやかな宝石の写真が並ぶ宝石商のカタログを眺めているような、表面の華麗さだけが頭に残ったという印象です。ストーリーよりも古風な美しさの文言が記憶に残るという感じでしょうか。
何回か繰り返して読むか、またはこの作者の他の作品をもっと読むか、あるいは識者の解説を読んだりすれば、より理解が深まるかもしれませんし、そうならないかもしれません。
三島由紀夫のデビュー作「花ざかりの森」のように、世間の評価はとても高いのだけど私はいまだにその良さが理解できてない、という作品もあります。
これから2冊目を読み始めます。
p.s. 今日の栄養成分はOK牧場。
















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます