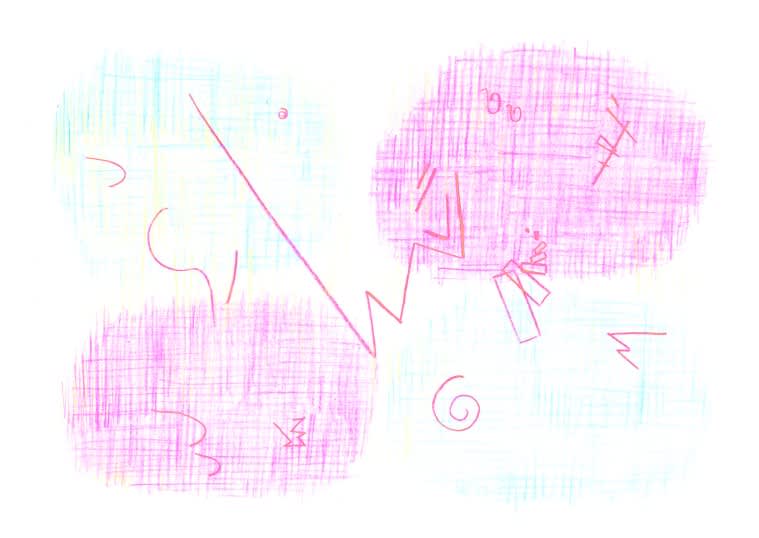3月に入り、寒さのピークはようやく過ぎたものの、それでも春の訪れにはまだしばらくかかりそうで、やはり冬は長いとあらためて実感せざるを得ないとはいえ、解散したプラス・マイナスの今後が気になってしょうがない今日この頃、皆さんご機嫌いかがですか的なR-1グランプリの感想文です。
明治がスポンサーになることで、ヨーグルトのR-1とのコラボという、長年の悲願がついに達成されたR-1グランプリ。今回から芸歴10年以内という制限が撤廃されましたが、それとネタ時間が3分から4分に変更されました。前からネタ時間が短いと思ってましたので、個人的には喜ばしいです。
個別の感想は以下の通り。まずはファーストステージから。
真輝志・・・高校に入学したての、一見平凡な少年。しかし隠れた才能があった?ドラマやマンガによくある、オープニングで「これはどのような物語か」「どんな結末が待ち受けているのか」をナレーションで示すという演出を利用したネタ。普通登場人物にナレーションは聞こえないが、なぜか聞こえてしまうことで、これから選択しようとしている活動が、つまらない結末をもたらすことを知ってしまう。
フィクションのお約束を逆手に取った、お遊びネタですね。英語のナレーション、なんて言ってたの?誰か教えて!あと、軟式ラグビーって実在するんですか?主人公の結末ばかりが示されるのかと思いきや、クラスメイトの女子も入ってきて、2人の物語が交差するというドラマチックな展開。全体のまとまりがよくできていました。
おそらくこれが全国はじめましての真輝志。「ほなええわ」の人として覚えられるかもしれません。
ルシファー吉岡・・・婚活パーティーに参加した男・戦原(そよぎはら)。しかし女性陣はパーティーのルールを理解しておらず、説明役を負わされてしまう。
1分ごとに対面相手が入れ代わる自己紹介タイムという形式をうまく利用しています。時間が1分しかないので、説明が終わるとともに相手が交代し、自己紹介をするヒマがない。同じパターンを繰り返すたびに、チャイムの「チーン」という音が主人公のガッカリ感の表れのようにむなしく響く。最初は説明するのが煩わしかった主人公が、だんだんムキになっていき、説明に対する責任感が生まれていく。
いや、よくできていますね。このシンプルな設定。日常の延長のようなありきたりなストーリーでよくここまで。「空回り」とか「孤軍奮闘」とか、お笑いの典型ですけど、その基本に立ち返りつつ精度の高さを見せつけられた思いです。
街裏ぴんく・・・ルシファーを称するのはともかく、「こう見えても女芸人」とは?ちょい不安なスタートでした。
作り話を実体験のように語る、ぴんくのファンタジー漫談。プールに行ったら石川啄木と遭遇、正岡子規やキュリー夫人まで登場するというタイムスリップ的な話。
ぴんくの漫談は、和田アキ子とX JAPANのToshiがケンカする話とか、芸能人が登場するのもありますけど、今回1本目にこのネタを持ってきたのは、認知度がほぼゼロだからでしょうね。自分のネタがファンタジー漫談だと知らなければ、事実を話してるのか、ウソの話なのかどうかが、よくわからない。芸能人が登場する話だと、本当のことと受け止めてしまうかもしれない。だから、作り話であるとすんなり理解してもらうために、歴史上の人物が登場する話にしたのです。その判断は正解でした。この1本目で街裏ぴんくという芸人を知らしめ、2本目のファイナルステージにつなぎ、優勝への流れを作ったのだと思います。
kento fukaya・・・マッチングアプリのネタ。男たちのプロフィールが奇妙なものばかりで混乱してしまう。フリップではなく、モニター使ってましたが、kentoの感覚ではフリップの変形(もしくは延長)なのでしょう。
最初は男の選択眼が厳しい女による毒舌ネタかと思いきや、登録している男の大半がおかしなやつらだった。ガラケーユーザーの僕には、iPhone 2Sのおかしさが理解できませんでした。「人人」を一発で「ひとんちゅ」と読めるのはスゴい。こういうプロフィールをひたすら考えるのが楽しくてしょうがないんでしょうね。それが伝わってきました。
陣内智則が指摘していた通り、くりちゃんの趣味がサプライズだったので、そこをオチに持ってくるべきだったと思います。あと、手にした「ト」の使い道が何かあったはずです。
寺田寛明・・・ツカミの「今日の偏見」、「インスタにしょっちゅう肉寿司の写真を載せる女は肉寿司がだぁいすき」って?思わず「そのまんまじゃねーか!」と叫んでしまいました。マイナスからのスタート。
国語辞典にネットのようなコメント欄があったら、というネタ。寺田らしい、知性を感じる考え込まれた作り。コメントによって、「言われてみればたしかにそうだな」と思わされる。聞いたことない言葉であってもちゃんと笑える構成。犬侍の、「応仁のわん」「ポメ騒動」みたいなダジャレは、いかにもネットのコメント欄にありそうなノリ。最後の「暗澹たる」の、「あんたんが重い樽を運んでいる」という解釈からの畳みかけで爆発していました。よくできていましたが、爆発、やや遅し。
サツマカワRPG・・・不審者と思わせといて、実は防犯ブザーの講習会。そういやサツマカワはカツラユーザーでしたね。今まで地毛を隠していたのが、武器として使う決意を固めたということでしょうか。カツラを取ったサツマカワ、うっすら遠藤憲一に似てますね。
お父さんの肉声バージョンに対する当たりが強すぎる。特定のユーモアに憎しみを抱いているのでしょうか。最後、子供と思いきや幽霊だったというオチ、少々安易に思いました。こういう「私のことが見えるんですか?」と話しかけられるのって、よくコントで使われてますよね。驚かす手法として便利なんでしょうけど、いろんな芸人さんが使ってるのを見てると、あまり軽々しくやらないでほしいと思っちゃいます。
大会後、でか美ちゃんとの結婚を発表したサツマカワ。末永くお幸せに。
吉住・・・彼氏の両親の家に挨拶に来た女。実は頻繁にデモ活動している危険人物だった。吉住の得意とする世界観。可愛い子ぶった振る舞いと狂気のギャップ。初め「ナオキさん」だったのが、2回目から「ナオくん」になっており、その礼儀のわきまえなさが、イタいキャラであることをさりげなく示しています。この作り込み、実にうまい。
多くの人が指摘していることですが、演技力も高く、ネタの世界に引き込まれます。さすが女優。個人的に今大会で一番よかったです。
なんでも、吉住のこのネタに対し、SNSで非難の声が上がっているそうで。いわく、「デモを揶揄するのはよくない」。あのね、これはお笑いなんですよ。冗談でコミカルに描いているのであって、本気でバカにしているわけじゃないんです。弱い立場にいる人を、さらに追い詰めかねない表現ならともかく、この程度で揶揄ってねえ。なんにでも難癖つけたがる人って、どこにでもいますね。
トンツカタン お抹茶・・・かりんとうの車のネタ・・・ってなんじゃそりゃ?かりんとうで作られた自動車が街を疾走。ミュージックビデオよろしく歌が情景を説明する。
歌ってるのは本人ではなく、録音された他人の声(ひょっとしたらボイスチェンジャーかも)で、たまに入るコーラスが本人。逆じゃない?もうわけがわからない。わからな過ぎて、「もう徹底的に好きなようにやってくれ」という気分になってしまいます。かりんとうと抹茶の相性のよさは認めざるを得ないとしても。審査員泣かせのネタ。あとなんか、ひさしぶりにかりんとうが食べたくなりました。
曲の完成度は高いので、聴いていて気持ちよくなります。しかし、「気持ちよさ」が「面白さ」を上回ってしまった感が否めません。ネタとして賞レースに持ってくるより、TikTokで流したほうがいいんじゃないでしょうか。バズりますよ、きっと。お抹茶はもう、好き勝手やらせるのが一番いい芸人のひとりと認めていいでしょう。トンツカタンではこのエキセントリックさがいっさい表れていませんが、そのほうがいいのでしょうか。トリオだとあまり目立てないので、その反動でこのようなピンネタが生まれてる、とか。それと、ここまでキャラが立ってるとは知りませんでした。なんとなくおとなしいタイプかと思っていたのに、妙にポジティブな陽キャ。このキャラだけで売れる余地アリです。
この世界観、クセになってしまうかもしれません。クセになる、つまりお抹茶にハマっちゃうということです。
どくさいスイッチ企画・・・ツチノコを発見した男の人生。よくも悪くもツチノコに振り回される一生を送る。リアルな描写を重視したんでしょうけど、10分後・3時間後・18時間後あたりは省いていいと思います。それよりもっとドラマチックなことが起こる場面を入れてたら、笑いが増えていたはずです。リアリティを多少犠牲にして、非現実的な飛躍をもうちょっと入れていたら。それでも充分面白かったですけどね。
どくさいはこれからもアマチュアのまま活動を続けるのでしょうか。だとしても、ネタ番組に呼ばれるようになってほしいです。
続きましてファイナルステージ。
吉住・・・窃盗事件の現場に駆けつけた鑑識。そこは交際相手の会社だった。彼氏の前では可愛い子ぶり、上司の前では冷静なプロの顔になる。ひとつ思ったのが、この「ツン」と「デレ」の切り替わりがもっと激しく行われてたらよかったんじゃないか、ということ。あと、浮気が発覚して態度豹変しますけど、その冷酷に詰め寄るさまが「ツン」と「デレ」より面白いので、このパートをもっと長くしてたら、と思いました。
1本目がよすぎたせいで、こちらがイマイチに見えているのかもしれません。
街裏ぴんく・・・実は自分はモーニング娘。の初期メンバーだったという告白。その舞台裏を打ち明ける。1本目で自己紹介は済んでますから、みんなファンタジーを素直に楽しめます。悦夫・越・嗚咽。漢字で入力して確認したくなりました。
トータルで感じたこと。台本の出来(面白さ)とは別に、話術の巧みさというのもあって、巧みであればあるほど「つい引き込まれる」とか「ずっと聞いてられる」ようになります。落語や講談などの話芸に共通する心地よさ。ぴんくにはその巧みさがある。加えて、熱量。とにかく懸命に、大きな声でまくし立てるその熱量に、聞き手は「本当のことを話している」と同意せざるを得ません。同意するといっても、このデタラメな話をまんま信じるということではなく、「ウソとわかりつつもノリを共有し、ファンタジーの世界にともに入り込む」ということです。それによって、ぴんくの世界を内側から眺めているような感覚になり、よりおかしくなるのです。この熱量あっての優勝だったと言えましょう。
ぴんく、本当におめでとう。R-1には夢がある。
ルシファー吉岡・・・アパートの隣人の騒音に、苦情を言いにきた男。しかしそれよりも、隣人の大学生ケンジ君の、ラブコメ(もしくはリアリティ番組)のような日常の熱心な視聴者(?)だった。このネタのネックは、登場人物が多いこと。ケンジとその友人、ミカミ、ユキコ、ヨシエ、レイナが出てきますが(本筋と関係ないけど、名前の古くささにルシファーの年齢が表れている)、ピン芸なので、当然のことながら観ている側で想像して補うしかありません。この想像、5人もいると把握が大変。誰がどんなキャラだか、それぞれの関係性はどんなだか、覚えながら話のスジを追わなきゃいけない。僕は正直、1回観ただけでは理解できませんでした。このわかりにくさが敗因ではないでしょうか。せめて3人くらいにしておけば。ケンジとユキコとレイナの三角関係だけでも成立したはずです(脳科学的に、人は3つまでのものなら同時に把握できるけど、4つ以上となると把握が困難になるのだそうです)。「じゃないんだよ」の前の間はよかったですね。
それより気になったのが、今回2本とも下ネタではなかったところ。なにか心境の変化でもあったのでしょうか。それとも、下ネタかどうかにこだわらずネタ作りをして、たまたま出来た強いネタが下じゃなかった、ということなのでしょうか。本人に訊いてみたい気もします。
今回芸歴制限の撤廃により、エントリー数が過去最高になりました。当然全体のレベルも上がっているわけです。芸歴10年以内なのは、10年目の真輝志と、9年目の吉住だけ。
苦労人に報われてほしいと望んでいる僕にとって、今大会は喜ばしい結果となりました。ぴんくは以前悪役専門の俳優事務所に入っていたそうで、自分でコワモテだと言ってますけど、僕はカワイイ顔してると思います。愛されキャラになる素質アリだと。これから起こるブレイクに期待。ネタのストックたくさんあるでしょうから、ネタ番組に定期的に呼ばれるようになってほしいです。
なんだかんだ言って、結局盛り上がるR-1。これからもドラマを起こし、スターを輩出してくれることでしょう。
不正がバレないよう頑張ってください。
明治がスポンサーになることで、ヨーグルトのR-1とのコラボという、長年の悲願がついに達成されたR-1グランプリ。今回から芸歴10年以内という制限が撤廃されましたが、それとネタ時間が3分から4分に変更されました。前からネタ時間が短いと思ってましたので、個人的には喜ばしいです。
個別の感想は以下の通り。まずはファーストステージから。
真輝志・・・高校に入学したての、一見平凡な少年。しかし隠れた才能があった?ドラマやマンガによくある、オープニングで「これはどのような物語か」「どんな結末が待ち受けているのか」をナレーションで示すという演出を利用したネタ。普通登場人物にナレーションは聞こえないが、なぜか聞こえてしまうことで、これから選択しようとしている活動が、つまらない結末をもたらすことを知ってしまう。
フィクションのお約束を逆手に取った、お遊びネタですね。英語のナレーション、なんて言ってたの?誰か教えて!あと、軟式ラグビーって実在するんですか?主人公の結末ばかりが示されるのかと思いきや、クラスメイトの女子も入ってきて、2人の物語が交差するというドラマチックな展開。全体のまとまりがよくできていました。
おそらくこれが全国はじめましての真輝志。「ほなええわ」の人として覚えられるかもしれません。
ルシファー吉岡・・・婚活パーティーに参加した男・戦原(そよぎはら)。しかし女性陣はパーティーのルールを理解しておらず、説明役を負わされてしまう。
1分ごとに対面相手が入れ代わる自己紹介タイムという形式をうまく利用しています。時間が1分しかないので、説明が終わるとともに相手が交代し、自己紹介をするヒマがない。同じパターンを繰り返すたびに、チャイムの「チーン」という音が主人公のガッカリ感の表れのようにむなしく響く。最初は説明するのが煩わしかった主人公が、だんだんムキになっていき、説明に対する責任感が生まれていく。
いや、よくできていますね。このシンプルな設定。日常の延長のようなありきたりなストーリーでよくここまで。「空回り」とか「孤軍奮闘」とか、お笑いの典型ですけど、その基本に立ち返りつつ精度の高さを見せつけられた思いです。
街裏ぴんく・・・ルシファーを称するのはともかく、「こう見えても女芸人」とは?ちょい不安なスタートでした。
作り話を実体験のように語る、ぴんくのファンタジー漫談。プールに行ったら石川啄木と遭遇、正岡子規やキュリー夫人まで登場するというタイムスリップ的な話。
ぴんくの漫談は、和田アキ子とX JAPANのToshiがケンカする話とか、芸能人が登場するのもありますけど、今回1本目にこのネタを持ってきたのは、認知度がほぼゼロだからでしょうね。自分のネタがファンタジー漫談だと知らなければ、事実を話してるのか、ウソの話なのかどうかが、よくわからない。芸能人が登場する話だと、本当のことと受け止めてしまうかもしれない。だから、作り話であるとすんなり理解してもらうために、歴史上の人物が登場する話にしたのです。その判断は正解でした。この1本目で街裏ぴんくという芸人を知らしめ、2本目のファイナルステージにつなぎ、優勝への流れを作ったのだと思います。
kento fukaya・・・マッチングアプリのネタ。男たちのプロフィールが奇妙なものばかりで混乱してしまう。フリップではなく、モニター使ってましたが、kentoの感覚ではフリップの変形(もしくは延長)なのでしょう。
最初は男の選択眼が厳しい女による毒舌ネタかと思いきや、登録している男の大半がおかしなやつらだった。ガラケーユーザーの僕には、iPhone 2Sのおかしさが理解できませんでした。「人人」を一発で「ひとんちゅ」と読めるのはスゴい。こういうプロフィールをひたすら考えるのが楽しくてしょうがないんでしょうね。それが伝わってきました。
陣内智則が指摘していた通り、くりちゃんの趣味がサプライズだったので、そこをオチに持ってくるべきだったと思います。あと、手にした「ト」の使い道が何かあったはずです。
寺田寛明・・・ツカミの「今日の偏見」、「インスタにしょっちゅう肉寿司の写真を載せる女は肉寿司がだぁいすき」って?思わず「そのまんまじゃねーか!」と叫んでしまいました。マイナスからのスタート。
国語辞典にネットのようなコメント欄があったら、というネタ。寺田らしい、知性を感じる考え込まれた作り。コメントによって、「言われてみればたしかにそうだな」と思わされる。聞いたことない言葉であってもちゃんと笑える構成。犬侍の、「応仁のわん」「ポメ騒動」みたいなダジャレは、いかにもネットのコメント欄にありそうなノリ。最後の「暗澹たる」の、「あんたんが重い樽を運んでいる」という解釈からの畳みかけで爆発していました。よくできていましたが、爆発、やや遅し。
サツマカワRPG・・・不審者と思わせといて、実は防犯ブザーの講習会。そういやサツマカワはカツラユーザーでしたね。今まで地毛を隠していたのが、武器として使う決意を固めたということでしょうか。カツラを取ったサツマカワ、うっすら遠藤憲一に似てますね。
お父さんの肉声バージョンに対する当たりが強すぎる。特定のユーモアに憎しみを抱いているのでしょうか。最後、子供と思いきや幽霊だったというオチ、少々安易に思いました。こういう「私のことが見えるんですか?」と話しかけられるのって、よくコントで使われてますよね。驚かす手法として便利なんでしょうけど、いろんな芸人さんが使ってるのを見てると、あまり軽々しくやらないでほしいと思っちゃいます。
大会後、でか美ちゃんとの結婚を発表したサツマカワ。末永くお幸せに。
吉住・・・彼氏の両親の家に挨拶に来た女。実は頻繁にデモ活動している危険人物だった。吉住の得意とする世界観。可愛い子ぶった振る舞いと狂気のギャップ。初め「ナオキさん」だったのが、2回目から「ナオくん」になっており、その礼儀のわきまえなさが、イタいキャラであることをさりげなく示しています。この作り込み、実にうまい。
多くの人が指摘していることですが、演技力も高く、ネタの世界に引き込まれます。さすが女優。個人的に今大会で一番よかったです。
なんでも、吉住のこのネタに対し、SNSで非難の声が上がっているそうで。いわく、「デモを揶揄するのはよくない」。あのね、これはお笑いなんですよ。冗談でコミカルに描いているのであって、本気でバカにしているわけじゃないんです。弱い立場にいる人を、さらに追い詰めかねない表現ならともかく、この程度で揶揄ってねえ。なんにでも難癖つけたがる人って、どこにでもいますね。
トンツカタン お抹茶・・・かりんとうの車のネタ・・・ってなんじゃそりゃ?かりんとうで作られた自動車が街を疾走。ミュージックビデオよろしく歌が情景を説明する。
歌ってるのは本人ではなく、録音された他人の声(ひょっとしたらボイスチェンジャーかも)で、たまに入るコーラスが本人。逆じゃない?もうわけがわからない。わからな過ぎて、「もう徹底的に好きなようにやってくれ」という気分になってしまいます。かりんとうと抹茶の相性のよさは認めざるを得ないとしても。審査員泣かせのネタ。あとなんか、ひさしぶりにかりんとうが食べたくなりました。
曲の完成度は高いので、聴いていて気持ちよくなります。しかし、「気持ちよさ」が「面白さ」を上回ってしまった感が否めません。ネタとして賞レースに持ってくるより、TikTokで流したほうがいいんじゃないでしょうか。バズりますよ、きっと。お抹茶はもう、好き勝手やらせるのが一番いい芸人のひとりと認めていいでしょう。トンツカタンではこのエキセントリックさがいっさい表れていませんが、そのほうがいいのでしょうか。トリオだとあまり目立てないので、その反動でこのようなピンネタが生まれてる、とか。それと、ここまでキャラが立ってるとは知りませんでした。なんとなくおとなしいタイプかと思っていたのに、妙にポジティブな陽キャ。このキャラだけで売れる余地アリです。
この世界観、クセになってしまうかもしれません。クセになる、つまりお抹茶にハマっちゃうということです。
どくさいスイッチ企画・・・ツチノコを発見した男の人生。よくも悪くもツチノコに振り回される一生を送る。リアルな描写を重視したんでしょうけど、10分後・3時間後・18時間後あたりは省いていいと思います。それよりもっとドラマチックなことが起こる場面を入れてたら、笑いが増えていたはずです。リアリティを多少犠牲にして、非現実的な飛躍をもうちょっと入れていたら。それでも充分面白かったですけどね。
どくさいはこれからもアマチュアのまま活動を続けるのでしょうか。だとしても、ネタ番組に呼ばれるようになってほしいです。
続きましてファイナルステージ。
吉住・・・窃盗事件の現場に駆けつけた鑑識。そこは交際相手の会社だった。彼氏の前では可愛い子ぶり、上司の前では冷静なプロの顔になる。ひとつ思ったのが、この「ツン」と「デレ」の切り替わりがもっと激しく行われてたらよかったんじゃないか、ということ。あと、浮気が発覚して態度豹変しますけど、その冷酷に詰め寄るさまが「ツン」と「デレ」より面白いので、このパートをもっと長くしてたら、と思いました。
1本目がよすぎたせいで、こちらがイマイチに見えているのかもしれません。
街裏ぴんく・・・実は自分はモーニング娘。の初期メンバーだったという告白。その舞台裏を打ち明ける。1本目で自己紹介は済んでますから、みんなファンタジーを素直に楽しめます。悦夫・越・嗚咽。漢字で入力して確認したくなりました。
トータルで感じたこと。台本の出来(面白さ)とは別に、話術の巧みさというのもあって、巧みであればあるほど「つい引き込まれる」とか「ずっと聞いてられる」ようになります。落語や講談などの話芸に共通する心地よさ。ぴんくにはその巧みさがある。加えて、熱量。とにかく懸命に、大きな声でまくし立てるその熱量に、聞き手は「本当のことを話している」と同意せざるを得ません。同意するといっても、このデタラメな話をまんま信じるということではなく、「ウソとわかりつつもノリを共有し、ファンタジーの世界にともに入り込む」ということです。それによって、ぴんくの世界を内側から眺めているような感覚になり、よりおかしくなるのです。この熱量あっての優勝だったと言えましょう。
ぴんく、本当におめでとう。R-1には夢がある。
ルシファー吉岡・・・アパートの隣人の騒音に、苦情を言いにきた男。しかしそれよりも、隣人の大学生ケンジ君の、ラブコメ(もしくはリアリティ番組)のような日常の熱心な視聴者(?)だった。このネタのネックは、登場人物が多いこと。ケンジとその友人、ミカミ、ユキコ、ヨシエ、レイナが出てきますが(本筋と関係ないけど、名前の古くささにルシファーの年齢が表れている)、ピン芸なので、当然のことながら観ている側で想像して補うしかありません。この想像、5人もいると把握が大変。誰がどんなキャラだか、それぞれの関係性はどんなだか、覚えながら話のスジを追わなきゃいけない。僕は正直、1回観ただけでは理解できませんでした。このわかりにくさが敗因ではないでしょうか。せめて3人くらいにしておけば。ケンジとユキコとレイナの三角関係だけでも成立したはずです(脳科学的に、人は3つまでのものなら同時に把握できるけど、4つ以上となると把握が困難になるのだそうです)。「じゃないんだよ」の前の間はよかったですね。
それより気になったのが、今回2本とも下ネタではなかったところ。なにか心境の変化でもあったのでしょうか。それとも、下ネタかどうかにこだわらずネタ作りをして、たまたま出来た強いネタが下じゃなかった、ということなのでしょうか。本人に訊いてみたい気もします。
今回芸歴制限の撤廃により、エントリー数が過去最高になりました。当然全体のレベルも上がっているわけです。芸歴10年以内なのは、10年目の真輝志と、9年目の吉住だけ。
苦労人に報われてほしいと望んでいる僕にとって、今大会は喜ばしい結果となりました。ぴんくは以前悪役専門の俳優事務所に入っていたそうで、自分でコワモテだと言ってますけど、僕はカワイイ顔してると思います。愛されキャラになる素質アリだと。これから起こるブレイクに期待。ネタのストックたくさんあるでしょうから、ネタ番組に定期的に呼ばれるようになってほしいです。
なんだかんだ言って、結局盛り上がるR-1。これからもドラマを起こし、スターを輩出してくれることでしょう。
不正がバレないよう頑張ってください。