多分、批判している人の殆どが、貰わなくても何の差し支えもない人間
が給付を受けている事を問題視しているのに、制度そのものを非難して
いるかのように解釈して反論している人の、何と多いことか。特に、芸人
を擁護するついで(?)に、問題視した政治家を批判している人って
ナニ?としか思えないんですが。
*************************************************************************
どうもです。
数日で出来ると思ってたものが、結局は一週間(トータルで二週間弱)
掛かってしまいました。それも1点のみ orz。
週のアタマにちょっと凹む出来事があって、そこから回復してようやく
完成させはしたものの、有言不実行すぎる自分にまた凹むという・・・。

まあそれはともかくとして、AMX‐014〈ドーベンウルフ〉です。
〈ガンダムMk-Ⅴ〉をベースに開発された機体なんですが、メタ的な
経緯も含めて出自が出自だけに、アニメ本編のみを元に書かれた資料
では〈サイコガンダムMk-Ⅱ〉を参考に開発された、となっていることが
多いようですな。
ジオン側で生まれたサイコミュ関連技術のうち、連邦側が研究・解析し
つつも再現しきれない部分をコンピュータで補助する技術を、さらに
ネオ・ジオンが援用する訳で、解析する元になる機体がサイコⅡでも
G-Ⅴでも、状況はさほど変わらないといえば変わらないかも知れません
が。
《一般(非NT)兵士によるオールレンジ攻撃》を目指した機体といえば
先日ここでも言及した〈ハンマ・ハンマ〉がある訳ですが、あちらで到達
できなかったレベルをこいつは達成したからこそ(〈ザクⅢ〉を競合で
降して?(*1))制式採用されたんでしょうな。そこに連邦系技術の介在が
あるとすれば、ハンマ・ハンマの《立ち位置》も自ずと定まってくる訳で。
今回ドーベンウルフを取り上げる以上、G‐Ⅴに言及しない訳にもいか
なくて、今回の画稿をベースに差分だけ描き変えれば、そんなに時間も
掛からないと思われ(*2)、とりあえず今週末にでもご覧いただけるよう、
最大限の努力をする所存であります(・・・ってどこの政治家?)。
////////////////////////////////////////////////////////////
*1:《ザクⅢに競り勝って主力機に選定された》という意味の解説文がつくことの多い
ドーベンなんですが、ザクⅢが量産されていたとしている資料があったり、実際
いろんな場面でザクⅢが登場していたり、ザクⅢの方が(非公式?なものも含め)
バリエーションが豊富だったり(まあ『ガンダムUC』絡みで、多少ドーベン・バリエも
増えてきてはいますが)、単純にドーベンウルフをネオ・ジオン(アクシズ)の主力機
と断定することに、少なくない躊躇いを覚えるのも、また事実で。
*2:だから先週末の時点で2点、とか目論んでいた訳ですが(…反省)。
が給付を受けている事を問題視しているのに、制度そのものを非難して
いるかのように解釈して反論している人の、何と多いことか。特に、芸人
を擁護するついで(?)に、問題視した政治家を批判している人って
ナニ?としか思えないんですが。
*************************************************************************
どうもです。
数日で出来ると思ってたものが、結局は一週間(トータルで二週間弱)
掛かってしまいました。それも1点のみ orz。
週のアタマにちょっと凹む出来事があって、そこから回復してようやく
完成させはしたものの、有言不実行すぎる自分にまた凹むという・・・。

まあそれはともかくとして、AMX‐014〈ドーベンウルフ〉です。
〈ガンダムMk-Ⅴ〉をベースに開発された機体なんですが、メタ的な
経緯も含めて出自が出自だけに、アニメ本編のみを元に書かれた資料
では〈サイコガンダムMk-Ⅱ〉を参考に開発された、となっていることが
多いようですな。
ジオン側で生まれたサイコミュ関連技術のうち、連邦側が研究・解析し
つつも再現しきれない部分をコンピュータで補助する技術を、さらに
ネオ・ジオンが援用する訳で、解析する元になる機体がサイコⅡでも
G-Ⅴでも、状況はさほど変わらないといえば変わらないかも知れません
が。
《一般(非NT)兵士によるオールレンジ攻撃》を目指した機体といえば
先日ここでも言及した〈ハンマ・ハンマ〉がある訳ですが、あちらで到達
できなかったレベルをこいつは達成したからこそ(〈ザクⅢ〉を競合で
降して?(*1))制式採用されたんでしょうな。そこに連邦系技術の介在が
あるとすれば、ハンマ・ハンマの《立ち位置》も自ずと定まってくる訳で。
今回ドーベンウルフを取り上げる以上、G‐Ⅴに言及しない訳にもいか
なくて、今回の画稿をベースに差分だけ描き変えれば、そんなに時間も
掛からないと思われ(*2)、とりあえず今週末にでもご覧いただけるよう、
最大限の努力をする所存であります(・・・ってどこの政治家?)。
////////////////////////////////////////////////////////////
*1:《ザクⅢに競り勝って主力機に選定された》という意味の解説文がつくことの多い
ドーベンなんですが、ザクⅢが量産されていたとしている資料があったり、実際
いろんな場面でザクⅢが登場していたり、ザクⅢの方が(非公式?なものも含め)
バリエーションが豊富だったり(まあ『ガンダムUC』絡みで、多少ドーベン・バリエも
増えてきてはいますが)、単純にドーベンウルフをネオ・ジオン(アクシズ)の主力機
と断定することに、少なくない躊躇いを覚えるのも、また事実で。
*2:だから先週末の時点で2点、とか目論んでいた訳ですが(…反省)。












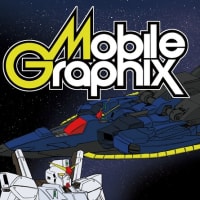







センチネルが正史に組み込まれなければ(G-Vがドーベンの準備稿として終わってれば)
「ダウンサイジングサイコMk-Ⅱ」という当初の説明の方が妥当と思えるぐらい
サイコMk-Ⅱ⇔G-Vの間でサイコ寄りなんですね。
(センチネル中でサイコミュハンドや胸部ビーム砲を「無い」としたのも大きいかな?
ま、実際使ってたら作品の雰囲気ブチコワシだったろうしw)
腰サイドのアーマーと脛部分ぐらいしか(ほぼ)同じデザインの部位がなくて、
差分だけ描いて差し替えるという手が、思ったほど効率的ではないんですよね。
結局、イチから描いているので全然作業が進まない・・・orz
コクピットの配置とか全く違っていたり胸部(腹部?)のビーム砲がなかったり、
機体構造的にも共通部分が少なくて、《魔改造》レベルではちょっと作れそうに
ないですね、コレ。
(準サイコミュシステムなどを解析して取り込みつつも)一から設計し直した機体
とするには、中途半端に(笑)似過ぎてはいるんですけど。
サイコミュハンドとメガランチャー機能を持たせて遠距離攻撃に重点を置いたドーベンウルフに対して
G-Vはむしろ斬り込み上等な高機動MSですよねぇ。
「常人なら失神する程の加速度」で機動するし、シールドと言いながらブースター、だしw
その差からG-V→ドーベンウルフの機体特性の変更をそう考えると
過剰な機動能力の代わりに遠距離火力、斬り込んでくる敵に対しては
サイコミュハンドによるオールレンジ攻撃能力で…といったところでしょうか?
ところで、インコムについてひとつ
あれ「敵の意表を突く牽制」みたいにしか使われてませんが
現代でのスマートミサイルが着弾までの映像を送ってくる事を考えると
「山越えカメラ機能」も合わせ持ってる、と考えるのはどんなもんでしょう?
で障害物が少ない空域では敵とは垂直の方向に打ち出して
「ものすごーく幅の広い測距儀」として機能させる、とかw
(Sガンダムみたいに一個の場合でも本体⇔インコムの視野差で)
アクシズと連邦の戦闘経験や用兵思想の違いでしょうか。
GVは極端な高機動をアクシズで使いこなせる人材が居ないのかも。
→ 烈風羅可庵さま
>インコムについてひとつ
>「山越えカメラ機能」も合わせ持ってる、と考えるのはどんなもんでしょう?
エルメスのビットにはモノアイが付いてましたし、攻撃端末周辺の状況を
パイロットが知る必要があったのは間違いないですから、ファンネルやインコム
にも(パッと見でそういうデザインにはなってないですけど)カメラやセンサー
の機能は付いていたでしょうね。
攻撃(の際の周辺状況確認)に使うだけでなく、距離をとっての索敵や偵察に
使うというのはこちらでも考えていたんですが、
>敵とは垂直の方向に打ち出して
>「ものすごーく幅の広い測距儀」として機能させる
コレいいですね(笑)。有線端末を展開する以上、相手との距離も重要な情報
ですし。
測距儀として撃ち出す場合はまっすぐ一直線にでしょうし、回収する時間も
短くて済むのかも。
→にゃるるさま
>GVとドーベンウルフってムーバブルフレームだけ共通で
う~む、先のコメントでも書きましたが、胸~腹周りの構造が全く違いますし、
腕もサイコミュハンドがあるので、フレームレベルで共通とは言い難いと思うん
ですよね。
仮に共通部分があるとしても、せいぜい腰から下、脚部だけになってしまうん
ではないかと。
>アクシズと連邦の戦闘経験や用兵思想の違い
一般人用の準サイコミュシステムを積んでいるとはいえ、サイコガンダムの
流れで単機での運用を想定されたG‐Vと、一般人用だからこそ量産して集団で
運用しようとしたドーベンウルフという違いはあるかも知れないですね。
って考えると「腰の部分にあるドラム状パーツ」が挙げられるんじゃ無いでしょうか
で、GVのビームカノンがサーベルモードと切り替える時の軸だから丸い、じゃなく
「内部に反応炉を収めて、同時に外郭はムーバブルフレームとして動作の要」
って仮説はどうでしょう?
(ドーベンの腹部メガ粒子砲もここに直結、と見えますし)
で、膝というか脹ら脛のスラスター基部も同様のモノだと考えると
ζの倍以上・5000kw台という出力の説明にもなるかな?と。
>腰の部分にあるドラム状のパーツ
ドーベンの(上半分が胸部に埋まり込んで?半円状の)ドラムパーツは、腹部
ビーム砲との兼ね合いからジェネレータ説もアリだと思うんですけど、G‐Vの
方はここから直接ハッチが開いているようにも見えるので、コクピットブロック
がドラム容積の大半を占めていると解釈してました。
横に幅広くなっている点から左右に(やや小型の?)ジェネレータが・・・という
可能性もないではないとも思いますが。
(過剰な機動能力の代わりの)遠距離火力を付加するための電源として、ドラム内
にジェネレータを増強(換装?)。メガ粒子砲の設置もあって容積圧迫を受けた
コクピットは胸部に移された、という感じでしょうか。
似た形状のパーツの、外郭部分はムーバブルフレームの一部として機体駆動を
担うが、用途(=郭内に収められる機械部品の機能)が違う、というのは可能
なんでしょうかね。
・・・と、ここまで考えてスペックデータを確認してみたら、G‐V:5,320KW、
ドーベンウルフ:5,250KW で、むしろ出力は下がってるんですね。MISSION ZZ版
のスペックだと4,340KW で丁度良かった(?)のに・・・orz
逆に、脹脛へのジェネレータ設置がジオン系の発想にない機構だとすれば、
ドーベンウルフにも(基本的な外観形状も含めて)そのまま継承されたと考える
と、丁度いい理屈付けにできるかも知れないですね。
古い車雑誌(それこそスーパーカーブームの頃w)のF1記事で
「アルファロメオのエンジンがパワーは有るんだけど重い、
その原因がストレスメンバーとして応力がかけられないエンジンボディ
(別個にフレームが要る)」だったなぁ…と思い出した所から数分で組み上がった
「フレームとして応力を受けられるジェネレータ」という妄想なんで穴は多いと思いますw
ただ、ガンダムMk-Ⅱが「脹ら脛に反応炉」だし、ありかな?とも。
あと、クィンマンサの足まわりも似た構成と言えませんかな?
■フレーム内ジェネレータ
ドーベンウルフの説明としてはアリアリだと思うんですよ。ただG‐Vだと
厳しいんじゃないかと。
結局、基本そのまま《魔改造》とするには構造が違い過ぎ、準サイコミュほか
基本システムを取り込みつつ新規設計とするにはあまりにも似過ぎているという
中途半端さが全ての原因なんですよね。
総カントクにダメ出しされたからとはいえ、デザイン変更するのにどうして
あそこまで手を加えたんでしょうかね、当時のデザイナー氏は?
■脹脛にジェネレータ
>クィンマンサの足回りも似た構成だと
それはありますね。ネオ・ジオン(アクシズ)後期MSの脛周りの類似性について
は、確かカトキ氏も『ガンダムA』誌内のコラムで言及していて、クシャトリア
のデザインに反映させたと言っていたと思います。
脛にジェネレータが組まれているか否かを明言していたかはちょっと今すぐ
確認できないですが、明言しているのであればそれこそしめたもの(笑)ですし、
明言していないのであれば「そういうことにしておく」のもアリではないかと。