書籍名; 「経営進化論」[1990]
著者;北原貞輔
発行所;有斐閣 1990.1.30発行
このシリーズはメタエンジニアリングで「文化の文明化」を考える際に参考にした著作の紹介です。『 』内は引用部分です。
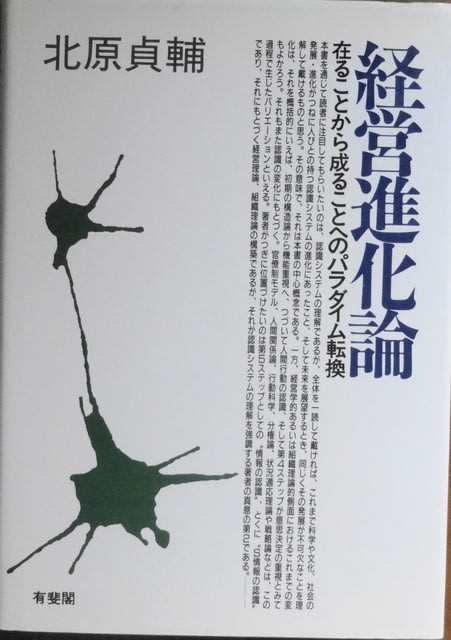
読み始める前に;
表紙には、副題の「在ることから成ることへのパラダイム転換」とともに、7行もの但し書きがある。その言葉からは、あまりにも強い「システム論」指向が感じられた。しかし、最後にはガイア論が持ち出されたので、文明論的にも納得することができた。
曰く『本書を通じて読者に注目してもらいたいのは、認識システムの理解であるが、全体を通読して戴ければ、これまで科学や文化、社会の発展・進化がつねに人々の持つ認識システムの進化にあったこと、そして未来を展望するとき、同じくその発展が不可欠なことを理解して戴けるものと思う。その意味で、それは本書の中心概念である。』
さらに続けて、『一方、経営学的あるいは組織理論的側面におけるこれまでの変化は、それを概括的にいえば、初期の構造論から機能重視へ、つづいて人間行動の認識、そして第4ステップが意思決定の重視とみてもよかろう。それもまた認識の変化にもとづく。 官僚制モデル、人間関係論、行動科学、分権論、状況適応理論や戦略論などは、この過程で生じたバリエーションといえる。 』
経営戦略を決めるのは、CEOたるリーダーであり、システムが働くのは、その後の実践段階であろう。科学や文化史を見れば、パラダイムシフトは特定の個人(天才)により始まった事例のほうが多いように思う。システム論は、経営に最も大切な「アジリティー」を失う可能性が高い。認識がすべてを決定づけてゆくという考え方には、数学者独特の哲学的な匂いを感じた。
序文;
「序文」には、全16章の概要が述べられている、古代ギリシャ哲学から現代にいたる認識論の展開なのだが、認識論の説明と、それに基づく経営進化論が交互に記されている。ここでは、著者特有の純システム論については割愛する。
『本書の目的は,経営進化の研究にある。それは科学や文化の進化と不可分の 関係にあり,人びとの持つ認識の変化,つまり世界観の変化と切り離して論じることはできない。』が、すべてを表している。
『第3章では,現代経営に多大の影響を与えてきた還元主義的機械論に基礎をおくテーラーの効率主義哲学と,それにもとづく科学的管理法,その分岐論としての経営科学の諸タイプ,情報理論,制御理論の意義について述べ,すでに今世紀の初頭,先進科学者たちの間で起こっていた還元主義思想からの科学思想の転換について説明する。』つまり、その時代、時代に生まれた様々な新たな論理の認識のもとに、経営が行われてきたというわけであろう。
『第5章は,還元主義的機械論科学を導入した科学的経営についての説明であるが,現実経営は,その発展過程で多くの困難に遭遇する。このため,それらを克服する目的で現れてきたドラッカーの分権論,メィョーに端を発する人 間関係論からハ-ズバーグの行動科学などについて一考する。』
つまり、経営の進化は「科学や文化の進化と不可分の 関係にあり,」というわけである。
『第8章は経営・経済・社会の変化とそれにともなって生まれた状況適応理論の説明に当てられ,それを前提に第9章でシステミック経営について説明する。』
『第10章では,ダーウイン以降の進化論について述べる。(中略)とくに共生を無視して経営進化について論じれば,それは ダーウインへの逆行に結びつき,弱肉強食の闘争の論理に転落する恐れを秘めていることが理解されるものと思う。』
この辺りから、近代から続く現代の進化の方向性への疑問が始まっている。
『第12章では,サイバネティクス概念の発展について述べ,先端科学者たちへの「制御重視から発展を含む逸脱増幅過程の認識」への変化を説明する。(中略)管理という用語の持つ意味が,制御・順応的適応・ 創造的適応に分けられること,そして後の二者がゆらぎを持つ管理として重要な意味を持つことが理解できるであろう。』
管理の本質は制御なのだが、そこから逸脱する順応型と創造型により発生するゆらぎの認識が重要さを増してきたという事であろう。つまり、通常のシステム論では説明できない複雑性の問題になる。
『第13章は,メタ・インフォーメーションの説明であるが,ここで初めて情報概念の全体像が明らかになる。そのとき組織が意味的メタ情報関連で定義され、動態的かつインビジブルなことが真に理解されるであろう。それらを基礎に、社会や文化の進化から倫理の進化について論究するが、国際的視野に立った経営を考えるとき,この概念の理解は不可欠となる。そして,つねに量の上位に質のあることが理解されるであろう。』
情報概念の全体像として、インフォーメーションの質の階層としての上位であるメタ/4インフォーメーションの説明を試みている。
『最終16章のグローバル・ネオマネージメントは、,経営進化の最終ステップである。それは端的にいってこれまで人間が最下等と見てきた微生物に感謝する経営である。(中略)生理機能を破壊してまでも求める豊かさとは何を意味するのであろうか。人類が、なお未来に希望を持つとすれば、グローバル・ネオマネジメンの概念を無視することはできまい。』(pp.ⅰ~ⅴ)
冒頭の言葉にあるとおりに、経営の進化は科学や文化の進化と不可分であり,論理的な手法でその時代を正しく認識をしていれば、自動的にスパイラルアップしてゆくとしている。その中で、近代に始まる人間圏による唯物論がゆきすぎて、微生物をも含む自然圏でのグローバル・ネオマネジメンの概念が必須となってきたというわけであろう。
各論;
第1章 ギリシャ科学から17世紀の科学革命へ
プラトンの「自然の世界を数学的に表現可能」という概念と、アリストテレスのか『海洋生物の研究に従事し、その中で植物や動物、さらに人間に対しては数学的形式は適用できないと結論し、機能や過程を重視する立場をとった。』(pp.8)の対比を行っている。
第2章 還元主義的機械論科学の降盛
ガリレオやニュートンの思想に基礎を置く20世紀の還元主義的機械論万能の産業界は、その哲学が崩壊の方向に向かっていると断言をしている。
『偶然や不可逆性,複雑性の背後に,絶対的かつ不変の数学的真理があるのではなく,偶然を含んで変化してゆく複雑性こそが,自然の真の姿なのである。れわれは、機械はあくまでも機械論者がいう“無知な人間が作った人工物ということを忘れてはならない。 自然科学の世界では,
すでに19世紀,ガリレオ的唯物論科学から大きく転じ始めていたのである 。』(pp.62)
第10章 進化の科学
『ミクロ世界とマクロ世界の関連のなかで生物が生を保持していることを意味するものであるが,このことは,生物が相互に他の生物の環境の一部を構成していて,さまざまな方法で相互に作用し合って生を保っているという事実を示すのである。』(pp.205)
これは、明らかに自然圏から分離独立した人間圏が、再び自然圏の一部に帰ることを意味している。経営と生物圏の相似性を示しているのであろう。
第13章 メタ・インフォーメーション
『科学や文化・社会の進化、あるいは国際的視野に立ったマネジメント,人類の生存といったよりグローバルな問題に目を向けようとすれば、われわれは,メタ情報の持つ意義について考えておかなければならない。』8pp.263)
で始まるこの章は、思考過程におけるシステム的な階層を説明している。
① 0-システムの特質はすべて情報で表される。
② 分子進化を決定づけるのは構造情報である。
③ 構造情報はシステムの発展に応じて発展する。
④ システムを構成する相互関連的要素間には情報の流れがある。』
ここで、0-システムの説明は、第10章に次のようにある。
『ハンガリーの行動遺伝学者ツアニイの解説を用い,以下,その概要について説明する。彼によれば、水素,窒素、 酸素,燐,硫黄などを含む単純な混合物をI つのシステムとしたとき,それが紫外線の照射あるいは放電にさらされると,そのシステムはエネルギーを吸収し,そのなかで物質循環(material cycle) を引き起こし,ますます複雑な混合物になって,そのなかにアミノ酸・糖・有機塩基などのより高い生物的意味を持った混合物が現れるという。彼は,そのようなシステムを0-システム(zero-system)と名づけた。』(pp.200)
メタ情報については、次のように説明をしている。
『生物の進化は、メタレベルがメタ・メタレベルと自発的に構造化されていくことで成り立つわけであるが 、それは相互関連の変化を通じた階層構造の形成を意味する。相互関連のあると ころには何らかの情報の流れがある。自動接触・反応連鎖・自己言及などの諸現象は,これを無視して説明することはできない。そこに相互関連⇒情報通信⇒上述の現象⇒新たな相互関連の相互因果ループが成り立ち,それを通じて生じる継続的なメタレベルの形成、そしてメタ情報のメタ・メタ情報への継続的な発展が見られる。』(pp.264)
さらに続けて、メタ情報の認識として、『メタ情報とは,相互関連を意義づける一段上位の情報のことであり,通信に ついていえば,メタコミュニケーション情報のことをいう。その意味では進化や発展,そして創発や階層性を意義づける情報のことであるといってもよく, ひとり人間だけでなく,生物・非生物間にも成り立つ上位情報のことと理解しなければならない。』(pp.271)
最近のことで言えば、DNAに含まれる様々な遺伝子情報もメタレベルの情報なのだろう。
第14章 進化的経営
ここでは、モデルが登場する。
『A・Wスミスは、経営進化の5段階モデルを提示した。その第1段階から第4段階まで象徴的経営,静態的経営、科学的経営、システミック経営で、われわれもそれを大枠として受け入れ、すでに第2,5,9章で説明した。彼の第5段階は、自己実現に目的をおく戦略的経営で,それを彼は未来に対する期待であるという。
ここに自己実現とは、たしかに利己・没我、両者調和の上に成り立つ概念と解釈されているが,それはまた自己の欲するようにありたいりとう意味の個中心の概念でありる。』(pp.301)
第16章 グローバル・マネージメント
全社的品質経営に関して、TQC ⇒TQM ⇒IMQという進化の過程を説明した後で、
『われわれは、すでに第14章で進化的経営について説明したが,そのなかでIMQにふれた。それは仕事の質の重視にもとづく国際性を含めた社会統合的品質経営のことを意味する。けれ,ども,それだけでは自然環境問題は消極的に含まれているだけである。グローバルの意味することは,地球ないしは宇宙次元までも考慮に含めた経営のことをいう。つまり進化的経営それ自体がガイアなかの1つの活動という認識である。』(pp.145)
ガイア論は一時期(この著書が発表された時期に一致)世界的に流行をしたが、あまりに誇大なために、一般化には進まなかった。しかし、人類社会の問題をガイアまで広げたことは、21世紀に相応しい。
『川や海の汚染,人口増にもとづく食糧問題、子供の非行や自殺,工業発展の副産物としての酸性雨郊外などが頻発しているのも否定できない事実である。カプラによれば,それらはすべて還元的科学的経営からの置土産である。われわれは,科学的経営から脱し、システミック経営 ⇒ 進化的経営から,さらにグローバル・ネオマネージメントへ進まねばならない。』(pp.145)
最終章の結論としては、次の一節がある。
『自然という全体,つまりガイアは,そのなかに素粒子,原子,分子,有機体,経営,生態系,国家などといったあらゆる自然的諸実在を含んで成り立っている。このとき,それらの各レベルが生存と満足を満たしていれば,そのような状態こそが,各レペルにとって最高の価値状態を維持していることといわれる。このため状態価値はひとり人間だけを対象に成り立つのではない。』(pp.347)
ここにおいて、副題の「在ることから成ることへのパラダイム転換」が蘇る。さらに、アリストテレスの自然学から倫理学までの進化の過程も復活してくるという状態になったように思う。冒頭にアリストテレスの話が詳しく述べられたのも、このための伏線だったのであろう。
著者;北原貞輔
発行所;有斐閣 1990.1.30発行
このシリーズはメタエンジニアリングで「文化の文明化」を考える際に参考にした著作の紹介です。『 』内は引用部分です。
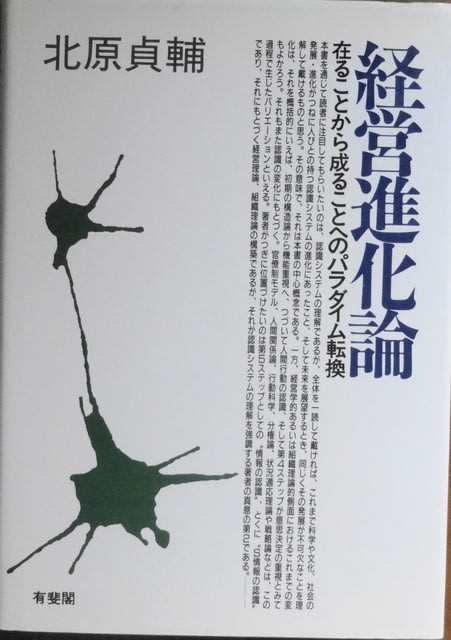
読み始める前に;
表紙には、副題の「在ることから成ることへのパラダイム転換」とともに、7行もの但し書きがある。その言葉からは、あまりにも強い「システム論」指向が感じられた。しかし、最後にはガイア論が持ち出されたので、文明論的にも納得することができた。
曰く『本書を通じて読者に注目してもらいたいのは、認識システムの理解であるが、全体を通読して戴ければ、これまで科学や文化、社会の発展・進化がつねに人々の持つ認識システムの進化にあったこと、そして未来を展望するとき、同じくその発展が不可欠なことを理解して戴けるものと思う。その意味で、それは本書の中心概念である。』
さらに続けて、『一方、経営学的あるいは組織理論的側面におけるこれまでの変化は、それを概括的にいえば、初期の構造論から機能重視へ、つづいて人間行動の認識、そして第4ステップが意思決定の重視とみてもよかろう。それもまた認識の変化にもとづく。 官僚制モデル、人間関係論、行動科学、分権論、状況適応理論や戦略論などは、この過程で生じたバリエーションといえる。 』
経営戦略を決めるのは、CEOたるリーダーであり、システムが働くのは、その後の実践段階であろう。科学や文化史を見れば、パラダイムシフトは特定の個人(天才)により始まった事例のほうが多いように思う。システム論は、経営に最も大切な「アジリティー」を失う可能性が高い。認識がすべてを決定づけてゆくという考え方には、数学者独特の哲学的な匂いを感じた。
序文;
「序文」には、全16章の概要が述べられている、古代ギリシャ哲学から現代にいたる認識論の展開なのだが、認識論の説明と、それに基づく経営進化論が交互に記されている。ここでは、著者特有の純システム論については割愛する。
『本書の目的は,経営進化の研究にある。それは科学や文化の進化と不可分の 関係にあり,人びとの持つ認識の変化,つまり世界観の変化と切り離して論じることはできない。』が、すべてを表している。
『第3章では,現代経営に多大の影響を与えてきた還元主義的機械論に基礎をおくテーラーの効率主義哲学と,それにもとづく科学的管理法,その分岐論としての経営科学の諸タイプ,情報理論,制御理論の意義について述べ,すでに今世紀の初頭,先進科学者たちの間で起こっていた還元主義思想からの科学思想の転換について説明する。』つまり、その時代、時代に生まれた様々な新たな論理の認識のもとに、経営が行われてきたというわけであろう。
『第5章は,還元主義的機械論科学を導入した科学的経営についての説明であるが,現実経営は,その発展過程で多くの困難に遭遇する。このため,それらを克服する目的で現れてきたドラッカーの分権論,メィョーに端を発する人 間関係論からハ-ズバーグの行動科学などについて一考する。』
つまり、経営の進化は「科学や文化の進化と不可分の 関係にあり,」というわけである。
『第8章は経営・経済・社会の変化とそれにともなって生まれた状況適応理論の説明に当てられ,それを前提に第9章でシステミック経営について説明する。』
『第10章では,ダーウイン以降の進化論について述べる。(中略)とくに共生を無視して経営進化について論じれば,それは ダーウインへの逆行に結びつき,弱肉強食の闘争の論理に転落する恐れを秘めていることが理解されるものと思う。』
この辺りから、近代から続く現代の進化の方向性への疑問が始まっている。
『第12章では,サイバネティクス概念の発展について述べ,先端科学者たちへの「制御重視から発展を含む逸脱増幅過程の認識」への変化を説明する。(中略)管理という用語の持つ意味が,制御・順応的適応・ 創造的適応に分けられること,そして後の二者がゆらぎを持つ管理として重要な意味を持つことが理解できるであろう。』
管理の本質は制御なのだが、そこから逸脱する順応型と創造型により発生するゆらぎの認識が重要さを増してきたという事であろう。つまり、通常のシステム論では説明できない複雑性の問題になる。
『第13章は,メタ・インフォーメーションの説明であるが,ここで初めて情報概念の全体像が明らかになる。そのとき組織が意味的メタ情報関連で定義され、動態的かつインビジブルなことが真に理解されるであろう。それらを基礎に、社会や文化の進化から倫理の進化について論究するが、国際的視野に立った経営を考えるとき,この概念の理解は不可欠となる。そして,つねに量の上位に質のあることが理解されるであろう。』
情報概念の全体像として、インフォーメーションの質の階層としての上位であるメタ/4インフォーメーションの説明を試みている。
『最終16章のグローバル・ネオマネージメントは、,経営進化の最終ステップである。それは端的にいってこれまで人間が最下等と見てきた微生物に感謝する経営である。(中略)生理機能を破壊してまでも求める豊かさとは何を意味するのであろうか。人類が、なお未来に希望を持つとすれば、グローバル・ネオマネジメンの概念を無視することはできまい。』(pp.ⅰ~ⅴ)
冒頭の言葉にあるとおりに、経営の進化は科学や文化の進化と不可分であり,論理的な手法でその時代を正しく認識をしていれば、自動的にスパイラルアップしてゆくとしている。その中で、近代に始まる人間圏による唯物論がゆきすぎて、微生物をも含む自然圏でのグローバル・ネオマネジメンの概念が必須となってきたというわけであろう。
各論;
第1章 ギリシャ科学から17世紀の科学革命へ
プラトンの「自然の世界を数学的に表現可能」という概念と、アリストテレスのか『海洋生物の研究に従事し、その中で植物や動物、さらに人間に対しては数学的形式は適用できないと結論し、機能や過程を重視する立場をとった。』(pp.8)の対比を行っている。
第2章 還元主義的機械論科学の降盛
ガリレオやニュートンの思想に基礎を置く20世紀の還元主義的機械論万能の産業界は、その哲学が崩壊の方向に向かっていると断言をしている。
『偶然や不可逆性,複雑性の背後に,絶対的かつ不変の数学的真理があるのではなく,偶然を含んで変化してゆく複雑性こそが,自然の真の姿なのである。れわれは、機械はあくまでも機械論者がいう“無知な人間が作った人工物ということを忘れてはならない。 自然科学の世界では,
すでに19世紀,ガリレオ的唯物論科学から大きく転じ始めていたのである 。』(pp.62)
第10章 進化の科学
『ミクロ世界とマクロ世界の関連のなかで生物が生を保持していることを意味するものであるが,このことは,生物が相互に他の生物の環境の一部を構成していて,さまざまな方法で相互に作用し合って生を保っているという事実を示すのである。』(pp.205)
これは、明らかに自然圏から分離独立した人間圏が、再び自然圏の一部に帰ることを意味している。経営と生物圏の相似性を示しているのであろう。
第13章 メタ・インフォーメーション
『科学や文化・社会の進化、あるいは国際的視野に立ったマネジメント,人類の生存といったよりグローバルな問題に目を向けようとすれば、われわれは,メタ情報の持つ意義について考えておかなければならない。』8pp.263)
で始まるこの章は、思考過程におけるシステム的な階層を説明している。
① 0-システムの特質はすべて情報で表される。
② 分子進化を決定づけるのは構造情報である。
③ 構造情報はシステムの発展に応じて発展する。
④ システムを構成する相互関連的要素間には情報の流れがある。』
ここで、0-システムの説明は、第10章に次のようにある。
『ハンガリーの行動遺伝学者ツアニイの解説を用い,以下,その概要について説明する。彼によれば、水素,窒素、 酸素,燐,硫黄などを含む単純な混合物をI つのシステムとしたとき,それが紫外線の照射あるいは放電にさらされると,そのシステムはエネルギーを吸収し,そのなかで物質循環(material cycle) を引き起こし,ますます複雑な混合物になって,そのなかにアミノ酸・糖・有機塩基などのより高い生物的意味を持った混合物が現れるという。彼は,そのようなシステムを0-システム(zero-system)と名づけた。』(pp.200)
メタ情報については、次のように説明をしている。
『生物の進化は、メタレベルがメタ・メタレベルと自発的に構造化されていくことで成り立つわけであるが 、それは相互関連の変化を通じた階層構造の形成を意味する。相互関連のあると ころには何らかの情報の流れがある。自動接触・反応連鎖・自己言及などの諸現象は,これを無視して説明することはできない。そこに相互関連⇒情報通信⇒上述の現象⇒新たな相互関連の相互因果ループが成り立ち,それを通じて生じる継続的なメタレベルの形成、そしてメタ情報のメタ・メタ情報への継続的な発展が見られる。』(pp.264)
さらに続けて、メタ情報の認識として、『メタ情報とは,相互関連を意義づける一段上位の情報のことであり,通信に ついていえば,メタコミュニケーション情報のことをいう。その意味では進化や発展,そして創発や階層性を意義づける情報のことであるといってもよく, ひとり人間だけでなく,生物・非生物間にも成り立つ上位情報のことと理解しなければならない。』(pp.271)
最近のことで言えば、DNAに含まれる様々な遺伝子情報もメタレベルの情報なのだろう。
第14章 進化的経営
ここでは、モデルが登場する。
『A・Wスミスは、経営進化の5段階モデルを提示した。その第1段階から第4段階まで象徴的経営,静態的経営、科学的経営、システミック経営で、われわれもそれを大枠として受け入れ、すでに第2,5,9章で説明した。彼の第5段階は、自己実現に目的をおく戦略的経営で,それを彼は未来に対する期待であるという。
ここに自己実現とは、たしかに利己・没我、両者調和の上に成り立つ概念と解釈されているが,それはまた自己の欲するようにありたいりとう意味の個中心の概念でありる。』(pp.301)
第16章 グローバル・マネージメント
全社的品質経営に関して、TQC ⇒TQM ⇒IMQという進化の過程を説明した後で、
『われわれは、すでに第14章で進化的経営について説明したが,そのなかでIMQにふれた。それは仕事の質の重視にもとづく国際性を含めた社会統合的品質経営のことを意味する。けれ,ども,それだけでは自然環境問題は消極的に含まれているだけである。グローバルの意味することは,地球ないしは宇宙次元までも考慮に含めた経営のことをいう。つまり進化的経営それ自体がガイアなかの1つの活動という認識である。』(pp.145)
ガイア論は一時期(この著書が発表された時期に一致)世界的に流行をしたが、あまりに誇大なために、一般化には進まなかった。しかし、人類社会の問題をガイアまで広げたことは、21世紀に相応しい。
『川や海の汚染,人口増にもとづく食糧問題、子供の非行や自殺,工業発展の副産物としての酸性雨郊外などが頻発しているのも否定できない事実である。カプラによれば,それらはすべて還元的科学的経営からの置土産である。われわれは,科学的経営から脱し、システミック経営 ⇒ 進化的経営から,さらにグローバル・ネオマネージメントへ進まねばならない。』(pp.145)
最終章の結論としては、次の一節がある。
『自然という全体,つまりガイアは,そのなかに素粒子,原子,分子,有機体,経営,生態系,国家などといったあらゆる自然的諸実在を含んで成り立っている。このとき,それらの各レベルが生存と満足を満たしていれば,そのような状態こそが,各レペルにとって最高の価値状態を維持していることといわれる。このため状態価値はひとり人間だけを対象に成り立つのではない。』(pp.347)
ここにおいて、副題の「在ることから成ることへのパラダイム転換」が蘇る。さらに、アリストテレスの自然学から倫理学までの進化の過程も復活してくるという状態になったように思う。冒頭にアリストテレスの話が詳しく述べられたのも、このための伏線だったのであろう。









