歴史推理小説 レッド赤川の余呉川 川湊幻想
※この記事は歴史推理小説です宜しく御理解下さいませ。楽しく読んで下さい。
登場人物紹介
※レッド赤川
旧滋賀県伊香郡「現滋賀県長浜市」出身。賎ケ岳城郭遺跡群を今から約40年前より
その遺構を詳細調査し現地城郭遺跡調査派の民間歴史研究家。民俗学から地名学。
歴史地理と幅広い広角な知識と視野に裏打ちされた史観から次々に滋賀県内の城郭
遺跡を発見解明していく劇画で言えばゴルゴ13や名整形外科ブラック、ジャツクの
様な、一種異様な世界観を持つ伝説の歴史名探偵その洞察力は常人の次元を超える。
※黒田タタラ
常に常識や既存の歴史知識を基調に持つ常識派、レッド赤川に常に反発するも歴史
の現場や現状をレッド赤川に見せられ歴史の現場の深淵に衝撃を受ける向学心の人。
※桐糸餅弘
元歴史とロマンの町と言われた町の住人この短編架空小説では軽妙なボケをかます。
※息長太郎(おきながいらっこ)
レッド赤川の兄弟とも従弟ともされる謎の古代史城郭研究家
レッド赤川
伊香胡と言う地名に限りなく大陸の胡人や遊牧民族や大陸の風を感じさせますね?
桐糸餅弘
滋賀県高島市では遊牧民しか使用しないオルドス型刀剣の鋳型石が出土しています。
黒田タタラ
高島郡と騎馬は何か関係があるのでしょうか?高島や浅井の鉄穴は広く知られてる。
レッド赤川
高島には牧野地名や饗場地名や万木に関係する地名や延喜式に掲載の鞆結駅がある。
越前朝倉義景館の堀からは「御者たやとの」騎馬飼育の田屋氏の記載がありますね。
桐糸餅弘
万木は「万騎」なのでしょうか?万木と書いて「ゆるぎ」と高島では読みますよね?
かって木ノ本では牛馬市が開かれ高島郡からは牛馬が木ノ本に来たとも言われてます!
黒田タタラ
赤川烈道先生?いやレッド赤川先生、旧滋賀県伊香郡の勇出山「ゆるぎ山」に行き
ましよう!唐川の赤後寺の観音様のルーツはどこにあるのでしょうか?また延喜式
の伊香郡にはアカの表音の神社が掲載されていますよ!これは一体何を意味する?

桐糸餅弘
うんうん、まるで赤出し味噌汁状態ですね?そうそう赤だしの連続と言う感じですわ。
レッド赤川
唐川赤後寺の観音様?のルーツはやはり中国唐代の観世音菩薩像がその見本やルーツ
となっているのではないでしょうかな?

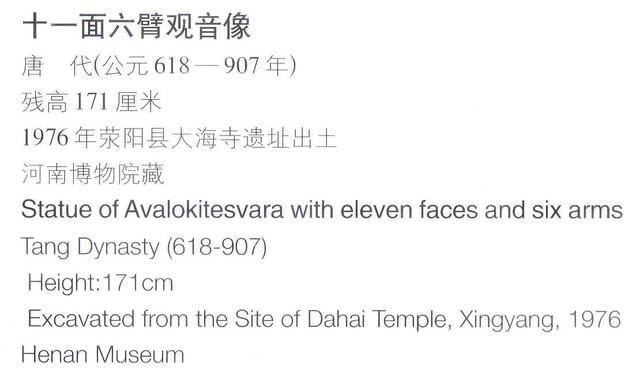
レッド赤川
懐かしい余呉川だ!余呉川には川湊があったと私は推測しています。何故ならば小谷
城下にも船場の辻なる川湊地名が残ってる。余呉川にも川湊があったと私は推理する。

黒田タタラ
無茶な発想です。余呉湖には湖上を行く舟が近世まで存在しましたが余呉川には無い。
しかし琵琶湖の尾上に存在した旧余呉河川を利用した旧尾上漁港は小船舶が繋留された。
桐糸餅弘
賎ケ岳トンネルの入口の国道8号線は太古の湖の底の様な地面の窪みがありますね?
それに木ノ本周辺の人に聞くと太古に余呉湖とは異なる伊香湖と呼ばれる湖が存在
した証拠に水田の底には芦「アシ」などの地下茎が見つかると聞きます。また太古
の余呉川は勇出山の東麓を廻って流れていて西山と勇出山が開削されて太古の余呉
川は水のない空からの川、つまりは唐川と言う集落名になったと聞き及んでいます。
レッド赤川
勇出山の北麓の伊香平野には古代条理の水田の跡が残っていました。だからその話
は神代の神話の世界または古墳時代の伊香氏の伝説の世界かと思います。もっとも
勇出山の東側に田部の集落があり大和朝廷の墾田制前の時代の田部を連想させます?
余呉川沿いの余呉町東野国安の堺には『東野家文書』?に周囲800mの湖沼が存在し
小字奈良寺からは水成固生鉄の「たかし小僧」が出土してます。つまり芦や水茎を
持つ植物に金属が付着して煙管「キセル」の様になった状態の赤さびた遺物を言う。
黒田タタラ
とにかく唐川や東高田や磯野集落の北の赤川沿いを歩いてみましょうよ!
↓ 勇出山が正しい表記です!

レッド赤川
これは凄い!赤後寺。赤分寺。余呉川に赤川。赤尾。赤の語彙の連鎖反応ではないのか?
ここだ!東高田に余呉川の川湊「かわみなと」が存在したに違いない!必ず水の神を祀る
祠や水に関わる伝説や「余呉川の川湊の意味する地名」があるはと私は推理しています。

田黒タタラ
またまたレッド赤川先生は飛躍しすぎた発想や妄想をされますね!?
レッド赤川
妄想ではなく推理だ!飛躍なんか私はしていない!赤後寺。赤分寺。赤川。等の地名は閼伽は
サンスクリット語アルギャの音写で阿伽「アカ」遏伽、あつかとも書く。観音信仰の聖水の
「阿伽/アカ」と係る言葉でしょう。
閼伽アカを汲む専用の井戸 閼伽井あかい
閼伽アカを入れる桶 閼伽桶あかおけ
閼伽桶を置く棚 閼伽棚あかだな
閼伽アカを入れる器 閼伽器あかき
閼伽水を桶から器に移す坏 閼伽坏あかづき
閼伽水に浮かべて供える樒しきみ 閼伽の花あかのはなと言う。
桐糸餅弘
余呉川と赤川の合流点の東高田の地名に船に関する地名がないのか?赤川先生と探しましよう!
黒田タタラ
そんなの空想にしか過ぎませんよ!レッド赤川先生の発想は異端です!
レッド赤川
さてどうかな?東高田の地名を調べると!あるんだなあ~コレが!
穴津と呼ばれる強烈な港湾地名の小字か゛記載されています。穴津
是は本当に意味が深い強烈な言葉で地名なのです!

桐糸餅弘
赤川先生!穴津とは凄い地名ですなあ!足が震えて来ました。僕はゾクゾクしてきましたよ!
黒田タタラ
何が凄いんですか?近江伊香郡黒田村には穴師地名の集落がありますし小字の踏鞴タタラも
あります、また布施姓もありますし、別に私は驚きはしませんが?
レッド赤川
伊香郡東高田の小字「穴津」も伊香郡黒田郷の小字踏鞴「タタラ」もスゴイ地名ですよ!
ちなみに『和名抄』に「坂田郡阿那郷」の項に「近江国吾名邑」あなの村と記されてます。
また『日本書記』の垂仁紀には
「天日槍自菟道河泝之 北入近江國吾名邑而暫住 復更自近江 經若狹國 西到但馬國則定住處也
是以近江國鏡村谷陶人 則天日槍之從人也 故天日槍娶但馬出嶋人 太耳女麻多烏 生但馬諸助也
諸助生但馬日楢杵 日楢杵生清彦 清彦生田道間守也」とある。
とくにアメノヒボコが★「北入近江國吾名邑而暫住」とある事に注目!だから北近江の伊香郡の
東高田の小字「穴津」地名は驚くべき地名とひとつと言えます!『和名抄』の「坂田郡阿那郷」
の項には「近江国吾名邑」の記述はとても重要かと思います。これは「あなむら」と読むんです。
黒田タタラ
赤川先生!滋賀県 坂田 郡西黒田村を放浪中の息長太郎(おきながいらっこ)先生から
近江西黒田村の長浜市布勢町の不思議な画像が送られてくました!次郎元気か?兄太郎と!

レッド赤川
息長の兄は城郭遺跡調査においては、天才的かつ、自虐的な人物だ!何んだこの画像は?
なに?長浜市布勢町の「穴伏」地名か?是は金太郎伝説に西黒田村の斧や金属地名だな?
桐糸餅弘
赤川先生!旧伊香郡の赤尾に即刻行きましようよ!
田黒タタラ
私には、何の事だがサッパリ解らないんですわな?
レッド赤川
何?延喜式内「布施立石神社」が赤尾に存在します。さもあらん!近江三布施とは蒲生郡
の布施氏、坂田郡の布施氏は近江三布施と呼ばれている。兄の息長太郎は、長浜市の布勢と
名越に白鳩山城を発見した。凄い慧眼のある特殊な人物だ!
田黒タタラ
私達も赤川先生と赤尾山城跡から山尾根を降ったら式内「布施立石神社」に到着です。
中世において赤尾氏は伊香郡の地頭職代的な家系で浅井氏と縁戚関係にもある由緒ある家柄。
さてまたまた布施が登場しましたね?たしか伊香郡木ノ本町に北布施と言う所もありますよ。
思います。
レッド赤川
たしか延喜式内『伊香具坂神社』が伊香郡木ノ本町に北布施には存在します。
また赤尾には延喜式内『阿加穂神社』が存在したと記憶します。アカホ=赤尾ですね!
レッド赤川
そうでしたね!『信長公記』の天正元年の記録には小谷城主の浅井備前守長政が赤尾美作
屋敷で自害する場面が描写されていました。浅井氏と赤尾氏は縁戚で縁が深いとも言えます。
レッド赤川
さても東高田の穴津地名には驚嘆しましたが、東高田の延喜式内社の櫟崎神社は勇出山の
南麓にあるんです。余呉川と赤川沿いの東高田に注目しましよう。水流の交わる所には必ず
や水神が祀られていたり、水に関わる伝説が残っているはずです!
田黒タタラ
ブログ 湖北「観音の里たかつき ふるさとまつり」から引用しますと
「延暦24年(805)伝教大師が東高田へ訪れた時、川底から一条の光明が差して
いるものがあり、それが現在祀られている本尊の十一面観音だったと伝えられている。
最澄は早速草庵を作り、青陽山 赤分寺と名付けた。
それからは東西からたくさんの有縁の信者たちが群をなして参詣されるので、ここに六つの坊
を境内に建立し、人々に便宜を図りました。このことはやがて足利将軍の耳にも達して篤く庇護
され、武運長久の祈願所となったた。永正元年(1504年)、京極氏と浅井亮政の戦乱で戦禍に
あってしまいますが、このご本尊だけは免れたという。とあります。
レッド赤川
うんそれも重要ですが磯野丹波らの先祖の城郭が伊香郡磯野山に存在し、丹波守の先祖は磯野
の宮澤丸にいたと推定されます。やがて浅井氏一族の大橋安芸守が磯野山城を預かった伝承がある。
ので、東高田「穴津」地名を含めて水の神、弁財天をも奉斎していた可能性があるあると思います。
黒田タタラ
あるんですよ!江戸時代の作なんですが、東高田の赤分寺にも水の神様弁財天が祀られてます。
レッド赤川
たしか?浅井氏の小谷城にも水の神、弁財天丸や日枝山王神を祀る山王丸が存在した事が東浅井
郡誌には記載されていました。いわいる信仰曲輪の「弁財天曲輪」と「山王神曲輪」の世界です。
山王曲輪は現在の山王丸の場所と思われますが?弁財天丸の位置は全く不明なのです。おそらく
は池や井戸に関わる水に関わる場所に弁財天曲輪が存在したしだと思われます。
桐糸餅弘
あるんですよ。あるんですよ。彦根にも、、、犬上郡と坂田郡の境目の城、佐和山城にも過去
には佐和山内湖に面した石ケ崎町の湊跡の石垣や大洞弁財天が存在した。現在も残っていますよ!
松原内湖とは元来芹川と矢倉川が流れ込んでいた要港なんですよ!つまり弁財天は水の神であり
港湾の神でもある。米と係る宇賀神と言う解釈もできます。『大洞弁財天古城主帳』には中世の
近江各地の土豪の城館主を供養した記録が残っています。
レッド赤川
浅井の勇将磯野丹波守員昌は佐和山城で織田軍団と対峙して8か月も籠城した上に
降伏開城して織田信長から近江高島郡を与えられて、早速舟で高島郡に赴いております。
松原内湖は当時佐和山城の重要な水の表玄関口だったんです。あの織田信長も松原内湖
の利便性を考え芹川から大木を流して大船の建造を実施しています。浅井の磯野丹波も
琵琶湖の水軍だったと思う。
黒田タタラ
また変な事を言われる。佐和山の磯野が船舶をつかつて他所の城を攻めたなど聞いた
事がありません。
レッド赤川
あるんですよ。あるんですよ。それが『近江温故禄』のなかに彦根の日夏山城攻めの
様子が水軍の磯野氏として描写されています。佐和山の松原内湖から琵琶湖湖岸を曽根
沼まで南下してつまり宇曽川河口から船舶で当時佐々木六角方の日夏山城つまり荒神山
城を攻めた生々しい伝承記録だと思います。

桐糸餅弘
東高田から磯野にいたり余呉川を渡ると伊香郡の大森山が見えてきます。旧八日市の
東近江にも布施山城や大森山城もあり不思議に思いますね。
レッド赤川
後白河法皇編集の『梁塵秘抄』には全く謎の文言があります。
「近江におかしき歌枕、老曾轟、蒲生野布施の池、安吉の橋、伊香具野余呉の湖の滋賀の浦に、
新羅が立てたりし持仏堂の金の柱。」真に謎に満ちた文言と歌枕の羅列であります。ちなみに
金の柱は旧八日市つまり東近江に伝承が今も残っています。
桐糸餅弘
伊香郡の大森古墳遠望します。

レッド赤川
伊香郡の大森神社を訪れましょう!きっと水軍磯野氏のヒント隠れていると思います。
大森神社 (オオモリ)
御祭神 彦火々出見命 豊玉姫命
御由緒 揚野郷阿曽津庄の総社といい、伊香厚行の創祀にかかると伝える。首記によれば、
東柳野、中柳野、西柳野、重則、松尾、5ヶ村1つ所也、氏子磯野、西物部は、雨乞ひ掛る
計りなり、云々とある。明治9年村社に列せられた。とあります。
桐糸餅弘
すごいなあ~あの伝説の有名な琵琶湖水没都市伝説の揚野郷★「阿曽津庄」★の総社が大森大明神ですか?

レッド赤川
赤川や東高田の「穴津」地名そして磯野集落、そしてまた大森山の切通し道も併せて見学しておきましよう。

レッド赤川
この道は西野へ、そして海老坂へ琵琶湖水没都市伝説の揚野郷「阿曽津庄」へと続く若狭街道かもしれません。
写真には浅井郡の葛籠尾崎が遠望されて感慨深いものがある。また葛籠尾崎には陣壺「ジンツボ」なる不思議
な大穴も残っているのですよ。鉄穴かもしれませんね?

レッド赤川
どうも私は七里村に起源を持つ、佐和山城の磯野丹波守の一族は船を操る水軍の様に思えます。
レッド赤川
余談ですが大昔には伊香郡の余呉湖畔の北には「エレの宮」があったとか?
やがて 延喜式内神社 長浜市余呉町中之郷 鉛練日子神社になったとか?「エレヒコ神社」です。
また余呉町中之郷には赤子山なる地名も残っているのです。これもレッドだ!
金属伝承関連地名と考えてよいと思います。中之郷には中山姓が多く夜泣き石
の伝説も西天神方面に、残っています。彦根の中山には古代製鉄溶鉱炉が発見
されていますが、それは円形ではなく、角形つまり四角だと言われております。
★発想の転換①!高月大森山の前方後方墳の紹介。
※大森古墳(山畑1号墳)
また前方後方墳が見学したくなった。旧滋賀県伊香郡高月町松尾山の丘陵先端「大森山切通の南」1号墳は尾根上に分布する古墳群中唯一の前方後方墳で、全長62m、2002年の調査で後方部から庄内式土器が出土し、三世紀前半の築造と見られ驚く。更にまた三世紀後半に後方部にさらに盛り土を高くし、方形張り出し部を加え双方中円墳の様相に作り替えられているらしい事が解った。まさか?こんな身近な長浜市に卑弥呼と同時代の特殊な墳丘があるとは驚きで近江国伊香郡と言う地域の歴史的起源の古さに驚く。古墳と延喜式神社は違う時代の遺跡なのだが、往々にして集落においては祖先の塚として遠い遠祖の神代の旧跡として解釈される場合もある。
★発想の転換②!更なる発想の転換。長浜市高月町の東柳野への神社探訪。
仕事も仲間もツテもいない私。よるべなき孤独の身の私は東柳野を一人でに歩いた。神社が見えてきたが石柱は明確に神社名が読めず見ずらかった。

社殿に到着すると正確に読めた。売比田神社である。ひめた神社と読むのだ。

売比田と書いて「ヒメタ」と読む事は正しく古い。何故ならば延喜式の原典にも項註して解説している。もちろん比売多と書くのも正しい。現地神社はより古い神社名を用いたものだろう?もっとも売比田と書いて「ヒメタ」と読む事に意味が深いと思われる。
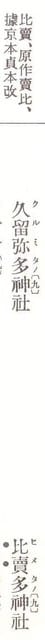
しかし売比田神社の相殿「あいどの」の久留美弥多神社「クルミタ」の名称には私は仰天して驚く!
「近江・若狭・越前 寺院神社大事典」には
売比多神社 ヒメタ神社
東柳野「近江国伊香郡/現長浜市」の青柳に鎮座する。 祭神豊玉姫命。相殿に久留弥多神「くるみたのかみ」を祀る。 「延喜式」神名帳の伊香郡「比売多神社」に、相殿「あいどの」は同じく「久留弥多神社」に比定される。
[中略]
相殿の久留弥多神は、唐川「旧近江国伊香郡高月町」日吉神社境内の観音堂に安置する平安時代作千手観音と菩薩像の足枘と像底に「久留弥多大明神」「御本地」と墨書(製作時より後世のもの)があり、両像が同神の本地仏であったことが知られる。 もとは唐川に鎮座していたが、天正年中(1573-92)兵乱に罹災し、東柳野の売比多神社に合祀されたと伝える。
赤後寺
湧出山の南麓に鎮座する日吉神社の境内にあった寺で、現在は観音堂が残る。 行基の草創と伝え、最澄が聖観音像を納めたという。[中略]堂内に安置する木造千手観音立像・木造菩薩立像は平安時代の作で、国指定重要文化財。 両像に「久留弥多大明神」「御本地」の墨書があり、式内社久留弥多神社の本地仏であったことが知られ、日吉神社を式内社に比定する説もある。
※さてさてややこしい 「御本地垂迹」ほんちすいじやく説が登場して頭がシビレルのだが?この久留弥多大明神が変化してやがて「ころり弥陀」と解釈されコロリカンノンへと解釈されたのであろうか?「微笑」
★発想の転換③!ころり転んで振りの出しの姫塚へ戻る
滋賀県神社庁の資料によると ※は長谷川解説
【延喜式神名帳】比売多神社 近江国 伊香郡鎮座
(旧地)売比多神社旧地
(合祀)久留弥多神社 ※A合祀とは併せて祀ると言う意味。
【現社名】売比多神社
【住所】滋賀県長浜市高月町東柳野1192
北緯35度28分17秒,東経136度12分50秒
【祭神】莵上壬命 (合祀)豊玉姫命 久留彌多神
【例祭】4月2日 例祭
【社格】旧村社
【由緒】由緒不詳
もとは姫塚古墳の地に鎮座※B比売多神社は元来姫塚古墳に鎮座していた。
応永年中現地へ遷
明治9年2月村社
【関係氏族】比売陀君
【鎮座地】当初鎮座の地は姫塚古墳(前方後円墳)が応永年中に現在の地に移る。
※この記事は歴史推理小説です宜しく御理解下さいませ。楽しく読んで下さい。
登場人物紹介
※レッド赤川
旧滋賀県伊香郡「現滋賀県長浜市」出身。賎ケ岳城郭遺跡群を今から約40年前より
その遺構を詳細調査し現地城郭遺跡調査派の民間歴史研究家。民俗学から地名学。
歴史地理と幅広い広角な知識と視野に裏打ちされた史観から次々に滋賀県内の城郭
遺跡を発見解明していく劇画で言えばゴルゴ13や名整形外科ブラック、ジャツクの
様な、一種異様な世界観を持つ伝説の歴史名探偵その洞察力は常人の次元を超える。
※黒田タタラ
常に常識や既存の歴史知識を基調に持つ常識派、レッド赤川に常に反発するも歴史
の現場や現状をレッド赤川に見せられ歴史の現場の深淵に衝撃を受ける向学心の人。
※桐糸餅弘
元歴史とロマンの町と言われた町の住人この短編架空小説では軽妙なボケをかます。
※息長太郎(おきながいらっこ)
レッド赤川の兄弟とも従弟ともされる謎の古代史城郭研究家
レッド赤川
伊香胡と言う地名に限りなく大陸の胡人や遊牧民族や大陸の風を感じさせますね?
桐糸餅弘
滋賀県高島市では遊牧民しか使用しないオルドス型刀剣の鋳型石が出土しています。
黒田タタラ
高島郡と騎馬は何か関係があるのでしょうか?高島や浅井の鉄穴は広く知られてる。
レッド赤川
高島には牧野地名や饗場地名や万木に関係する地名や延喜式に掲載の鞆結駅がある。
越前朝倉義景館の堀からは「御者たやとの」騎馬飼育の田屋氏の記載がありますね。
桐糸餅弘
万木は「万騎」なのでしょうか?万木と書いて「ゆるぎ」と高島では読みますよね?
かって木ノ本では牛馬市が開かれ高島郡からは牛馬が木ノ本に来たとも言われてます!
黒田タタラ
赤川烈道先生?いやレッド赤川先生、旧滋賀県伊香郡の勇出山「ゆるぎ山」に行き
ましよう!唐川の赤後寺の観音様のルーツはどこにあるのでしょうか?また延喜式
の伊香郡にはアカの表音の神社が掲載されていますよ!これは一体何を意味する?

桐糸餅弘
うんうん、まるで赤出し味噌汁状態ですね?そうそう赤だしの連続と言う感じですわ。
レッド赤川
唐川赤後寺の観音様?のルーツはやはり中国唐代の観世音菩薩像がその見本やルーツ
となっているのではないでしょうかな?

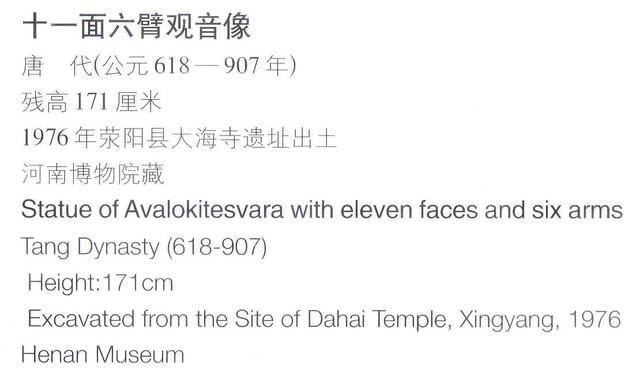
レッド赤川
懐かしい余呉川だ!余呉川には川湊があったと私は推測しています。何故ならば小谷
城下にも船場の辻なる川湊地名が残ってる。余呉川にも川湊があったと私は推理する。

黒田タタラ
無茶な発想です。余呉湖には湖上を行く舟が近世まで存在しましたが余呉川には無い。
しかし琵琶湖の尾上に存在した旧余呉河川を利用した旧尾上漁港は小船舶が繋留された。
桐糸餅弘
賎ケ岳トンネルの入口の国道8号線は太古の湖の底の様な地面の窪みがありますね?
それに木ノ本周辺の人に聞くと太古に余呉湖とは異なる伊香湖と呼ばれる湖が存在
した証拠に水田の底には芦「アシ」などの地下茎が見つかると聞きます。また太古
の余呉川は勇出山の東麓を廻って流れていて西山と勇出山が開削されて太古の余呉
川は水のない空からの川、つまりは唐川と言う集落名になったと聞き及んでいます。
レッド赤川
勇出山の北麓の伊香平野には古代条理の水田の跡が残っていました。だからその話
は神代の神話の世界または古墳時代の伊香氏の伝説の世界かと思います。もっとも
勇出山の東側に田部の集落があり大和朝廷の墾田制前の時代の田部を連想させます?
余呉川沿いの余呉町東野国安の堺には『東野家文書』?に周囲800mの湖沼が存在し
小字奈良寺からは水成固生鉄の「たかし小僧」が出土してます。つまり芦や水茎を
持つ植物に金属が付着して煙管「キセル」の様になった状態の赤さびた遺物を言う。
黒田タタラ
とにかく唐川や東高田や磯野集落の北の赤川沿いを歩いてみましょうよ!
↓ 勇出山が正しい表記です!

レッド赤川
これは凄い!赤後寺。赤分寺。余呉川に赤川。赤尾。赤の語彙の連鎖反応ではないのか?
ここだ!東高田に余呉川の川湊「かわみなと」が存在したに違いない!必ず水の神を祀る
祠や水に関わる伝説や「余呉川の川湊の意味する地名」があるはと私は推理しています。

田黒タタラ
またまたレッド赤川先生は飛躍しすぎた発想や妄想をされますね!?
レッド赤川
妄想ではなく推理だ!飛躍なんか私はしていない!赤後寺。赤分寺。赤川。等の地名は閼伽は
サンスクリット語アルギャの音写で阿伽「アカ」遏伽、あつかとも書く。観音信仰の聖水の
「阿伽/アカ」と係る言葉でしょう。
閼伽アカを汲む専用の井戸 閼伽井あかい
閼伽アカを入れる桶 閼伽桶あかおけ
閼伽桶を置く棚 閼伽棚あかだな
閼伽アカを入れる器 閼伽器あかき
閼伽水を桶から器に移す坏 閼伽坏あかづき
閼伽水に浮かべて供える樒しきみ 閼伽の花あかのはなと言う。
桐糸餅弘
余呉川と赤川の合流点の東高田の地名に船に関する地名がないのか?赤川先生と探しましよう!
黒田タタラ
そんなの空想にしか過ぎませんよ!レッド赤川先生の発想は異端です!
レッド赤川
さてどうかな?東高田の地名を調べると!あるんだなあ~コレが!
穴津と呼ばれる強烈な港湾地名の小字か゛記載されています。穴津
是は本当に意味が深い強烈な言葉で地名なのです!

桐糸餅弘
赤川先生!穴津とは凄い地名ですなあ!足が震えて来ました。僕はゾクゾクしてきましたよ!
黒田タタラ
何が凄いんですか?近江伊香郡黒田村には穴師地名の集落がありますし小字の踏鞴タタラも
あります、また布施姓もありますし、別に私は驚きはしませんが?
レッド赤川
伊香郡東高田の小字「穴津」も伊香郡黒田郷の小字踏鞴「タタラ」もスゴイ地名ですよ!
ちなみに『和名抄』に「坂田郡阿那郷」の項に「近江国吾名邑」あなの村と記されてます。
また『日本書記』の垂仁紀には
「天日槍自菟道河泝之 北入近江國吾名邑而暫住 復更自近江 經若狹國 西到但馬國則定住處也
是以近江國鏡村谷陶人 則天日槍之從人也 故天日槍娶但馬出嶋人 太耳女麻多烏 生但馬諸助也
諸助生但馬日楢杵 日楢杵生清彦 清彦生田道間守也」とある。
とくにアメノヒボコが★「北入近江國吾名邑而暫住」とある事に注目!だから北近江の伊香郡の
東高田の小字「穴津」地名は驚くべき地名とひとつと言えます!『和名抄』の「坂田郡阿那郷」
の項には「近江国吾名邑」の記述はとても重要かと思います。これは「あなむら」と読むんです。
黒田タタラ
赤川先生!滋賀県 坂田 郡西黒田村を放浪中の息長太郎(おきながいらっこ)先生から
近江西黒田村の長浜市布勢町の不思議な画像が送られてくました!次郎元気か?兄太郎と!

レッド赤川
息長の兄は城郭遺跡調査においては、天才的かつ、自虐的な人物だ!何んだこの画像は?
なに?長浜市布勢町の「穴伏」地名か?是は金太郎伝説に西黒田村の斧や金属地名だな?
桐糸餅弘
赤川先生!旧伊香郡の赤尾に即刻行きましようよ!
田黒タタラ
私には、何の事だがサッパリ解らないんですわな?
レッド赤川
何?延喜式内「布施立石神社」が赤尾に存在します。さもあらん!近江三布施とは蒲生郡
の布施氏、坂田郡の布施氏は近江三布施と呼ばれている。兄の息長太郎は、長浜市の布勢と
名越に白鳩山城を発見した。凄い慧眼のある特殊な人物だ!
田黒タタラ
私達も赤川先生と赤尾山城跡から山尾根を降ったら式内「布施立石神社」に到着です。
中世において赤尾氏は伊香郡の地頭職代的な家系で浅井氏と縁戚関係にもある由緒ある家柄。
さてまたまた布施が登場しましたね?たしか伊香郡木ノ本町に北布施と言う所もありますよ。
思います。
レッド赤川
たしか延喜式内『伊香具坂神社』が伊香郡木ノ本町に北布施には存在します。
また赤尾には延喜式内『阿加穂神社』が存在したと記憶します。アカホ=赤尾ですね!
レッド赤川
そうでしたね!『信長公記』の天正元年の記録には小谷城主の浅井備前守長政が赤尾美作
屋敷で自害する場面が描写されていました。浅井氏と赤尾氏は縁戚で縁が深いとも言えます。
レッド赤川
さても東高田の穴津地名には驚嘆しましたが、東高田の延喜式内社の櫟崎神社は勇出山の
南麓にあるんです。余呉川と赤川沿いの東高田に注目しましよう。水流の交わる所には必ず
や水神が祀られていたり、水に関わる伝説が残っているはずです!
田黒タタラ
ブログ 湖北「観音の里たかつき ふるさとまつり」から引用しますと
「延暦24年(805)伝教大師が東高田へ訪れた時、川底から一条の光明が差して
いるものがあり、それが現在祀られている本尊の十一面観音だったと伝えられている。
最澄は早速草庵を作り、青陽山 赤分寺と名付けた。
それからは東西からたくさんの有縁の信者たちが群をなして参詣されるので、ここに六つの坊
を境内に建立し、人々に便宜を図りました。このことはやがて足利将軍の耳にも達して篤く庇護
され、武運長久の祈願所となったた。永正元年(1504年)、京極氏と浅井亮政の戦乱で戦禍に
あってしまいますが、このご本尊だけは免れたという。とあります。
レッド赤川
うんそれも重要ですが磯野丹波らの先祖の城郭が伊香郡磯野山に存在し、丹波守の先祖は磯野
の宮澤丸にいたと推定されます。やがて浅井氏一族の大橋安芸守が磯野山城を預かった伝承がある。
ので、東高田「穴津」地名を含めて水の神、弁財天をも奉斎していた可能性があるあると思います。
黒田タタラ
あるんですよ!江戸時代の作なんですが、東高田の赤分寺にも水の神様弁財天が祀られてます。
レッド赤川
たしか?浅井氏の小谷城にも水の神、弁財天丸や日枝山王神を祀る山王丸が存在した事が東浅井
郡誌には記載されていました。いわいる信仰曲輪の「弁財天曲輪」と「山王神曲輪」の世界です。
山王曲輪は現在の山王丸の場所と思われますが?弁財天丸の位置は全く不明なのです。おそらく
は池や井戸に関わる水に関わる場所に弁財天曲輪が存在したしだと思われます。
桐糸餅弘
あるんですよ。あるんですよ。彦根にも、、、犬上郡と坂田郡の境目の城、佐和山城にも過去
には佐和山内湖に面した石ケ崎町の湊跡の石垣や大洞弁財天が存在した。現在も残っていますよ!
松原内湖とは元来芹川と矢倉川が流れ込んでいた要港なんですよ!つまり弁財天は水の神であり
港湾の神でもある。米と係る宇賀神と言う解釈もできます。『大洞弁財天古城主帳』には中世の
近江各地の土豪の城館主を供養した記録が残っています。
レッド赤川
浅井の勇将磯野丹波守員昌は佐和山城で織田軍団と対峙して8か月も籠城した上に
降伏開城して織田信長から近江高島郡を与えられて、早速舟で高島郡に赴いております。
松原内湖は当時佐和山城の重要な水の表玄関口だったんです。あの織田信長も松原内湖
の利便性を考え芹川から大木を流して大船の建造を実施しています。浅井の磯野丹波も
琵琶湖の水軍だったと思う。
黒田タタラ
また変な事を言われる。佐和山の磯野が船舶をつかつて他所の城を攻めたなど聞いた
事がありません。
レッド赤川
あるんですよ。あるんですよ。それが『近江温故禄』のなかに彦根の日夏山城攻めの
様子が水軍の磯野氏として描写されています。佐和山の松原内湖から琵琶湖湖岸を曽根
沼まで南下してつまり宇曽川河口から船舶で当時佐々木六角方の日夏山城つまり荒神山
城を攻めた生々しい伝承記録だと思います。

桐糸餅弘
東高田から磯野にいたり余呉川を渡ると伊香郡の大森山が見えてきます。旧八日市の
東近江にも布施山城や大森山城もあり不思議に思いますね。
レッド赤川
後白河法皇編集の『梁塵秘抄』には全く謎の文言があります。
「近江におかしき歌枕、老曾轟、蒲生野布施の池、安吉の橋、伊香具野余呉の湖の滋賀の浦に、
新羅が立てたりし持仏堂の金の柱。」真に謎に満ちた文言と歌枕の羅列であります。ちなみに
金の柱は旧八日市つまり東近江に伝承が今も残っています。
桐糸餅弘
伊香郡の大森古墳遠望します。

レッド赤川
伊香郡の大森神社を訪れましょう!きっと水軍磯野氏のヒント隠れていると思います。
大森神社 (オオモリ)
御祭神 彦火々出見命 豊玉姫命
御由緒 揚野郷阿曽津庄の総社といい、伊香厚行の創祀にかかると伝える。首記によれば、
東柳野、中柳野、西柳野、重則、松尾、5ヶ村1つ所也、氏子磯野、西物部は、雨乞ひ掛る
計りなり、云々とある。明治9年村社に列せられた。とあります。
桐糸餅弘
すごいなあ~あの伝説の有名な琵琶湖水没都市伝説の揚野郷★「阿曽津庄」★の総社が大森大明神ですか?

レッド赤川
赤川や東高田の「穴津」地名そして磯野集落、そしてまた大森山の切通し道も併せて見学しておきましよう。

レッド赤川
この道は西野へ、そして海老坂へ琵琶湖水没都市伝説の揚野郷「阿曽津庄」へと続く若狭街道かもしれません。
写真には浅井郡の葛籠尾崎が遠望されて感慨深いものがある。また葛籠尾崎には陣壺「ジンツボ」なる不思議
な大穴も残っているのですよ。鉄穴かもしれませんね?

レッド赤川
どうも私は七里村に起源を持つ、佐和山城の磯野丹波守の一族は船を操る水軍の様に思えます。
レッド赤川
余談ですが大昔には伊香郡の余呉湖畔の北には「エレの宮」があったとか?
やがて 延喜式内神社 長浜市余呉町中之郷 鉛練日子神社になったとか?「エレヒコ神社」です。
また余呉町中之郷には赤子山なる地名も残っているのです。これもレッドだ!
金属伝承関連地名と考えてよいと思います。中之郷には中山姓が多く夜泣き石
の伝説も西天神方面に、残っています。彦根の中山には古代製鉄溶鉱炉が発見
されていますが、それは円形ではなく、角形つまり四角だと言われております。
★発想の転換①!高月大森山の前方後方墳の紹介。
※大森古墳(山畑1号墳)
また前方後方墳が見学したくなった。旧滋賀県伊香郡高月町松尾山の丘陵先端「大森山切通の南」1号墳は尾根上に分布する古墳群中唯一の前方後方墳で、全長62m、2002年の調査で後方部から庄内式土器が出土し、三世紀前半の築造と見られ驚く。更にまた三世紀後半に後方部にさらに盛り土を高くし、方形張り出し部を加え双方中円墳の様相に作り替えられているらしい事が解った。まさか?こんな身近な長浜市に卑弥呼と同時代の特殊な墳丘があるとは驚きで近江国伊香郡と言う地域の歴史的起源の古さに驚く。古墳と延喜式神社は違う時代の遺跡なのだが、往々にして集落においては祖先の塚として遠い遠祖の神代の旧跡として解釈される場合もある。
★発想の転換②!更なる発想の転換。長浜市高月町の東柳野への神社探訪。
仕事も仲間もツテもいない私。よるべなき孤独の身の私は東柳野を一人でに歩いた。神社が見えてきたが石柱は明確に神社名が読めず見ずらかった。

社殿に到着すると正確に読めた。売比田神社である。ひめた神社と読むのだ。

売比田と書いて「ヒメタ」と読む事は正しく古い。何故ならば延喜式の原典にも項註して解説している。もちろん比売多と書くのも正しい。現地神社はより古い神社名を用いたものだろう?もっとも売比田と書いて「ヒメタ」と読む事に意味が深いと思われる。
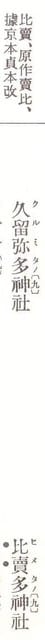
しかし売比田神社の相殿「あいどの」の久留美弥多神社「クルミタ」の名称には私は仰天して驚く!
「近江・若狭・越前 寺院神社大事典」には
売比多神社 ヒメタ神社
東柳野「近江国伊香郡/現長浜市」の青柳に鎮座する。 祭神豊玉姫命。相殿に久留弥多神「くるみたのかみ」を祀る。 「延喜式」神名帳の伊香郡「比売多神社」に、相殿「あいどの」は同じく「久留弥多神社」に比定される。
[中略]
相殿の久留弥多神は、唐川「旧近江国伊香郡高月町」日吉神社境内の観音堂に安置する平安時代作千手観音と菩薩像の足枘と像底に「久留弥多大明神」「御本地」と墨書(製作時より後世のもの)があり、両像が同神の本地仏であったことが知られる。 もとは唐川に鎮座していたが、天正年中(1573-92)兵乱に罹災し、東柳野の売比多神社に合祀されたと伝える。
赤後寺
湧出山の南麓に鎮座する日吉神社の境内にあった寺で、現在は観音堂が残る。 行基の草創と伝え、最澄が聖観音像を納めたという。[中略]堂内に安置する木造千手観音立像・木造菩薩立像は平安時代の作で、国指定重要文化財。 両像に「久留弥多大明神」「御本地」の墨書があり、式内社久留弥多神社の本地仏であったことが知られ、日吉神社を式内社に比定する説もある。
※さてさてややこしい 「御本地垂迹」ほんちすいじやく説が登場して頭がシビレルのだが?この久留弥多大明神が変化してやがて「ころり弥陀」と解釈されコロリカンノンへと解釈されたのであろうか?「微笑」
★発想の転換③!ころり転んで振りの出しの姫塚へ戻る
滋賀県神社庁の資料によると ※は長谷川解説
【延喜式神名帳】比売多神社 近江国 伊香郡鎮座
(旧地)売比多神社旧地
(合祀)久留弥多神社 ※A合祀とは併せて祀ると言う意味。
【現社名】売比多神社
【住所】滋賀県長浜市高月町東柳野1192
北緯35度28分17秒,東経136度12分50秒
【祭神】莵上壬命 (合祀)豊玉姫命 久留彌多神
【例祭】4月2日 例祭
【社格】旧村社
【由緒】由緒不詳
もとは姫塚古墳の地に鎮座※B比売多神社は元来姫塚古墳に鎮座していた。
応永年中現地へ遷
明治9年2月村社
【関係氏族】比売陀君
【鎮座地】当初鎮座の地は姫塚古墳(前方後円墳)が応永年中に現在の地に移る。


























※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます