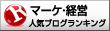マーケティング研究 他社事例 609 「AIと雇用と可能性と人間社会との共存 1」 ~意思決定もAIに代替えされる!?~
「アメリカの全雇用の約47%がコンピューターによる自動化で10年から20年先に失われるリスクにさらされている」
2013年にこのセンセーショナルな内容を世界に披露した、オックスフォード大学のマイケル・オズボーン教授はベイズ機械学習の専門家としてAI研究の最先端を追って来ました。
雇用の未来、AIの未来とはどういったものなのか?
オズボーン教授の話を以下の通りです。
「AIが持つ潜在的な可能性は、実に変革的だ。AIはまず『意思決定の独占権』を人類から奪う・そもそも巨大で複雑なシステムの中で人間が全てを知るのは不可能である。しかし、アルゴリズムには限界がない。全システムからデータを取れる。アルゴリズムはどの人間より情報通になり得る。これにより意思決定を人間だけに頼る事で生じていた様々な問題が、解決に向かう事は明らかだ。そのため多くの組織は、アルゴリズムをうまく活用し、これまで人間が作ってきた仕組みを再考し始めている。歴史をひもとけば、人間だけがやってきた多くのタスクが、次々と技術で自動化されてきた。だが、アルゴリズムやAIはただ単に人間に取って代わるだけではなく、これまでにない利便性を提供する。私たちがここ数年注目してきたものの一つは、電子商取引で消費者が買いそうな商品を薦めてくるAIだ。消費者の膨大な購買データにアクセスできるアルゴリズムで、人の販売員より、良い提案をするようになってきている。こうした状況を踏まえれば、AIによる変革は、単純労働だけが人から置き換わるわけではない。意思決定や微妙な判断すらAIに取って代わられる。定型的な情報処理は最初に置き換わりそうだ。バックオフィスの仕事や、税理士や会計係の仕事の一部も置き換わるとみていい」
オズボーン教授のいう事通りなら、AIによって職を失う人が続出し社会が混乱するのは避けられません。
しかし歴史を振り返ると、それでも技術革新は社会に普及してきました。
オズボーン教授は言います。
「かつて社会の支配者は、技術革新に積極的に反対した。古い例として、1589年のイギリスのエリザベス1世による抵抗がある。繊維工場のウイリアム・リーが開発した機械を使用禁止にしたのだ。女王は、機械が平均的な労働者の仕事を奪い、政治が不安的になるのを嫌った。これは、様々な歴史を通じて、驚くほど共通してみられた現象である。為政者は国家の崩壊を懸念し、技術が人の仕事を奪うのを許さなかった。だがそうしている間に。アフリカ大陸が発見され、社会に変化が起きた。新しい貿易の機会が開かれ、新興の商人階級に政治力が移った。商人や実業家は、技術導入に反対する勢力に対抗するため政治力を高めていった」
新大陸の発見による取引機会の拡大によって得られた民間の経済力の高まりが、社会の意思決定のゲームチェンジャーになり、技術革新の実用化につながったというわけです。
では新大陸がもはや存在しない現代では、痛みを伴う技術革新の導入には歯止めがかかる可能性はないのでしょうか?
「現在のAIの技術革新の状況は、歴史上の多くの出来事に当てはめることができる。恐らく一番似ているのが、18世紀に起きたイギリスの産業革命だ。産業革命では、まず紡績業が自動化され、後に蒸気機関車などの自動化手段が導入された。これらは社会に変革を生み出され、社会はとても豊かになった。だが、機械の素早い導入は労働者にとっては不都合であり、多くの人が反対した。18世紀に紡績業で新たな技術が導入された時は、労働者からの抵抗を政府が鎮圧した。暴徒を遮断するため、軍も派遣した。フランスのナポレオンと戦うより、技術導入に対する反対勢力の鎮圧を優先した。スムーズな機械導入の背後に強力な政治力があった。機械が導入された後、労働者の収入は40年間低迷した。イギリスのリバプールやマンチェスターのような労働者が集中する主要都市では、多くの労働者の平均余命が31~32歳と短命化し、世界平均より10年も短くなった」
しかし、そうした状況は次第に変わっていきます。
技術革新は長期的には社会全体にメリットをもたらすからです。
「流れが変わったのは、機械が生み出した富が社会全体で共有され、平均的な労働者も利益を得るようになってからだ。労働者を守る規則の影響もあり、人々は、技術がヒトカラ労働を奪うのではなく、人間にできないことを補完したり、つらいことを代わりに担ってくれたりすることを理解した。機械の導入は、長期的には人に新たな機会をもたらし、幸福につながると納得した。AIでも同じだろう」
もっとも、技術革新が人類にもたらす恩恵を享受するには、個人として技術変化の波に乗り、過渡期を乗り切らねばなりません。
つまり労働力としてAIに勝たねばなりません。
では人間がAIに勝てそうなこととは何でしょうか?
オズボーン教授は、社会的な知性は最も難度が高いとしています。
社会的な知性とは、交渉や説得なを示します。
「21世紀は、AIが人間の仕事を覚えていく時代になりそうである。逆に言えば、AIは、人間ができる全てを出来るようにはならない。人間らしさは備わらないだろう。アルゴリズムでは、人類を根本的に理解することはできない。例えばAIが、葬儀社のような共感が必要なサービスができるとは思えない。こういった仕事では、個別対応と心のこもったケアを最優先する方が、理に適う。加えて人間的な認知、型にはまらない創造性や独創性を使う仕事もAIには難しい」
(続く)
下記は彩りプロジェクトのご紹介です。
ご興味があればご一読下さい。
経営の根幹は「人」です。働く人次第で成果が変わります。自分事で働く社員を増やし、価値観を同じくし働く事で働きがいも増します。
彩りプロジェクトでは、風土改革を軸にした「私の職場研修」、「未来を創るワークショップ研修」等、各企業の課題に合わせた研修をご提案差し上げます。ITソフトメーカー、製造メーカー、商社、小売業者、社会福祉法人、NPO法人等での研修実績があります。
研修と一言と言っても、こちらの考え方を一方的に押し付ける事はしません。実感いただき、改善課題を各自が見つけられる様な研修をカスタマイズしご提案しているのが、彩りプロジェクトの特徴です。
保育園・幼稚園へご提供している研修【私の保育園】【私の幼稚園】は大変ご好評をいただいています。
また、貴社に伺って行う研修を40,000円(1h)からご用意しておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
メール info@irodori-pro.jp
HP https://www.fuudokaikaku.com/
お問合せ https://www.fuudokaikaku.com/ホーム/お問い合わせ/
成長クリエイター 彩りプロジェクト 波田野 英嗣
「アメリカの全雇用の約47%がコンピューターによる自動化で10年から20年先に失われるリスクにさらされている」
2013年にこのセンセーショナルな内容を世界に披露した、オックスフォード大学のマイケル・オズボーン教授はベイズ機械学習の専門家としてAI研究の最先端を追って来ました。
雇用の未来、AIの未来とはどういったものなのか?
オズボーン教授の話を以下の通りです。
「AIが持つ潜在的な可能性は、実に変革的だ。AIはまず『意思決定の独占権』を人類から奪う・そもそも巨大で複雑なシステムの中で人間が全てを知るのは不可能である。しかし、アルゴリズムには限界がない。全システムからデータを取れる。アルゴリズムはどの人間より情報通になり得る。これにより意思決定を人間だけに頼る事で生じていた様々な問題が、解決に向かう事は明らかだ。そのため多くの組織は、アルゴリズムをうまく活用し、これまで人間が作ってきた仕組みを再考し始めている。歴史をひもとけば、人間だけがやってきた多くのタスクが、次々と技術で自動化されてきた。だが、アルゴリズムやAIはただ単に人間に取って代わるだけではなく、これまでにない利便性を提供する。私たちがここ数年注目してきたものの一つは、電子商取引で消費者が買いそうな商品を薦めてくるAIだ。消費者の膨大な購買データにアクセスできるアルゴリズムで、人の販売員より、良い提案をするようになってきている。こうした状況を踏まえれば、AIによる変革は、単純労働だけが人から置き換わるわけではない。意思決定や微妙な判断すらAIに取って代わられる。定型的な情報処理は最初に置き換わりそうだ。バックオフィスの仕事や、税理士や会計係の仕事の一部も置き換わるとみていい」
オズボーン教授のいう事通りなら、AIによって職を失う人が続出し社会が混乱するのは避けられません。
しかし歴史を振り返ると、それでも技術革新は社会に普及してきました。
オズボーン教授は言います。
「かつて社会の支配者は、技術革新に積極的に反対した。古い例として、1589年のイギリスのエリザベス1世による抵抗がある。繊維工場のウイリアム・リーが開発した機械を使用禁止にしたのだ。女王は、機械が平均的な労働者の仕事を奪い、政治が不安的になるのを嫌った。これは、様々な歴史を通じて、驚くほど共通してみられた現象である。為政者は国家の崩壊を懸念し、技術が人の仕事を奪うのを許さなかった。だがそうしている間に。アフリカ大陸が発見され、社会に変化が起きた。新しい貿易の機会が開かれ、新興の商人階級に政治力が移った。商人や実業家は、技術導入に反対する勢力に対抗するため政治力を高めていった」
新大陸の発見による取引機会の拡大によって得られた民間の経済力の高まりが、社会の意思決定のゲームチェンジャーになり、技術革新の実用化につながったというわけです。
では新大陸がもはや存在しない現代では、痛みを伴う技術革新の導入には歯止めがかかる可能性はないのでしょうか?
「現在のAIの技術革新の状況は、歴史上の多くの出来事に当てはめることができる。恐らく一番似ているのが、18世紀に起きたイギリスの産業革命だ。産業革命では、まず紡績業が自動化され、後に蒸気機関車などの自動化手段が導入された。これらは社会に変革を生み出され、社会はとても豊かになった。だが、機械の素早い導入は労働者にとっては不都合であり、多くの人が反対した。18世紀に紡績業で新たな技術が導入された時は、労働者からの抵抗を政府が鎮圧した。暴徒を遮断するため、軍も派遣した。フランスのナポレオンと戦うより、技術導入に対する反対勢力の鎮圧を優先した。スムーズな機械導入の背後に強力な政治力があった。機械が導入された後、労働者の収入は40年間低迷した。イギリスのリバプールやマンチェスターのような労働者が集中する主要都市では、多くの労働者の平均余命が31~32歳と短命化し、世界平均より10年も短くなった」
しかし、そうした状況は次第に変わっていきます。
技術革新は長期的には社会全体にメリットをもたらすからです。
「流れが変わったのは、機械が生み出した富が社会全体で共有され、平均的な労働者も利益を得るようになってからだ。労働者を守る規則の影響もあり、人々は、技術がヒトカラ労働を奪うのではなく、人間にできないことを補完したり、つらいことを代わりに担ってくれたりすることを理解した。機械の導入は、長期的には人に新たな機会をもたらし、幸福につながると納得した。AIでも同じだろう」
もっとも、技術革新が人類にもたらす恩恵を享受するには、個人として技術変化の波に乗り、過渡期を乗り切らねばなりません。
つまり労働力としてAIに勝たねばなりません。
では人間がAIに勝てそうなこととは何でしょうか?
オズボーン教授は、社会的な知性は最も難度が高いとしています。
社会的な知性とは、交渉や説得なを示します。
「21世紀は、AIが人間の仕事を覚えていく時代になりそうである。逆に言えば、AIは、人間ができる全てを出来るようにはならない。人間らしさは備わらないだろう。アルゴリズムでは、人類を根本的に理解することはできない。例えばAIが、葬儀社のような共感が必要なサービスができるとは思えない。こういった仕事では、個別対応と心のこもったケアを最優先する方が、理に適う。加えて人間的な認知、型にはまらない創造性や独創性を使う仕事もAIには難しい」
(続く)
下記は彩りプロジェクトのご紹介です。
ご興味があればご一読下さい。
経営の根幹は「人」です。働く人次第で成果が変わります。自分事で働く社員を増やし、価値観を同じくし働く事で働きがいも増します。
彩りプロジェクトでは、風土改革を軸にした「私の職場研修」、「未来を創るワークショップ研修」等、各企業の課題に合わせた研修をご提案差し上げます。ITソフトメーカー、製造メーカー、商社、小売業者、社会福祉法人、NPO法人等での研修実績があります。
研修と一言と言っても、こちらの考え方を一方的に押し付ける事はしません。実感いただき、改善課題を各自が見つけられる様な研修をカスタマイズしご提案しているのが、彩りプロジェクトの特徴です。
保育園・幼稚園へご提供している研修【私の保育園】【私の幼稚園】は大変ご好評をいただいています。
また、貴社に伺って行う研修を40,000円(1h)からご用意しておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
メール info@irodori-pro.jp
HP https://www.fuudokaikaku.com/
お問合せ https://www.fuudokaikaku.com/ホーム/お問い合わせ/
成長クリエイター 彩りプロジェクト 波田野 英嗣